
「博士の愛した数式」で「フィールズ賞」を受賞した日本人数学者のことを書きましたが、気になったので調べてみました。
1990年、京都大学数理解析研究所の森重文教授、当時39歳。「経歴と業績」が載っていました。業績の部分は何が書いてあるのかよく分かりません!!根性のある方は最後まで読んでみてください。
1973年 京都大学理学部卒、
1975年 京都大学大学院で修士号取得、
1978年 京都大学から理学博士の学位を得る。
1975年 京都大学理学部助手。
1977-80年、米国ハーバード大学助教授。
1980年 名古屋大学理学部専任講師。
1981-82年 米国プリンストン高級研究所の研究員。
1982年 名古屋大学助教授、1988年教授。
1990年 京都大学数理解析研究所教授となり現在に至る。
学生時代から一貫して代数幾何学の研究を精力的に行い、著しい成果をあげてきた。とりわけ、「接バンドルが豊富なら射影空間である」というハーツホーンの予想を解決した論文は、代数多様体の構造論における最初の一般的な定理として歴史に刻まれるものであり、そこで開発された証明の技法がさらに洗練され「端射線の理論」となった。
これは代数多様体および有理写像の構造の研究に有力な手段を与えるもので、これにより2次元の壁を乗り越えて高次元代数多様体の構造を解明することが可能になった。さらに極小モデルの存在を3次元の場合に示すことに成功し、1990年に京都で開かれた国際数学者会議でフィールズ賞を受けた。
この他1983年日本数学会彌永賞、84年中日文化賞、88年日本数学会秋季賞(川又雄二郎と共に)、89年井上賞、90年アメリカ数学会コール(Cole)賞、日本学士院賞(飯高茂、川又雄二郎と共に)を受ける。さらに1990年には文化功労者に選ばれた。
「日本の科学者・技術者100人」http://www.civic.ninohe.iwate.jp/100W/index01.html
ちなみに森教授は日本人で3人目(他の2人は1954年の小平邦彦、1970年の広中平祐)のフィールズ賞受賞者ですが、受賞当時、日本の研究機関に所属していた数学者としては日本(アジア)初だそうです。1951年生まれということは55歳くらいですよね。まだまだ若い研究者ですね。
私が書いた「数学は美術だ」という言葉はたしか受賞した時の言葉として新聞で読んだのですが、「美術」の部分は「デザイン」とか「芸術」とか別の言葉だったかもしれません。「端射線の理論」がどんなものかは見当もつきませんが、美しい曲線?なのでしょうね。
1990年、京都大学数理解析研究所の森重文教授、当時39歳。「経歴と業績」が載っていました。業績の部分は何が書いてあるのかよく分かりません!!根性のある方は最後まで読んでみてください。
1973年 京都大学理学部卒、
1975年 京都大学大学院で修士号取得、
1978年 京都大学から理学博士の学位を得る。
1975年 京都大学理学部助手。
1977-80年、米国ハーバード大学助教授。
1980年 名古屋大学理学部専任講師。
1981-82年 米国プリンストン高級研究所の研究員。
1982年 名古屋大学助教授、1988年教授。
1990年 京都大学数理解析研究所教授となり現在に至る。
学生時代から一貫して代数幾何学の研究を精力的に行い、著しい成果をあげてきた。とりわけ、「接バンドルが豊富なら射影空間である」というハーツホーンの予想を解決した論文は、代数多様体の構造論における最初の一般的な定理として歴史に刻まれるものであり、そこで開発された証明の技法がさらに洗練され「端射線の理論」となった。
これは代数多様体および有理写像の構造の研究に有力な手段を与えるもので、これにより2次元の壁を乗り越えて高次元代数多様体の構造を解明することが可能になった。さらに極小モデルの存在を3次元の場合に示すことに成功し、1990年に京都で開かれた国際数学者会議でフィールズ賞を受けた。
この他1983年日本数学会彌永賞、84年中日文化賞、88年日本数学会秋季賞(川又雄二郎と共に)、89年井上賞、90年アメリカ数学会コール(Cole)賞、日本学士院賞(飯高茂、川又雄二郎と共に)を受ける。さらに1990年には文化功労者に選ばれた。
「日本の科学者・技術者100人」http://www.civic.ninohe.iwate.jp/100W/index01.html
ちなみに森教授は日本人で3人目(他の2人は1954年の小平邦彦、1970年の広中平祐)のフィールズ賞受賞者ですが、受賞当時、日本の研究機関に所属していた数学者としては日本(アジア)初だそうです。1951年生まれということは55歳くらいですよね。まだまだ若い研究者ですね。
私が書いた「数学は美術だ」という言葉はたしか受賞した時の言葉として新聞で読んだのですが、「美術」の部分は「デザイン」とか「芸術」とか別の言葉だったかもしれません。「端射線の理論」がどんなものかは見当もつきませんが、美しい曲線?なのでしょうね。


















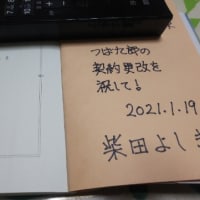


チンプンカンプンです。
「端射線理論」とは何か調べてみたのですが、
脳みそが溶けそうでした。
「端射線理論」って私は文字をコピーしたんだけど、「たんしゃせん」以外に読めないよね。でも、変換しても出てこない!!
もっとももう二度と入力することはないだろうけど・・・。
こういう方の地道な努力で世の中便利に
快適に暮らせるようになっているのですね。
私はホームページからコピーしただけで読みきれませんでした。というより文章が頭に入ってこないのです。
こういうのがすらすら分かる人がいるんですよね。天才っていうんでしょうね!!
さらには学問に限らず、何かの道を究めた人が求めるものも「美しさ」ではないでしょうか?
それらの美しさを私たちに教えてくれる偉大な人たち(湖の騎士様も含めて)に感謝です。