テレビで「鍋特集」をやっていてその中で奈良県の「飛鳥鍋」というのを紹介していました。文字通り飛鳥時代から伝わる鍋だそうですが、なんと「牛乳鍋」です。そのとき出演者の一人が
「まさに『醍醐味』だね。醍醐というのは『牛乳』のことなんだよ。」
◆醍醐味-物事の本当のおもしろさ、深い味わい。また、仏教で最上の教え。
という程度にしか知らなかったので、早速調べてみました。
「醍醐味(だいごみ)-語源由来辞典」←こちらのページの引用になりますが、
乳を精製する過程の五段階を「五味」と言い、
「乳(にゅう)」
↓
「酪(らく)」
↓
「生酥(しょうそ)」
↓
「熟酥(じゅくそ)」
↓
「醍醐」
の順に上質なものだそうです。そこから「最上の教え」を「醍醐味」。
出典は「涅槃経」
牛より乳を出し 乳より酪を出し 酪より生酥を出し 生酥より熟酥を出し
熟酥より醍醐を出すが如し。
醍醐最上なり。
もし服する者あらば衆病皆除く。
あらゆる諸楽ことごとくその中に入るが如く。
仏もまたかくの如し。
チーズやヨーグルトや生クリーム(これはない?)を飛鳥の時代の人々が食べていたのかと思うと不思議な気分になります。1500年前のチーズなんてのがどこかのお寺に残っていたりして・・・。
「まさに『醍醐味』だね。醍醐というのは『牛乳』のことなんだよ。」
◆醍醐味-物事の本当のおもしろさ、深い味わい。また、仏教で最上の教え。
という程度にしか知らなかったので、早速調べてみました。
「醍醐味(だいごみ)-語源由来辞典」←こちらのページの引用になりますが、
乳を精製する過程の五段階を「五味」と言い、
「乳(にゅう)」
↓
「酪(らく)」
↓
「生酥(しょうそ)」
↓
「熟酥(じゅくそ)」
↓
「醍醐」
の順に上質なものだそうです。そこから「最上の教え」を「醍醐味」。
出典は「涅槃経」
牛より乳を出し 乳より酪を出し 酪より生酥を出し 生酥より熟酥を出し
熟酥より醍醐を出すが如し。
醍醐最上なり。
もし服する者あらば衆病皆除く。
あらゆる諸楽ことごとくその中に入るが如く。
仏もまたかくの如し。
チーズやヨーグルトや生クリーム(これはない?)を飛鳥の時代の人々が食べていたのかと思うと不思議な気分になります。1500年前のチーズなんてのがどこかのお寺に残っていたりして・・・。


















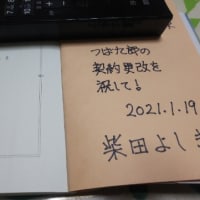


飛鳥時代の人々が牛乳やチーズ、想像するとおかしいですね!
1500年前のチーズ…あったとしても、ブルーチーズもびっくりだと思います
そういえば、お釈迦さんが苦行を終えたとき、苦行以降初めて口にした食べ物が 牛乳だったような気がします。
真偽ははっきりしませんが、牛乳って仏教には深いかかわりがあるんですね。
ちなみに牛乳を指し出した少女の名はスジャータです。
スジャーター スジャーター スジャーアタア~
醍醐味は、お年寄りの間ではまだ多少使われたり、また醍醐寺などのお寺の名前から読める人も若干はいますが、「だいごあじ」なんて読む人も多く寂しい限りです。
所で、モンゴルなどでは、羊の乳からたくさんの発酵製品を作り出していて中国でも食べられていたし、古く日本に入って来たにもにも関わらず、バターもチーズも、記録的には、信長や秀吉、家康が口にした程度の記録が残っている位で、一般の人々の口には殆ど入らなかったのは何故なんでしょうね。
水戸光圀など牧場まで作って牛乳を広めようと試みたと聞いているのに・・。
多くの人達の口に入ったのは、明治以後の事。
何か理由があるのでしょうか?
全然知らなかったです
お勉強になりました
世界の食文化ってすごいですよね。
その地域で生きていく為に発展して
いったんでしょうね。
わたしもせっせと飲まなくちゃ
そのほか旧約聖書のアブラハム、キリスト、マホメットも牛乳(乳製品)を食しているんだとか。
一番古い食品らしいですよ。
ブックマークの件、勝手にごめんね。
それからありがとう!
起源はヨーロッパではなく、アジアだという説もあるくらい古くからモンゴル、中国では乳製品が作られているようですね。
日本にも伝わったのになぜなんでしょうね。
黄門さんは新し物好きなんですね。
新しいわけじゃないのか?(珍しいもの好き?)
大学時代に北海道の友人の家に遊びに行って
搾りたての牛乳をいただいたことがあります。
友人のお母さんに「癖があるから飲めない人もいるよ。」と言われましたが、
私はOK!でした。おいしかった。
なんてたって、友人の家の前は広い牧場で
牛がねそべっている、まさに「牧場の朝」。
最高でした。