神葬祭
2006-06-15 | 日常
初めて神式の葬儀に参列しました。基本的には仏式と変わりませんが、「二礼二拍手一礼」の時の「二拍手」が「しのび手」といって音を立てないようにするというのを初めて知りました。また、焼香はなく、「お洗米」といってお米を研いだものがお皿に入っていて、それをお焼香と同じようにします。
戒名はなく、本名に男性は「命(みこと)」とつけます。神となり、その後、家を守ってくれるそうです。女性は「刀自命(とじのみこと)」または、「姫命(ひめのみこと)」。
日本史で習ったような記憶がかすかにありますが、「神仏習合」「廃仏毀釈」といった言葉で分かるとおり、日本では神道と仏教とが、地域ごと、時代ごとに様々な変遷をしてきたようです。
現在ではこういった儀式はずいぶんと簡略化されていますが、故人をしのぶ気持ちは昔も今も変わらないものです。親しければ親しいほど悲しみは徐々に強くなります。むしろ、葬儀がすんで何日か経った後の方がつらくなるような気がします。人は必ず死を迎えるのですが、「どう死ぬのか」は自分で決められません。ただ、少しでも「自分の死に方」を考えておくことは必要かもしれません。
余談ですが、静岡の中部?では火葬を済ませてから葬儀を行います。これは仏式も同じです。ですから、私は棺桶を前にした葬式の場面はテレビの演出だと思っていました。
戒名はなく、本名に男性は「命(みこと)」とつけます。神となり、その後、家を守ってくれるそうです。女性は「刀自命(とじのみこと)」または、「姫命(ひめのみこと)」。
日本史で習ったような記憶がかすかにありますが、「神仏習合」「廃仏毀釈」といった言葉で分かるとおり、日本では神道と仏教とが、地域ごと、時代ごとに様々な変遷をしてきたようです。
現在ではこういった儀式はずいぶんと簡略化されていますが、故人をしのぶ気持ちは昔も今も変わらないものです。親しければ親しいほど悲しみは徐々に強くなります。むしろ、葬儀がすんで何日か経った後の方がつらくなるような気がします。人は必ず死を迎えるのですが、「どう死ぬのか」は自分で決められません。ただ、少しでも「自分の死に方」を考えておくことは必要かもしれません。
余談ですが、静岡の中部?では火葬を済ませてから葬儀を行います。これは仏式も同じです。ですから、私は棺桶を前にした葬式の場面はテレビの演出だと思っていました。


















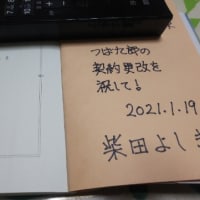


故人の冥福を祈りつつ、時々みんなで思い出話でもしたいと思います。
火葬の後に葬儀となると、なくなったご本人の顔を見ることが出来るのは、近い方達だけなのですか?
葬儀は地方によっても違うのでしょうか。
これからだんだんと葬儀に参列する事も
多くなるんだろうな。
悲しい事が多くなるのは嫌ですね。
もしもなら、サッカーしている途中に、
心臓発作なんてどうかな。
ちょっと不謹慎でした。すみません。
初めてだったので他の人の焼香の仕方をみて粗相のないようにと緊張しました
火葬を済ませてから葬式と言うのははじめて知りました。こちらでは亡くなった時間によっては2昼夜置かれる場合もあります
祖母の場合もそうでしたが、たくさんの方がお別れに来ていただき故人を偲ぶことができました
お通夜に見えた方は顔を見ることができますが、納棺から火葬までは親族と親しい方だけです。
どうしてこのあたりだけそうなのかは、分かりません。機会があったら調べて見たいと思います。
多くなるんだろうな
私も30歳を過ぎた頃からそんな思いが強くなりました。悲しいけれど受け入れていかなければならない現実ですね。
それと例えば
畳の上で死ぬ
臓器を提供する
骨は海に捨てる
といったことも決めておきたいかな。(私がこれらを望んでいるわけではなく、あくまでも例です)
これらは自分だけで決めておいてもどうしようもないので家族とよく話しておく必要があります。「臓器提供」は残された家族にとってはつらいことかもしれませんしね。