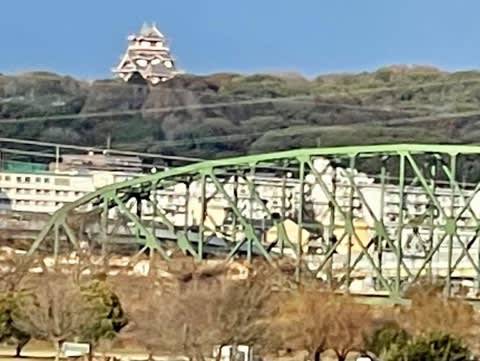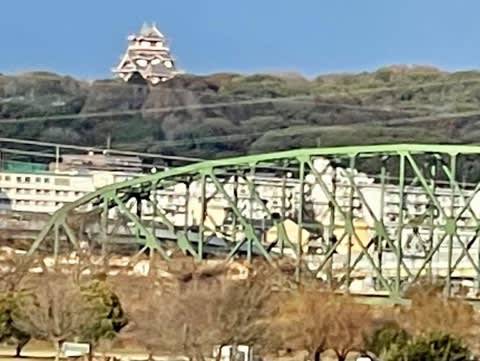「問題だらけの資本主義」がのさばってしまった理由とは――世界的学者が名指しした「意外な真犯人」
デイリー新潮 より 240125 新潮社
1989年に「ベルリンの壁」が崩壊し、共産主義の敗北が決定的になった。
しかしその直後,それまで親米保守の論客として知られていた国際政治学者の高坂正堯氏(1934~1996年)は,意外にも「資本主義批判」ともいえる内容の講演を行った。
[世界産業労働組合によるポスター「資本主義的システムのピラミッド構造(Pyramid of Capitalist System)」(1911)]
【写真】世界的学者が“問題だらけの資本主義”に残した「名言」「自由放任の思想がこれまでのさばってきたのは――」
高坂氏は、アメリカや日本の社会の問題点を次々と指摘しながら、世界的に高名な経済学者ケインズの名言を紹介して、資本主義への自省を強く促した。
高坂氏の「幻の名講演」を初めて書籍化した新刊『歴史としての二十世紀』(新潮選書)から、一部を再編集して紹介する。
***
私も極楽トンボではありませんから、アメリカという相手の病状をつぶさに調べて、その精神状態、身体状態をチェックしなければならないと思っています。
チェックリストの項目を挙げると,まず繁栄の一つの要因であった福祉国家の問題です。
これは経済の論理からいえば、一部の恵まれない人を豊かにし、所得を平均化する機能を果たします。それがうまく機能せず、もっと平均化すべきアメリカでさえ、1920年代と比べて所得は平均化しています。
助けられた人にとって、それが好ましかったかどうかはさておき、社会全体が利益を得ていることは間違いない。
なぜなら、所得の平均化で全体の購買力が上昇するからです。
一部の人が金持ちで、他の大部分が貧乏な場合と、大体がほどほど豊かな場合、後者の方が売れるものは多い。
衣類や食べ物の需要は金持ちも貧乏人もだいたい同じです。いかに豊かでも車を3台買う人は滅多にいない。
それよりは、安物でも90%の人間が1台持つ方が車は売れるわけです。
⚫︎福祉にも負の側面がある
購買力の増大は国内市場の拡大につながり、経済成長が内需により可能になる。
作った商品を売り捌けないから、マーケットを求めて外国に出ていく帝国主義に対して、国内の分配を適度に均等にして国内市場を成長させるべきだという議論です。
これはイギリス労働党中道から出てきましたが、それに則った政策が社会福祉の充実でした。
運悪く落ちこぼれそうになった人を助けるのは、当人だけでなく、社会全体にとってプラスになります。
ひと1人を救うのにどれだけたくさん手間がかかるか想像してください。彼を見守るのに1人、事務方もその人専属ではありませんが誰か必要ですから、それは人員がマイナス1以下になることを意味します。
それでも、病気や貧困に陥ってドロップアウトする人がいないようにする制度は素晴らしいものです。
ただ、助けられた人にとって、100%プラスになるとは限らないことがあります。
それが続くと「助けられ癖」ができるだけでなく、逆に「助けてくれた人を恨む」ことすら起こります。
恵まれない人を助ける効果は全体としては間違いなくプラスですが、被救済者に負の効果を及ぼすケースもあるのです。
「〈いい人〉の政治家が戦争戦争の時代に逆戻りした今、現実主義の視点から「二度の世界大戦」と「冷戦」を振り返る必要がある。
世界恐慌、共産主義、大衆の台頭、文明の衝突……国際政治学者の「幻の名講演」を初の書籍化【解題・細谷雄一】📙『歴史としての二十世紀』(新潮選書)
⚫︎肥大化する政治機能
戦後資本主義は社会福祉を制度内に組み込んで、以前にも増して強固になりました。
だが、問題がないでもない。今の社会が民主主義ならば、国民の力は強いはずです。
しかし、別のものが大きくなっていないでしょうか。
50年前を思い出せば、町役場、市役所、区役所は規模が今の5分の1ぐらいでした。
古い役所と新しい役所、有楽町の旧都庁と新宿の東京都庁を比べれば、庁舎がいかに大きくなったかがわかります。
そして、その分、行政権力も強大になっている一方、当の住民の力が強くなったとはいえない。「みんな」と言いながら、本当のところ役所が大きくなっているのです。
そのように、政治機能がとてつもなく大きくなり、政治家がやらなければいけない仕事は桁外れに増えました。
今の政治家は気の毒です。私は年に2回くらい永田町に行く用事があるので知っていますが、朝7時50分の自民党本部前、日本中であそこほど、人が頻繁に出入りしている場所はありません。
他は警察と自衛隊関連の施設くらいでしょうか。8時前から勉強会、会議に出て、宴会の後帰るのが10時、11時。議会の審議でときどき居眠りでもしなければ身がもたない。
それだけ働いても、彼らが特に優秀になったという話も聞きません。
私は固い信念がありまして、人間の頭が動くのは1日に4時間が限度です。それ以上の頭脳労働は絶対無理です。
仕事は増えて、時間は足りないので、オーバーワークで、頭がズタズタの綿みたいになっているはずです。
寝る暇もないようなオーバーワークをせざるをえない理由は、政治機能の肥大化にあるのです。
現在の東京都庁。古い役所と新しい役所、有楽町の旧都庁と新宿の東京都庁を比べれば、庁舎がいかに大きくなったかがわかる
⚫︎ケインズの名言から考える
福祉国家と民主主義の両立、資本主義の将来性には、依然としてそのような問題が残っていますが、共産主義が潰れたので、資本主義が手放しにいい、ということになってしまいました。
その点については、私が敬愛するケインズによる「自由放任の思想がここまで人々に信用されてきたのは、それを攻撃した社会主義や共産主義の人たちがよほど出来が悪かったからだ」という誰も引用しない名言があります。
半世紀前によくこんな傲慢でありながら鋭い指摘をしたと感心させられますが、今の時代、この意味をもう一度噛み締めるべきでしょう。
ケインズは経済学者ですが、難解な理論は専門家にまかせておいて、彼の素晴らしいのは人物評伝であり、ちょっとした発言であり、さらにその中の批判や悪口です。
「自由放任の思想がこれまでのさばってきたのは、資本主義と自由放任を批判する思想があまりにもくだらなかったから」とは、見事な一刀両断です。
出来の悪い共産主義との対抗関係があったから、自分たちのシステムが本当にいいのか悪いのかを考えるのを怠ってきた。そのことを今こそ考えるべきではないでしょうか。
デイリー新潮編集部