すらすら読める養生訓/立原昭二/講談社
貝原益軒の養生訓の本である。
しかし、どうしても大きな文字で読みたいので、学術的な価値などにこだわらず、この本を選んだ。
読む前から、本の評価をするのは変な話だが、実は本屋で何度か立ち読みしているので内容はわかっているのである。
どうしても座右の書にしたかった本なのだが、どの本も文字が小さく読んでて疲れを覚えたので、この本を見つけてこれだ!と思った。
本の紹介は、私があれこれ言うより、著者の紹介の方がが素晴らしいと思うので、こちらをご紹介させていただく。
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%99%E3%82%89%E3%81%99%E3%82%89%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E9%A4%8A%E7%94%9F%E8%A8%93-%E7%AB%8B%E5%B7%9D-%E6%98%AD%E4%BA%8C/dp/406212582X/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1264763275&sr=1-4
出版社 / 著者からの内容紹介
「養生の術をまなんで、よくわが身をたもつべし。長生きすれば、楽多く益多し」
ここには、長生きするのが養生の目的ではなく、老後を楽しく過ごすために養生をする、という益軒の人生哲学がある。
「養生の術は 先(まず)心気を養うべし」
『養生訓』といえば、からだの養生とすぐ思いがちだが、益軒は心の養生を優先して説いている。それは心身相関の確固とした理念、からだは心によって養われ、心はからだによって養われるという考えからである。だから益軒はまず、「養生の第一歩は心と気を養うことである」、だから「心を和らかにし、気を平らかにし」と説き、「心を養いからだを養う工夫は1つである」と言うのである。<本文より>
内容(「BOOK」データベースより)
「養生の術をまなんで、よくわが身をたもつべし。長生きすれば、楽多く益多し」ここには、長生きするのが養生の目的ではなく、老後を楽しく過ごすために養生をする、という益軒の人生哲学がある。
貝原益軒の養生訓の本である。
しかし、どうしても大きな文字で読みたいので、学術的な価値などにこだわらず、この本を選んだ。
読む前から、本の評価をするのは変な話だが、実は本屋で何度か立ち読みしているので内容はわかっているのである。
どうしても座右の書にしたかった本なのだが、どの本も文字が小さく読んでて疲れを覚えたので、この本を見つけてこれだ!と思った。
本の紹介は、私があれこれ言うより、著者の紹介の方がが素晴らしいと思うので、こちらをご紹介させていただく。
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%99%E3%82%89%E3%81%99%E3%82%89%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E9%A4%8A%E7%94%9F%E8%A8%93-%E7%AB%8B%E5%B7%9D-%E6%98%AD%E4%BA%8C/dp/406212582X/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1264763275&sr=1-4
出版社 / 著者からの内容紹介
「養生の術をまなんで、よくわが身をたもつべし。長生きすれば、楽多く益多し」
ここには、長生きするのが養生の目的ではなく、老後を楽しく過ごすために養生をする、という益軒の人生哲学がある。
「養生の術は 先(まず)心気を養うべし」
『養生訓』といえば、からだの養生とすぐ思いがちだが、益軒は心の養生を優先して説いている。それは心身相関の確固とした理念、からだは心によって養われ、心はからだによって養われるという考えからである。だから益軒はまず、「養生の第一歩は心と気を養うことである」、だから「心を和らかにし、気を平らかにし」と説き、「心を養いからだを養う工夫は1つである」と言うのである。<本文より>
内容(「BOOK」データベースより)
「養生の術をまなんで、よくわが身をたもつべし。長生きすれば、楽多く益多し」ここには、長生きするのが養生の目的ではなく、老後を楽しく過ごすために養生をする、という益軒の人生哲学がある。










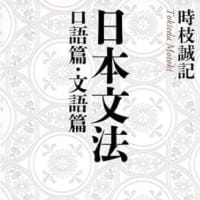




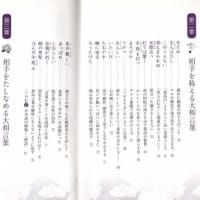
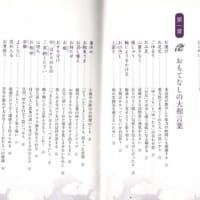
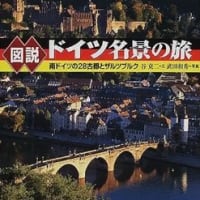
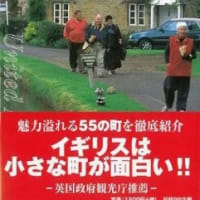
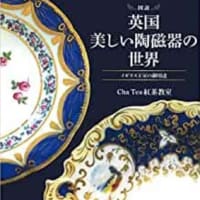






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます