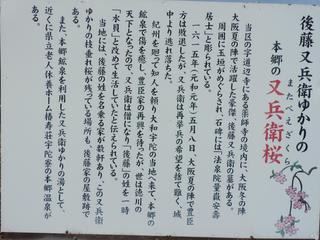奈良県桜井市初瀬にある「長谷寺」は、西国三十三所観音霊場の第八番札所であり、日本でも有数の観音霊場として知られるお寺です。
大和と伊勢を結ぶ初瀬街道を見下ろす、初瀬山の中腹に本堂が建つお寺です。初瀬山は牡丹の名所であり、今150種類以上・7,000株と言われる牡丹が満開になっています。
今回は、牡丹が満開の「花の御寺 長谷寺」を紹介したいと思います。
古くから「花の御寺」と称されてい「長谷寺」は、『枕草子』『源氏物語』『更級日記』など多くの古典文学にも登場するお寺としても有名です。
満開の牡丹と共に、色々な花が咲く「長谷寺」は「花の御寺」と称されるように、とても見応えのあるお寺でした!