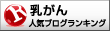私は学生時代のことはよく憶えていない。
もちろん学校へは通ったのだが、何だか当時のことが夢のような、あるいは何かの本で読んだ物語のような、他人事に思えてならない。
もちろん当時もAとかBとかの評価はあったが、最終的には大学進学ということが教師たちの〝目標〟だった。
要するに受験である。
学科の中では国語(英語)が得意だった。
国語の入試問題はいつも出典が決まっていて、私の時はミルトンの『失楽園』とシェークスピアの『あらし』だった。
私はもともとシェークスピアは好きだったが、ミルトンは苦手で、意味のわからないところが多かった。
でも入試ではスラスラと暗誦できて、今でも屋根裏部屋には国語だけは抜群の成績でパスした賞状が残っている。
そのためには私もミルトンを必死になって暗記したものである。
今でもその中からところどころの文章がふっと口をついて出てくることがある。
学生時代の勉強が無駄でなかったことを証明するために一、二節紹介してみよう。
人の心は、今おかれたその場で、
それみずから地獄を天国となし、
天国を地獄となす。
これは女性患者を治療した際に浮かんだ一節である。
その人は腰のあたりに激痛を覚える。
一か月入院してX線をはじめとする徹底的な診察を受けたが、どこにも異常は見当らなかった。
が痛みは本ものである。
本当に痛いのであるが、原因は精神的なものだったのである。
この方はお子さんにも恵まれ、経済的にも困っていない。
本人も「うちは決してお金持ちではありませんが、要るだけのお金はあります」と述べているほどである。
なのに一体何が不満なのか。
それは、家事に追われ、家に縛りつけられていることが不満なのである。
本当は外に出て働きたい。
大勢の人と触れ合いたい。
が、ご主人がそれを許してくれない。
「家を守るのが女の仕事だ」―そう言われて仕方なく買物と料理と掃除と洗濯と育児の毎日を送っている。
その欲求不満が痛みを惹き起こしているのだった。
私のところへ来て治療を受けると、その時は完全とまではいかないが殆んど痛みらしい痛みを感じないまでになる。
が帰宅して二日もするとまた痛みがぶり返す。
ミルトンが言うように彼女の心が〝それみずから天国を地獄となし〟ているのだった。
こうしたケースは決して珍しくない。
少なく見ても訪れる人の半数が、自分の置かれた環境に対する不平不満からどこかに痛みを覚えている。
それを助長するのが取越苦労と罪悪感である。
既成宗教のほとんどが罪と罰の恐ろしさを説いている。
善い行いは報われ、悪いことをすると神が罰を与えると説き、その原理に基いて善と悪の基準をこしらえている。
ところが実際にはその掟に背いた者が必ずしも不幸になっていない。
中にはむしろのびのびと生き甲斐ある人生を送っている者がいる。
そこで宗教家は因果応報は死後に精算されるのだという言い逃れをする。
教義に忠実に従っておれば死後に永遠の生命を授かり、背いた者は永遠の天罰を受けると説く。
英国ではこれが子供時代に教え込まれる。
公立小学校の教科書には聖者や祈祷書からのそれに関する引用が盛り込まれている。
「ですから、皆さんも良い行いをしましょう。
そうすれば死んだ時に天国に召されます。
もし悪いことをしたら罰として地獄へ送られ、永遠の苦しみを受けることになるのです」という結論になる。
むろん生長するにつれて理性的判断力が出てくる。
もっとあか抜けした哲学に触れるチャンスもある。
死後について、永遠の生命について、あるいは因果律について、その真相に目覚める人もいる。
が大半の人は心の奥に子供時代に吹き込まれた永遠の罰に対する恐怖と罪の意識と、それはどうしても避けられないのだという観念が巣くっているのである。
家庭の主婦がもしも自分の生涯の仕事は家事だと思い、夫に尽くすことだと思い、それ以外のことをすることは悪であると思い込んでいるとしたら、その観念はやがて心理学でいう罪責複合(無意識の罪責感)を生む。
これは魂を蝕む恐ろしい観念である。
みずからの心に地獄をこしらえる。
それがまず心の病を生み、それが身体の病気へと発展していく。
その病気の種類は数え切れないほどである。
患者を一、二度治療して何の変化も見られない時は、私はその人の置かれた環境について質問してみる。
すると挫折感、不満のタネ、憤満、取越苦労、罪悪感、等々が浮かび上がってくる。
これだ、と私は睨む。
本当の治療はこれらの心理的要因を取り除くことにある。
つまりその患者にとって本当に必要なのは人生哲学であり、霊的真理の理解なのだ。
そこで私は霊の世界の話を持ち出す。
そういう世界、そういう真理があることを指摘したあと、その世界の存在を明らかにしてくれた先覚者、書物、道標を紹介する。
患者は人生に希望の灯を見出す。
その灯が迷信を生んだ他愛ないタブーや罪の意識を駆逐していく。

もちろん学校へは通ったのだが、何だか当時のことが夢のような、あるいは何かの本で読んだ物語のような、他人事に思えてならない。
もちろん当時もAとかBとかの評価はあったが、最終的には大学進学ということが教師たちの〝目標〟だった。
要するに受験である。
学科の中では国語(英語)が得意だった。
国語の入試問題はいつも出典が決まっていて、私の時はミルトンの『失楽園』とシェークスピアの『あらし』だった。
私はもともとシェークスピアは好きだったが、ミルトンは苦手で、意味のわからないところが多かった。
でも入試ではスラスラと暗誦できて、今でも屋根裏部屋には国語だけは抜群の成績でパスした賞状が残っている。
そのためには私もミルトンを必死になって暗記したものである。
今でもその中からところどころの文章がふっと口をついて出てくることがある。
学生時代の勉強が無駄でなかったことを証明するために一、二節紹介してみよう。
人の心は、今おかれたその場で、
それみずから地獄を天国となし、
天国を地獄となす。
これは女性患者を治療した際に浮かんだ一節である。
その人は腰のあたりに激痛を覚える。
一か月入院してX線をはじめとする徹底的な診察を受けたが、どこにも異常は見当らなかった。
が痛みは本ものである。
本当に痛いのであるが、原因は精神的なものだったのである。
この方はお子さんにも恵まれ、経済的にも困っていない。
本人も「うちは決してお金持ちではありませんが、要るだけのお金はあります」と述べているほどである。
なのに一体何が不満なのか。
それは、家事に追われ、家に縛りつけられていることが不満なのである。
本当は外に出て働きたい。
大勢の人と触れ合いたい。
が、ご主人がそれを許してくれない。
「家を守るのが女の仕事だ」―そう言われて仕方なく買物と料理と掃除と洗濯と育児の毎日を送っている。
その欲求不満が痛みを惹き起こしているのだった。
私のところへ来て治療を受けると、その時は完全とまではいかないが殆んど痛みらしい痛みを感じないまでになる。
が帰宅して二日もするとまた痛みがぶり返す。
ミルトンが言うように彼女の心が〝それみずから天国を地獄となし〟ているのだった。
こうしたケースは決して珍しくない。
少なく見ても訪れる人の半数が、自分の置かれた環境に対する不平不満からどこかに痛みを覚えている。
それを助長するのが取越苦労と罪悪感である。
既成宗教のほとんどが罪と罰の恐ろしさを説いている。
善い行いは報われ、悪いことをすると神が罰を与えると説き、その原理に基いて善と悪の基準をこしらえている。
ところが実際にはその掟に背いた者が必ずしも不幸になっていない。
中にはむしろのびのびと生き甲斐ある人生を送っている者がいる。
そこで宗教家は因果応報は死後に精算されるのだという言い逃れをする。
教義に忠実に従っておれば死後に永遠の生命を授かり、背いた者は永遠の天罰を受けると説く。
英国ではこれが子供時代に教え込まれる。
公立小学校の教科書には聖者や祈祷書からのそれに関する引用が盛り込まれている。
「ですから、皆さんも良い行いをしましょう。
そうすれば死んだ時に天国に召されます。
もし悪いことをしたら罰として地獄へ送られ、永遠の苦しみを受けることになるのです」という結論になる。
むろん生長するにつれて理性的判断力が出てくる。
もっとあか抜けした哲学に触れるチャンスもある。
死後について、永遠の生命について、あるいは因果律について、その真相に目覚める人もいる。
が大半の人は心の奥に子供時代に吹き込まれた永遠の罰に対する恐怖と罪の意識と、それはどうしても避けられないのだという観念が巣くっているのである。
家庭の主婦がもしも自分の生涯の仕事は家事だと思い、夫に尽くすことだと思い、それ以外のことをすることは悪であると思い込んでいるとしたら、その観念はやがて心理学でいう罪責複合(無意識の罪責感)を生む。
これは魂を蝕む恐ろしい観念である。
みずからの心に地獄をこしらえる。
それがまず心の病を生み、それが身体の病気へと発展していく。
その病気の種類は数え切れないほどである。
患者を一、二度治療して何の変化も見られない時は、私はその人の置かれた環境について質問してみる。
すると挫折感、不満のタネ、憤満、取越苦労、罪悪感、等々が浮かび上がってくる。
これだ、と私は睨む。
本当の治療はこれらの心理的要因を取り除くことにある。
つまりその患者にとって本当に必要なのは人生哲学であり、霊的真理の理解なのだ。
そこで私は霊の世界の話を持ち出す。
そういう世界、そういう真理があることを指摘したあと、その世界の存在を明らかにしてくれた先覚者、書物、道標を紹介する。
患者は人生に希望の灯を見出す。
その灯が迷信を生んだ他愛ないタブーや罪の意識を駆逐していく。