8月7日 (水曜日) 晴れ
今日からは”暑中見舞いから残暑見舞い”へ立秋である。
朝方、窓から入り込む風はさわやかで少し冷えた感じであった。
よく観察してみると秋の気配を感じる。
夏の風と秋の涼やかな風が混在し始め、空を見上げれば巻雲なども!
でも8月、夏本番である。
孫君も市民プールに行くらしく、大騒ぎである。
背は伸びて大きいが太らないなあ~!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
永六輔さんがラジオで言っていた。
”8月は 6日9日 15日”
という、説明の必要のない句?が
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
朝日のコラムには
きのうに続き、死者と通じ合うということについて。
来日中の米国のアカデミー賞監督、オリバー・ストーンさんが、
広島の原爆ドームや平和記念資料館を訪れた。
本紙のインタビューに「あの日の瞬間を感じた」と答えている。
☆個人的には広島・長崎・知覧特攻会館に行って観ているが
凝視するのが辛くなって、自然と涙が出てくるのは
私だけではないだろう。
▼感じる力、想像する力が大切というメッセージだ。
「瀕死(ひんし)の被爆者がさまよっていた。
川に浮き沈みする遺体も見えた」。
この後、長崎と沖縄にも行く。
米軍事戦略の最前線で苦しむ沖縄への「連帯」を、かねて語っている。
米軍ヘリが墜落したばかりの現地で何を感じるだろうか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼「生き残った者は、死者の無念を自分自身の生き方として
受け止めなければならない」。
仙台で被災した宗教人類学者、山形孝夫さんの言葉だ。
~~~~~~~~~~~~~~~
近著『黒い海の記憶』の副題は「いま、死者の語りを聞くこと」
▼♪わたしは何を残しただろう……。
☆朝日新聞(12月6日夕刊)に掲載された彼のインタビュー記事
彼が、8歳の時、母親が海で自死したのです。
彼は、母親が独り言のように「死にたい」とつぶやくのを耳にしていたそうです。
でも、彼は、父にも姉にも言えなかった。
母はなぜ死んだんだろう。
身を切られる悲しみは、いつの間にか
遠い出来事として、心から消え去っていって・・・。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
それが、40代になり、修道士たちの聞き取り調査のため
エジプトに行き、砂漠を歩いていたある日、
不意に聞こえてきたのは、 紛れもなく母の声。
忘れたはずの母の存在。
でも、ずぅーっと、自分の心の中で母が生き続けたことを知り、 驚きます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そして、キリスト教への接近、彼の研究の核心には、
母の死があったことを自覚するのです。
彼は、定年間近に、その不思議な経験をエッセーにしました。
(『砂漠の修道院』88年日本エッセイスト・クラブ賞受賞)
書き始めたら、記憶が噴き出して、
母親と交わした言葉、
その時の情景の色や音、匂いまでもがよみがえってきて
涙が止まらなかったそうです。
懐かしい至福の時。
それは、封印していた耐え難い悲しみを
解放した瞬間だったわけです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
山形氏は、語ります。
「悲しみは、人間の成熟に大切な栄養剤です。
悲しみは、新しい生き方に変化する。」
セミナーにいらっしゃるみなさんが素敵なのも、
うなずけました。
~~~~~~~~~
みなさん、必死に悲しみから学ぼうとしているんですね。
みなさん、必死に悲しみを糧に成長しようとしているんですね。
=================
山形さんはNHKの復興支援ソング「花は咲く」の歌詞に目をとめる。
ここで歌っているのは死者ではないか。

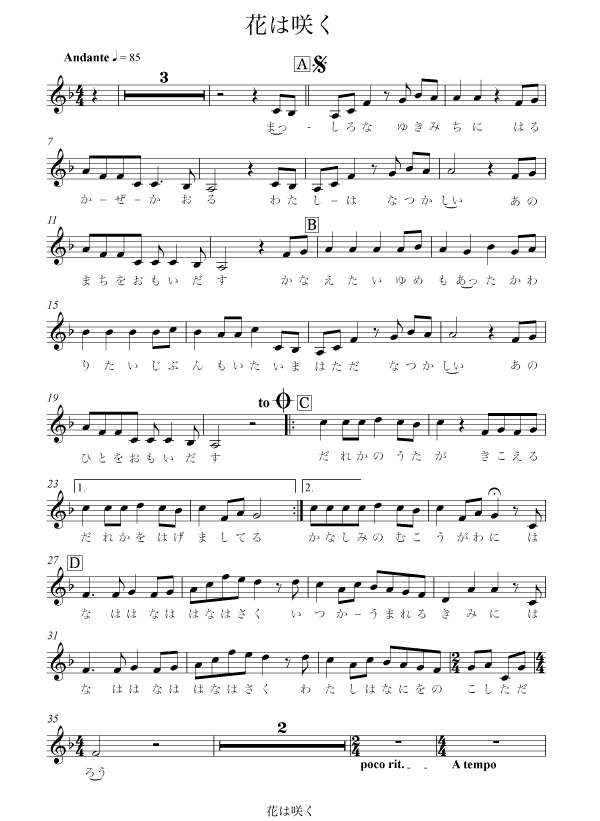
だから、口ずさむとひとりでに涙があふれてくるのだ、と
~~~~~~~~~~~
▼国策のため、繁栄のため、豊かさのためと称して、
過去にどれだけの人々が犠牲にされてきたことか。
戦争も、原爆も、沖縄の基地も、原発事故も。
犠牲を強いる構造に抗(あらが)うには死者と共闘しなければならないと、
山形さんは訴える。
それは「殺すな」の哲学を徹底することだ、と
▼8月、列島の各地で死者の声が聞かれるのだろう。
平和への、未来への思いがこもごも語られるだろう。じっと耳を傾けたい。
20130807
=======================

今日からは”暑中見舞いから残暑見舞い”へ立秋である。

朝方、窓から入り込む風はさわやかで少し冷えた感じであった。
よく観察してみると秋の気配を感じる。
夏の風と秋の涼やかな風が混在し始め、空を見上げれば巻雲なども!
でも8月、夏本番である。

孫君も市民プールに行くらしく、大騒ぎである。

背は伸びて大きいが太らないなあ~!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
永六輔さんがラジオで言っていた。
”8月は 6日9日 15日”
という、説明の必要のない句?が
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
朝日のコラムには
きのうに続き、死者と通じ合うということについて。
来日中の米国のアカデミー賞監督、オリバー・ストーンさんが、
広島の原爆ドームや平和記念資料館を訪れた。
本紙のインタビューに「あの日の瞬間を感じた」と答えている。
☆個人的には広島・長崎・知覧特攻会館に行って観ているが
凝視するのが辛くなって、自然と涙が出てくるのは
私だけではないだろう。

▼感じる力、想像する力が大切というメッセージだ。
「瀕死(ひんし)の被爆者がさまよっていた。
川に浮き沈みする遺体も見えた」。
この後、長崎と沖縄にも行く。
米軍事戦略の最前線で苦しむ沖縄への「連帯」を、かねて語っている。
米軍ヘリが墜落したばかりの現地で何を感じるだろうか?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▼「生き残った者は、死者の無念を自分自身の生き方として
受け止めなければならない」。
仙台で被災した宗教人類学者、山形孝夫さんの言葉だ。
~~~~~~~~~~~~~~~
近著『黒い海の記憶』の副題は「いま、死者の語りを聞くこと」
▼♪わたしは何を残しただろう……。
☆朝日新聞(12月6日夕刊)に掲載された彼のインタビュー記事
彼が、8歳の時、母親が海で自死したのです。
彼は、母親が独り言のように「死にたい」とつぶやくのを耳にしていたそうです。
でも、彼は、父にも姉にも言えなかった。
母はなぜ死んだんだろう。
身を切られる悲しみは、いつの間にか
遠い出来事として、心から消え去っていって・・・。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
それが、40代になり、修道士たちの聞き取り調査のため
エジプトに行き、砂漠を歩いていたある日、
不意に聞こえてきたのは、 紛れもなく母の声。
忘れたはずの母の存在。
でも、ずぅーっと、自分の心の中で母が生き続けたことを知り、 驚きます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そして、キリスト教への接近、彼の研究の核心には、
母の死があったことを自覚するのです。
彼は、定年間近に、その不思議な経験をエッセーにしました。
(『砂漠の修道院』88年日本エッセイスト・クラブ賞受賞)
書き始めたら、記憶が噴き出して、
母親と交わした言葉、
その時の情景の色や音、匂いまでもがよみがえってきて
涙が止まらなかったそうです。
懐かしい至福の時。
それは、封印していた耐え難い悲しみを
解放した瞬間だったわけです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
山形氏は、語ります。
「悲しみは、人間の成熟に大切な栄養剤です。
悲しみは、新しい生き方に変化する。」
セミナーにいらっしゃるみなさんが素敵なのも、
うなずけました。
~~~~~~~~~
みなさん、必死に悲しみから学ぼうとしているんですね。
みなさん、必死に悲しみを糧に成長しようとしているんですね。
=================
山形さんはNHKの復興支援ソング「花は咲く」の歌詞に目をとめる。
ここで歌っているのは死者ではないか。

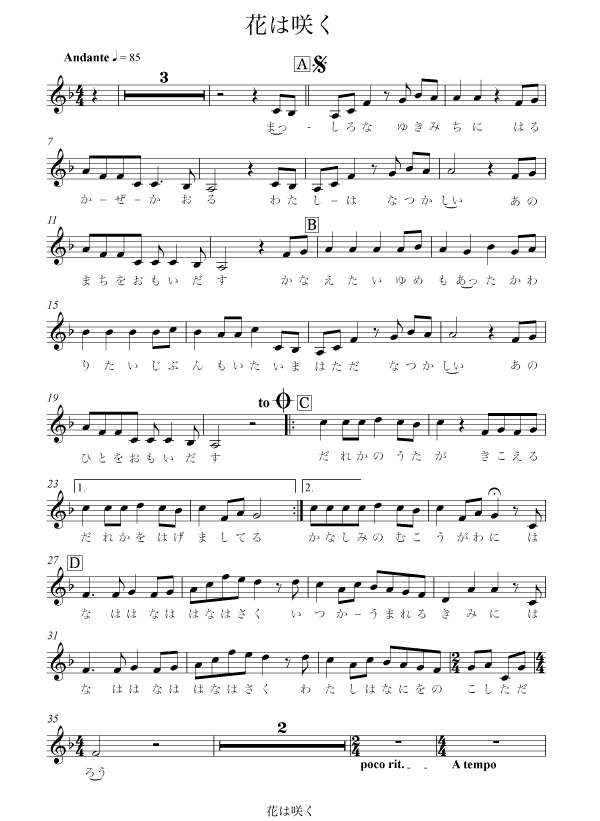
だから、口ずさむとひとりでに涙があふれてくるのだ、と
~~~~~~~~~~~
▼国策のため、繁栄のため、豊かさのためと称して、
過去にどれだけの人々が犠牲にされてきたことか。
戦争も、原爆も、沖縄の基地も、原発事故も。
犠牲を強いる構造に抗(あらが)うには死者と共闘しなければならないと、
山形さんは訴える。
それは「殺すな」の哲学を徹底することだ、と
▼8月、列島の各地で死者の声が聞かれるのだろう。
平和への、未来への思いがこもごも語られるだろう。じっと耳を傾けたい。
20130807
=======================









