日野宿を出た私たち、旅の仲間一行はまずは日野台へと続く長い坂道を登ってゆきます。
【大坂上通り(日野駅北側)】

日野宿の西のはずれにある坂下地蔵(西の地蔵)から先、旧来の街道は線路で分断されて渡れませんので、一旦戻ってJR中央線の高架をくぐり線路の反対側(北側)へ出ます。
そこから日野駅のホームに沿って、大坂上通りを歩いていきます。
写真の左側がちょど日野駅のホームになります。かつての街道は踏切で線路を渡り、途中でこの大坂上通りに合流していました。
【大坂上通り・中央自動車道下】

けっこう勾配のある坂道が続いていきます。
正面の高架が中央自動車道。その下をくぐり、今年一番の暑さの中、坂道を上ります。
長閑な雰囲気ですけどね…暑さに坂道はちょっとキツイ。
【日野台】

坂道を上りきってしばらく歩くと、都道256号線に再び合流します。長閑な雰囲気から一転、交通量は激増です。
この辺りは多摩川の河岸段丘上で、日野台(古くは日野台地)と呼ばれています。河岸段丘をえっちらおっちら、上ってきたわけですね。
【上人塚(日野自動車敷地内)】

都道256号に合流してすぐ、街道沿いに日野自動車の広大な敷地が広がっています。
この日野自動車の敷地内に、上人塚と呼ばれる塚があります。普段は見ることはできませんが、年に1回、東京都文化財ウィークに合わせてのイベントで公開されるのだとか。
で、上人塚。
実は私、もうずいぶん前になりますが、見たことがあります。盛り土がされた小さな古墳?みたいなイメージでした。
日野用水を開削した佐藤隼人を称えて造られたとも、この地が荒れ地だったころ、狐が上人に化けて人をたぶらかしたことに由来するとも言われています。
古い本には、烽火台かもしれないとも記されていました。そもそも日野という地名は、烽火台があった土地を意味する飛火野からきているといわれています。河岸段丘上のこの辺りだったら、烽火台を築くには絶好のロケーションだったのでしょうね。
【日野台の一里塚】

江戸から10里目の一里塚。日野自動車のフェンスに説明文が掛かっていますが、それ以外には何もなし。昭和30、40年代までは塚の痕跡が残っていたようですが、今は住宅地に変わってしまっています。もう少し西へ進むと一里塚公園があるようですが、今回はパス。
8里目の本宿、9里目の万願寺と、ふたつ一里塚を見ていないので、お久しぶり~って感じです。
【日野市から八王子市へ】

日野台の一里塚を過ぎてしばらくすると、いよいよ八王子市。でも宿場まではまだまだ距離があります。
【八王子市高倉町付近の甲州街道】

かつてこの辺りは高倉野とか高倉原と呼ばれ、それこそ草茫々の地だったそうです。狐が上人に化け、狸がポンポコリンを踊るだけならまだしも、追剥や野党が跋扈する魑魅魍魎、物騒な場所だったとか。
江戸時代中期(享保年間ころ)に新田開発が行われ、集落ができました。粟須新田(八王子の粟之須村からの移住)と日野本郷新田(日野からの移住)です。その後、街道沿いに茶屋なども出来て、休憩する旅人もあったようです。
粟須新田は戸数21、日野本郷新田は戸数7。多いのか少ないのか、どうでしょうか?
【お屋敷】

街道沿いに立派な門の家がけっこうあります。
高倉野にできた新田の名主さんのお屋敷かな?なんて想像しながら歩くのも楽しいものです。
【高倉稲荷神社】

1718(享保3)年に建てられた高倉新田の鎮守様とのこと。それ以上の情報はネットで調べてもヒットしませんでした。
高倉新田、先ほどの高倉野にできた粟須新田と日野本郷新田の総称のことでしょうね。まさにふたつの新田が開発されたのとぴったり一致する創建年代です。
【高倉稲荷神社・社殿】

境内はシーンと静まり返っていました。木々が木陰を作っていて、まさに村の鎮守様って雰囲気です。
【火の見櫓】

高倉稲荷神社の横に、今はあまり見なくなった火の見櫓が建っています。
子供の頃、どこにでも普通に火の見櫓ってあった気がしますが、もう最近はそんなもの使わないのでしょうね。いつの日か、火の見櫓を文化財に指定にしよう!なんて動きも出てくるのかな?














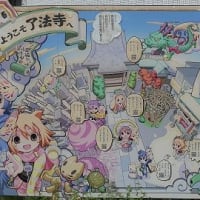





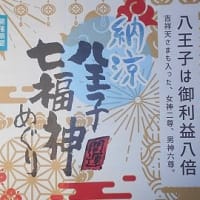
みんなのブログからきました。
詩を書いています・・・よろしくお願いします。
甲州街道を歩く旅、基本的に月に1回、真夏と真冬は避けているため、いったい山梨に入るのはいつになることやら…。
気長に歩いていきます。