
昨夜はチェリビダッケの命日でもあったが、ベームを書いて後は日付変更線を越えて書けなかった。それで、一日遅れのチェリ記事。
チェリビダッケの思い出話は、このブログのあちらこちらに、同じ事を何度も書いていると思う。
最初の衝撃は1974年夏のFM放送で。その後、年に数回のFMライヴはひとつひとつが印象深い。
実演は、1977年初来日、78年の2度目の来日。80年、ロンドン響との大阪での2日間。そこから10年飛んで90年、大阪でのブル8。93年、名古屋でのハイドンと「悲愴」、大阪でのブル4。
今回は、1978年3月、読響への2度目の客演を聴いた思い出を・・・。
プログラムは・・・
会場は神奈川県民ホールだった。
以下は、まことにオハズカシイけど当時の日記から・・・・
1978年3月19日(日)晴れ
15日に東京に行った。
予定では16日に出て、18日の朝に帰るつもりだったがN村君からTel.があり、「チェリビダッケの練習が聴ける」とのことで一日早く行った由。
セルジュ・チェリビダッケの練習と次の日の本番。
これは久しく記憶にこびりついていることだろう。
モーツァルト(ジュピター)の、驚くべき透明な響き、第2楽章の超名演、トリスタンも、すごく感動した。
そして、レスピーギのフィナーレの猛烈なffff!!!
以後これらの曲の違う演奏を・・・(あまりにハズカシイので省略)・・・・ではないだろうか。
東京ではN村君宅、タケマサの下宿に泊り、演奏会当日にドリーム号(国鉄の夜行バス)で帰った。
昨日は伊勢混の演奏会があったし、今日はTVで小沢ボストンの「幻想sym」をやっていた。(日記引用、ここまで)
・・・とまあ、ね、東京(横浜)から帰ってからの日記であり、どうにもこうにも晒すのにためらわれる部分もあるのだが、とにかく、半年ぶりに読響を振った演奏会は、初回以上のインパクトだった。
「ジュピター」は、全体に音量かなり控えめな中での非常に繊細で透明な演奏だった。
それでも、第1楽章では、オケの鳴りがイマイチの感もあり、音楽が「痩せた」感じもしたが、第2楽章の思いっきりロマンティックに歌うのには驚いた。
出だしの動機が2回短い和音で切られた後の三回目、今度は長いハーモニーの中にメロディが溶け込んでいく所の、まるで「無に吸い込まれていく」みたいなディミヌエンド。以降、後年のチェリでも聴いたことがないような遅く歌いきっていく第2楽章だった。
本当に、後にも先にも、あんなジュピターの第2楽章は聴いたことがない。
転じて第3楽章、第4楽章では、速い目のテンポ、軽量級のオケ・バランスで進み、特に終楽章の清々しさは渓流の如く肌にぴりりと、しかし熱く流れていった。
チェリビダッケは、ここではあまり体を動かさず、上体のわずかな動きと例の緻密な腕や指の動きでオーケストラの中に「独自の世界」を創っていくようだった。
「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死は、74年に衝撃的なFMライヴを聴いており、どうしても「あの感動をもう一度」と期待してしまった。
指揮台に上がったチェリがお辞儀を済ませて、さっとオーケストラの方に向き直った時、燕尾服の裾が指揮台の手すりに乗っかったままだった。彼は気付かず棒を構え、緊張をはらんだ静寂の中から曲が始まった。
私は、彼の燕尾服の裾が、いつ手すりのバーから滑り落ちるのかと、そんなことが気になって純粋に演奏に没入できなかった。
もう一つ没入できなかったことは、先のFM放送で、彼はこの曲のクライマックスで、とんでもない大声を出していたのだが、今日この会場でも、あの箇所で、やはり彼はあのように叫ぶのだろうかという期待と「いや、そんなこと、どうでもええやないか」という相反する気持ちが入り混じって、それで、どうも没入できないうちに曲は進んでいった。
で、その箇所でどうだったのかと言うと、少なくとも、私の席には、彼の声は聞こえなかった(と思う)。
だから、「愛の死」の方の、響きがどんどん澄んで昇華していくあたりは、私はよく覚えている。
圧倒的だったのは「ローマの松」。
これは、もう、今までにも「松」を語るたびに、同じようなことを書いているけども、これは本当に凄かった。
とにかくオーケストラの演奏会で、あんなに圧倒され興奮させられたのは、ほかに数えるほどしかない。
彼の指揮では音量の増加にとてつもないエネルギーが感じられ、物理的な音量差以上に、内面的な力感とでも言うようなインパクトがあった。
リハの日の夜は、東京文化会館で小澤征爾指揮ボストン響が、この「ローマの松」を演奏した。桐朋学園の別動隊が通路に立ち、最後は音の洪水の有様だったそうだが、それを会場で聴いていた知人は、昼間に聴いたチェリのリハーサルでの演奏を思い出し、そのあまりの違いに涙が出てきたと言った。
小澤ボストンの「松」も悪くはなかったのだろうが、チェリビダッケの演奏と比べると、あまりに野放図で楽天的に聴こえたらしい。そのことを彼女は「チェリのフォルティシモにはもっと『心がこもっていた』」と言った。
雑誌「音楽現代」78年5月号に、木下晃氏が原稿を寄せている。(以下、引用)
・・・(前略)・・・きらめくばかりの色彩が最弱音にかわり、ゆっくりとやがて大地を揺るがすような歩みへと向かった。「ローマの松」。すざまじいばかりのエネルギーの奔出。その持続力と集中力はまるで全能の神々の行進を聞く思いであった。たまたま客席に来ていたフルートの名手、オーレル・ニコレも「ブラボー!チェリビダッケ!」と叫んでいた。・・・(中略)・・・音楽界、というより批評の世界では、チェリビダッケの評価をめぐって二分された観がある。しかし、このことだけは確実にいえる。チェリビダッケは、読売日響の楽員や聴衆の心にある音楽を引き出そうとつとめたのであり、自分の音楽観を押しつけたのではない。そして圧倒的多数の聴衆はそのことを実感したのである。・・・(後略)

終演後、サインの列に並び、急いで東京まで戻り、ギリギリ間に合った夜行バスで帰路についた。

チェリビダッケの思い出話は、このブログのあちらこちらに、同じ事を何度も書いていると思う。
最初の衝撃は1974年夏のFM放送で。その後、年に数回のFMライヴはひとつひとつが印象深い。
実演は、1977年初来日、78年の2度目の来日。80年、ロンドン響との大阪での2日間。そこから10年飛んで90年、大阪でのブル8。93年、名古屋でのハイドンと「悲愴」、大阪でのブル4。
今回は、1978年3月、読響への2度目の客演を聴いた思い出を・・・。
プログラムは・・・
モーツァルトの交響曲第41番「ジュピター」
ワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死
レスピーギ/交響詩「ローマの松」
ワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死
レスピーギ/交響詩「ローマの松」
会場は神奈川県民ホールだった。
以下は、まことにオハズカシイけど当時の日記から・・・・
1978年3月19日(日)晴れ
15日に東京に行った。
予定では16日に出て、18日の朝に帰るつもりだったがN村君からTel.があり、「チェリビダッケの練習が聴ける」とのことで一日早く行った由。
セルジュ・チェリビダッケの練習と次の日の本番。
これは久しく記憶にこびりついていることだろう。
モーツァルト(ジュピター)の、驚くべき透明な響き、第2楽章の超名演、トリスタンも、すごく感動した。
そして、レスピーギのフィナーレの猛烈なffff!!!
以後これらの曲の違う演奏を・・・(あまりにハズカシイので省略)・・・・ではないだろうか。
東京ではN村君宅、タケマサの下宿に泊り、演奏会当日にドリーム号(国鉄の夜行バス)で帰った。
昨日は伊勢混の演奏会があったし、今日はTVで小沢ボストンの「幻想sym」をやっていた。(日記引用、ここまで)
・・・とまあ、ね、東京(横浜)から帰ってからの日記であり、どうにもこうにも晒すのにためらわれる部分もあるのだが、とにかく、半年ぶりに読響を振った演奏会は、初回以上のインパクトだった。
「ジュピター」は、全体に音量かなり控えめな中での非常に繊細で透明な演奏だった。
それでも、第1楽章では、オケの鳴りがイマイチの感もあり、音楽が「痩せた」感じもしたが、第2楽章の思いっきりロマンティックに歌うのには驚いた。
出だしの動機が2回短い和音で切られた後の三回目、今度は長いハーモニーの中にメロディが溶け込んでいく所の、まるで「無に吸い込まれていく」みたいなディミヌエンド。以降、後年のチェリでも聴いたことがないような遅く歌いきっていく第2楽章だった。
本当に、後にも先にも、あんなジュピターの第2楽章は聴いたことがない。
転じて第3楽章、第4楽章では、速い目のテンポ、軽量級のオケ・バランスで進み、特に終楽章の清々しさは渓流の如く肌にぴりりと、しかし熱く流れていった。
チェリビダッケは、ここではあまり体を動かさず、上体のわずかな動きと例の緻密な腕や指の動きでオーケストラの中に「独自の世界」を創っていくようだった。
「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死は、74年に衝撃的なFMライヴを聴いており、どうしても「あの感動をもう一度」と期待してしまった。
指揮台に上がったチェリがお辞儀を済ませて、さっとオーケストラの方に向き直った時、燕尾服の裾が指揮台の手すりに乗っかったままだった。彼は気付かず棒を構え、緊張をはらんだ静寂の中から曲が始まった。
私は、彼の燕尾服の裾が、いつ手すりのバーから滑り落ちるのかと、そんなことが気になって純粋に演奏に没入できなかった。
もう一つ没入できなかったことは、先のFM放送で、彼はこの曲のクライマックスで、とんでもない大声を出していたのだが、今日この会場でも、あの箇所で、やはり彼はあのように叫ぶのだろうかという期待と「いや、そんなこと、どうでもええやないか」という相反する気持ちが入り混じって、それで、どうも没入できないうちに曲は進んでいった。
で、その箇所でどうだったのかと言うと、少なくとも、私の席には、彼の声は聞こえなかった(と思う)。
だから、「愛の死」の方の、響きがどんどん澄んで昇華していくあたりは、私はよく覚えている。
圧倒的だったのは「ローマの松」。
これは、もう、今までにも「松」を語るたびに、同じようなことを書いているけども、これは本当に凄かった。
とにかくオーケストラの演奏会で、あんなに圧倒され興奮させられたのは、ほかに数えるほどしかない。
彼の指揮では音量の増加にとてつもないエネルギーが感じられ、物理的な音量差以上に、内面的な力感とでも言うようなインパクトがあった。
リハの日の夜は、東京文化会館で小澤征爾指揮ボストン響が、この「ローマの松」を演奏した。桐朋学園の別動隊が通路に立ち、最後は音の洪水の有様だったそうだが、それを会場で聴いていた知人は、昼間に聴いたチェリのリハーサルでの演奏を思い出し、そのあまりの違いに涙が出てきたと言った。
小澤ボストンの「松」も悪くはなかったのだろうが、チェリビダッケの演奏と比べると、あまりに野放図で楽天的に聴こえたらしい。そのことを彼女は「チェリのフォルティシモにはもっと『心がこもっていた』」と言った。
雑誌「音楽現代」78年5月号に、木下晃氏が原稿を寄せている。(以下、引用)
・・・(前略)・・・きらめくばかりの色彩が最弱音にかわり、ゆっくりとやがて大地を揺るがすような歩みへと向かった。「ローマの松」。すざまじいばかりのエネルギーの奔出。その持続力と集中力はまるで全能の神々の行進を聞く思いであった。たまたま客席に来ていたフルートの名手、オーレル・ニコレも「ブラボー!チェリビダッケ!」と叫んでいた。・・・(中略)・・・音楽界、というより批評の世界では、チェリビダッケの評価をめぐって二分された観がある。しかし、このことだけは確実にいえる。チェリビダッケは、読売日響の楽員や聴衆の心にある音楽を引き出そうとつとめたのであり、自分の音楽観を押しつけたのではない。そして圧倒的多数の聴衆はそのことを実感したのである。・・・(後略)

終演後、サインの列に並び、急いで東京まで戻り、ギリギリ間に合った夜行バスで帰路についた。













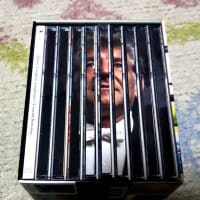

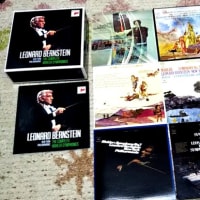
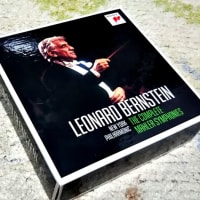

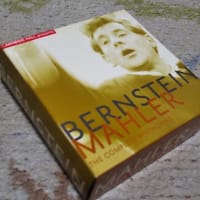

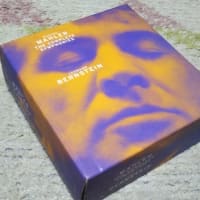


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます