
昨日は、午前中は次男の施設にて保護者面談。
昼に自宅に帰って、一息ついたあと、津市のコンサートに出向きました。
前から楽しみにしていた上岡氏指揮新日フィルです。
午後2時からの公開練習には残念ながら間に合わず、本番を聴かせてもらいました。
新日本フィルハーモニー交響楽団
上岡敏之音楽監督就任披露演奏会
♪♪♪♪プログラム♪♪♪♪
ベートーヴェン/交響曲第1番 ハ長調 op.21
モーツァルト/ファゴット協奏曲 変ロ長調 K.191
ファゴット:河村幹子(新日本フィル 首席ファゴット奏者)
休憩20分
シューマン/交響曲第2番 ハ長調 op.61
アンコール/モーツァルト/交響曲第41番「ジュピター」より第4楽章
三重県文化会館 大ホール
2017.03.19(sun.)16:00開演
上岡さんの指揮を実際に聴くのは初めて。
とても楽しみにしていた演奏会でした。
ベートーヴェンは出だしを聴いた瞬間は「重厚アプローチ?」と思いましたが、主部に入ると、なんとも快活でキラキラした演奏に。
私の聴いていた場所(2階席下手側前方)では、弦の細かい動きが残響にまみれてやや聴き取りにくかったのですが、はっきり聞こえていればさぞやスリリングで気持ちよかったかと思いました。
氏の指揮はちょっと「カルロス・クライバー系」(?)の表情豊かなもので、私は半分くらい目を閉じて聴いていました。
リピート後の提示部に抉りが感じられ、なんか耳をそばだてざるを得ない雰囲気に。
第1楽章が華々しく終わったら会場から拍手が・・・!
いくら三重県津市とは言え、さすがにこういうの最近は久しく経験してしなかったのですが、でも、高揚感に素直に反応したという感じで悪くはなかった。
第2楽章は速いテンポで美しく軽やかで匂うように進みました。
弱音部の絶妙なバランスと音色の美しさが際立っていました。
第3楽章も快速。聴いていて本当に気持ちいい。
最後の和音はすぅっとディミヌエンドして消え、終楽章にすぐ突入せずに一服。
そのあと始まった終楽章は、序奏はもったいぶらず、音をやや短く刈り込んで、まるでピクニックに行くような軽やかな雰囲気が新鮮だなぁと思っていたら続く主部は超快速。
デカ過ぎず細過ぎず、躍動感と美しさをふりまいたベト1でした。
モーツァルトのファゴット協奏曲は、実はあまり家で聴いておりません。ほかの管楽器協奏曲はけっこう聴いているのにね。
やはり、この曲もモーツァルトの魅力ある名曲であります。
ファゴットの幅広く暖かい音色と、人数絞って透明度を増したオーケストラとのコントラストがすばらしかった。
河村さんのファゴット、安定感のある柔らかい響きと豊かな音量で、当然ながらカデンツァでは会場は水を打ったような静けさに。
そして上岡さんの指揮、特に第2楽章後半でのピアニシモ多用がゾクゾクしました。
休憩後はシューマン2番。
聴く前からワクワクです。
冒頭の金管の長いフレーズの下(裏?)で鳴っている弦や木管のデリケイトな表情がとても新鮮で、「なんて魅力的な曲なんや!」と思いながら聴いていました。
開始後わずか数十秒の間に、なんとも多くのものが詰まっていて、そして、それらが呼応し合っていながら全体としては融合していて、そして美しい。
ディスクなどで何度も聴いている2番ですが、この冒頭部分にこんな奥深さを感じたのは初めてでした。
私はドイツに行ったことはないし「ドイツ的」とかよく見聞きするものの、それがどんなものなのかよく分らないのですが、ひょっとして、今聴いているみたいなのがドイツ的というものなのかな?などと思ったりもしました。
その後は、例によって上岡氏のアグレッシヴかつ天衣無縫的な指揮にて第2楽章まで一気に聴き進んだ感じ。
第3楽章では不覚にも(朝からのバタバタの疲れか?)最後の数分、睡魔に襲われました。しかし終楽章開始前にしっかり覚醒し、この魅力的な楽曲をしっかり堪能しました。
終楽章の例のパウゼをけっこう長い目に取ったりして、なかなかやりますやん。
アンコールはうれしいジュピター終楽章、快速版。
コンサート・マスターは崔 文洙(チェ・ムンス)氏。先月の大阪フィルに続いてお世話になりました(?)。

新日フィルは毎年三重県(津市)に来てくれていますが、地域拠点契約というのを結んでいるそうで、今年で20周年になるそうです。
日本センチュリー響も毎年来てくれますが、どちらも、こういう関係を絶やさず、ずっと続けていってほしいと願っています。
昼に自宅に帰って、一息ついたあと、津市のコンサートに出向きました。
前から楽しみにしていた上岡氏指揮新日フィルです。
午後2時からの公開練習には残念ながら間に合わず、本番を聴かせてもらいました。
新日本フィルハーモニー交響楽団
上岡敏之音楽監督就任披露演奏会
♪♪♪♪プログラム♪♪♪♪
ベートーヴェン/交響曲第1番 ハ長調 op.21
モーツァルト/ファゴット協奏曲 変ロ長調 K.191
ファゴット:河村幹子(新日本フィル 首席ファゴット奏者)
休憩20分
シューマン/交響曲第2番 ハ長調 op.61
アンコール/モーツァルト/交響曲第41番「ジュピター」より第4楽章
三重県文化会館 大ホール
2017.03.19(sun.)16:00開演
上岡さんの指揮を実際に聴くのは初めて。
とても楽しみにしていた演奏会でした。
ベートーヴェンは出だしを聴いた瞬間は「重厚アプローチ?」と思いましたが、主部に入ると、なんとも快活でキラキラした演奏に。
私の聴いていた場所(2階席下手側前方)では、弦の細かい動きが残響にまみれてやや聴き取りにくかったのですが、はっきり聞こえていればさぞやスリリングで気持ちよかったかと思いました。
氏の指揮はちょっと「カルロス・クライバー系」(?)の表情豊かなもので、私は半分くらい目を閉じて聴いていました。
リピート後の提示部に抉りが感じられ、なんか耳をそばだてざるを得ない雰囲気に。
第1楽章が華々しく終わったら会場から拍手が・・・!
いくら三重県津市とは言え、さすがにこういうの最近は久しく経験してしなかったのですが、でも、高揚感に素直に反応したという感じで悪くはなかった。
第2楽章は速いテンポで美しく軽やかで匂うように進みました。
弱音部の絶妙なバランスと音色の美しさが際立っていました。
第3楽章も快速。聴いていて本当に気持ちいい。
最後の和音はすぅっとディミヌエンドして消え、終楽章にすぐ突入せずに一服。
そのあと始まった終楽章は、序奏はもったいぶらず、音をやや短く刈り込んで、まるでピクニックに行くような軽やかな雰囲気が新鮮だなぁと思っていたら続く主部は超快速。
デカ過ぎず細過ぎず、躍動感と美しさをふりまいたベト1でした。
モーツァルトのファゴット協奏曲は、実はあまり家で聴いておりません。ほかの管楽器協奏曲はけっこう聴いているのにね。
やはり、この曲もモーツァルトの魅力ある名曲であります。
ファゴットの幅広く暖かい音色と、人数絞って透明度を増したオーケストラとのコントラストがすばらしかった。
河村さんのファゴット、安定感のある柔らかい響きと豊かな音量で、当然ながらカデンツァでは会場は水を打ったような静けさに。
そして上岡さんの指揮、特に第2楽章後半でのピアニシモ多用がゾクゾクしました。
休憩後はシューマン2番。
聴く前からワクワクです。
冒頭の金管の長いフレーズの下(裏?)で鳴っている弦や木管のデリケイトな表情がとても新鮮で、「なんて魅力的な曲なんや!」と思いながら聴いていました。
開始後わずか数十秒の間に、なんとも多くのものが詰まっていて、そして、それらが呼応し合っていながら全体としては融合していて、そして美しい。
ディスクなどで何度も聴いている2番ですが、この冒頭部分にこんな奥深さを感じたのは初めてでした。
私はドイツに行ったことはないし「ドイツ的」とかよく見聞きするものの、それがどんなものなのかよく分らないのですが、ひょっとして、今聴いているみたいなのがドイツ的というものなのかな?などと思ったりもしました。
その後は、例によって上岡氏のアグレッシヴかつ天衣無縫的な指揮にて第2楽章まで一気に聴き進んだ感じ。
第3楽章では不覚にも(朝からのバタバタの疲れか?)最後の数分、睡魔に襲われました。しかし終楽章開始前にしっかり覚醒し、この魅力的な楽曲をしっかり堪能しました。
終楽章の例のパウゼをけっこう長い目に取ったりして、なかなかやりますやん。
アンコールはうれしいジュピター終楽章、快速版。
コンサート・マスターは崔 文洙(チェ・ムンス)氏。先月の大阪フィルに続いてお世話になりました(?)。

新日フィルは毎年三重県(津市)に来てくれていますが、地域拠点契約というのを結んでいるそうで、今年で20周年になるそうです。
日本センチュリー響も毎年来てくれますが、どちらも、こういう関係を絶やさず、ずっと続けていってほしいと願っています。












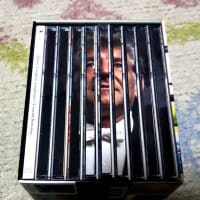

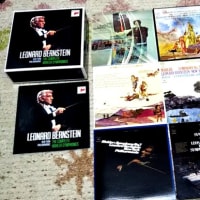
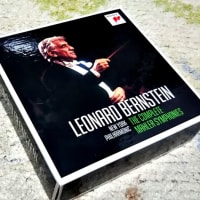

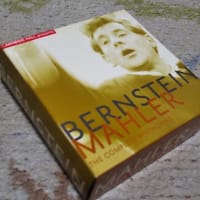

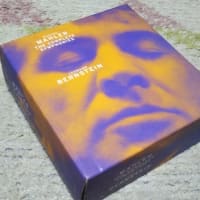


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます