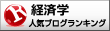最近ある読書会で、徳田秋声の『あらくれ』を扱った。その報告を兼ねて、当作品を論じてみたい。だから当論には、読書会に参加した方々のもろもとの意見や見識が織り込まれていることをあらかじめお断りしておきたい。ただし、文責がすべて私に存することはいうまでもない。
以下を読んで、みなさんに、『あらくれ』を読む楽しみが増えた、あるいは、読んだことはあるがかくかくしかじかのことは気づかなかった、と思っていただければ、これに勝る喜びはない。
その1 『あらくれ』の概要
『あらくれ』は、1915年(大正四年)の一月から七月まで「読売新聞」に連載された。また、単行本として年内に新潮社から刊行されている。秋声、四五歳のときである。新聞連載後すぐに単行本になったくらいだから、連載中はおおむね好評だったのだろう。むろん、秋声はいわゆる流行作家の部類に入る人ではない。
作品世界の時代背景について触れよう。六三節の「その頃初(ママ)まった外国との戦争」という文言が日露戦争を指しているものと思われることや、九二節の「そのころ開かれてあった博覧会」が、一九〇七年(明治四〇年)の東京勧業博覧会を指しているものと思われることなどから、当作品は、おおよそ一九〇〇年(明治三三年)から一九一〇~十一年(明治四三~四四年)まで、主人公のお島の年齢で言えば一八歳から二九~三〇歳までの一〇年間ほどを扱っている。
教科書的な言い方になるが、日本資本主義は、一八九四年の日清戦争の前後に第一次産業革命を成し遂げて軽工業部門を充実させ、十九〇四年の日露戦争の前後に第二次産業革命を成し遂げて重工業部門を充実させた。北九州市の八幡製鉄所が操業し始めたのが一九〇二年である。また日本は、日露戦争ではじめて近代総力戦なるものを経験している。
このことを勘案するならば、お島は、日本が本格的に近代化の道を歩みはじめる真っ只中を体ごとでがむしゃらに駆け抜けたことになる。お島がそのことを意識していないのは確かであるが、そのことがお島の有為転変に深い影を落としているのもこれまた確かなことなのである。時代は、すなわち、歴史は、お島の身振りの隅々にまでその振動を伝えているのである。それを軽く見積もって、解説文(大杉重男)中にあるように、「この小説は、しかし決して一人の女性の『歴史』ではなく、むしろ『歴史』への抵抗の荒々しいドキュメントである」などと蓮實重彦的な小さな知識人村のなかで自己満足的に言挙げするのは間違っている。つまらないことでもある。幼稚であるとさえ言えよう。なぜなら、当時の人々は、上記の時代の振動を当然のこととして感じ取りながら、この作品を読んだはずであるからだ。また、その振動を我が事として感じ取ることができなくなった私たちが、それをいささかなりとも感じ取ることができる隘路を見つけ出すことは、「読む」という営為に自ずと織り込まれることになるからだ。それを言葉の上でだけ拒否してみても何の意味もない。当たり前のことである。
その2 登場人物
〔お島〕主人公。実母から「暴(あら)い怒と惨酷な折檻」を受け続け、「昔気質の律儀な」父の計らいで七つの年に養父母のところに貰われてくる。良く言えばなにがあっても屈せずへこたれない性格、悪く言えばあまり深く物事を考えようとしない直情径行タイプ。また、良く言えば気前が良い、悪く言えば見栄っ張りで浪費癖がある。男勝りで荒い気性。情は深い。
○父母たち:過酷な現実をお島に思い知らせる存在
〔養父母〕紙漉き業を営んでほそぼそと暮らしていたが、ひとりの六部(巡礼)を泊めたことで大金を手にしてからは、にわかに身代が太り、地所などをどんどん買い入れるようになった。そのきっかけを養父母は、牧歌的な報恩譚として語るが、お島は、学校の友人たちなどから、養父母家に泊まった六部はその晩急病のために落命し、その懐に入っていた財布に大量の小判があったのを養父母が盗んだにちがいないと聞いた。お島は、そのことが気にかかってしかたがなくなる。養父の名は作中で記されていないが、養母の名は、「おとら」である。養父母は、お島の手に財産が渡らないように策謀をめぐらす。お島はそのことを後に知る。
〔実父母〕王子界隈で植木屋を営む。昔は庄屋で、その頃も界隈の人たちから尊敬されていた。祖父は、将軍家の出遊のおりの休憩所として広々とした庭を献納した。お島の実母は、父の二度目の妻で、近辺の安料理屋にいた賎しい出である。実父母の名は作中で記されていない。実母は、幼いお島の小さい手に焼火箸を押しつけたりして、彼女を虐待し続けた。実父は、そのことを思い悩み、お島の遣(やり)場に困ること、たびたびであった。そのことを物語る印象的な場面を引用しておこう。
お島は爾(その)とき、ひろびろした水のほとりへ出て来たように覚えている。それは尾久の渡あたりでもあったろうか。のんどりした暗碧(ぺき)なその水の面(おも)には、まだ真珠色の空の光がほのかに差していて、静かに漕いでゆく淋しい舟の影が一つ二つみえた。岸には波がだぶだぶと浸って、怪獣のような暗い木の影が、そこに揺めいていた。お島の幼い心も、この静かな景色を眺めているうちに頭のうえから爪先まで、一種の畏怖と安易とにうたれて、黙ってじっと父親の痩せた手に縋(すが)っているのであった。
場所の説明をしておくと、文中の「尾久の渡」は「小台の渡し」とも呼ばれ、江戸時代から江北・西新井・草加方面への交通の要所として賑わっていた。西新井大師や六阿弥陀のひとつである沼田の恵明寺に詣でる人々も多く利用した。隅田川(荒川)をはさんで、北岸はいまの足立区小台2丁目、南岸は荒川区西尾久3丁目である。大江戸の北限の一環をなしていたと言っていいだろう。お島は、そういう場所で幼少期を過ごしたことになる。
さて、引用のなかで分かりにくいのは、「お島の幼い心も、この静かな景色を眺めているうちに頭のうえから爪先まで、一種の畏怖と安易とにうたれて」の箇所だろう。「畏怖」については、次の引用で明らかになる。そのうえで「安易」についても述べよう。
その時お島の父親は、どういう心算(つもり)で水のほとりへなぞ彼女をつれて行ったのか、今考えてみても父親の心持は素(もと)より解らない。或は渡しを向こうへ渡って、そこで知合の家(うち)を尋ねてお島の躰の始末をする目算であったであろうが、お島はその場合、水を見ている父親の暗い顔の底に、或可恐(あるおそろ)しい惨忍な思着(おもいつき)が潜んでいるのではないかと、ふと幼心に感づいて、怯えた。父親の顔には悔恨と懊悩の色が現われていた。
水を見ている父親の暗い顔の底に潜んでいる「或可恐(あるおそろ)しい惨忍な思着(おもいつき)」とは、文中にはっきりと書き記されてはいないが、お島を水に沈めて殺してしまうことである。とはいうものの、ここでの秋声の書きぶりは微妙である。要するに、次のようなことなのではなかろうか。実母から虐待を受け続けている幼いお島は、父親に無条件ですがりつくよりほかにない。父親としては、そういう娘を愛おしく思う気持ちがないわけではないのだが、その脳裏には、賎しい身分の妻との一時の感情に任せただけの安易な再婚を悔いる気持ちや、妻とお島との諍いに疲れ果てて一時的に思考力を低下させた状態で「この子さえいなければ」という漠然とした感情がうっすらと漂っていたのではなかろうか。その様子に、父親に頼り切ったお島は、幼い自分にとってその存在理由など到底推し量ることなどかなわない大人のひんやりとした世界の殺伐としたものを鋭敏に感じ取ったのではないだろうか。それゆえ、お島は「怯え」「畏怖」を感じたのだろう。
とはいうものの、それだけであれば、お島はこの体験をいわゆるトラウマとして受けとめざるをえなくなる。それは、生きるエネルギーの致命的な毀損、さらには、極端な場合、精神的な死を刻印されざるをえなくなる。それを本能的に避けようとして、お島は、「畏怖」と同時に「安易」にもうたれるほかはなかった。つまり「安易」は、お島の生きようとする意欲を象徴していると言っていいだろう。幼い子どもの心のなかで、実はそういう激しいドラマが演じられる場合があることが、「一種の畏怖と安易」という一見なにげない、しかし腑に落ち難い言葉の並列から汲み取ることができる。
登場人物の説明に要求される簡潔さを犠牲にして長々と引用し、それらに対する自分の見解をも述べたのには、じつは理由があるのだが、それについては後ほど触れる。では、登場人物の説明を続けよう。
〔植源(うえげん)の隠居〕父の仲間うち。奉公人の扱いが酷。お島の嫁入り先の世話をする。
〔小野田(後出)の父〕お島の三番目の夫の父。田舎で一人暮らしをしている。家や田畑が人手に渡って零落し、みすぼらしい姿で土いじりをする日々を過ごしている。「お島は慄然(ぞっ)とするほど厭であった」。夫婦で面倒を見ることになる。
○男たち・・・田舎臭くて野暮な「作」と「小野田」は、お島の好みではなく、色白で洗練された「鶴さん」や「浜屋」が彼女の好み。しかし人生は、彼女の好み通りにはなかなかならない。
〔作(作太郎)〕お島の養父の兄であるやくざ者と、旅芸人との間にできた子ども。養父母にずっとこき使われてきた。「お島からは豚か何ぞのように忌嫌われた」。養父母の策略で、お島の戸籍上の最初の夫となる。
〔鶴さん〕植源の隠居の世話で、お島が嫁ぐ。お島より十歳ほど年上。植源の隠居の生まれ故郷の出で、若いころから実直に働き、神田で缶詰屋を営む。「色白で目鼻立ちのやさしい」鶴さんは、浮気でお島を困らせ、お島は嫉妬に悩み抜く。
〔浜屋〕お島が鶴さんと別れた後、商売をしていた兄が仕事の手助けとして彼女を連れていった山国のS町にある旅館の主人。旅館の屋号がそのまま主人の名前として作中で使われている。妻帯者であるが、お島と恋仲になる。「色の白い面長な優男(やさおとこ)」で「大い声では物も言わないような、温順(おとな)しい男」である。その妻は、肺病のため生家に帰されている。
〔小野田〕父親の従姉にあたる伯母の下谷の家に出入りしていた裁縫師。お島は彼と洋服屋を始め、所帯を持つ。愛情ではなく主に実利的なつながりで夫婦になった。小野田の過剰な性欲に困り果てる。
○女たち・・・旧社会の犠牲者として描かれている
〔おゆう〕植源の隠居の息子房吉の嫁。昔からずっと鶴さんに惚れている。結局、鶴さんへの事実上の「心中立」をすることになる。
〔狂女〕小野田の昔からの女。夫はいるが、小野田との関係はずっと続き、その浮気現場をお島に押さえられて、精神に変調をきたすようになる。
その3 作中におけるお島の身の振り方の軌跡
*年号との対応関係は推定の域を出ないが、せいぜい1年ほどの誤差である。その推定の根拠を示すのは、煩雑に過ぎるので、省略する。不明な点があれば、遠慮なく言っていただけたなら幸いである。
☆1900年(明治三三年);一八歳。作との婚礼話が耳に入る。「私死んでも作なんどと一緒になるのは厭です。」
☆同年秋;養父母やその関係者たちの策謀によって作との祝言をあげさせられたお島は養家を飛び出す。「ふん、御父さんや御母さんに、私のことなんか解るものですか。彼奴等(あいつら)は寄ってたかって私を好いようにしようと思っているんだ。」
☆1901年(明治三四年)春;一九歳。植源の隠居の世話で、神田の缶詰屋の鶴さんに嫁ぐ。鶴さんの激しい女性関係のせいで夫婦仲はうまくいかない。「どうせ長持のしない身上(すぐに離婚するという意味―引用者注)だもの。今のうち好きなこと(贅沢なおしゃれー引用者注)をしておいた方が、此方の得さ。あの人だって、私に隠して勝手な真似をしているんじゃないか。」
☆1902年(明治三五年)夏の末;二〇歳。鶴さんとの一年足らずの結婚生活の後、植源に居候をしていたお島は、兄の壮太郎に連れられて山国のS町に行く。そこで浜屋と恋仲になる。「他人のなかに育って来たお蔭で、誰にも痒いところへ手の達(とど)くように気を使うことに慣れている自分が、若主人の背を、昨夜も流してやったことが憶出された。然うした不用意の誘惑から来た男の誘惑を、弾返すだけの意地が、自分になかったことが悲しまれた。『鶴さんで懲々している!』お島はその時も、溺れてゆく自分の成行に不安を感じた。」
☆1903年(明治三六年)五月末;二一歳。浜屋の生家や近所への聞こえを憚って、浜屋と縁続きの山の温泉宿へ移される。そこへ、噂を聞きつけた実父が彼女を引取りに来た。「『帰ってみて、もし行くところがなくて困るような時には、いつでも遣って来るさ。』浜屋は切符を渡すとき、お島に私語(ささや)いた。」
お島と浜屋とのつながりは、その後浜屋が死ぬときまで細く長く続く。
☆同年、盆過ぎ。東京下谷で独り身で暮らしている、父方の伯母のところに身を預ける。そこで伯母の裁縫の手伝いをするようになる。
☆1904年(明治三七年)二月;二二歳。「時にはお島の坐っている裁物板の側への来て、寝そべって笑談(じょうだん)を言合ったりしていた小野田と云う若い裁縫師と一緒に、お島が始(ママ)めて自分自身の心と力を打籠めて働けるような仕事に取着こうと思い立ったのは、その頃初(ママ)まった外国との戦争が、忙しい其等の人々の手に、色々の仕事を供給している最中であった。自分の仕事に思うさま働いてみたい―――奴隷のような是迄の境界(きょうがい)に、盲動と屈従とを強いられて来た彼女の心に、然うした欲望の目覚めて来たのは、一度山から出て来て、お島をたずねてくれた浜屋の主人と別れた頃からであった。」
いささか脱線をする。ここは、この小説にとって、極めて重要な局面である。実父母や養父母やその関係者によって、過酷な運命を強いられてきたお島が、力強く社会的な自立を果たそうとするきかっけを具体的な職業に見出しているのである。
このくだりで連想するのは、やや飛躍するようであるが、石光真清著(石光真人編集)『石光真清の手記三 望郷の歌』(中公文庫)に登場する軍人・本郷源三郎である。彼は、貧農の出であるが、地元の人々の援助を得て、陸軍幼年学校から士官学校へと進み、若くして将校となった人である。彼は、昔ならそのようなことが決してありえなかったことをよく分かっている人であった。それゆえ、そのような幸運を自分にもたらしてくれた明治という時代への心からの感謝の念を主人公の真清の目の前で率直に表明し、満足の笑みを絶やすことなく日露戦争の激闘のなかで軍人らしい死を従容として迎えた。
お島に、源三郎のような国家への忠誠心が欠落しているのはいうまでもない。そういう意味では、お島と源三郎とは違う。しかしながら、日露戦争という日本史上初の近代的な総力戦によってもたらされた国民的な熱気が、そういう違った人物において違った現れ方をした、という言い方はできるような気がする。また、それは、生まれ落ちた環境がたとえどんなに不利なものであろうと、当人の頑張り如何でどうにかなるというオプティミズムが、この国民戦争によって本格的に市井人にもたらされた、と言いかえても良いように思う。そのような時代の気風の変化の刻印を、お島の自立心の芽生えに見出すのは、さほどの難事ではないように思われる。先ほど述べたことを繰り返そう。時代は、すなわち、歴史は、お島の身振りの隅々にまでその振動を伝えているのである。脱線は、以上である。
☆1904年、年末;日露戦争で消費される柿色の防寒外套を作る仕事を請け負っている小野田の雇われ先の工場で、ミシン台に坐ることを覚え、また、自分に営業能力があることを自覚する。やがて、芝で小野田と店を出し、人を雇い入れるようになる。
☆1905年(明治三八年)冬の初め;二三歳。戦争景気が終わり、経営の行き詰った芝の店を引き払って、月島に移る。苦しい経営状態が続く。性の不一致に起因する諍いが小野田との間で絶えない。苦し紛れに買ったねずみ講のようなものが当たり、かろうじて年を越すことができた。それで、しばし小野田と和解をする。
☆1906年(明治三九年)三月;二四歳。経営難で万策が尽き、月島の店を引き払い、小野田の故郷に近いNというかなり繁華な都会に半年ほど住む。小野田の妹の家の二階で寝泊りをする。律儀な暮らしぶりに慣れた地方都市の気風にお島はついになじむことができなかった。
☆同年九月頃;着の身着のままで東京に舞い戻った二人は、築地の川西(小野田の昔の雇い主か?)の洋服店に夫婦住み込みとなる。川西がお島に性的関係を迫ったのをお島が拒絶したのが原因で店を出る。愛宕(現港区)の印判屋の奥の三畳一室を借りる。そこに注文したミシンを置いて仕事を始める。仕事はそれなりに順調な滑り出しだったが、性の不一致によるお島の苦痛は続く。
☆1907年(明治四〇年)三月~七月の間;二五歳。根津に引越し、やっと落ち着いた暮らしができるようになる。上野で催されている東京勧業博覧会のおかげで、根津も結構な賑わいを見せていた。そこに、小野田の父が住み着くようになり、また、お島が1902年当時お世話になった山国S町の人々を呼び寄せたりした。そこにはこなかったが、浜屋ともたびたび顔を合わせた。
*「『それは東京にも滅多にないような好い男よ。』お島は笑いながら応えたが、自分にも顔の赤くなるのを禁じ得なかった。」という描写などから察するに、お島が心底惚れ抜いた男は浜屋である。
☆1909~10年(明治四二~四三年);二七~八歳。本郷に店を持つ。洋風の本格的な洋服屋。お島は、洋服を着て自転車に乗り仕事を取るようになる。当時としては珍しいこと。
☆1910~11年(明治四三~四四年)初夏;二八~九歳。浜屋に会いに山国に行くが、浜屋はすでに死んでいた。そのまま家には戻らずに、遠い山のなかの温泉場に数日間逗留する。そこに、目をかけている職人を二人呼び寄せて、「事によったら、上さんあの店を出て、この人に裁をやってもらって、独立(ひとりだち)でやるかも知れないよ。」と告げる。
*なにがあろうとへこたれてしまわずに、ひたすら前向きに生きようとするお島の姿が浮かび上がってくるだろう。それを、秋声は、変に大げさに称揚したりしないで、彼女の性格的な欠点もしっかりと見据えながら、描き出している。人間的な欠陥を抱えながらも、お島の言動には真実味があり、そこに読み手は美しさを感じることになる。
その4 夏目漱石の『あらくれ』評 「徳田氏の作物には、フイロソフイーがない」
夏目漱石の『あらくれ』評が面白い。読書会参加者によれば、有名なのだそうだ。やや長くなるが、引用しよう。
『あらくれ』は何処をつかまへても嘘らしくない。此嘘らしくないのは、此人の作物を通じての特色だらうと思ふが、世の中は苦しいとか、穢はしいとか―――穢はしいでは当らんまいかも知れない。女学生などの用ひる言葉に「随分ね」と云ふのがある。私はその言葉をここに借用するが、つまり世の中は随分なものだといふやうな意味で、何処から何処まで嘘がない。
尤(もっと)も他の意味で「まこと」の書いてあるのとは違ふ。従つて読んで了ふと、「御尤もです」というやうな言葉はすぐ出るが「お陰様で」と云ふ言葉は出ない。「お陰様で」と云ふ言葉は普通「お陰様で有りがたうございました」とか、「お陰様で利益を得ました」とか、「お陰様で面白うございました」とか云ふ場合に多く用ひられるやうである。私のここでいふ「お陰様で」も矢張り同じやうな意味であることは、断るまでもないであらう。(中略)
つまり徳田氏の作物は現実其儘(そのまま)を書いて居るが、其裏にフイロソフイーがない。尤も現実其物がフイロソフイーなら、それまでであるが、目の前に見せられた材料を圧搾する時は、かう云ふフイロソフイーになるといふ様な点は認める事が出来ぬ。フイロソフイーがあるとしても、それは極めて散漫である。然し私はフイロソフイーが無ければ小説ではないと云ふのではない。又徳田氏自身はさう云ふフイロソフイーを嫌って居るのかも知れないが、さう云ふアイデアが氏の作物には欠けて居る事は事実である。始めから或るアイデアがあつて、それに当て嵌めて行くやうな書き方では、不自然の物とならうが、事実其の儘を書いて、それが或るアイデアに自然に帰着して行くと云ふやうなものが、所謂深さのある作物であうと考へる。徳田氏にはこれがない。
(「文壇のこのごろ」(大阪朝日新聞)大正四年十月十一日)
ここには、漱石と秋声の作家としての資質の違いがはっきりと出ているという意味で、とても興味深い。漱石が「フイロソフイー」と呼んだものを、秋声は、「理屈」あるいは「さかしら」として嫌うのではないかと私は感じる。その意味で、漱石の「徳田氏自身はさう云ふフイロソフイーを嫌って居る」という言葉は、正鵠を射たものである。
では、「理屈」や「さかしら」という意味ではない「フイロソフイー」が本当に『あらくれ』にないのかといえば、そんなことはない、というのが私の考えである。それは、上記の「その2 登場人物」で、「幼い子どもの心のなかで、実はそういう激しいドラマが演じられる場合があることが、『一種の畏怖と安易』という一見なにげない、しかし腑に落ち難い言葉の並列から汲み取ることができる」と述べたことを思い出していただければ、よく分かるのではないだろうか。つまり、秋声には人間がよく見えているのである。その曇りのない目に映ったものを「フイロソフイー」と呼ぶことを躊躇すべき理由が私には見つけられない。小説における「フイロソフイー」とはそういうものであって、それ以外のものではないと言っても過言ではないのだ。
このことは、読み手の存在を織り込むとよりはっきりとすると思われる。読み手が生の営みにおいてうすうす感じ取っていたものを、文字ではっきりと記されたとき、それを目にした読み手は「そのとおり」と腑に落ちて、心を動かされる。これが、小説を含む言語表現によってもたらされた感動なるものの基本イメージなのではなかろうか。この場合読み手は、書き手の「理屈」なり「観念」なりに心を動かされているのではなくて、書き手の、いわば目に映った人間の真実味に心を動かされるのである。
小説における「フイロソフイー」の意味の取り違えは、漱石の小説に一定の限界もしくは瑕疵を与えてしまっているように思われる。『行人』における過剰な論理癖が読み手にもたらす辟易感や『こころ』における「先生」の妻の心理への洞察の致命的な欠如などは、その端的な例である。そういう限界や瑕疵をまぬがれているのは、小説では『門』の前半部分、随筆では『夢十夜』あるいは『硝子戸の中』である、というのが私の見立てである。『道草』もそういう作品であると聞いているが、残念ながら未読である。
また、この両者の、リアリティをめぐる対立は、日本近代文学に底流するふたつの流れのそれを象徴しているとも言いうる。それは、坪内逍遥が『小説神髄』で述べた「おのれの意匠をもて、善悪正邪の情感をば作設くる事をなさず、只傍観してありのままに模写する心得にてあるべきなり」というリアリズム観と、二葉亭四迷が『小説総論』で述べた「模写といえることは実相(すなわち現象―引用者注)を借りて虚相(すなわち本質―引用者注)を写し出すことなり」というリアリズム観との対立として描くことができるだろう。単純に、逍遥は四迷によって乗り越えられたとするのは、その後の文学の流れを見誤ることにつながりかねないのである。
その5 秋声の風貌
読書会のメンバーのひとりが、巻末の写真をみながらつくづく「秋声の風貌は、よく分かっている人、できた人という感じだ」と感慨を漏らした。あまりにも当を得た意見だったので、なんだか、笑ってしまったほどだった。この小説を書く人は、こういう顔をしているはずというイメージにぴったりなのである。その写真そのものではないが、ひとつ参考までに掲げておこう。

〈コメント〉
☆Commented by miyazatotatsush さん
美津島明様
徳田秋声「あらくれ」論を拝読いたしました。
私も徳田秋声の小説はあまり(というかほとんど)読んでいないのですが、十数年前、偶然、彼の遺作の「縮図」を読み、いたく感動したことがあります。
この小説は秋声の死で、中途で終わっておりますが、主人公の初老の男(といっても、今なら七十代の感じ)と、元芸者で置屋の主人の女との、何気ない会話から、昔はねんごろだったふたりの、今は互いを労わる関係のなかから、過去の情景があわあわと甦るところに感動しました。
秋声の文体が「いぶし銀」と呼ばれるゆえんが解ったような気がしました。
ブログに掲げられた秋声の写真の寒々とした世界の孤高の姿からもそれが伝わりました。
☆Commented by 美津島明 さん
To miyazatotatsushさん
宮里さん、コメントをいただきましてどうもありがとうございます。『縮図』がいいのですね。今度、読んでみます。
若いころは、どうしても「スター」級の文学者にばかり目が向きがちです。むろん、私もそうでした。「スター」とは、もちろん漱石・鴎外・芥川・太宰・三島・大江・村上春樹たちのことです。「スター」たちには「スター」たちの良さがあります。花にたとえれば、真っ赤な薔薇や向日葵の艶やかさ・美しさが彼らにはあります。しかし、どう転んでも、彼らには、野に咲く花の素朴で地味な美しさを醸し出すことはかないません。別に、それを非難しているわけではないのですけれど。
個人的に、最近は、年を取ったせいか、艶やかで派手な花をみてもあまり感動しなくなりました。というか、ややうるさく感じるくらいです。むしろ、道ばたになにげなく咲いている花の美しさに心惹かれるものがあるのですね。「スター」ではない地味な文学者たちの良さが視野に入ってきたのも、要するに、そういう感受性の変化のせいなのかもしれませんね。
*****
徳田秋声『あらくれ』に出てくる魅力的な言葉について
『あらくれ』には、耳慣れぬ言葉が散見される。この作品が約一世紀前に書かれたものであることを考えれば、それは当然のことといえる。
しかしながら、その意味を分からずに読み飛ばしてしまうにはあまりも惜しいと感じるほどに、魅力を発散している言葉がたくさんあるのだ。当時の人々の生活感情がそこに織り込まれているような印象を受けるから、というのが主な原因であるような気がする。また、身体性を濃密に感じさせる言葉が少なくないのである。もともと私は、身体性の密度の高い言葉を好むところがあるのではあるが(たとえば、「見る」より「目にする」を好み、「読者」より「読み手」を好む)。
そういう言葉を、これからいくつか取り上げてみたいと思う。ちなみに、カッコ内のページは、講談社文芸文庫のそれである。
○のんどり(P9);「のんどりとした暗碧なその水の面(おも)には~」という使われ方をしている。のどかなさま、のんびりとしたさまの意。「今日一日、のんどりと過ごした。」などと言えば、それだけで肩の凝りがほぐれていくようだ。
○業つく張(P10);「この業つく張め」。実母がお島を罵倒する言葉である。昔の悪態語には、言われた方が心底堪える迫力がある。当作品には登場しないが、「このぼけ茄子が」なんてのも、生活感情がうかがえて、なかなか味がある。
○六部(P11);諸国の社寺を遍歴する巡礼。六十六部の略で、六十六部の法華経を一部ずつ霊地に納めることからその名がついた。後には、死後の冥福を祈るため、鉦(かね)や鈴を鳴らし、厨子(仏像や経巻を入れた両扉の箱)を負って家ごとに銭を乞い歩いた。私の興味・関心に引き寄せると、津軽三味線弾きの原型がこれである。その存在から、日本各地に「六部殺し(ろくぶごろし)」の民話・怪談が生まれた。ある農家が旅の六部を殺して金品を奪い、それを元手にして財を成したが、生まれた子供が六部の生まれ変わりでかつての犯行を断罪する、というものである。『あらくれ』は、「六部殺し」を部分的に下地にしている。
○いらいらしい(P16);「彼女のいらいらしい心」という使われ方をしている。昔は、「いらいら」が擬態語としてのみならず、形容詞の語幹の一部としても使われていたことが分かる。
○天刑病(P20);ハンセン氏病(らい病)。天の刑罰としての病ということであるから、差別感情が濃厚である。本文中でも「汚い天刑病者」という言い方をしている。
○疳症(P23);一般的にはちょっとした刺激にもすぐ怒る性質。激しやすい気質の意。ここでは、「一日取りちらかった其処らを疳症らしく取片着けたりしていた」という使われ方をしていることから見て、異常に潔癖な性質の意である。この派生的な意味では、昨今あまり使われなくなったのではないだろうか。
○ひきる(P27);蚕が繭をかける状態になること。元は甲州弁らしい。生糸業が衰退してしまった今日ではもはや死語(そうではない地域がまだあるとは思うが)。当作品では、「もうひきるばかりになっている蚕」という使われ方をしている。
○から薄ぼんやり(P30);うすのろであること。また、そのような人。意味は「薄ぼんやり」と同じなのだろうが、「から」=「空」がつくとその意味が強調され、強烈なインパクトが加味される。昔の人々は、悪態語の天才である。ここでは、「から薄ぼんやりなお花」という使われ方をしている。
○懲りずまに(P31);「ま」は、そのような状態であるの意を表す接尾語。前の失敗に、懲りもしないで。しょうこりもなく。とても便利でニュアンスに富んだ言い方のように感じるが、なぜかめったにお目にかからない。作中では、「作は懲りずまに善くお島の傍へ寄って来た」という使われ方。
当初はこれくらいで終わりにしようかと思っていたのだが、思いのほか興に乗ってきたので、このまま続けよう。
○因業(P34);頑固で思いやりのないこと。人に対する仕打ちが情け容赦もなくひどいさま。もとは、仏教用語。前世の悪行が招いたこと、というニュアンス。根の深い欠陥という意味合いと、その人のせいではないからそれを受ける側は諦めるほかないという意味合いとがある。「――おやじ」。作中では「因業を言張って許りもいられなかった。」という使われ方をしている。
○大束(P46);「おおたば」と読む。①大ざっぱなこと。また、そのさま。大まか。雑。②偉そうな態度をすること。また、そのさま。ここでは、お島が「大束を極込んだ」とあるので、①の意味。「悪く―なことを言って落着いているよ」〈紅葉・多情多恨〉
とか、「―を言うな、駈落の身分じゃないか」〈鏡花・婦系図〉といった用例がある。
○口入屋(P47);奉公人などを世話する業者。おもに、身分の低い者を対象とする職業斡旋業者。江戸時代がその活動の全盛期。
○心中立(P102);「しんじゅうだて」。自分の心の中をすっかり見せ、契を交わした相手に愛の証拠を見せ、恋愛の誠実性を立証すること。黒髪を切って相手に渡したり、指を切ったり、さらには、命を捧げたり、とエスカレートしていく。遊郭での恋愛のルール・マナー・エチケットがもともとの姿で、それが、一般人にも流布していったのではないだろうか。「みんな鶴さんへの心中立だ。」これは、鶴さんのことで錯乱状態に陥ったおゆうが、自宅の庭の井戸に飛び込もうとしたことを、お島がそう感じたというくだりである。
○兇状持(P116);「きょうじょうもち」。殺人などの凶悪な犯罪を犯した者。前科者より強い意味を持つ。「寒い冬空を、防寒具の用意すらなかった兄の壮太郎は、古い蝙蝠傘を一本もって、宛然(さながら)兇状持か何ぞのような身すぼらしい風をして、そこから汽車に乗っていった。」それをふまえると、この描写のわびしさがひとしお感じられる。
○石楠花(P135);これは単に、私が読み方を知らなかったので調べてみただけのことである。「しゃくなげ」と読む。ちなみに、「木瓜」はどう読むか、お分かりだろうか。「ぼけ」である。
○饅頭(P151);読みは、もちろん「まんじゅう」だが、どうもおかしいと思って調べてみると、「饅頭の形に似たアイロン台の一種」とあった。「小野田は顔を顰めながら、仕事道具の饅頭を枕に寝そべりながら、気の長そうな応答(うけこたえ)をしていた。」とあるのだから、食べ物の「饅頭」でないことは分かるだろう。
○射幸心(P162);偶然に利益を得ようとする心。分かるような分からないような感じだったので、調べてみたらやはりよく分かっていなかった、という次第。宝くじを買う心理などを言う。
○業腹(P175);しゃくにさわること。「ごうはら」と読む。「自分の腕と心持とが、全く誤解されているのも業腹であった。」野心家のお島の心持ちは、地方都市の堅実な暮らしぶりにどっぷり浸かった人々には分からないことを、お島は憤っているのである。
○ぼんつく(P183);馬鹿の意。またまた素敵な悪態語が出てきた。
○女唐服(P219);「めとうふく」と読む。本来は、唐服の婦人物のことをいうのだが、当時は洋服のことをそう呼んだ。女唐は、西洋婦人をあなどっていった言葉。当時の、洋服に対する意識がうかがわれる言葉。女性の洋装が珍しかったのだろう。