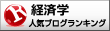本作品は、書き下ろし長編評論として、講談社より一九五九年一月に刊行されました。吉本隆明の『言語にとって美とはなにか』(一九六五年)の先駆的な作品と位置づけることも可能でしょう。吉本は『言語美』において、言語の本質としての自己表出性と指示表出性を導きの糸にすることによって文学作品の本質にアプローチするという当時としては斬新な批評スタイルを採っています。その五年ほど前に、江藤は本作品においてすでに、文体の特徴から文学作品の本質にアプローチするという、日本の文芸批評史において画期的な批評スタイルを採っています。何が書かれているかにではなく、どのように書かれているかに江藤は着目したのでした。そこから、吉本が、言語それ自体に着目して作品を論じるところまでは、あと一歩のへだたりであったといまからなら振り返ることができるでしょう。二人ともに、文学の自立的価値とは何かについての深い洞察と鋭い直観があります。彼らの斬新な営為は、それに基づいたものなのです。
当時としては、いずれも随分見栄えの良い、つまりカッコイイ批評スタイルだったものと思われます。鋭敏な若い人たちは、そんな彼らにぐっと惹きつけられたのではないでしょうか。日本の良質な知性がそのエネルギーを惜しみなく傾注した文芸批評の黄金時代ならではの精神風景と言っていいでしょう。ほかに小林秀雄や福田恆存や竹内好なんかもいたわけですからね。思えば、いまではみんな死んでしまってこの世にはいないのです。私の心の少なからぬ部分は、いまだにその時代を彷徨っていることを白状しておきましょう。私がこの世に生を受けてまだほんの二・三年経ったくらいのときのことなんですけどね。これは、おそらく一生続くのでしょう。一種の病気です。
年譜をながめてみると、本作品の誕生をめぐって、当時の江藤は少なからず屈託があったものと思われます。講談社文芸文庫から引用します。
・一九五七年(昭和三二年・二五歳) 三月、慶応義塾大学文学部英文科を卒業。四月、同大学院に進学。指導教授は西脇順三郎。五月、三浦慶子と結婚。仲人は奥野信太郎。武蔵野市吉祥寺に住む。
・一九五八年(昭和三三年・二六歳) 一月ごろ(?)、「ものを書いているなら大学院を辞めるように」という勧告を受け、以後、大学に行かなくなる。春、講談社から書き下ろしを依頼され、夏から秋にかけて執筆(『作家は行動する』として翌年刊)。十一月、『奴隷の思想を排す』(文芸春秋新社)刊。
・一九五九年(昭和三十四年・二十七歳)一月、『作家は行動する』(講談社)刊。三月、大学院を中退。八月、『海賊の唄』(みすず書房)刊。秋、目黒区下目黒に転居。
・一九六〇年(昭和三五年・二八歳)五月、安保騒動があり、石原慎太郎・大江健三郎・谷川俊太郎・開高健・羽仁進らとともに「若い日本の会」に参加。抗議集会を開いたり、声明を出したりした。
屈託の最たるものは、「ものを書いているなら大学院を辞めるように」という勧告の件(くだり)でしょう。これは、西脇順三郎によってなされたものなのでしょうか。それはとりあえず措くとして、自分の筆力に深い自信を持っていたにちがいない江藤からすれば、この勧告にはひたすら反発を覚えたに違いありません(五六年に江藤は『夏目漱石』を上梓しています)。愛する女がそばにいることも、心を強くする材料になったことでしょう。怖いものなんかありません。これまでずっと優等生だった江藤は、このとき生まれてはじめて本格的に「グレ」たのだと言えるでしょう。
「グレ」の本質は、既成の秩序の担い手としての「父なるもの」への抗いです。当時の江藤にとって抗いの対象としての「父なるもの」とは、大学院の指導教授としての西脇順三郎であり(要論証)、安保改定をゴリ押ししようとする岸信介首相であったのでしょう。彼が、安保をめぐって大江健三郎と肩を並べていたなんて、時代を感じさせますね。そのせいでもないのでしょうが、本作品において、江藤は大江をほとんど絶賛せんばかりの筆致を危うく示そうとするほどの評価ぶりです。例えば、こんなふうに。
この作品(『飼育』のことー引用者)の中心的なイメージは、「黒人兵」と、「夏」と、「戦争」である。しかも黒人兵は「光り輝く逞しい筋肉をあらわにした夏、僕らを黒い重油でまみれさせる」汎神論的な子供達の夏であり、「僕ら」と「黒人兵」とは「暑さ」という「共通な快楽」で結ばれている。これらの有機的に一体化したイメージと「遠い国の洪水のような戦争」とは対比され、いわば一種のフーガを奏しているであろう。そして黒人兵がにわかに兇暴な敵になり、「僕の指と掌をぐしゃぐしゃに叩きつぶし」はじめるとき、いままで弱奏されていた「戦争」の主題が急に接近し、「子供達」の主題は急に消えて行く。「もう僕は子供ではない」という「啓示」と、現に自分が「戦争」に接触したという経験――その二つの主題の交錯をこのように明瞭に描き出していくものは、いうまでもなく作者の「文体」以外のものではない。この豊富なイメージの世界は、かりに繊細であるにせよきわめて論理的な、明確な行動によって支えられている。
大江の『飼育』は、『文学界』一九五八年1月号 に発表され、その年の芥川賞受賞作品となっています。当時においていまだ評価の定まらない話題作についての、いまにおいても通用する評価軸 を早々と確立してしまった江藤の批評的辣腕ぶりには、舌を巻かざるをえません。江藤は、『飼育』の秀逸性を当時においてすでに的確に捉えていたのです。
的確な評価軸の確立という観点からすれば、本作品における江藤の、第一次戦後派の文体上の達成への着眼を取り上げないわけにはいきません。
彼(野間宏『暗い絵』の主人公―引用者注)は絵を見ている。(中略)彼はすでにブリューゲルの絵のイメージが反映している荒涼とした「自然」のなかを、重い足どりで進みはじめている。そしてその「自然」は、一九三〇年代の京都帝大の学生にとってのリアリティーであると同時に、現に作者の周囲にひろがっている混沌とした「現実」でもある。要するにこれは完全に主体化された風景のイメージであって、鋭敏な読者はこの文体に参加するとき、弱音器をつけて奏せられるコントラバスの低い、重い、あえぐような繋留音の持続にふれるであろう。それはほかならぬ作者自身のあえぎであり、大地も、太陽も、地平線も、一様にアニメイトされ、いま彼の「存在」と切りはなすことのできないものとしてある。このような持続感は、過去のどのような表現、語彙、文脈によってもあらわされない。野間氏はあえぎ、「悩みと痛みと疼き」によって歩みつづけながらきわめて大胆に形骸を切り開き、まったく新しい行動の軌跡――「文体」をのこしていく。
この『暗い絵』に対する評価が、吉本の『言語美』における『暗い絵』に対するそれに濃い影を落としていることは、私見によれば、言を俟ちません。第一次戦後派に対する評価のテンプレートは、江藤・吉本の両氏によって形作られたと言っても過言ではないでしょう。
ところで、先ほど私は、当時の江藤は「グレ」ていたと申し上げました。その明らかな痕跡が本作品にも見られます。それは、小林秀雄に対する意外なくらいの低い評価です。というか、乗り超えるべき、日本文学の最大の強敵として小林がイメージされていというべきでしょう。
志賀直哉、小林秀雄氏らは、現実に負の行動の論理――負の文体を確立しえた人である。文学史家は、彼らにおいて最高の批評があり、最高の小説があるというであろう。しかし、そのような評価は、価値を完全に逆立ちさせている。われわれはむしろ、彼らにおいて文学が完全に圧殺された、ということを証明しなければならない。近代の日本文学においては「最高の批評」が批評を殺りくし、「最高の小説」が小説を絞殺している。その事実を知らないかぎり、散文はわれわれにとって永遠に無縁のものとならざるをえない。
ここで小林秀雄は志賀直哉と並べられ、徹底糾弾をされています。一〇年後のゲバルト学生も顔負けなくらいの激しさです。当時の江藤にとって、小林秀雄は、抗うべき文学上の「父なるもの」としてイメージされていたのではないでしょうか。
ところが、安保闘争で大江と共闘を組んだ一九六〇年の翌年に、江藤は『小林秀雄』を上梓し、小林秀雄賛歌を朗々と歌い上げました。この「転向」は周囲を驚かせ、「変節」として批判され、安保で敗れたとはいうもののまだまだ意気盛んだった当時の進歩派言論界において、江藤はほとんど四面楚歌のような孤立を余儀なくされました。しかし、そのことによって江藤の文学的な確信が揺らぐことはついにありませんでした。ここから、江藤と戦後的なものとの間に決定的な隔たりが生じはじめ、江藤の保守思想家としての個性的な足跡が印されていくことになります。
『小林秀雄』において、江藤は小林をいわば文学的な意味での「永遠の青年」として描き出しています。そのことで、かつての自分が小林に投影していた、抗うべき対象としての「父なるもの」という観念からの自己脱却を図り、それを実現しえたという確かな手応えを感じたからこそ、江藤は揺らがなかったのではないでしょうか。
では、「父なるもの」は、江藤においてその後どうなったのか。それについての突っ込んだお話は、私などより、当ブログの寄稿者である先崎さんに、いずれ存分に語っていただいた方が良いように思われます。
当時としては、いずれも随分見栄えの良い、つまりカッコイイ批評スタイルだったものと思われます。鋭敏な若い人たちは、そんな彼らにぐっと惹きつけられたのではないでしょうか。日本の良質な知性がそのエネルギーを惜しみなく傾注した文芸批評の黄金時代ならではの精神風景と言っていいでしょう。ほかに小林秀雄や福田恆存や竹内好なんかもいたわけですからね。思えば、いまではみんな死んでしまってこの世にはいないのです。私の心の少なからぬ部分は、いまだにその時代を彷徨っていることを白状しておきましょう。私がこの世に生を受けてまだほんの二・三年経ったくらいのときのことなんですけどね。これは、おそらく一生続くのでしょう。一種の病気です。
年譜をながめてみると、本作品の誕生をめぐって、当時の江藤は少なからず屈託があったものと思われます。講談社文芸文庫から引用します。
・一九五七年(昭和三二年・二五歳) 三月、慶応義塾大学文学部英文科を卒業。四月、同大学院に進学。指導教授は西脇順三郎。五月、三浦慶子と結婚。仲人は奥野信太郎。武蔵野市吉祥寺に住む。
・一九五八年(昭和三三年・二六歳) 一月ごろ(?)、「ものを書いているなら大学院を辞めるように」という勧告を受け、以後、大学に行かなくなる。春、講談社から書き下ろしを依頼され、夏から秋にかけて執筆(『作家は行動する』として翌年刊)。十一月、『奴隷の思想を排す』(文芸春秋新社)刊。
・一九五九年(昭和三十四年・二十七歳)一月、『作家は行動する』(講談社)刊。三月、大学院を中退。八月、『海賊の唄』(みすず書房)刊。秋、目黒区下目黒に転居。
・一九六〇年(昭和三五年・二八歳)五月、安保騒動があり、石原慎太郎・大江健三郎・谷川俊太郎・開高健・羽仁進らとともに「若い日本の会」に参加。抗議集会を開いたり、声明を出したりした。
屈託の最たるものは、「ものを書いているなら大学院を辞めるように」という勧告の件(くだり)でしょう。これは、西脇順三郎によってなされたものなのでしょうか。それはとりあえず措くとして、自分の筆力に深い自信を持っていたにちがいない江藤からすれば、この勧告にはひたすら反発を覚えたに違いありません(五六年に江藤は『夏目漱石』を上梓しています)。愛する女がそばにいることも、心を強くする材料になったことでしょう。怖いものなんかありません。これまでずっと優等生だった江藤は、このとき生まれてはじめて本格的に「グレ」たのだと言えるでしょう。
「グレ」の本質は、既成の秩序の担い手としての「父なるもの」への抗いです。当時の江藤にとって抗いの対象としての「父なるもの」とは、大学院の指導教授としての西脇順三郎であり(要論証)、安保改定をゴリ押ししようとする岸信介首相であったのでしょう。彼が、安保をめぐって大江健三郎と肩を並べていたなんて、時代を感じさせますね。そのせいでもないのでしょうが、本作品において、江藤は大江をほとんど絶賛せんばかりの筆致を危うく示そうとするほどの評価ぶりです。例えば、こんなふうに。
この作品(『飼育』のことー引用者)の中心的なイメージは、「黒人兵」と、「夏」と、「戦争」である。しかも黒人兵は「光り輝く逞しい筋肉をあらわにした夏、僕らを黒い重油でまみれさせる」汎神論的な子供達の夏であり、「僕ら」と「黒人兵」とは「暑さ」という「共通な快楽」で結ばれている。これらの有機的に一体化したイメージと「遠い国の洪水のような戦争」とは対比され、いわば一種のフーガを奏しているであろう。そして黒人兵がにわかに兇暴な敵になり、「僕の指と掌をぐしゃぐしゃに叩きつぶし」はじめるとき、いままで弱奏されていた「戦争」の主題が急に接近し、「子供達」の主題は急に消えて行く。「もう僕は子供ではない」という「啓示」と、現に自分が「戦争」に接触したという経験――その二つの主題の交錯をこのように明瞭に描き出していくものは、いうまでもなく作者の「文体」以外のものではない。この豊富なイメージの世界は、かりに繊細であるにせよきわめて論理的な、明確な行動によって支えられている。
大江の『飼育』は、『文学界』一九五八年1月号 に発表され、その年の芥川賞受賞作品となっています。当時においていまだ評価の定まらない話題作についての、いまにおいても通用する評価軸 を早々と確立してしまった江藤の批評的辣腕ぶりには、舌を巻かざるをえません。江藤は、『飼育』の秀逸性を当時においてすでに的確に捉えていたのです。
的確な評価軸の確立という観点からすれば、本作品における江藤の、第一次戦後派の文体上の達成への着眼を取り上げないわけにはいきません。
彼(野間宏『暗い絵』の主人公―引用者注)は絵を見ている。(中略)彼はすでにブリューゲルの絵のイメージが反映している荒涼とした「自然」のなかを、重い足どりで進みはじめている。そしてその「自然」は、一九三〇年代の京都帝大の学生にとってのリアリティーであると同時に、現に作者の周囲にひろがっている混沌とした「現実」でもある。要するにこれは完全に主体化された風景のイメージであって、鋭敏な読者はこの文体に参加するとき、弱音器をつけて奏せられるコントラバスの低い、重い、あえぐような繋留音の持続にふれるであろう。それはほかならぬ作者自身のあえぎであり、大地も、太陽も、地平線も、一様にアニメイトされ、いま彼の「存在」と切りはなすことのできないものとしてある。このような持続感は、過去のどのような表現、語彙、文脈によってもあらわされない。野間氏はあえぎ、「悩みと痛みと疼き」によって歩みつづけながらきわめて大胆に形骸を切り開き、まったく新しい行動の軌跡――「文体」をのこしていく。
この『暗い絵』に対する評価が、吉本の『言語美』における『暗い絵』に対するそれに濃い影を落としていることは、私見によれば、言を俟ちません。第一次戦後派に対する評価のテンプレートは、江藤・吉本の両氏によって形作られたと言っても過言ではないでしょう。
ところで、先ほど私は、当時の江藤は「グレ」ていたと申し上げました。その明らかな痕跡が本作品にも見られます。それは、小林秀雄に対する意外なくらいの低い評価です。というか、乗り超えるべき、日本文学の最大の強敵として小林がイメージされていというべきでしょう。
志賀直哉、小林秀雄氏らは、現実に負の行動の論理――負の文体を確立しえた人である。文学史家は、彼らにおいて最高の批評があり、最高の小説があるというであろう。しかし、そのような評価は、価値を完全に逆立ちさせている。われわれはむしろ、彼らにおいて文学が完全に圧殺された、ということを証明しなければならない。近代の日本文学においては「最高の批評」が批評を殺りくし、「最高の小説」が小説を絞殺している。その事実を知らないかぎり、散文はわれわれにとって永遠に無縁のものとならざるをえない。
ここで小林秀雄は志賀直哉と並べられ、徹底糾弾をされています。一〇年後のゲバルト学生も顔負けなくらいの激しさです。当時の江藤にとって、小林秀雄は、抗うべき文学上の「父なるもの」としてイメージされていたのではないでしょうか。
ところが、安保闘争で大江と共闘を組んだ一九六〇年の翌年に、江藤は『小林秀雄』を上梓し、小林秀雄賛歌を朗々と歌い上げました。この「転向」は周囲を驚かせ、「変節」として批判され、安保で敗れたとはいうもののまだまだ意気盛んだった当時の進歩派言論界において、江藤はほとんど四面楚歌のような孤立を余儀なくされました。しかし、そのことによって江藤の文学的な確信が揺らぐことはついにありませんでした。ここから、江藤と戦後的なものとの間に決定的な隔たりが生じはじめ、江藤の保守思想家としての個性的な足跡が印されていくことになります。
『小林秀雄』において、江藤は小林をいわば文学的な意味での「永遠の青年」として描き出しています。そのことで、かつての自分が小林に投影していた、抗うべき対象としての「父なるもの」という観念からの自己脱却を図り、それを実現しえたという確かな手応えを感じたからこそ、江藤は揺らがなかったのではないでしょうか。
では、「父なるもの」は、江藤においてその後どうなったのか。それについての突っ込んだお話は、私などより、当ブログの寄稿者である先崎さんに、いずれ存分に語っていただいた方が良いように思われます。