14日、太平洋の向こう側からアベノミクスに対する強力な援護射撃がなされました。『さっさと不況を終わらせろ』の著者でノーベル賞経済学者のポール・クルーグマン氏が、アベノミクスを高く評価する記事をニューヨーク・タイムズに載せたのです。好都合なことに、ハンドル・ネームTakabedaiさんがご自身のブログにその和訳を公開なさっています(インターネットってスゴイですね)。それをご紹介しながら、コメントをつけたいと思います。ただし、一部分表現を変えさせていただきました。もちろん、意味内容は変えておりません。http://takabedai.blogspot.jp/2013/01/blog-post_15.html
動き出した日本(原題Japan Steps Out” )
失業率が高止まりしているのに、世界の先進国の経済政策はまちがった原則論を信奉して何年も"麻痺”している状態だった。雇用を作り出そうとする試みはすべて極端な結論を持ち出されては停止させられてきた。財政支出を増やそうとすると国債が暴落する!とか、紙幣を刷ろうとするとインフレーションが爆発する!とか、極端な悲観論者たちが騒ぎ立てる。何をしても結果など出ないのだから何もするな、というわけだ。ただ今までのような厳しい耐久生活に耐えよ、というわけだ。
「ハイパーインフレ・オオカミ少年」は海の向こうにもうようよと棲息しているようです。「 何をしても結果など出ないのだから何もするな」。これは、ひっきりなしにマスメディアに登場するアベノミクス批判の本質をズバリ言い当てています。寸鉄人を刺す、とはこのことです。シビレるなぁ。
しかしある一つの経済大国が、つまりは他でもない日本がこの状態を打破しようと動き出したように見える。
これは我々が捜し求めていたような異端者ではない。日本の政府は何度も政権交代を繰り返したけど、これまで何かが変わるようなことはなかったと思う。新しい首相となった安倍晋三氏。彼は一度政権を担った人物だけど、彼の復帰は何年も誤った経済運営を続けてきた自民党とともに、”恐竜”の復帰を予感させた。さらに日本は人口と比較して巨大な政府債務を抱えているため、他の先進国と比較しても新しい政策を試す余地がさらに限られているとみられていた。
しかし安倍首相は日本の長い不況を終わらせるとの公約の下、既に不況原理主義者が言うような政策とは違った新しい政策に着々と挑んでいるように見える。そしてその最初の踏み出しは上々のようだ。
日本の今までの背景を少し紹介すると、2008年の金融危機よりはるか前から日本は不況に苦しんできた。株価の崩落と不動産バブルの破裂を受けて日本が不況に陥った時に、日本の政策は常に過小で、遅すぎ、そして一貫性を欠いてきた。
確かに日本は大規模な財政支出を行ってきたが、財政赤字を気にするあまり引き締めに転じて、何度も確かな回復の目を摘んできてしまった。そして90年代の終わりには既にやっかいなデフレーションが根付いてしまった。2000年に入ってから日本の中央銀行である日銀はお金を刷ることによってデフレと戦おうと努力した。しかしすぐにまた引き締めに転じてデフレが消え去る機会を葬り去ってしまった。
クルーグマンは、九七年以降の日本の財政政策と金融政策が、デフレからの脱却のための一貫したものでなかったことを指摘し、批判しているのです。日本のマスコミはこれまで(そうしていまにおいても)、一貫して積極財政を叩き続け(土建国家批判!)、日銀の金融政策の重要性をまったくといっていいほどに理解してきませんでした。そうしてひたすらに、日銀と財務省が供給する情報をヘドロのように垂れ流し続けてきました。日本のマスコミは、国力弱体のために陰謀を張り巡らせてきたというのではなく、単に不勉強で能力が低いだけだったのです。彼らは、学力が足りないのに学級委員にだけはなりたがる中身が空っぽの権威主義的な生徒のようなものだったのです。
このことが示しているのは、日本は2008年から続く高失業率や災禍を経験する必要はなかったってことなんだ。(中略)
これまでの日本の経験は、僕らにもう一つの教訓を教えてくれる。長く続いた不況からの脱出は難しいってのは確かなんだけど、それは主に政策遂行者に果敢な政策を採らせることが難しいことから生じているってことを。つまり問題の本質は経済的な問題というよりも政治上・知性上の問題だということなんだ。実際のところ、積極政策のリスクは悲観論者が君たちに信じ込ませたいリスクよりもずいぶんと小さいものなんだよ。
クルーグマン先生の尻馬に乗ります。私はたびたび経済問題の本質には、「誤った思想」をいかに乗り越えるかという問題がある、と申し上げてきました。言いかえれば、狂った羅針盤には、デフレ脱却の能力がはじめからなかった、ということです。私は、政府内とアカデミズムの市場原理主義者や構造改革原理主義者や規制緩和原理主義者、財務省内の緊縮財政原理主義者、日銀内の金融引き締め原理主義者のことを言っているのです。彼らは、寄ってたかって日本をデフレ地獄に日本を叩き込み続けてきた無駄飯喰らいの連中です。
巷間言われている政府債務や赤字の問題について考えてみよう。ここアメリカでは我々はいつも「財政赤字を減らさなければならない、さもないとギリシャみたいになる」と警告している。しかしギリシャは通貨発行権なき国家であって、アメリカとは似ても似つかない国だよ。アメリカはよっぽど日本のほうに似ている。悲観論者は破滅の兆候として、長期金利の度々の上昇を挙げながら財政破綻の可能性を論じ続けるんだけど、いつまでたってもその日は来ない。日本政府は依然として1%以下の金利で長期国債を発行することができるってのに。
「さあ、財政破綻だ!」「ほらハイパーインフレだ!」と「オオカミ少年」たちはデフレ状況下で吠え続けました。そうして、いまだに懲りることもなく同じ吠え声を上げています。
そして安倍首相だ。首相はより高い物価を目指すように日銀に圧力をかけながら、それによって政府債務の一部を償却しようとして、同時に積極的な財政政策を行うことを高らかに宣言した。で、それにたいしてマーケットはどう反応したか?
あらゆる反応が良好だと答えておこう。長いことマイナスであった期待インフレ率が、言いかえれば、マーケットによって目下のデフレが長いこと続くと予想されていた期待インフレ率が勢いよくプラスのレベルに入ってきているのだ。にもかかわらず政府債務の金利はまったく変化しているようには見えない。これは、まずまずのインフレが続いていけば日本の財政事情が急速に改善していくことを予見してくれているんだ。円の為替レートも下がり続け、これは本当にいいニュースだ、輸出状況も大幅に改善していくことだろう。
「日本の財政事情が急速に改善していくことを予見してくれている」。これは、緊縮財政原理主義者が言い募ってきた財政再建そのものです。彼らが主張する歳出削減によってではなく、大胆な量的緩和と積極的な財政出動によってこそ財政再建が実現すると、クルーグマンは言っているのです。真理はいつも「水が上から下に流れるように無理のないものである」、との念を強くします。
要するに、安倍氏はすばらしい結果を出して原理主義者たちをあしらうことに成功したんだ。
安倍首相は外交的にそんなに”良心的”な政治家ではないよ、と僕に忠告してくれる日本の政治にいくらか詳しい人がいる。そんな人たちによれば、彼は利益誘導型の古いタイプの政治家に過ぎないそうだ。
だけどそれがなんだっていうんだろう。彼の意図がどこにあろうと彼が今やっていることは原理主義を打破しているのだ。彼が成功した暁には何かすばらしいことが起こったことを意味するだろう。つまりそれは世界の他の国々に対してどうやって不況から脱出するのかについての模範を示してくれているのだ。
私は、いまの安倍首相を世界水準の政治家であると思っています。言いかえれば、彼は経済政策や外交における世界レベルでの常識・良識がなんであるのかをよくわきまえていて、その常識・良識を着実に大胆に踏み行おうとしているのではないかと思っているのです。その視野の広さゆえの風通しの良さこそがいまの彼の自信にあふれた態度の根底にあるものなのではないでしょうか。
とは言うものの、一方では楽観ばかりしてはいられない状況もあります。それを列挙します。
一つ目。小泉構造改革を推進した経済財政諮問会議が三年五ヶ月ぶりに復活しました。今年の半ばをメドに作成される予定の当会議の方針の名前がなんと「骨太の方針」なのです。私は、この名前を目にすると新自由主義の権化・竹中平蔵の顔が浮かんできます。新聞でこの「骨太」の文字を目にしたとき、大袈裟ではなく恐怖感と不快感が湧いてきました。事実安倍首相は、当会議のメンバーとして竹中平蔵を提案したとのこと。ところが、麻生財務大臣と甘利経産大臣が難色を示したので実現しなかったそうです(朝日新聞一月十日)。
二つ目。当会議のメンバーにこれまたゴリゴリの新自由主義者にして「オオカミ少年」の伊藤元重(東大大学院教授)とこれまたゴリゴリの新自由主義者・高橋進(日本総合研究所理事長)がいること。いずれも要注意人物です。伊藤元重を迎えたのは、安倍首相の石破幹事長懐柔策なのではないかと推測します。
三つ目。産業競争力会議のメンバーに竹中平蔵がいること。竹中は、規制緩和とTPP参加を強力に推し進めようとするでしょう。その動きが一定以上の力をもってしまうと、デフレ脱却の足を引っ張ることになります。
政治は妥協の産物であります。だから、たとえ安倍首相が心の底からの国民経済派であるとしても、同じ考え方の人間だけで政府機構という巨大組織を固めることが不可能なことは、私にも理解できます。しかしながらそのことは、政治にはミイラ取りがミイラになる危険が伴うことを意味するのではないでしょうか。それゆえ、優れた政治家は理想を追求する情熱を保持し続ける強い意志の持ち主であると同時に、海千山千の手練手管も駆使できる「人たらし」であることも求められるのでしょう。その矛盾する要求にどこまで応えられるか、そこは安倍首相の力量次第というよりほかはありません。そういう意味で、安倍首相をかつてのように心理的に「孤立」に追い込むのが一番まずい状況なのではないかと思われます。
動き出した日本(原題Japan Steps Out” )
失業率が高止まりしているのに、世界の先進国の経済政策はまちがった原則論を信奉して何年も"麻痺”している状態だった。雇用を作り出そうとする試みはすべて極端な結論を持ち出されては停止させられてきた。財政支出を増やそうとすると国債が暴落する!とか、紙幣を刷ろうとするとインフレーションが爆発する!とか、極端な悲観論者たちが騒ぎ立てる。何をしても結果など出ないのだから何もするな、というわけだ。ただ今までのような厳しい耐久生活に耐えよ、というわけだ。
「ハイパーインフレ・オオカミ少年」は海の向こうにもうようよと棲息しているようです。「 何をしても結果など出ないのだから何もするな」。これは、ひっきりなしにマスメディアに登場するアベノミクス批判の本質をズバリ言い当てています。寸鉄人を刺す、とはこのことです。シビレるなぁ。
しかしある一つの経済大国が、つまりは他でもない日本がこの状態を打破しようと動き出したように見える。
これは我々が捜し求めていたような異端者ではない。日本の政府は何度も政権交代を繰り返したけど、これまで何かが変わるようなことはなかったと思う。新しい首相となった安倍晋三氏。彼は一度政権を担った人物だけど、彼の復帰は何年も誤った経済運営を続けてきた自民党とともに、”恐竜”の復帰を予感させた。さらに日本は人口と比較して巨大な政府債務を抱えているため、他の先進国と比較しても新しい政策を試す余地がさらに限られているとみられていた。
しかし安倍首相は日本の長い不況を終わらせるとの公約の下、既に不況原理主義者が言うような政策とは違った新しい政策に着々と挑んでいるように見える。そしてその最初の踏み出しは上々のようだ。
日本の今までの背景を少し紹介すると、2008年の金融危機よりはるか前から日本は不況に苦しんできた。株価の崩落と不動産バブルの破裂を受けて日本が不況に陥った時に、日本の政策は常に過小で、遅すぎ、そして一貫性を欠いてきた。
確かに日本は大規模な財政支出を行ってきたが、財政赤字を気にするあまり引き締めに転じて、何度も確かな回復の目を摘んできてしまった。そして90年代の終わりには既にやっかいなデフレーションが根付いてしまった。2000年に入ってから日本の中央銀行である日銀はお金を刷ることによってデフレと戦おうと努力した。しかしすぐにまた引き締めに転じてデフレが消え去る機会を葬り去ってしまった。
クルーグマンは、九七年以降の日本の財政政策と金融政策が、デフレからの脱却のための一貫したものでなかったことを指摘し、批判しているのです。日本のマスコミはこれまで(そうしていまにおいても)、一貫して積極財政を叩き続け(土建国家批判!)、日銀の金融政策の重要性をまったくといっていいほどに理解してきませんでした。そうしてひたすらに、日銀と財務省が供給する情報をヘドロのように垂れ流し続けてきました。日本のマスコミは、国力弱体のために陰謀を張り巡らせてきたというのではなく、単に不勉強で能力が低いだけだったのです。彼らは、学力が足りないのに学級委員にだけはなりたがる中身が空っぽの権威主義的な生徒のようなものだったのです。
このことが示しているのは、日本は2008年から続く高失業率や災禍を経験する必要はなかったってことなんだ。(中略)
これまでの日本の経験は、僕らにもう一つの教訓を教えてくれる。長く続いた不況からの脱出は難しいってのは確かなんだけど、それは主に政策遂行者に果敢な政策を採らせることが難しいことから生じているってことを。つまり問題の本質は経済的な問題というよりも政治上・知性上の問題だということなんだ。実際のところ、積極政策のリスクは悲観論者が君たちに信じ込ませたいリスクよりもずいぶんと小さいものなんだよ。
クルーグマン先生の尻馬に乗ります。私はたびたび経済問題の本質には、「誤った思想」をいかに乗り越えるかという問題がある、と申し上げてきました。言いかえれば、狂った羅針盤には、デフレ脱却の能力がはじめからなかった、ということです。私は、政府内とアカデミズムの市場原理主義者や構造改革原理主義者や規制緩和原理主義者、財務省内の緊縮財政原理主義者、日銀内の金融引き締め原理主義者のことを言っているのです。彼らは、寄ってたかって日本をデフレ地獄に日本を叩き込み続けてきた無駄飯喰らいの連中です。
巷間言われている政府債務や赤字の問題について考えてみよう。ここアメリカでは我々はいつも「財政赤字を減らさなければならない、さもないとギリシャみたいになる」と警告している。しかしギリシャは通貨発行権なき国家であって、アメリカとは似ても似つかない国だよ。アメリカはよっぽど日本のほうに似ている。悲観論者は破滅の兆候として、長期金利の度々の上昇を挙げながら財政破綻の可能性を論じ続けるんだけど、いつまでたってもその日は来ない。日本政府は依然として1%以下の金利で長期国債を発行することができるってのに。
「さあ、財政破綻だ!」「ほらハイパーインフレだ!」と「オオカミ少年」たちはデフレ状況下で吠え続けました。そうして、いまだに懲りることもなく同じ吠え声を上げています。
そして安倍首相だ。首相はより高い物価を目指すように日銀に圧力をかけながら、それによって政府債務の一部を償却しようとして、同時に積極的な財政政策を行うことを高らかに宣言した。で、それにたいしてマーケットはどう反応したか?
あらゆる反応が良好だと答えておこう。長いことマイナスであった期待インフレ率が、言いかえれば、マーケットによって目下のデフレが長いこと続くと予想されていた期待インフレ率が勢いよくプラスのレベルに入ってきているのだ。にもかかわらず政府債務の金利はまったく変化しているようには見えない。これは、まずまずのインフレが続いていけば日本の財政事情が急速に改善していくことを予見してくれているんだ。円の為替レートも下がり続け、これは本当にいいニュースだ、輸出状況も大幅に改善していくことだろう。
「日本の財政事情が急速に改善していくことを予見してくれている」。これは、緊縮財政原理主義者が言い募ってきた財政再建そのものです。彼らが主張する歳出削減によってではなく、大胆な量的緩和と積極的な財政出動によってこそ財政再建が実現すると、クルーグマンは言っているのです。真理はいつも「水が上から下に流れるように無理のないものである」、との念を強くします。
要するに、安倍氏はすばらしい結果を出して原理主義者たちをあしらうことに成功したんだ。
安倍首相は外交的にそんなに”良心的”な政治家ではないよ、と僕に忠告してくれる日本の政治にいくらか詳しい人がいる。そんな人たちによれば、彼は利益誘導型の古いタイプの政治家に過ぎないそうだ。
だけどそれがなんだっていうんだろう。彼の意図がどこにあろうと彼が今やっていることは原理主義を打破しているのだ。彼が成功した暁には何かすばらしいことが起こったことを意味するだろう。つまりそれは世界の他の国々に対してどうやって不況から脱出するのかについての模範を示してくれているのだ。
私は、いまの安倍首相を世界水準の政治家であると思っています。言いかえれば、彼は経済政策や外交における世界レベルでの常識・良識がなんであるのかをよくわきまえていて、その常識・良識を着実に大胆に踏み行おうとしているのではないかと思っているのです。その視野の広さゆえの風通しの良さこそがいまの彼の自信にあふれた態度の根底にあるものなのではないでしょうか。
とは言うものの、一方では楽観ばかりしてはいられない状況もあります。それを列挙します。
一つ目。小泉構造改革を推進した経済財政諮問会議が三年五ヶ月ぶりに復活しました。今年の半ばをメドに作成される予定の当会議の方針の名前がなんと「骨太の方針」なのです。私は、この名前を目にすると新自由主義の権化・竹中平蔵の顔が浮かんできます。新聞でこの「骨太」の文字を目にしたとき、大袈裟ではなく恐怖感と不快感が湧いてきました。事実安倍首相は、当会議のメンバーとして竹中平蔵を提案したとのこと。ところが、麻生財務大臣と甘利経産大臣が難色を示したので実現しなかったそうです(朝日新聞一月十日)。
二つ目。当会議のメンバーにこれまたゴリゴリの新自由主義者にして「オオカミ少年」の伊藤元重(東大大学院教授)とこれまたゴリゴリの新自由主義者・高橋進(日本総合研究所理事長)がいること。いずれも要注意人物です。伊藤元重を迎えたのは、安倍首相の石破幹事長懐柔策なのではないかと推測します。
三つ目。産業競争力会議のメンバーに竹中平蔵がいること。竹中は、規制緩和とTPP参加を強力に推し進めようとするでしょう。その動きが一定以上の力をもってしまうと、デフレ脱却の足を引っ張ることになります。
政治は妥協の産物であります。だから、たとえ安倍首相が心の底からの国民経済派であるとしても、同じ考え方の人間だけで政府機構という巨大組織を固めることが不可能なことは、私にも理解できます。しかしながらそのことは、政治にはミイラ取りがミイラになる危険が伴うことを意味するのではないでしょうか。それゆえ、優れた政治家は理想を追求する情熱を保持し続ける強い意志の持ち主であると同時に、海千山千の手練手管も駆使できる「人たらし」であることも求められるのでしょう。その矛盾する要求にどこまで応えられるか、そこは安倍首相の力量次第というよりほかはありません。そういう意味で、安倍首相をかつてのように心理的に「孤立」に追い込むのが一番まずい状況なのではないかと思われます。












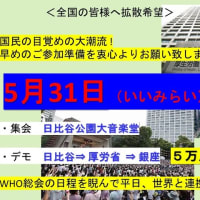















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます