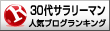三国無双や信長の野望といった歴史モノに特化したマニアックなソフトを信じがたい値段で売る
ニッチ(でありながらそこそこメジャー)なゲームメーカーとは関係ありません。
先日、新入社員の歓迎会で楽器を弾くという話をしました。
それが、今日。
会社に楽器を持っていくと部長クラスの人の机脇スペース(ちょっと広め)を占拠する旨の届出を
別途出すことになって大変めんどくさいので、一旦帰宅してから歓迎会に出かけました。
オケの皆さんとは長い付き合いなので、今さら自転車でチェロを運んでも誰も突っ込まないと思いますが、
やはりオケに携わっていない人にとってはその光景は奇異に映るようでした。
で、演奏。今までクラシック一筋でしか楽器を弾いてこなかった僕にとっては、
ポップスのボーカルを楽器で弾くというのは、そういう機会をもらえたのは、
光栄なことであり、勉強になることでした。
◇ ここからが今日のBlogの本題。この◇内以外は、読んでもらえなくてもいい。
具体的には…
オケの曲を弾いているときにあまり意識したことがありませんでしたが、
僕は相対音感というものを今までバカにしすぎていたみたいです。
多分、「相対音感をバカにする」ということの意味を具体的に書いたほうが良いのでしょう。
たとえば音程を取る練習をするとき、皆さんはどんな練習をしますか?
…って訊いても仕方がないので、僕の従来の考え方を申し上げます。
絶対音感的に正しい音程を取ることです。
なぜなら、それが完璧だから。
より完璧にするために、「絶対音感的に正しい音程を取り続けること」と書き換えましょうか。
センスがきちんと磨けていないのに絶対音感が自分にあると勘違いしている態度です。
チューナー使って音程とっても、いいんだぜ。って言ってる人もいる。
おめでたいな。
必要以上に自分を卑下したくありませんが、多分、巧くならない練習の仕方なんだなと思い知りました。
何故、そう感じたか?
昨日今日のボーカル練習を通じて感じたことですが、絶対音感頼りの練習は、
前後の音との関係を無視したひどくちぐはぐな音程を持ったものになりやすいからです。
一つ一つの音を自分で聴いて、その一つ一つの音にジャッジを利かせる代わりに
前後の音との関係(調性といってもいいのでしょう)には注意が向きません。
ボーカル部分を弾いていると、前後の音の関係がわかりやすく重要で、
それが果たされないときの気持ち悪さがクラシック音楽の数倍ある、ような気がしました。
(実際に歌ではそれが重要なのか、それともフレーズを口ずさんだ回数の違いが
前後の音の確固とした関係性を僕の中に形作り、違和感を生んだのかはよくわかりません。)
カラオケでいくら♭1個つけた状態に設定して歌っても
それで「音程が半音分悪い」とは誰も指摘しないわけで、
まさかあの装置の意味が
「絶対音感的に正しくなくてもいいから曲としての音程感を保つことに
意識を集中しろ、そっちのが重要だ」
ってことだったとは。
(高い声が出ない人のための救済措置だと、ずっと思ってました。)
今日まで気付かなかった。
ニッチ(でありながらそこそこメジャー)なゲームメーカーとは関係ありません。
先日、新入社員の歓迎会で楽器を弾くという話をしました。
それが、今日。
会社に楽器を持っていくと部長クラスの人の机脇スペース(ちょっと広め)を占拠する旨の届出を
別途出すことになって大変めんどくさいので、一旦帰宅してから歓迎会に出かけました。
オケの皆さんとは長い付き合いなので、今さら自転車でチェロを運んでも誰も突っ込まないと思いますが、
やはりオケに携わっていない人にとってはその光景は奇異に映るようでした。
で、演奏。今までクラシック一筋でしか楽器を弾いてこなかった僕にとっては、
ポップスのボーカルを楽器で弾くというのは、そういう機会をもらえたのは、
光栄なことであり、勉強になることでした。
◇ ここからが今日のBlogの本題。この◇内以外は、読んでもらえなくてもいい。
具体的には…
オケの曲を弾いているときにあまり意識したことがありませんでしたが、
僕は相対音感というものを今までバカにしすぎていたみたいです。
多分、「相対音感をバカにする」ということの意味を具体的に書いたほうが良いのでしょう。
たとえば音程を取る練習をするとき、皆さんはどんな練習をしますか?
…って訊いても仕方がないので、僕の従来の考え方を申し上げます。
絶対音感的に正しい音程を取ることです。
なぜなら、それが完璧だから。
より完璧にするために、「絶対音感的に正しい音程を取り続けること」と書き換えましょうか。
センスがきちんと磨けていないのに絶対音感が自分にあると勘違いしている態度です。
チューナー使って音程とっても、いいんだぜ。って言ってる人もいる。
おめでたいな。
必要以上に自分を卑下したくありませんが、多分、巧くならない練習の仕方なんだなと思い知りました。
何故、そう感じたか?
昨日今日のボーカル練習を通じて感じたことですが、絶対音感頼りの練習は、
前後の音との関係を無視したひどくちぐはぐな音程を持ったものになりやすいからです。
一つ一つの音を自分で聴いて、その一つ一つの音にジャッジを利かせる代わりに
前後の音との関係(調性といってもいいのでしょう)には注意が向きません。
ボーカル部分を弾いていると、前後の音の関係がわかりやすく重要で、
それが果たされないときの気持ち悪さがクラシック音楽の数倍ある、ような気がしました。
(実際に歌ではそれが重要なのか、それともフレーズを口ずさんだ回数の違いが
前後の音の確固とした関係性を僕の中に形作り、違和感を生んだのかはよくわかりません。)
カラオケでいくら♭1個つけた状態に設定して歌っても
それで「音程が半音分悪い」とは誰も指摘しないわけで、
まさかあの装置の意味が
「絶対音感的に正しくなくてもいいから曲としての音程感を保つことに
意識を集中しろ、そっちのが重要だ」
ってことだったとは。
(高い声が出ない人のための救済措置だと、ずっと思ってました。)
今日まで気付かなかった。