【訂正など】
1)〔幸徳秋水の病歴〕前号の記述に関して以下の書き込みがあった。
<Unknown (Unknown)=2017-06-11 12:39
知る限りでは喉頭癌で「余命一年半」と執刀医に宣告され(1904/4)、「一年有半:生前の遺稿」(岩波文庫)を書いた中江兆民(1847-1901)が、「がん告知」患者の第一号だろう。
いつ宣告されたのか知らんが、死亡年より後ということはありえないだろう。>
<Unknown (Unknown)
2017-06-11 12:51
調べてみた。
余命宣告を行ったのは堀内謙吉医師。どうしてこの医師をナンバ氏が「執刀医」と表記したのか分からない。宣告は、明治34年4月。すなわち、1901年だ。おそらく34と1901を混同したのだろう。
因みに、篤志病理解剖の結果、兆民の死因は喉頭がんではなく食道がんであることが分かったらしい。>
Unknownさんのご指摘に感謝する。岩波文庫「一年有半・続一年有半」にある年譜によると兆民の生存年は1847(弘化4)年〜1901(明治34)年である。私の誤記だ。訂正する。
兆民が大阪の耳鼻咽喉科医・堀内謙吉により「喉頭がん」の診断を受けたのは、1901/4のことだ。堀内謙吉は緒方洪庵の外孫で、ドイツ・フライブルグ大学に留学し医学博士号を得ているから、普通の町医者ではない。堀内はこの時に兆民のたっての頼みにより、「余命1年半、よく養生すれば2年」という余命告知をしている。当初は「腫瘍切開(喉頭全摘)」の予定だったが、「一年有半もあれば、まだ著述ができる」と考えた兆民が堀内医師と話しあい、手術は止め、保存的治療をすることになった。
ところが兆民夫妻が東京へ引きあげたいと話したところ、「途中で(癌腫による)気管閉塞の可能性があるので極めて危険」といわれて、5/26同医院で気管切開術を行い、傷口から銀製のカニューレを気管内に挿入している。8/25に大阪で撮影された写真が残っているが、包帯を巻いた頚の下部、胸骨のすぐ上にカニューレの開口部が認められる。(立川昭二「病の人間史」新潮社、1989、p.51))
 (気管切開術後の中江兆民)
(気管切開術後の中江兆民)
この写真を見ると、包帯を巻いた下頸部に穴が開いており、喉頭がんが摘出された後のようにも見える。実際には両頸部にがんの局所浸潤があったことは後に病理解剖で確認されている。写真でもそのつもりで見ると、左下顎—左下頸部の皮下に異常な腫大がある。
「世の中の人は根本的切開と気管切開の違いが分かっていないので、(公表されると、がんを全摘したものと思い)祝いの手紙が沢山来た」と兆民は書いている。
どうもこの辺に「兆民の喉頭がん」についての誤解(私もその一人だが)の出発点があるようだ。堀内医師は診断医であり、がん告知と余命告知を行い、銀製気管カニューレの設置術を行っているので、「執刀医」としても間違いではないが、私は後頭部腫瘍の「摘出医」と思っていた。
その後、大阪中之島の旅館に滞在し、療養を続けた。
その間、8/3博文舘社員が、出来上がった「一年有半」の原稿を受け取りに大阪に来ている。(同本は9/2に博文舘から出版され、初版1万部が3日で売り切れたそうだ。)
兆民夫妻は9/7大阪を発ち、途中で観光・保養し、9/10東京の自宅に戻った。翌日、東大耳鼻咽喉科の岡田和一郎助教授が小石川の兆民自宅に往診している。以後彼が兆民の主治医となった。
弟子の幸徳秋水による「兆民先生・兆民先生行状記」(岩波文庫)にも、東大で手術を受けたという記述がなく、岩波文庫「一年有半・続一年有半」にある年譜にも、東大での手術についての記録がない。よって兆民は大阪での気管切開以外には手術を受けていないと思われる。
12/13に夕方「がん悪液質」のため自宅で死亡。12/14に弟子たちが棺を東大病理学教室まで運び、遺言に従って病理解剖が行われた。幸徳秋水「兆民先生」には、秋水の解剖見聞記と葬儀で弔辞を述べた大石誠之助(和歌山の医師、後に大逆事件に連座して刑死)の感想が含まれている。
話を要約すると、1901/4〜1901/9/6まで兆民は大阪で堀内医師による治療(気管切開を含む)を受けていた。
9/10東京へ戻ってからは東京帝大耳鼻咽喉科の岡田医師にかかっている。しかしここでは手術を受けていない。
大阪の堀内医師と東京の岡田医師を兆民に紹介したのは、井田進也「2001年の中江兆民」(光芒社、2001/12)によると、兆民の従兄弟で医師・細菌学博士の浅川範彦だという。このために、兆民の治療をめぐる大阪と東京の医師たちの連係プレーが、すみやかに成立したと思われる。
さて兆民の「喉頭がん」だが、当時のことでレントゲン撮影とか組織生検は行われていない。肉眼所見だけで堀内医師は診断したし、東大の医師も喉頭鏡で観察して同じ診断に達したものと思われる。
これを「食道がん」としているのは、病理解剖所見に基づいて書かれた、酒井シヅ「病が語る日本史」(講談社学術文庫、2008/8)である。ただこの本には原資料の引用がない。
この「喉頭がん」から「食道がん」への診断転換の理由がよくわからないが、立川昭二「病の人間史:明治・大正・昭和」(新潮社、1989/12)には、病理解剖の執刀者、山極勝三郎教授による病理解剖所見(プロトコル)が取りあげられており、「臨床診断=喉頭がん」、「剖検診断=食道がん」と記載されている。これでプロトコルの記載が根拠だとわかった。
遺体の体重20Kgというのが痛々しい。それにしては「脳重量415匁」(1,556グラム)というのには驚く。(匁表示になっているのは、立川昭二が12/17「読売新聞」の「故兆民居士遺体解剖」という記事から引用しているからで、当時の新聞は好んでこの手の記事を掲載した。)
1902年における55歳男子の脳重量平均値は1389グラムである。(簑島高・編「日本人人体正常数値表」技報堂、1974)兆民の脳はそれを167g(12%)上まわり、死亡時体重の7.8%を占める。
なお井田進也「2001年の中江兆民」は、主として耳鼻科医の意見や学会誌を引用し、「下咽頭がん」説を述べている。彼は大阪成人病センター名誉院長佐藤武男(耳鼻咽喉科医)の意見として、兆民のがんの発生部位は左下咽頭の「梨状陥凹部」であり、広義の下咽頭がんで、池田勇人首相もこのタイプのがんだったと記している。
改めて立川昭二が引用している岡田助教授が兆民を往診した時の記録(兆民死後に学会誌に掲載された)を精読すると、患者は「枯れて、瘦せ果てた状態。筋肉・脂肪共に消耗」、「何とか舌を引き出し、小喉頭鏡を入れて検査」すると、「下咽頭粘膜には異常がなく、下から腫瘍により瀰漫性に圧迫され、食道入口は喉頭外にある腫瘍により、左側から圧迫されてわずかに四分の一の通路が残っている。腫瘍は左梨状窩にあり、びまん性に周囲に広がり、腫脹・突起していて喉頭腔をほとんど閉塞している」(意訳)とある。
原発部位についてはこれでほぼ確定だ。要するに臨床的には喉頭がんと診断されたが、病理解剖で「食道がん」とされた。しかし耳鼻科の岡田や佐藤の解釈では、下咽頭梨状窩に発生した「下咽頭がん」で、喉頭を侵し、さらに肺にも浸潤する特殊ながんだったというわけだ。下咽頭部で気管と食道が分岐するから、この部位の局所解剖は非常に複雑だ。
当時の医学では「下咽頭がん」と「上部食道がん」を厳密に区別するのは無理だったと思う。あと必要なのはがんの病理組織学的所見だが、遺体から摘出された喉頭・食道腫瘤は少なくとも耳鼻科教室に標本として保存されたことが岡田の症例報告の一部から判明する。病理学教室にも保存されたかも知れない。
その顕微鏡所見が知りたいが、ちょっと手がかりがない。
山田風太郎「人間臨終図鑑」(徳間書店、1986/9)、
服部敏良「事典・有名人の死亡診断 近代編」(吉川弘文館、2010/5)は共に喉頭がん説である。
中江兆民の仕事は多々あるが、「続一年有半」という日本初のオリジナル哲学書を書いたことが、最大の業績として上げられるだろう。彼はこれを「ナカエイズム」と称している。書名が「哲学」とも「理学」ともなっていないので、知名度が低いのが残念だ。(兆民の哲学は、自然科学を基礎として霊魂とか意思の自由など、哲学の課題を論じており、現在の知識に照らしてもきわめて妥当である。論理主体の科学哲学とは異なる。)彼が創始となったものとして、
1. 医師にがん告知と余命告知を求めたこと、
2. 余命を知り2冊の本を書いたこと、
3. 篤志病理解剖を希望したこと、
4. 葬儀をせず、日本初の告別式を(弟子たちが)行ったこと(参列者1000人)
などが上げられるだろう。
兆民は声を失っており、癌末期の「悪液質」の状態にあったが、「続一年有半」を9月13日から正味わずか10日間で書き上げた。死んだ時の体重はわずか20キロだったが、脳の重さは1.56キロもあった。脳の萎縮がまったくない。どうしてこんなことが可能だったのだろうか?
我田引水といわれるかも知れないが、これは兆民の脳が、身体の脂肪と筋肉を分解してケトン体に変え、これを燃料として活動したからだと思われる。病床から起きることもままならず、参考書の類はいっさい手にしていない(と弟子幸徳秋水が述べている)。脳中に蓄えられた記憶のみを素材として、あの書をわずか10日で書いた。好きだった酒ももちろん飲めなくなっていた。
がん性悪液質の患者で、食道入口部の狭窄のため、食事もほんど取れないのに、あれほど透徹した論理で、哲学、宗教、自然科学の知識を駆使して、首尾一貫した著述をなしえるには、きわめて高い集中力と持続力を必要とする。「死への不安」などが生じては仕事ができない。
つまり兆民は「安心立命」の境地を維持できたのだろう。それはからだがある種の「オートファジー」(自分で自分を食うこと)の状態となり、体脂肪と筋肉を分解して産生されるケトン体を、脳が燃料とする「ケトン体エンジン」によりフル回転したからだろう。ケトン体は脳が好んで取り込むが、がん細胞はグルコースを優先的に取り込むから、逆にがん細胞への栄養補給が抑制され、兆民は誰もが驚く驚異的スピードで「続一年有半」の執筆を完了できたのではないか?と思っている。
2)〔書評〕「買いたい新書」の書評に、
No.376:鴻巣友季子(編)「ルイス・キャロル」, 集英社文庫
No.377:金素雲「朝鮮史譚」(講談社学術文庫)
を取り上げました。
前者は「不思議の国アリス」、「鏡の国のアリス」など数学者ルイス・キャロルの童話を一冊にまとめ、有名な画家ジョン・テニエルの挿絵も添えたもので、コンパクトでお買い得品です。
後者は朝鮮人の作家(1908-1981)が、高麗王朝による朝鮮統一から李氏朝鮮王朝の滅亡(日韓併合)まで、二王朝千年の歴史を17の短編小説により描いたもので、わかりやすいのが特徴です。
こちらの「新着順一覧」から目当ての本の書評にたどりつけます。
http://www.frob.co.jp/kaitaishinsho/new2.php
No.372. 旦部幸博『コーヒーの科学:「おいしさ」はどこで生まれるのか』(講談社ブルーバックス)なぜか評者のNo.と掲載順がずれてしまいました。
1)〔幸徳秋水の病歴〕前号の記述に関して以下の書き込みがあった。
<Unknown (Unknown)=2017-06-11 12:39
知る限りでは喉頭癌で「余命一年半」と執刀医に宣告され(1904/4)、「一年有半:生前の遺稿」(岩波文庫)を書いた中江兆民(1847-1901)が、「がん告知」患者の第一号だろう。
いつ宣告されたのか知らんが、死亡年より後ということはありえないだろう。>
<Unknown (Unknown)
2017-06-11 12:51
調べてみた。
余命宣告を行ったのは堀内謙吉医師。どうしてこの医師をナンバ氏が「執刀医」と表記したのか分からない。宣告は、明治34年4月。すなわち、1901年だ。おそらく34と1901を混同したのだろう。
因みに、篤志病理解剖の結果、兆民の死因は喉頭がんではなく食道がんであることが分かったらしい。>
Unknownさんのご指摘に感謝する。岩波文庫「一年有半・続一年有半」にある年譜によると兆民の生存年は1847(弘化4)年〜1901(明治34)年である。私の誤記だ。訂正する。
兆民が大阪の耳鼻咽喉科医・堀内謙吉により「喉頭がん」の診断を受けたのは、1901/4のことだ。堀内謙吉は緒方洪庵の外孫で、ドイツ・フライブルグ大学に留学し医学博士号を得ているから、普通の町医者ではない。堀内はこの時に兆民のたっての頼みにより、「余命1年半、よく養生すれば2年」という余命告知をしている。当初は「腫瘍切開(喉頭全摘)」の予定だったが、「一年有半もあれば、まだ著述ができる」と考えた兆民が堀内医師と話しあい、手術は止め、保存的治療をすることになった。
ところが兆民夫妻が東京へ引きあげたいと話したところ、「途中で(癌腫による)気管閉塞の可能性があるので極めて危険」といわれて、5/26同医院で気管切開術を行い、傷口から銀製のカニューレを気管内に挿入している。8/25に大阪で撮影された写真が残っているが、包帯を巻いた頚の下部、胸骨のすぐ上にカニューレの開口部が認められる。(立川昭二「病の人間史」新潮社、1989、p.51))
 (気管切開術後の中江兆民)
(気管切開術後の中江兆民)この写真を見ると、包帯を巻いた下頸部に穴が開いており、喉頭がんが摘出された後のようにも見える。実際には両頸部にがんの局所浸潤があったことは後に病理解剖で確認されている。写真でもそのつもりで見ると、左下顎—左下頸部の皮下に異常な腫大がある。
「世の中の人は根本的切開と気管切開の違いが分かっていないので、(公表されると、がんを全摘したものと思い)祝いの手紙が沢山来た」と兆民は書いている。
どうもこの辺に「兆民の喉頭がん」についての誤解(私もその一人だが)の出発点があるようだ。堀内医師は診断医であり、がん告知と余命告知を行い、銀製気管カニューレの設置術を行っているので、「執刀医」としても間違いではないが、私は後頭部腫瘍の「摘出医」と思っていた。
その後、大阪中之島の旅館に滞在し、療養を続けた。
その間、8/3博文舘社員が、出来上がった「一年有半」の原稿を受け取りに大阪に来ている。(同本は9/2に博文舘から出版され、初版1万部が3日で売り切れたそうだ。)
兆民夫妻は9/7大阪を発ち、途中で観光・保養し、9/10東京の自宅に戻った。翌日、東大耳鼻咽喉科の岡田和一郎助教授が小石川の兆民自宅に往診している。以後彼が兆民の主治医となった。
弟子の幸徳秋水による「兆民先生・兆民先生行状記」(岩波文庫)にも、東大で手術を受けたという記述がなく、岩波文庫「一年有半・続一年有半」にある年譜にも、東大での手術についての記録がない。よって兆民は大阪での気管切開以外には手術を受けていないと思われる。
12/13に夕方「がん悪液質」のため自宅で死亡。12/14に弟子たちが棺を東大病理学教室まで運び、遺言に従って病理解剖が行われた。幸徳秋水「兆民先生」には、秋水の解剖見聞記と葬儀で弔辞を述べた大石誠之助(和歌山の医師、後に大逆事件に連座して刑死)の感想が含まれている。
話を要約すると、1901/4〜1901/9/6まで兆民は大阪で堀内医師による治療(気管切開を含む)を受けていた。
9/10東京へ戻ってからは東京帝大耳鼻咽喉科の岡田医師にかかっている。しかしここでは手術を受けていない。
大阪の堀内医師と東京の岡田医師を兆民に紹介したのは、井田進也「2001年の中江兆民」(光芒社、2001/12)によると、兆民の従兄弟で医師・細菌学博士の浅川範彦だという。このために、兆民の治療をめぐる大阪と東京の医師たちの連係プレーが、すみやかに成立したと思われる。
さて兆民の「喉頭がん」だが、当時のことでレントゲン撮影とか組織生検は行われていない。肉眼所見だけで堀内医師は診断したし、東大の医師も喉頭鏡で観察して同じ診断に達したものと思われる。
これを「食道がん」としているのは、病理解剖所見に基づいて書かれた、酒井シヅ「病が語る日本史」(講談社学術文庫、2008/8)である。ただこの本には原資料の引用がない。
この「喉頭がん」から「食道がん」への診断転換の理由がよくわからないが、立川昭二「病の人間史:明治・大正・昭和」(新潮社、1989/12)には、病理解剖の執刀者、山極勝三郎教授による病理解剖所見(プロトコル)が取りあげられており、「臨床診断=喉頭がん」、「剖検診断=食道がん」と記載されている。これでプロトコルの記載が根拠だとわかった。
遺体の体重20Kgというのが痛々しい。それにしては「脳重量415匁」(1,556グラム)というのには驚く。(匁表示になっているのは、立川昭二が12/17「読売新聞」の「故兆民居士遺体解剖」という記事から引用しているからで、当時の新聞は好んでこの手の記事を掲載した。)
1902年における55歳男子の脳重量平均値は1389グラムである。(簑島高・編「日本人人体正常数値表」技報堂、1974)兆民の脳はそれを167g(12%)上まわり、死亡時体重の7.8%を占める。
なお井田進也「2001年の中江兆民」は、主として耳鼻科医の意見や学会誌を引用し、「下咽頭がん」説を述べている。彼は大阪成人病センター名誉院長佐藤武男(耳鼻咽喉科医)の意見として、兆民のがんの発生部位は左下咽頭の「梨状陥凹部」であり、広義の下咽頭がんで、池田勇人首相もこのタイプのがんだったと記している。
改めて立川昭二が引用している岡田助教授が兆民を往診した時の記録(兆民死後に学会誌に掲載された)を精読すると、患者は「枯れて、瘦せ果てた状態。筋肉・脂肪共に消耗」、「何とか舌を引き出し、小喉頭鏡を入れて検査」すると、「下咽頭粘膜には異常がなく、下から腫瘍により瀰漫性に圧迫され、食道入口は喉頭外にある腫瘍により、左側から圧迫されてわずかに四分の一の通路が残っている。腫瘍は左梨状窩にあり、びまん性に周囲に広がり、腫脹・突起していて喉頭腔をほとんど閉塞している」(意訳)とある。
原発部位についてはこれでほぼ確定だ。要するに臨床的には喉頭がんと診断されたが、病理解剖で「食道がん」とされた。しかし耳鼻科の岡田や佐藤の解釈では、下咽頭梨状窩に発生した「下咽頭がん」で、喉頭を侵し、さらに肺にも浸潤する特殊ながんだったというわけだ。下咽頭部で気管と食道が分岐するから、この部位の局所解剖は非常に複雑だ。
当時の医学では「下咽頭がん」と「上部食道がん」を厳密に区別するのは無理だったと思う。あと必要なのはがんの病理組織学的所見だが、遺体から摘出された喉頭・食道腫瘤は少なくとも耳鼻科教室に標本として保存されたことが岡田の症例報告の一部から判明する。病理学教室にも保存されたかも知れない。
その顕微鏡所見が知りたいが、ちょっと手がかりがない。
山田風太郎「人間臨終図鑑」(徳間書店、1986/9)、
服部敏良「事典・有名人の死亡診断 近代編」(吉川弘文館、2010/5)は共に喉頭がん説である。
中江兆民の仕事は多々あるが、「続一年有半」という日本初のオリジナル哲学書を書いたことが、最大の業績として上げられるだろう。彼はこれを「ナカエイズム」と称している。書名が「哲学」とも「理学」ともなっていないので、知名度が低いのが残念だ。(兆民の哲学は、自然科学を基礎として霊魂とか意思の自由など、哲学の課題を論じており、現在の知識に照らしてもきわめて妥当である。論理主体の科学哲学とは異なる。)彼が創始となったものとして、
1. 医師にがん告知と余命告知を求めたこと、
2. 余命を知り2冊の本を書いたこと、
3. 篤志病理解剖を希望したこと、
4. 葬儀をせず、日本初の告別式を(弟子たちが)行ったこと(参列者1000人)
などが上げられるだろう。
兆民は声を失っており、癌末期の「悪液質」の状態にあったが、「続一年有半」を9月13日から正味わずか10日間で書き上げた。死んだ時の体重はわずか20キロだったが、脳の重さは1.56キロもあった。脳の萎縮がまったくない。どうしてこんなことが可能だったのだろうか?
我田引水といわれるかも知れないが、これは兆民の脳が、身体の脂肪と筋肉を分解してケトン体に変え、これを燃料として活動したからだと思われる。病床から起きることもままならず、参考書の類はいっさい手にしていない(と弟子幸徳秋水が述べている)。脳中に蓄えられた記憶のみを素材として、あの書をわずか10日で書いた。好きだった酒ももちろん飲めなくなっていた。
がん性悪液質の患者で、食道入口部の狭窄のため、食事もほんど取れないのに、あれほど透徹した論理で、哲学、宗教、自然科学の知識を駆使して、首尾一貫した著述をなしえるには、きわめて高い集中力と持続力を必要とする。「死への不安」などが生じては仕事ができない。
つまり兆民は「安心立命」の境地を維持できたのだろう。それはからだがある種の「オートファジー」(自分で自分を食うこと)の状態となり、体脂肪と筋肉を分解して産生されるケトン体を、脳が燃料とする「ケトン体エンジン」によりフル回転したからだろう。ケトン体は脳が好んで取り込むが、がん細胞はグルコースを優先的に取り込むから、逆にがん細胞への栄養補給が抑制され、兆民は誰もが驚く驚異的スピードで「続一年有半」の執筆を完了できたのではないか?と思っている。
2)〔書評〕「買いたい新書」の書評に、
No.376:鴻巣友季子(編)「ルイス・キャロル」, 集英社文庫
No.377:金素雲「朝鮮史譚」(講談社学術文庫)
を取り上げました。
前者は「不思議の国アリス」、「鏡の国のアリス」など数学者ルイス・キャロルの童話を一冊にまとめ、有名な画家ジョン・テニエルの挿絵も添えたもので、コンパクトでお買い得品です。
後者は朝鮮人の作家(1908-1981)が、高麗王朝による朝鮮統一から李氏朝鮮王朝の滅亡(日韓併合)まで、二王朝千年の歴史を17の短編小説により描いたもので、わかりやすいのが特徴です。
こちらの「新着順一覧」から目当ての本の書評にたどりつけます。
http://www.frob.co.jp/kaitaishinsho/new2.php
No.372. 旦部幸博『コーヒーの科学:「おいしさ」はどこで生まれるのか』(講談社ブルーバックス)なぜか評者のNo.と掲載順がずれてしまいました。












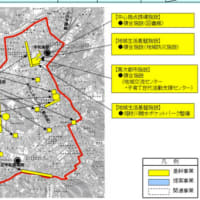
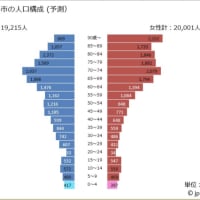



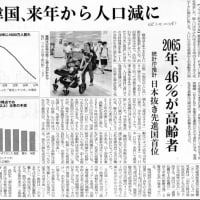










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます