【訂正など】
1)ひのえうま=前号で1966年丙午(ひのえうま)の年に「女児の選択的中絶が行われた」と書いたが、あの頃はまだ、出産前に羊水を採取してY染色体(性染色体)を調べるような技術は普及していなかった。もう一度総務省のグラフをよく見ると、この年は男子の出生数も激減していた。(付図1)これは2011年10月の総務省統計を資料としているので、2017年のデータとしては、縦軸の年齢階級に+6を足して読んでもらいたい。
「丙午の年に女児の選択的中絶があった」というのは、私の誤解だったので、お詫びして訂正したい。
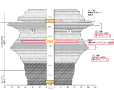
(付図1:2011年の日本の人口構成、10歳階級別グラフ・出典:総務省グラフ)
1945, 46年の出生数が少ないのは、多くの若い男が戦争に動員され、まだ復員していないか、復員していても、食うのが精一杯で、子供を作る余裕がなかったからである。1947(昭和22)年から出生数が急速に増え、これが「第一次ベビーブーム」世代を形成した。(いわゆる「団塊の世代」だ。)
1948/7に制定された「優生保護法」では、精神病や重篤な遺伝性疾患などによる「優生手術」以外の妊娠中絶は禁止されていた。これが急激な出産ブームにより、女性の社会的進出や経済的自立を妨げるとして(当時は保育園も幼稚園もなかった)、主に女性議員などの運動により、昭和24 (1949)年「母体保護」の観点から「経済的理由による中絶」が合法化された。
年別次の出生数を見れば、「第一次ベビーブーム」世代がいかに巨大な社会・経済的インパクトを与えたかがわかる。
この頃「経済的理由による中絶」は保険が利かず、自費だったから1960年代中頃まで、新聞に載る毎年の「長者番付」のトップテンには、「産婦人科医」が名を連ねていたのを記憶している。(これは後に「納税者番付」に変わり、現在は一切新聞に載らなくなった。)
このメルマガの読者から次のようなレスがあった。(本人の希望により匿名とする。)
<大学に入った年に、幼少時によくお世話になっていた、村でただ一人の内科医(小中の校医さん)の奥様から「◯◯ちゃんも医学部に入られたので、夏休みに受付の手伝いにでも来ていただけませんか?」と母が伝言され、ひと夏だけ行ったことがあります。
いっしょに開業しておられた娘婿さん(産婦人科医)の患者さんは、出産よりは妊娠中絶が圧倒的に多いことにショックを受けて、お盆を機に「宿題が残っていますから」といって辞めたことを覚えています。いわゆる経済的理由による人工妊娠中絶が認められていたころです。拝見したグラフでも丙午より前に第一次ベビーブームは下降線に入っていることを改めて認識し、政治の影響を感じました。>
私も病院から大学に異動し「学生相談室」を担当していた頃、母子家庭の女子学生が、母が病気で長期入院中に、サークルの男子学生と深い仲になり妊娠してしまった例の相談を、本人から受けたことがある。中絶可能月数の期限が近かった。泣いて後悔するその学生を見るに忍びず、大学付近で開業しておられた高校の先輩にあたる、ベテランの産婦人科医に連絡し、事情を話し「母体保護」条項による中絶手術をお願いしたことがある。
世の中はどう変わるか分からないもので、その後、コンドーム、ペッサリー、ピルなどの普及により「望まない妊娠」は激減した。つまり「少子化社会」の到来だ。その代わり「車社会」になり、整形外科医が流行り始めた。当時は、治療費は加害者負担で、通常の保険点数の倍額が請求されたので、整形外科医の年収が急増し、長者番付のトップテンが入れ替わった。
我々のクラスは40人編成だったが、整形外科が最も人気が高く、5人が進んだ。基礎医学では病理学が人気で私を含め4人が進んだ。整形外科も交通事故が減り、AIによる自動運転車が普及すると、骨折外傷は稀になる恐れがある。診断病理学も、AIが「遠隔自動診断」するようになると、患者や家族にセカンド・オピニオンを述べ、病気解説をしない病理医は失職するかも知れないと思う。
2)東大合格者数=前号のメルマガで
<週刊誌に載った今年の「東大合格者数」を見ると、福山附属が広島県のトップになっている。「どうしてか?」と(福山附属の下前弘司先生に)聞くと、以下の3つの要因が関与していることがわかった。
1)中高一貫教育で、受験生には東は岡山市から、西は尾道・三原市までが含まれる。つまり岡山県西部と広島県の東半分から生徒が集まる。当然、優秀な生徒が集まるはずだ。
2)広島市の場合、学院、修道という学費の高い私立校に優秀な生徒があつまり、附属には私学に進学できない中流層の子弟が集まる傾向がある。
3)アンケート調査をしたわけではないが、50人ぐらいの生徒と話してみて、みな「自己への自信」「達成意欲」が高いそうだ。
東大進学率と親の年収との間に高い相関関係があることは、すでによく知られているから、2)はその通りだと思う。>
と書いた。これについて彼のコメントがあった.
私の追加質問:<結局、「東大合格率の差は親の経済力で決まる」「広島市の場合はそれら親の子弟は、まず学院・修道に進む」ということが、福山と広島附属の東大合格率の差になりますか?>については、以下の返信があった
<そうですね。その2つの要素が大きく影響していると思います。
現時点で,東大進学者数が多い学校に入学するには,小学生のころから塾に通うのが当たり前なのです。当然,費用がかかりますから。
これは教育における経済格差で,固定化しつつあります。そこで,大学の附属学校は入学試験の改革をせよと言われているのです。お金をかけて塾に通わせないと入学できないような附属学校ではいけない,というわけです。>
<修道のことはあまりよく分かりませんが,学院は附属福山と同様,学校で学んだことを活用して様々なチャレンジをしています。数学オリンピックや国際地理オリンピックなど,全国規模・国際レベルのコンテストなどで活躍する生徒が多いのはそのせいです。附属福山の生徒もいろんなところで活躍していますよ。>
その後、下前さんから訂正希望のメールがあり、「50人と話した」というのは、広島附属の生徒の話で、福山附属については、
<広大附属福山の生徒となりますと,数千人という単位になります。
実際に授業において,もしくは担任,クラブ活動の顧問としてよく話をした生徒の実数はこれまでで3000人程度になるでしょうか。それ以外にも,様々な生徒の話は聞きますので,それ以上の実績があります。これくらいの規模の生徒と接してきた実績から,みな「自己への自信」「達成意欲」が高いという実感を持っています。これは,皆実の附属も福山附属も同じです。
あと,「学んだことを活用して様々な課題に取り組む意欲と能力」も挙げられると思います。>
とのことだそうだ。これも訂正してお詫びする。
そういえば今年、福山附属は生物学オリンピックでも入賞者が出たと記憶する。生徒だけでなく教師もより高い目標に向かってチャレンジして欲しいものだ。
個人的回想になるが、私がいた広島附属学校は小学生3クラス:120人、うち出来の悪いのが中学進学できず他校に転校、中学4クラス=160人、高校5クラス=200人だったと記憶する。中学で1クラス、高校で1クラス、外部からの採用があった。私は運よく高校受験で合格した。クラスは「5組」で、このクラスからは男子が4人、東大に進学したと記憶する。男女混成だったから男子については20%の東大進学率だ。隣の4組には的川泰宣というすごい秀才がいて、東大工学部に進みロケットの糸川博士に学び宇宙工学の専門家になって、今でも活躍している。
入学は昭和32(1957)年で、「学院」ができたのは在学中のことだったと記憶する。その後ミッション系の学校は、受験教育に力をいれ、大学合格率をたかめることでPRと受験生募集に力を入れた。保護された公立・国立学校は変革を怠り、長期衰退の道を歩むことになったと思う。
1年生の年は、学校が「UNESCO実験校」に指定されていて、一般社会や他校とちがい土曜日も休校だった。教師も週2日、「在宅研究日」があった。クラス替えもなく、担任(チューター)も3年間変わらなかった。出欠も取らなかったので、朝寝坊の私はしばしば一時限目の授業を欠席し、教室に行くと同じクラスの女の子に「重役出勤!」と言われたこともある。
「記事転載は事前にご連絡いただきますようお願いいたします」
1)ひのえうま=前号で1966年丙午(ひのえうま)の年に「女児の選択的中絶が行われた」と書いたが、あの頃はまだ、出産前に羊水を採取してY染色体(性染色体)を調べるような技術は普及していなかった。もう一度総務省のグラフをよく見ると、この年は男子の出生数も激減していた。(付図1)これは2011年10月の総務省統計を資料としているので、2017年のデータとしては、縦軸の年齢階級に+6を足して読んでもらいたい。
「丙午の年に女児の選択的中絶があった」というのは、私の誤解だったので、お詫びして訂正したい。
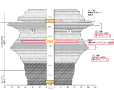
(付図1:2011年の日本の人口構成、10歳階級別グラフ・出典:総務省グラフ)
1945, 46年の出生数が少ないのは、多くの若い男が戦争に動員され、まだ復員していないか、復員していても、食うのが精一杯で、子供を作る余裕がなかったからである。1947(昭和22)年から出生数が急速に増え、これが「第一次ベビーブーム」世代を形成した。(いわゆる「団塊の世代」だ。)
1948/7に制定された「優生保護法」では、精神病や重篤な遺伝性疾患などによる「優生手術」以外の妊娠中絶は禁止されていた。これが急激な出産ブームにより、女性の社会的進出や経済的自立を妨げるとして(当時は保育園も幼稚園もなかった)、主に女性議員などの運動により、昭和24 (1949)年「母体保護」の観点から「経済的理由による中絶」が合法化された。
年別次の出生数を見れば、「第一次ベビーブーム」世代がいかに巨大な社会・経済的インパクトを与えたかがわかる。
この頃「経済的理由による中絶」は保険が利かず、自費だったから1960年代中頃まで、新聞に載る毎年の「長者番付」のトップテンには、「産婦人科医」が名を連ねていたのを記憶している。(これは後に「納税者番付」に変わり、現在は一切新聞に載らなくなった。)
このメルマガの読者から次のようなレスがあった。(本人の希望により匿名とする。)
<大学に入った年に、幼少時によくお世話になっていた、村でただ一人の内科医(小中の校医さん)の奥様から「◯◯ちゃんも医学部に入られたので、夏休みに受付の手伝いにでも来ていただけませんか?」と母が伝言され、ひと夏だけ行ったことがあります。
いっしょに開業しておられた娘婿さん(産婦人科医)の患者さんは、出産よりは妊娠中絶が圧倒的に多いことにショックを受けて、お盆を機に「宿題が残っていますから」といって辞めたことを覚えています。いわゆる経済的理由による人工妊娠中絶が認められていたころです。拝見したグラフでも丙午より前に第一次ベビーブームは下降線に入っていることを改めて認識し、政治の影響を感じました。>
私も病院から大学に異動し「学生相談室」を担当していた頃、母子家庭の女子学生が、母が病気で長期入院中に、サークルの男子学生と深い仲になり妊娠してしまった例の相談を、本人から受けたことがある。中絶可能月数の期限が近かった。泣いて後悔するその学生を見るに忍びず、大学付近で開業しておられた高校の先輩にあたる、ベテランの産婦人科医に連絡し、事情を話し「母体保護」条項による中絶手術をお願いしたことがある。
世の中はどう変わるか分からないもので、その後、コンドーム、ペッサリー、ピルなどの普及により「望まない妊娠」は激減した。つまり「少子化社会」の到来だ。その代わり「車社会」になり、整形外科医が流行り始めた。当時は、治療費は加害者負担で、通常の保険点数の倍額が請求されたので、整形外科医の年収が急増し、長者番付のトップテンが入れ替わった。
我々のクラスは40人編成だったが、整形外科が最も人気が高く、5人が進んだ。基礎医学では病理学が人気で私を含め4人が進んだ。整形外科も交通事故が減り、AIによる自動運転車が普及すると、骨折外傷は稀になる恐れがある。診断病理学も、AIが「遠隔自動診断」するようになると、患者や家族にセカンド・オピニオンを述べ、病気解説をしない病理医は失職するかも知れないと思う。
2)東大合格者数=前号のメルマガで
<週刊誌に載った今年の「東大合格者数」を見ると、福山附属が広島県のトップになっている。「どうしてか?」と(福山附属の下前弘司先生に)聞くと、以下の3つの要因が関与していることがわかった。
1)中高一貫教育で、受験生には東は岡山市から、西は尾道・三原市までが含まれる。つまり岡山県西部と広島県の東半分から生徒が集まる。当然、優秀な生徒が集まるはずだ。
2)広島市の場合、学院、修道という学費の高い私立校に優秀な生徒があつまり、附属には私学に進学できない中流層の子弟が集まる傾向がある。
3)アンケート調査をしたわけではないが、50人ぐらいの生徒と話してみて、みな「自己への自信」「達成意欲」が高いそうだ。
東大進学率と親の年収との間に高い相関関係があることは、すでによく知られているから、2)はその通りだと思う。>
と書いた。これについて彼のコメントがあった.
私の追加質問:<結局、「東大合格率の差は親の経済力で決まる」「広島市の場合はそれら親の子弟は、まず学院・修道に進む」ということが、福山と広島附属の東大合格率の差になりますか?>については、以下の返信があった
<そうですね。その2つの要素が大きく影響していると思います。
現時点で,東大進学者数が多い学校に入学するには,小学生のころから塾に通うのが当たり前なのです。当然,費用がかかりますから。
これは教育における経済格差で,固定化しつつあります。そこで,大学の附属学校は入学試験の改革をせよと言われているのです。お金をかけて塾に通わせないと入学できないような附属学校ではいけない,というわけです。>
<修道のことはあまりよく分かりませんが,学院は附属福山と同様,学校で学んだことを活用して様々なチャレンジをしています。数学オリンピックや国際地理オリンピックなど,全国規模・国際レベルのコンテストなどで活躍する生徒が多いのはそのせいです。附属福山の生徒もいろんなところで活躍していますよ。>
その後、下前さんから訂正希望のメールがあり、「50人と話した」というのは、広島附属の生徒の話で、福山附属については、
<広大附属福山の生徒となりますと,数千人という単位になります。
実際に授業において,もしくは担任,クラブ活動の顧問としてよく話をした生徒の実数はこれまでで3000人程度になるでしょうか。それ以外にも,様々な生徒の話は聞きますので,それ以上の実績があります。これくらいの規模の生徒と接してきた実績から,みな「自己への自信」「達成意欲」が高いという実感を持っています。これは,皆実の附属も福山附属も同じです。
あと,「学んだことを活用して様々な課題に取り組む意欲と能力」も挙げられると思います。>
とのことだそうだ。これも訂正してお詫びする。
そういえば今年、福山附属は生物学オリンピックでも入賞者が出たと記憶する。生徒だけでなく教師もより高い目標に向かってチャレンジして欲しいものだ。
個人的回想になるが、私がいた広島附属学校は小学生3クラス:120人、うち出来の悪いのが中学進学できず他校に転校、中学4クラス=160人、高校5クラス=200人だったと記憶する。中学で1クラス、高校で1クラス、外部からの採用があった。私は運よく高校受験で合格した。クラスは「5組」で、このクラスからは男子が4人、東大に進学したと記憶する。男女混成だったから男子については20%の東大進学率だ。隣の4組には的川泰宣というすごい秀才がいて、東大工学部に進みロケットの糸川博士に学び宇宙工学の専門家になって、今でも活躍している。
入学は昭和32(1957)年で、「学院」ができたのは在学中のことだったと記憶する。その後ミッション系の学校は、受験教育に力をいれ、大学合格率をたかめることでPRと受験生募集に力を入れた。保護された公立・国立学校は変革を怠り、長期衰退の道を歩むことになったと思う。
1年生の年は、学校が「UNESCO実験校」に指定されていて、一般社会や他校とちがい土曜日も休校だった。教師も週2日、「在宅研究日」があった。クラス替えもなく、担任(チューター)も3年間変わらなかった。出欠も取らなかったので、朝寝坊の私はしばしば一時限目の授業を欠席し、教室に行くと同じクラスの女の子に「重役出勤!」と言われたこともある。
「記事転載は事前にご連絡いただきますようお願いいたします」




























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます