【未来の物理学】「熱力学の第2法則」は、たんに物理学の法則にとどまらず、生物学の法則であることにはもうずいぶん昔に気づいていた。第一、遺伝子情報は化学物質による配列の違いであり、それは「最低3分子の配列の違いである」と予言していたのは物理学者のシュレジンガーである。
「熱力学の第2法則」いいかえれば「エントロピー増大の法則」が、経済学にも当てはまることを予想していたが、N.G.レーゲン「エントロピー法則と経済過程」(みすず書房, 1993)により、そのことは支持された。「価値」とは「情報」のことであり、それは「エントロピーの減少」により生み出される。
アインシュタインや湯川秀樹が、核兵器禁止運動に熱心にとり組んでいる頃は、何となく違和感を感じていた。
「彼らが推進した学問の結果として核兵器がある。ノーベル賞の権威を背景に、核兵器禁止運動をするなんておかしくないか?」
という違和感である。
「熱力学第2法則」がこれからの自然観、生命観、社会観の中心にならなければいけない…と思っていたところ、AMAZONから
ミチオ・カク(斉藤隆央訳)「2100年の科学ライフ」(NHK出版, 2012/9)が配達された。
どうしようもないフランス中世史学者の本で、頭が倦んでいたので、さっそく眼を通した。原題は<未来の物理学>で、どうして翻訳者として定評のある斉藤隆央がこんなタイトルに同意したのかわからない。また索引がないのもおかしい。(きっとNHK出版の編集者が強引だったのだろう)
基本は、
1)コンピューター
2)人工知能
3)医療
4)ナノテクノロジー
5)エネルギー
6)宇宙旅行
7)富
8)人類
について、未来における変化を予想したもので、技術の現状とその進歩の加速度を予想するところから、未来予測が行われている。
しかし、その根底におかれているのは「熱力学第2法則」に基づくエネルギー論で、「化石エネルギー依存型の文明は破綻する。恒星(太陽)の照射エネルギーで充足できる文明しか持続し得ない」という論点は一貫している。
正直言って、私は「熱力学第2法則」を中心に、物理化学、生命科学、経済学を統一的に論じられる時代が、こんなに早く来るとは思わなかった。
これまで「革命的」と称した思想は、すべて哲学、経済学、政治学のそれで、司馬遼太郎にいわせると「中心に証明できない芯をもつ」イデオロギーだった。
しかし、「熱力学第2法則」はイデオロギーではない。ちゃんと証明された物理法則である。
ミチオ・カクという人は、ニューヨーク市立大学の理論物理学の教授だそうだ。名前からして日系と思えるが、彼の「パラレル・ワールド」、「サイエンス・インポッシブル」(NHK出版)を訳した斉藤隆央も詳しくは触れていない。謎の作家だ。巻末に沢山の参考図書が引用されているが、邦訳されているのはR.ドーキンス「悪魔に仕える牧師」(早川書房,)だけであるのを見ても、あまりマークされていなかった作家だということがわかる。
理論物理学者のエルヴィン・シュレジンガーが「生命とはなにか」(1944, 岩波新書)で、遺伝子が2対の暗号表からなることを示唆して以来、分子生物学は大幅に発展した。暗号表がDNAであること、DNAが2本らせんから成り立っていること、暗号はATCGという4塩基の3組から構成されていること、各暗号に対応するアミノ酸まで、1970年代までにすべて解読された。
シュレジンガーの主張は、「遺伝子とは何を作りだすかという情報であり、それは世代を通じて非常に安定しているので、化学分子の結合の中に暗号として存在しているだろう」というものだった。DNAの二重らせんが遺伝子の本体であり、4種の塩基から3組が選び出されて1個のアミノ酸を措定していることが明らかになり、彼の予言は確定された。それとともに、生命科学は情報科学となった。
1993年には、「生命とは何か」の連続講演を記念して、「生命とは何か:それらかの50年」( 培風館)という記念シンポジウムが、ダブリンで開かれ、記録が出ている。
シュレジンガーの論述の根底をなすものは「エントロピー」である。つまり「生命」は、熱力学第2法則にさからう唯一無二の存在としてとらえられている。それは生命は食物により「エントロピーを減少させる」能力をもっている。(それを彼は誤解されやすい「生命は負のエントロピーを食べて生きている」という表現にしたのだが、)
生命のエントロピーが最小化された状態が、「生命情報」つまり遺伝子である。DNAはきわめて安定した物質で、固体状態では放射線にもびくともしない。
生命とは、この情報が「より低いエントロピー」を食物のかたちで取り入れ、個体を形成し、DNAを複製し、次の世代に引き継いで行くという現象である。
ここでは、
DNA +より低いエントロピー = 複製DNA +より高いエントロピー(環境への排泄物)
という関係が成立する。
この関係は、経済学における工場での商品(Comodity)の生産にも当てはまる。
原料 + より低いエントロピー(エネルギー源=化石燃料+人間労働)=商品 +より高いエントロピー(工場廃棄物+人間の疲労)
すなわち生産物が商品としての価値(Value)をもつのは、「エントロピーが低くなっている」=情報量が増加している、からである。
いまの経済学では価値と価格はしばしば混同されている。価格(Price)は市場における需要と供給の関係で決まるので、価値のないものも高価格で取り引きされることがある。
こうして「人体内部の機能学」=分子生物学と「人間の外的な生産活動の学」=経済学が、熱力学第2法則によって一元的、統一的に説明できるようになってきた。
振り返ると、文科系では、「文化相対主義」と「構造主義」があいまってさかんになり、その後は「ポスト構造主義」、「ポストモダン」になり、大きな文明論的な視座が消滅してしまった。枝葉末節を甲論乙駁して現在に至っている。原因は明白で、科学的立脚点を持たず、世論に迎合しているからだ。
この本でミチオ・カクが試みているのは、熱力学第2法則を中心にすえて、上記のさまざまな分野の近未来像(20年先)である。それ以後の2100年までは「世紀半ば」、「遠い未来」と区分けされているが、かなり空想的だ。ただ、楽観主義に充ちているのがよい。
興味深いのは例の「ムーアの法則」(コンピューターの性能は18ヶ月毎に倍になる:あるいはコンピューターのチップは18ヶ月毎に半値になる)が10年後には成り立たなくなるだろうという予測だ。
シリコン・ウェハーに刻まれるトランジスター・チップのサイズがどんどん小さくなって行くと、トランジスターが小さくなりすぎて、原子5個分くらいの厚みしかなくなる、そうなると「ハイゼンベルグの不確定性原理」が働く量子論の世界に入り、電子の流れ(電流)を制御するトランジスターの機能が成り立たなくなる。従って、「シリコン・コンピュータの時代」が終わる。代替素材が開発されなければ、コンピュータの進歩が終わる、という。
第7章「富の未来」も面白い。有形物を製造・販売する「商品資本主義」から知識と技能(サービス)が商品となる「知能資本主義」に移行すると説く。
脱工業化した社会では、旧来の成長の原動力、土地、資本、天然資源はもはや重要でなくなる。農産物の収量がアップしたので、輸出できるほどに食料が多く生産できるようになり、土地の重要性は減少した。資本は経済がグルーバル化した結果、国際市場からいくらでも調達できるようになった。天然資源の価格もインフレを調整すれば、長期的には価格が低下している、という。
これらの「量的資産」に変わって「質的な資源」つまり人々の資質、組織、やる気、自律性がますます重要になってくる。これが「知能資本」だという。「知能」というのは<インテリジェンス>の訳語かと思うが、「知識」<ノレッジ>という方がよいかも知れない。
ともかくこの「資質、組織、やる気、自律性」というのはレーゲンが、中進国が先進国へと<離陸>するために不可欠な要素だと指摘したものと同じである。
この本は、巻末の謝辞にあるように、ノーベル賞受賞者あるいはそれに匹敵する第一線の専門家300人以上にインタビューし、広範な文献渉猟をした上で書かれており、私が今年読んだ本でナンバーワンに相当する好著である。
「熱力学の第2法則」いいかえれば「エントロピー増大の法則」が、経済学にも当てはまることを予想していたが、N.G.レーゲン「エントロピー法則と経済過程」(みすず書房, 1993)により、そのことは支持された。「価値」とは「情報」のことであり、それは「エントロピーの減少」により生み出される。
アインシュタインや湯川秀樹が、核兵器禁止運動に熱心にとり組んでいる頃は、何となく違和感を感じていた。
「彼らが推進した学問の結果として核兵器がある。ノーベル賞の権威を背景に、核兵器禁止運動をするなんておかしくないか?」
という違和感である。
「熱力学第2法則」がこれからの自然観、生命観、社会観の中心にならなければいけない…と思っていたところ、AMAZONから
ミチオ・カク(斉藤隆央訳)「2100年の科学ライフ」(NHK出版, 2012/9)が配達された。
どうしようもないフランス中世史学者の本で、頭が倦んでいたので、さっそく眼を通した。原題は<未来の物理学>で、どうして翻訳者として定評のある斉藤隆央がこんなタイトルに同意したのかわからない。また索引がないのもおかしい。(きっとNHK出版の編集者が強引だったのだろう)
基本は、
1)コンピューター
2)人工知能
3)医療
4)ナノテクノロジー
5)エネルギー
6)宇宙旅行
7)富
8)人類
について、未来における変化を予想したもので、技術の現状とその進歩の加速度を予想するところから、未来予測が行われている。
しかし、その根底におかれているのは「熱力学第2法則」に基づくエネルギー論で、「化石エネルギー依存型の文明は破綻する。恒星(太陽)の照射エネルギーで充足できる文明しか持続し得ない」という論点は一貫している。
正直言って、私は「熱力学第2法則」を中心に、物理化学、生命科学、経済学を統一的に論じられる時代が、こんなに早く来るとは思わなかった。
これまで「革命的」と称した思想は、すべて哲学、経済学、政治学のそれで、司馬遼太郎にいわせると「中心に証明できない芯をもつ」イデオロギーだった。
しかし、「熱力学第2法則」はイデオロギーではない。ちゃんと証明された物理法則である。
ミチオ・カクという人は、ニューヨーク市立大学の理論物理学の教授だそうだ。名前からして日系と思えるが、彼の「パラレル・ワールド」、「サイエンス・インポッシブル」(NHK出版)を訳した斉藤隆央も詳しくは触れていない。謎の作家だ。巻末に沢山の参考図書が引用されているが、邦訳されているのはR.ドーキンス「悪魔に仕える牧師」(早川書房,)だけであるのを見ても、あまりマークされていなかった作家だということがわかる。
理論物理学者のエルヴィン・シュレジンガーが「生命とはなにか」(1944, 岩波新書)で、遺伝子が2対の暗号表からなることを示唆して以来、分子生物学は大幅に発展した。暗号表がDNAであること、DNAが2本らせんから成り立っていること、暗号はATCGという4塩基の3組から構成されていること、各暗号に対応するアミノ酸まで、1970年代までにすべて解読された。
シュレジンガーの主張は、「遺伝子とは何を作りだすかという情報であり、それは世代を通じて非常に安定しているので、化学分子の結合の中に暗号として存在しているだろう」というものだった。DNAの二重らせんが遺伝子の本体であり、4種の塩基から3組が選び出されて1個のアミノ酸を措定していることが明らかになり、彼の予言は確定された。それとともに、生命科学は情報科学となった。
1993年には、「生命とは何か」の連続講演を記念して、「生命とは何か:それらかの50年」( 培風館)という記念シンポジウムが、ダブリンで開かれ、記録が出ている。
シュレジンガーの論述の根底をなすものは「エントロピー」である。つまり「生命」は、熱力学第2法則にさからう唯一無二の存在としてとらえられている。それは生命は食物により「エントロピーを減少させる」能力をもっている。(それを彼は誤解されやすい「生命は負のエントロピーを食べて生きている」という表現にしたのだが、)
生命のエントロピーが最小化された状態が、「生命情報」つまり遺伝子である。DNAはきわめて安定した物質で、固体状態では放射線にもびくともしない。
生命とは、この情報が「より低いエントロピー」を食物のかたちで取り入れ、個体を形成し、DNAを複製し、次の世代に引き継いで行くという現象である。
ここでは、
DNA +より低いエントロピー = 複製DNA +より高いエントロピー(環境への排泄物)
という関係が成立する。
この関係は、経済学における工場での商品(Comodity)の生産にも当てはまる。
原料 + より低いエントロピー(エネルギー源=化石燃料+人間労働)=商品 +より高いエントロピー(工場廃棄物+人間の疲労)
すなわち生産物が商品としての価値(Value)をもつのは、「エントロピーが低くなっている」=情報量が増加している、からである。
いまの経済学では価値と価格はしばしば混同されている。価格(Price)は市場における需要と供給の関係で決まるので、価値のないものも高価格で取り引きされることがある。
こうして「人体内部の機能学」=分子生物学と「人間の外的な生産活動の学」=経済学が、熱力学第2法則によって一元的、統一的に説明できるようになってきた。
振り返ると、文科系では、「文化相対主義」と「構造主義」があいまってさかんになり、その後は「ポスト構造主義」、「ポストモダン」になり、大きな文明論的な視座が消滅してしまった。枝葉末節を甲論乙駁して現在に至っている。原因は明白で、科学的立脚点を持たず、世論に迎合しているからだ。
この本でミチオ・カクが試みているのは、熱力学第2法則を中心にすえて、上記のさまざまな分野の近未来像(20年先)である。それ以後の2100年までは「世紀半ば」、「遠い未来」と区分けされているが、かなり空想的だ。ただ、楽観主義に充ちているのがよい。
興味深いのは例の「ムーアの法則」(コンピューターの性能は18ヶ月毎に倍になる:あるいはコンピューターのチップは18ヶ月毎に半値になる)が10年後には成り立たなくなるだろうという予測だ。
シリコン・ウェハーに刻まれるトランジスター・チップのサイズがどんどん小さくなって行くと、トランジスターが小さくなりすぎて、原子5個分くらいの厚みしかなくなる、そうなると「ハイゼンベルグの不確定性原理」が働く量子論の世界に入り、電子の流れ(電流)を制御するトランジスターの機能が成り立たなくなる。従って、「シリコン・コンピュータの時代」が終わる。代替素材が開発されなければ、コンピュータの進歩が終わる、という。
第7章「富の未来」も面白い。有形物を製造・販売する「商品資本主義」から知識と技能(サービス)が商品となる「知能資本主義」に移行すると説く。
脱工業化した社会では、旧来の成長の原動力、土地、資本、天然資源はもはや重要でなくなる。農産物の収量がアップしたので、輸出できるほどに食料が多く生産できるようになり、土地の重要性は減少した。資本は経済がグルーバル化した結果、国際市場からいくらでも調達できるようになった。天然資源の価格もインフレを調整すれば、長期的には価格が低下している、という。
これらの「量的資産」に変わって「質的な資源」つまり人々の資質、組織、やる気、自律性がますます重要になってくる。これが「知能資本」だという。「知能」というのは<インテリジェンス>の訳語かと思うが、「知識」<ノレッジ>という方がよいかも知れない。
ともかくこの「資質、組織、やる気、自律性」というのはレーゲンが、中進国が先進国へと<離陸>するために不可欠な要素だと指摘したものと同じである。
この本は、巻末の謝辞にあるように、ノーベル賞受賞者あるいはそれに匹敵する第一線の専門家300人以上にインタビューし、広範な文献渉猟をした上で書かれており、私が今年読んだ本でナンバーワンに相当する好著である。












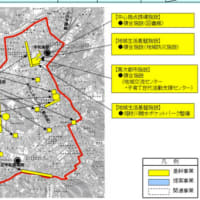
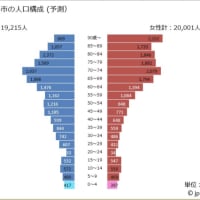



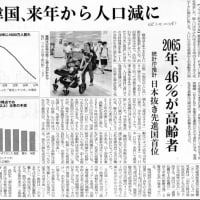










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます