【久間十義】四国のジャーナリストからメールがあり、7/4「共同」が日経に長編小説「禁断スカルペル」を連載した作家久間十義氏のインタビュー記事を配信していたことを知った。取っている四紙の見出しが不完全で、この記事が載っていなかったのか、読み落としたのか定かでない。
http://www.47news.jp/feature/medical/2017/07/post-1730.html
<「病、それから」 久間十義さん(小説家)変わった腎臓移植への考え>
あの小説は舞台が東北地方で、前半は普通の生体腎移植の話と異端の修復腎移植をしている医師グループの話、後半は東日本大震災により各地の透析施設が壊滅して行く中で、主人公の女医がドナー不足を解消するため「修復腎移植」(禁断のスカルペル=メスのこと)に乗り出すというものだった。
日本の脳死問題は、立花隆、梅原猛などの猛反対で「脳死を人間の死」とすることができず、欧米に決定的に遅れた。背景には「和田心臓移植」への疑惑を移植学会が払拭できなかったこともある。
そういう中で自殺を図って脳死状態になった実の息子を臓器ドナーとして提供する際の、苦悩と決断の過程を書いた、柳田邦男「犠牲(サクリファイス)―わが息子・脳死の11日」(文春文庫、1999)は日本人の脳死への理解を深め、脳死ドナーの増加にかなり貢献した。
よくドナーの肉親に「移植された臓器が生きている限り、死んだ人も生きている」と思う人があるらしいが、脳以外の臓器や細胞に「故人」が生きているのなら、肝臓や腎臓だけでなく、末梢血幹細胞移植のため献血した人や、胎盤血幹細胞移植のために胎盤を提供した人も、他人の中で自分の分身が生きていることになろう。
立花隆が「臨死体験」(文藝春秋、1994)で問題にした「脳死になっても聴覚がある」という矛盾は、脳死判定基準の厳格化により今では消滅した。聴覚性中枢はもっとも機能停止が遅れることは、まれに全身麻酔をかけて手術を受けた患者に術中の医師の会話を記憶している患者があることでもわかる。麻酔医が経験不足で、聴覚中枢が深麻酔に到達する前に手術を始めると、患者はちっとも痛くないし、声も出せず身動きもならないが、会話は全部聞こえているという事態が起こる。
ここで聴覚性幻覚が生じ「体外離脱」が起きると、「患者が斜め上方から自分を見下ろす」という幻覚になる。これが「臨死体験」の本質だ。要するに聴覚中枢まで破壊される「真の脳死」だと臨死体験は起こらない。
作家やジャーナリストにもよく勉強してもらって、修復腎移植を初めドナー提供者数が増えるように、ぜひご協力を願いたいものだ。
「記事転載は事前にご連絡いただきますようお願いいたします」
http://www.47news.jp/feature/medical/2017/07/post-1730.html
<「病、それから」 久間十義さん(小説家)変わった腎臓移植への考え>
あの小説は舞台が東北地方で、前半は普通の生体腎移植の話と異端の修復腎移植をしている医師グループの話、後半は東日本大震災により各地の透析施設が壊滅して行く中で、主人公の女医がドナー不足を解消するため「修復腎移植」(禁断のスカルペル=メスのこと)に乗り出すというものだった。
日本の脳死問題は、立花隆、梅原猛などの猛反対で「脳死を人間の死」とすることができず、欧米に決定的に遅れた。背景には「和田心臓移植」への疑惑を移植学会が払拭できなかったこともある。
そういう中で自殺を図って脳死状態になった実の息子を臓器ドナーとして提供する際の、苦悩と決断の過程を書いた、柳田邦男「犠牲(サクリファイス)―わが息子・脳死の11日」(文春文庫、1999)は日本人の脳死への理解を深め、脳死ドナーの増加にかなり貢献した。
よくドナーの肉親に「移植された臓器が生きている限り、死んだ人も生きている」と思う人があるらしいが、脳以外の臓器や細胞に「故人」が生きているのなら、肝臓や腎臓だけでなく、末梢血幹細胞移植のため献血した人や、胎盤血幹細胞移植のために胎盤を提供した人も、他人の中で自分の分身が生きていることになろう。
立花隆が「臨死体験」(文藝春秋、1994)で問題にした「脳死になっても聴覚がある」という矛盾は、脳死判定基準の厳格化により今では消滅した。聴覚性中枢はもっとも機能停止が遅れることは、まれに全身麻酔をかけて手術を受けた患者に術中の医師の会話を記憶している患者があることでもわかる。麻酔医が経験不足で、聴覚中枢が深麻酔に到達する前に手術を始めると、患者はちっとも痛くないし、声も出せず身動きもならないが、会話は全部聞こえているという事態が起こる。
ここで聴覚性幻覚が生じ「体外離脱」が起きると、「患者が斜め上方から自分を見下ろす」という幻覚になる。これが「臨死体験」の本質だ。要するに聴覚中枢まで破壊される「真の脳死」だと臨死体験は起こらない。
作家やジャーナリストにもよく勉強してもらって、修復腎移植を初めドナー提供者数が増えるように、ぜひご協力を願いたいものだ。
「記事転載は事前にご連絡いただきますようお願いいたします」












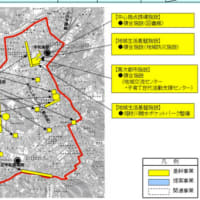
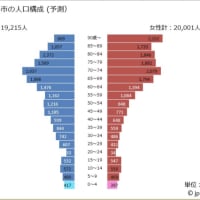



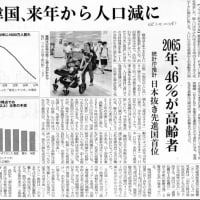










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます