【英語教育】英語はスペルと発音の食い違いが大きく、「読み書き」中心の日本の英語教育には問題がある。グルーバル時代の今日、「聞き話す」英語も重視されないといけない。別に英国英語や米国英語の発音でなくていい。フィリピンやインドの「ピジン英語」で十分なのだ。「ジャパングリッシュ」を恥じる必要はない。
「朝鮮日報」が『日本人の英語』(岩波新書)の著者マーク・ピーターセンを相手に、「日本人の英語能力」についてインタビューして、「韓国人の方が上」と言わせたがっているのには、腹が立つ。質問のもって行き方に意図が明瞭だ。
http://japanese.joins.com/article/464/170464.html?servcode=400§code=440
北朝鮮と一触即発の危機にあるのに、何という心根、なんという記事かと思う。
日本人の英語下手は、使う機会が少ないことが最大の原因だ。機会さえあれば、日本人はすぐ英語を必死で勉強する。
幕末から明治期がそうだ。東大では英語で授業した。
昭和20年の敗戦後、『日米英会話』を出した旺文社の赤尾好夫は飛ぶように売れて、大儲けした。
今、自民党が中心になり、大学の入学条件と卒業条件に総合的英語能力TOEFLと英語会話能力TOEICの試験点数が、一定上あることを要求するようにあらためようという動きがあるが、大賛成だ。それと同時に、国会議員から外交畑の役職に起用する場合にも、英語能力のある議員を起用してもらいたい。TPP交渉を進めるには、英語でジョークのひとつもいえるような人材が、腹をわって本音の話を進めるには必要だ。いちいち通訳を介していては、話は進まない。
カナダに交渉に行った自民党の若い代議士が、カナダの商務長官と話しているのをテレビで見て痛感した。向こうはにこやかに、こっちは苦虫を咬んだような顔をして、うつむいてしゃべっている。これではダメだ。
すでにTPP参加している国のうち、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、マレーシアは公用語が英語だ。ブルネイ、チリは違うが、「利害相反が生じた場合は、英語で交渉する」というのがTPPの規約だ。
どの国も英語に堪能な委員を出してくる。日本も国会議員にTOEFL受験を課すくらいの構えでやり、議員諸公の教養と英語能力を高めてもらいたい。「交渉は英語で、文書を確定するには英語正文と日本語複文で」というのが、外交の基本である。
安倍内閣にはひとつ、「国政選挙の立候補者はTOEFLの点数を選挙公報に明示すること」という法案を作ってもらいたい。馬鹿に高給を払いたくない。
ワイニンガーの『性と性格』が入手できたので、Webster「人名辞典」とP. Watson「The Modern Mind」から、「読書・思索ノート」に抜き書きをやった。日本語に訳して書くと、時間がかかるから万年筆で必要箇所を写し取る。
英語の本を見て感心するのは、書物名や固有一般名詞は原語のアルファベット表記になっていることだ。これは絶対に日本でもまねすべきだと思う。「性と性格」は辞典でもWatsonの本でも、Geschlecht und Charakterとドイツ語のままになっている。
かつて紀伊国屋がRachel Carsonの「Silent Spring」を『生と死の妙薬』訳して出版したことがあったが、さっぱり売れず、原題の『沈黙の春』に直したらベストセラーになった例がある。洋画の題名も同様で、「哀愁」の原題は「Warterloo Bridge」だ。国際会議の合間の懇親会で、カクテルを飲みながらの話題に出たら、「生と死の妙薬」とか「哀愁」しか知らない日本人は、話について行けないではないか。
こういう表記を日本語に取り入れるには、いまの縦書きでは無理なので、横書きに移行することを提唱しているわけである。
「新潟日報社」から出た福島放射線汚染モニターに関する本とミャンマー医療支援事業に関する本を頂いたが、どちらも横組みであるから、医学専門用語の略号や英語引用文献の表記が、いずれも無理なく読みやすく収まっている。写真もレイアウトが上下2枚で、説明文も収まりがよい。新潟は「ミクロスコピア」以来、文化発祥の地に変わった。
6月に娘が孫二人を連れて帰省する予定が決まったそうで、家内が張り切っている。亭主は残って仕事だそうで可哀想だ。
孫は日米の二重国籍だから、地元の小学校と幼稚園に入れてもらえる。2ヶ月でも3ヶ月でも、これをやると日本語能力は飛躍的に向上する。逆もそうで、音感が発達する時期に、英語環境に曝すと、日本人には難しい、RとL、BとV、CHUとTUとTSU、AとAE、EとIなどの聞き分け、話わけができるようになる。
そう思って、スタンフォード大で仕事したときは家族を同伴し、校長に理由を説明して、日本の学校を休ませ息子と娘を現地の学校に入学させた。
「The Modern Mind」は大型の850ページもある大著で、20世紀の「思想・芸術・文化・科学」の全分野を総めくりした本である。「よくもこんな本が書けたものよ」と思う。邦訳はない。
Weininger関係の部分を写し取って見て気づいたのは、著者は必ずしも原著を読んでいない、ということだ。索引と参考文献がしっかりしているから、それがわかるし、記載の間違いや間違いの原因もわかる。結局、以下の2書をベースに記述しているとわかった。これは通読したのではわからない。転記して引用文献番号から引用書も転記してみると、初めて分かる。
1)A. Janik & S. Toulmin(1973): Wittgenstein' Vienna. Weidenfeld & Nicolson, London
2)W.M. Johnston (1972): The Austrian Mind; An Intellectual and Social History 1848-1938. Univ. California Press, Berkeley, 1972
記載中の引用頻度を見ると、2が圧倒的に多い。引用ページも明示してあり、読者がすぐ検証できる。良心的著作である。
日本の読者は「丸暗記主義」だから、こういう記載を嫌がる手合いが多い。だから本の質が向上しない。
いずれこれらは古書で入手する予定だ。
英会話が上達する方法として、ピーターセンは「朝のNHKラジオ英会話講座」を薦めている。毎日やるというのが重要なのである。
私は朝寝坊だったから、無理だが、広大の学長だった原田康夫先生は毎朝自宅でゴルフの練習で汗を流し、その後ラジオで英会話を勉強した。オペラが好きでイタリアに留学したくらいだから、英語は得意でなかったが、この人の偉いところは「倦まずたゆまず努力する」ことにある。
40過ぎて始めたゴルフも、50過ぎて始めたヴァイオリンも、定年前に始めた英会話も、みな上手くなった。オペラに至っては80歳過ぎてもまだ舞台で主役を張っている。声量が落ちない。マイクなしでホールに声が行きわたる。まあ、万波誠の「腎移植1000例」と同様にギネスブックものだろう。
今は私も「ラジオ英会話」の時間くらいには起きられるようになったから、聴こうかと思うが、何しろ山の奥で、厚い壁と二重ガラスの仕事場を作ったもので電波がちゃんと届かない。入るのは出力の強い、北京放送か朝鮮語放送だ。屋外アンテナを設置する必要がある。
今は婆さんになって、秋田かどこかに住んでいるフランソワーズ・モレシャンさんは、若いときは美人だった。それもあって「NHKテレビ・フランス語会話」を学生時代に勉強した。基本的には「鼻をつまんでフランス語をしゃべれば英語になる」と認識できたのは、そのおかげである。
「書き写し」のよい点は、写しているうちに要点が見えてくることだ。要約の重要性については『要約・世界の文学』の書評で紹介した。
http://www.frob.co.jp/kaitaishinsho/book_review.php?id=1363851688
心理学では「注意力を持って観察し、それを自己意識していること」を「統覚」というこれを覚えるとなったら、難しい。 死しかし、デカルトの「われ思う故に我あり」が「すべては実在を疑いうるが、それを疑っている自己があることは疑えない」という意味であり、ライプニッツがラテン語のpercipere(捕まえる、理解する)を「意識的に五感を働かせる」という意味に使用したことを知れば、統覚の原語 apperceptionの理解は容易になる。
ライプニッツの用語から英語のperceive(認識する)が生まれ、視覚的、聴覚的、味覚的、触覚的、嗅覚的な感覚のすべてについて、総合的に意識した状態をあらわす言葉としてap-perceiveという言葉が作られたのである。「アパーセプション」の訳語としては「統合意識」といったほうがよいだろう。
「アパシーヴ」という過程においては、個々の一次情報を処理するのは不可能で、すでに「概念」として束になって記憶されている情報が、統合的に処理される。アパセプションはこの「論理演算」のことである。「知覚」(意識的感覚受容)の上位にある概念で、新しい概念形成つまり発明、発見に必要な意識作用である。
「AI」は現在、Autopsy Imaging(屍体画像処理)の意味で使われることが多いが、本来は「人工知能(Artificial Intelligence)」の意味だった。今、コンピュータは高速化し、将棋のプロを負かすところまで来たが、きっと情報処理にも「情報の階層づけと概念的クラスター化」が用いられているだろ。
「統覚」という用語は、percipere =perceive=perception=ap(up)-perceptionという「ことばの発生過程」を理解すれば、容易に理解できる概念である。日本では原語に各分野の学者が勝手な訳をあてて、それを学術用語にしたためいたずらに学術書の理解が困難になっている。ここでも横書きにして原語並記をすれば、問題はかなり解決する。
それはさておき、抜き書きのよいのは「自己要約」が進むことだ。この過程は同時にアパーセプションの過程でもあるから、記憶が完璧になる。同時に「統覚」なるものの意味も理解され、もうこれも記憶に残るだろう。
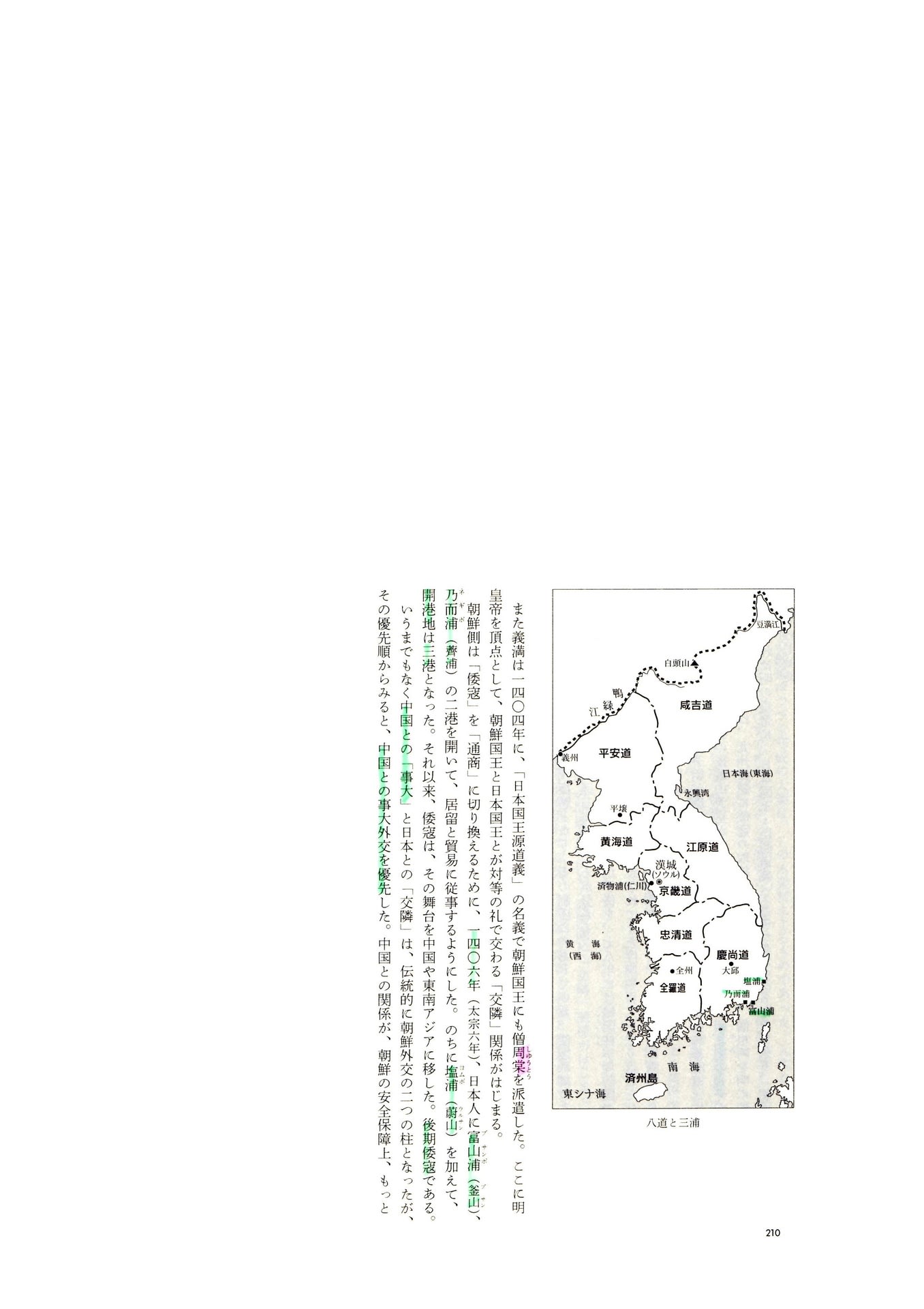
「朝鮮日報」が『日本人の英語』(岩波新書)の著者マーク・ピーターセンを相手に、「日本人の英語能力」についてインタビューして、「韓国人の方が上」と言わせたがっているのには、腹が立つ。質問のもって行き方に意図が明瞭だ。
http://japanese.joins.com/article/464/170464.html?servcode=400§code=440
北朝鮮と一触即発の危機にあるのに、何という心根、なんという記事かと思う。
日本人の英語下手は、使う機会が少ないことが最大の原因だ。機会さえあれば、日本人はすぐ英語を必死で勉強する。
幕末から明治期がそうだ。東大では英語で授業した。
昭和20年の敗戦後、『日米英会話』を出した旺文社の赤尾好夫は飛ぶように売れて、大儲けした。
今、自民党が中心になり、大学の入学条件と卒業条件に総合的英語能力TOEFLと英語会話能力TOEICの試験点数が、一定上あることを要求するようにあらためようという動きがあるが、大賛成だ。それと同時に、国会議員から外交畑の役職に起用する場合にも、英語能力のある議員を起用してもらいたい。TPP交渉を進めるには、英語でジョークのひとつもいえるような人材が、腹をわって本音の話を進めるには必要だ。いちいち通訳を介していては、話は進まない。
カナダに交渉に行った自民党の若い代議士が、カナダの商務長官と話しているのをテレビで見て痛感した。向こうはにこやかに、こっちは苦虫を咬んだような顔をして、うつむいてしゃべっている。これではダメだ。
すでにTPP参加している国のうち、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、マレーシアは公用語が英語だ。ブルネイ、チリは違うが、「利害相反が生じた場合は、英語で交渉する」というのがTPPの規約だ。
どの国も英語に堪能な委員を出してくる。日本も国会議員にTOEFL受験を課すくらいの構えでやり、議員諸公の教養と英語能力を高めてもらいたい。「交渉は英語で、文書を確定するには英語正文と日本語複文で」というのが、外交の基本である。
安倍内閣にはひとつ、「国政選挙の立候補者はTOEFLの点数を選挙公報に明示すること」という法案を作ってもらいたい。馬鹿に高給を払いたくない。
ワイニンガーの『性と性格』が入手できたので、Webster「人名辞典」とP. Watson「The Modern Mind」から、「読書・思索ノート」に抜き書きをやった。日本語に訳して書くと、時間がかかるから万年筆で必要箇所を写し取る。
英語の本を見て感心するのは、書物名や固有一般名詞は原語のアルファベット表記になっていることだ。これは絶対に日本でもまねすべきだと思う。「性と性格」は辞典でもWatsonの本でも、Geschlecht und Charakterとドイツ語のままになっている。
かつて紀伊国屋がRachel Carsonの「Silent Spring」を『生と死の妙薬』訳して出版したことがあったが、さっぱり売れず、原題の『沈黙の春』に直したらベストセラーになった例がある。洋画の題名も同様で、「哀愁」の原題は「Warterloo Bridge」だ。国際会議の合間の懇親会で、カクテルを飲みながらの話題に出たら、「生と死の妙薬」とか「哀愁」しか知らない日本人は、話について行けないではないか。
こういう表記を日本語に取り入れるには、いまの縦書きでは無理なので、横書きに移行することを提唱しているわけである。
「新潟日報社」から出た福島放射線汚染モニターに関する本とミャンマー医療支援事業に関する本を頂いたが、どちらも横組みであるから、医学専門用語の略号や英語引用文献の表記が、いずれも無理なく読みやすく収まっている。写真もレイアウトが上下2枚で、説明文も収まりがよい。新潟は「ミクロスコピア」以来、文化発祥の地に変わった。
6月に娘が孫二人を連れて帰省する予定が決まったそうで、家内が張り切っている。亭主は残って仕事だそうで可哀想だ。
孫は日米の二重国籍だから、地元の小学校と幼稚園に入れてもらえる。2ヶ月でも3ヶ月でも、これをやると日本語能力は飛躍的に向上する。逆もそうで、音感が発達する時期に、英語環境に曝すと、日本人には難しい、RとL、BとV、CHUとTUとTSU、AとAE、EとIなどの聞き分け、話わけができるようになる。
そう思って、スタンフォード大で仕事したときは家族を同伴し、校長に理由を説明して、日本の学校を休ませ息子と娘を現地の学校に入学させた。
「The Modern Mind」は大型の850ページもある大著で、20世紀の「思想・芸術・文化・科学」の全分野を総めくりした本である。「よくもこんな本が書けたものよ」と思う。邦訳はない。
Weininger関係の部分を写し取って見て気づいたのは、著者は必ずしも原著を読んでいない、ということだ。索引と参考文献がしっかりしているから、それがわかるし、記載の間違いや間違いの原因もわかる。結局、以下の2書をベースに記述しているとわかった。これは通読したのではわからない。転記して引用文献番号から引用書も転記してみると、初めて分かる。
1)A. Janik & S. Toulmin(1973): Wittgenstein' Vienna. Weidenfeld & Nicolson, London
2)W.M. Johnston (1972): The Austrian Mind; An Intellectual and Social History 1848-1938. Univ. California Press, Berkeley, 1972
記載中の引用頻度を見ると、2が圧倒的に多い。引用ページも明示してあり、読者がすぐ検証できる。良心的著作である。
日本の読者は「丸暗記主義」だから、こういう記載を嫌がる手合いが多い。だから本の質が向上しない。
いずれこれらは古書で入手する予定だ。
英会話が上達する方法として、ピーターセンは「朝のNHKラジオ英会話講座」を薦めている。毎日やるというのが重要なのである。
私は朝寝坊だったから、無理だが、広大の学長だった原田康夫先生は毎朝自宅でゴルフの練習で汗を流し、その後ラジオで英会話を勉強した。オペラが好きでイタリアに留学したくらいだから、英語は得意でなかったが、この人の偉いところは「倦まずたゆまず努力する」ことにある。
40過ぎて始めたゴルフも、50過ぎて始めたヴァイオリンも、定年前に始めた英会話も、みな上手くなった。オペラに至っては80歳過ぎてもまだ舞台で主役を張っている。声量が落ちない。マイクなしでホールに声が行きわたる。まあ、万波誠の「腎移植1000例」と同様にギネスブックものだろう。
今は私も「ラジオ英会話」の時間くらいには起きられるようになったから、聴こうかと思うが、何しろ山の奥で、厚い壁と二重ガラスの仕事場を作ったもので電波がちゃんと届かない。入るのは出力の強い、北京放送か朝鮮語放送だ。屋外アンテナを設置する必要がある。
今は婆さんになって、秋田かどこかに住んでいるフランソワーズ・モレシャンさんは、若いときは美人だった。それもあって「NHKテレビ・フランス語会話」を学生時代に勉強した。基本的には「鼻をつまんでフランス語をしゃべれば英語になる」と認識できたのは、そのおかげである。
「書き写し」のよい点は、写しているうちに要点が見えてくることだ。要約の重要性については『要約・世界の文学』の書評で紹介した。
http://www.frob.co.jp/kaitaishinsho/book_review.php?id=1363851688
心理学では「注意力を持って観察し、それを自己意識していること」を「統覚」というこれを覚えるとなったら、難しい。 死しかし、デカルトの「われ思う故に我あり」が「すべては実在を疑いうるが、それを疑っている自己があることは疑えない」という意味であり、ライプニッツがラテン語のpercipere(捕まえる、理解する)を「意識的に五感を働かせる」という意味に使用したことを知れば、統覚の原語 apperceptionの理解は容易になる。
ライプニッツの用語から英語のperceive(認識する)が生まれ、視覚的、聴覚的、味覚的、触覚的、嗅覚的な感覚のすべてについて、総合的に意識した状態をあらわす言葉としてap-perceiveという言葉が作られたのである。「アパーセプション」の訳語としては「統合意識」といったほうがよいだろう。
「アパシーヴ」という過程においては、個々の一次情報を処理するのは不可能で、すでに「概念」として束になって記憶されている情報が、統合的に処理される。アパセプションはこの「論理演算」のことである。「知覚」(意識的感覚受容)の上位にある概念で、新しい概念形成つまり発明、発見に必要な意識作用である。
「AI」は現在、Autopsy Imaging(屍体画像処理)の意味で使われることが多いが、本来は「人工知能(Artificial Intelligence)」の意味だった。今、コンピュータは高速化し、将棋のプロを負かすところまで来たが、きっと情報処理にも「情報の階層づけと概念的クラスター化」が用いられているだろ。
「統覚」という用語は、percipere =perceive=perception=ap(up)-perceptionという「ことばの発生過程」を理解すれば、容易に理解できる概念である。日本では原語に各分野の学者が勝手な訳をあてて、それを学術用語にしたためいたずらに学術書の理解が困難になっている。ここでも横書きにして原語並記をすれば、問題はかなり解決する。
それはさておき、抜き書きのよいのは「自己要約」が進むことだ。この過程は同時にアパーセプションの過程でもあるから、記憶が完璧になる。同時に「統覚」なるものの意味も理解され、もうこれも記憶に残るだろう。
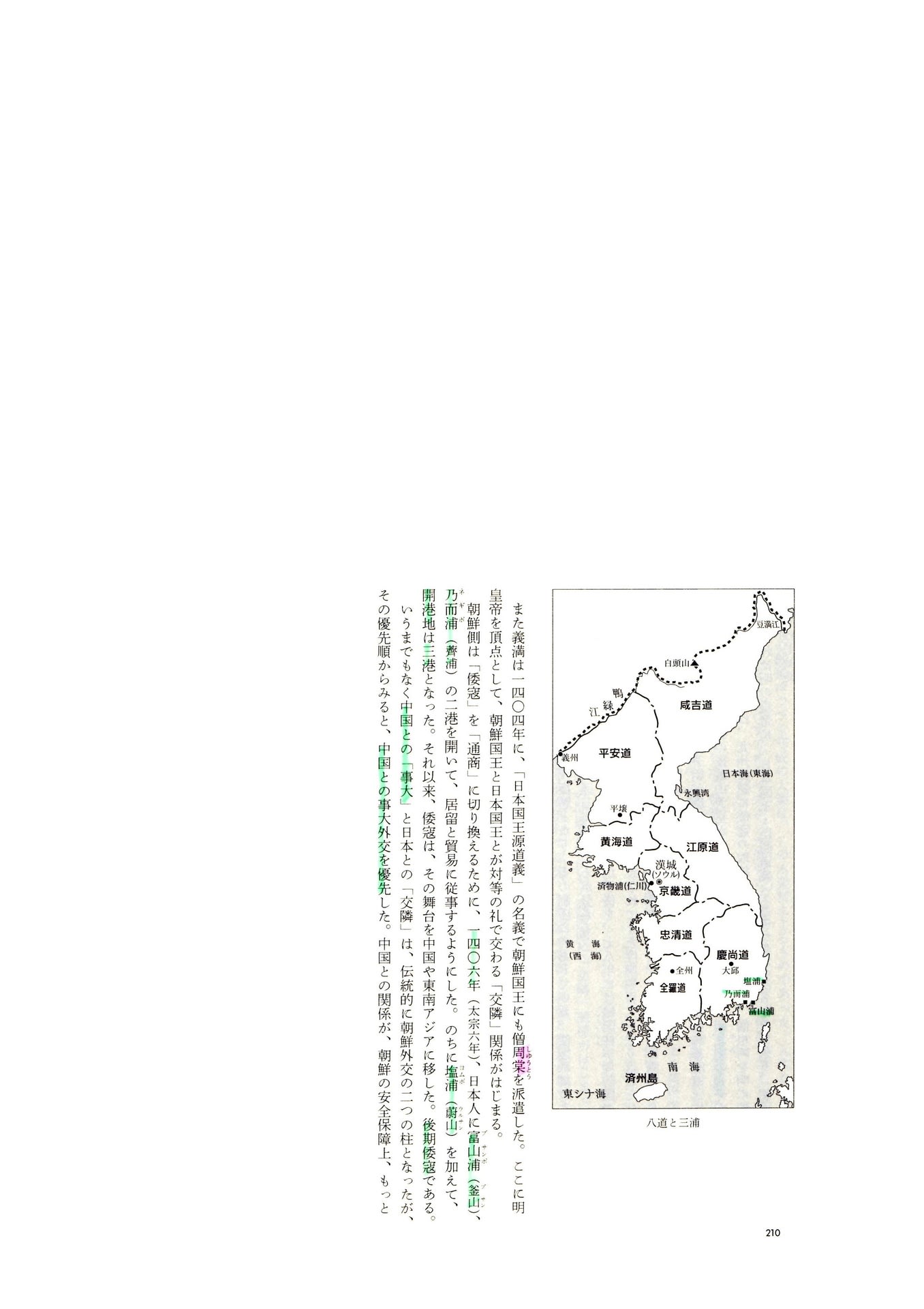




























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます