【せどり再考】前回「せどり」の語源を「背表紙で見て値打ちのある古書を選んだから」という説を紹介しました。
「書くが疑問のはじまり」で、寝室にある初版本の復刻本を調べたら、和綴じ本にはすべて背表紙がなかった。つまりタイトルは表表紙にしか題名が書いてない。だから「せどり」はできない。
日本の洋綴じ本は、最初和綴じ本をまねたから、背表紙にタイトルがなかった。
国木田独歩「武蔵野」は明治34年3月11日に「民友社」から刊行されているが、背表紙にタイトルがない。(添付1) おまけに著者検印もない。(添付2)
おまけに著者検印もない。(添付2)
つまり明治時代前半は和綴じ本、後半は洋綴じ本だが、和綴じ本のスタイルを踏襲していた。だから江戸時代と同じように、原稿は「書店買い取り」だったのではなかろうか。
これを変えたのが夏目漱石だと思われる。処女作「吾輩は猫である(上・虫・下)」(M38~40年)から、彼の本には「著者検印」がある。但し「検印紙」ではなく、本の奥付に直接印鑑が押してある。成島柳北「柳橋新誌」(M7年)も、坪内逍遙「小説神髄」(M18年)も和綴じ本だから、検印はない。
つまり「背取り」が可能になったのは、大正時代になり、本が基本的に洋綴じ本になってからだ。厚い表紙のある洋綴じ本でないと書棚には立てられない。
だから「せどり」という言葉は、恐らく昭和時代になって生まれたのであろう。
大正4年、籾山書店刊の森鷗外「雁」には本に直接、著者検印が押してある。これだと書店は、著者に印鑑を押しに来てもらうか、本を著者の家に運ばなくてはいけない。「大量印刷、大量販売」が始まる前は、そのいずれかであったに違いない。
「検印紙」の考案者が誰だかわからないが、確認できた「検印紙貼付本」は、大正7年「博文舘」刊、樋口一葉「たけくらべ」である。(貼付3)
「たけくらべ」は死の1年前に雑誌に発表されたが、単行本はこれが最初だと巻末の年表にある。これは一葉の毛筆による自筆原稿をそのまま本にしたもので、私には読めない。死後22年目にして、やっと単行本が出たわけで、哀れとも何とも、いいようがない。著作権者は「樋口邦子」となっている。一葉の本名は夏子だから、これは遺産相続者だろう。
つまり明治末から大正年間に、「著作権」という考え方が浸透し、原稿買い取りから印税方式へ、著者検印から「検印紙貼付」へと進化が起こったと考えられる。恐らくその原動力は、夏目漱石だろうと推測されるが、何しろ大学文学部国文科に人は多くても、テキストばかり研究していて、こんなテーマを研究する人がいない。「夏目漱石と著作権」というような本を見たことがない。
(山本順二「漱石の転職」, 彩流社によると、「吾輩は猫」で漱石は雑誌「ホトトギス」から原稿料を12~13円、出版社から「印税」を300円近くもらっている。明治40年、東京帝大を辞め「朝日」に入社する時には、「新聞連載小説を出版する際の版権は漱石に属する」ことを文書で確認している。
明治37年、漱石は東大から年俸800円、兼業していた一高から年700円、明治大学講師として年360円、合計1,860円以上の年収があった。
明治40年、「朝日新聞社」入社した時の条件は、月俸200円にボーナス2回という破格の待遇だった。年俸約2,800円だ。
同年の長野県小学教師初任給が10~13円である。)
日曜日の「産経抄」に永井荷風「断腸亭日乗」に関東大震災の記録があるとあり、岩波文庫のページを繰ったら、前に読んだ時の書き込みがあった。大正12(1923)年9月1日以後、10月3日まで断続的に約3頁にわたり記載がある。荷風は基本的に傍観者だから、帝都の荒廃を見て「自業自得、天罰覿面(てきめん)というべし」と書いている。(さすがに「産経抄」氏はこれには触れていない。)
で、地震が来た時、「書棚から書帙(しょちつ)が頭上に落下してきた」と書いている。つまり荷風の蔵書は大部分が和綴じ本で、「帙(ちつ)」という紐で括るタイプの紙箱に入っていた、ということだ。「洋行帰り」の荷風の蔵書がこれだから、当時、他の作家の蔵書はほとんど和書だったとみられる。
「書くが疑問のはじまり」で、寝室にある初版本の復刻本を調べたら、和綴じ本にはすべて背表紙がなかった。つまりタイトルは表表紙にしか題名が書いてない。だから「せどり」はできない。
日本の洋綴じ本は、最初和綴じ本をまねたから、背表紙にタイトルがなかった。
国木田独歩「武蔵野」は明治34年3月11日に「民友社」から刊行されているが、背表紙にタイトルがない。(添付1)
 おまけに著者検印もない。(添付2)
おまけに著者検印もない。(添付2)
つまり明治時代前半は和綴じ本、後半は洋綴じ本だが、和綴じ本のスタイルを踏襲していた。だから江戸時代と同じように、原稿は「書店買い取り」だったのではなかろうか。
これを変えたのが夏目漱石だと思われる。処女作「吾輩は猫である(上・虫・下)」(M38~40年)から、彼の本には「著者検印」がある。但し「検印紙」ではなく、本の奥付に直接印鑑が押してある。成島柳北「柳橋新誌」(M7年)も、坪内逍遙「小説神髄」(M18年)も和綴じ本だから、検印はない。
つまり「背取り」が可能になったのは、大正時代になり、本が基本的に洋綴じ本になってからだ。厚い表紙のある洋綴じ本でないと書棚には立てられない。
だから「せどり」という言葉は、恐らく昭和時代になって生まれたのであろう。
大正4年、籾山書店刊の森鷗外「雁」には本に直接、著者検印が押してある。これだと書店は、著者に印鑑を押しに来てもらうか、本を著者の家に運ばなくてはいけない。「大量印刷、大量販売」が始まる前は、そのいずれかであったに違いない。
「検印紙」の考案者が誰だかわからないが、確認できた「検印紙貼付本」は、大正7年「博文舘」刊、樋口一葉「たけくらべ」である。(貼付3)

「たけくらべ」は死の1年前に雑誌に発表されたが、単行本はこれが最初だと巻末の年表にある。これは一葉の毛筆による自筆原稿をそのまま本にしたもので、私には読めない。死後22年目にして、やっと単行本が出たわけで、哀れとも何とも、いいようがない。著作権者は「樋口邦子」となっている。一葉の本名は夏子だから、これは遺産相続者だろう。
つまり明治末から大正年間に、「著作権」という考え方が浸透し、原稿買い取りから印税方式へ、著者検印から「検印紙貼付」へと進化が起こったと考えられる。恐らくその原動力は、夏目漱石だろうと推測されるが、何しろ大学文学部国文科に人は多くても、テキストばかり研究していて、こんなテーマを研究する人がいない。「夏目漱石と著作権」というような本を見たことがない。
(山本順二「漱石の転職」, 彩流社によると、「吾輩は猫」で漱石は雑誌「ホトトギス」から原稿料を12~13円、出版社から「印税」を300円近くもらっている。明治40年、東京帝大を辞め「朝日」に入社する時には、「新聞連載小説を出版する際の版権は漱石に属する」ことを文書で確認している。
明治37年、漱石は東大から年俸800円、兼業していた一高から年700円、明治大学講師として年360円、合計1,860円以上の年収があった。
明治40年、「朝日新聞社」入社した時の条件は、月俸200円にボーナス2回という破格の待遇だった。年俸約2,800円だ。
同年の長野県小学教師初任給が10~13円である。)
日曜日の「産経抄」に永井荷風「断腸亭日乗」に関東大震災の記録があるとあり、岩波文庫のページを繰ったら、前に読んだ時の書き込みがあった。大正12(1923)年9月1日以後、10月3日まで断続的に約3頁にわたり記載がある。荷風は基本的に傍観者だから、帝都の荒廃を見て「自業自得、天罰覿面(てきめん)というべし」と書いている。(さすがに「産経抄」氏はこれには触れていない。)
で、地震が来た時、「書棚から書帙(しょちつ)が頭上に落下してきた」と書いている。つまり荷風の蔵書は大部分が和綴じ本で、「帙(ちつ)」という紐で括るタイプの紙箱に入っていた、ということだ。「洋行帰り」の荷風の蔵書がこれだから、当時、他の作家の蔵書はほとんど和書だったとみられる。












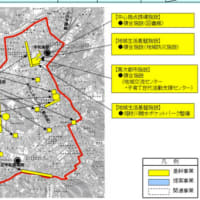
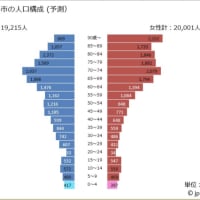



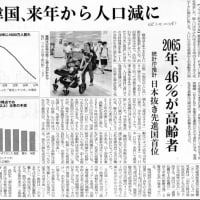










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます