「荒川最大の弱点」
 台風19号で足立区と葛飾区を結ぶ、京成電鉄の「荒川橋梁」が「荒川最大の弱点」という新聞記事が出ました。
台風19号で足立区と葛飾区を結ぶ、京成電鉄の「荒川橋梁」が「荒川最大の弱点」という新聞記事が出ました。
『戦前にかけられた鉄橋だが、この部分だけ堤防が他より低くえぐれている。高度成長期に下町一帯が地盤沈下した際、鉄橋部分も地盤が沈んだためだ。荒川堤防の他の箇所は土を盛って高さを確保したが、鉄橋の部分だけかさ上げが出来なかった。水が堤防を越えると市街地側の土手がえぐられ、決壊する。荒川が決壊すれば最悪の場合、都心は水没する。「このままだとあそこはもたない」万一の増水に備え、鉄橋に土嚢を大量に積み上げ増水に備える作戦をするようにとの連絡が入った。』(11月14日付朝日新聞「検証 台風19号~東京と災害」)
心配する地域住民の方からも問い合わせがあり、区議団で現場を調査に行きました。
台風の影響も生々しく、まだ土嚢が積んでありました。当分このままにしておくそうです。
また、区の担当者に京成本線荒川橋梁について説明をしてもらいました。
京成本線荒川橋梁の概要
京成本線荒川橋梁は、京成電気軌道(現在の京成電鉄)の青砥~日暮里間の開業に伴い、昭和6年(1931年)3月に完成し、同年12月19日に供用を開始しました。
以来、重要な交通機関として活躍し続け、現在では1日に約14万人の方々が利用しています。
広域的な地盤沈下
高度経済成長期の地下水の汲み上げにより江戸川区や江東区を中心に広域的に地盤沈下が生じ、最大で約4.5mの 沈下が確認されている所もあります。現在では沈下はほとんど収まっていますが、京成本線荒川橋梁の付近も約3.4mの地盤沈下が確認されています。
治水上の弱点
広域地盤沈下によって低くなってしまった堤防は、必要な高さまでかさ上げされました。
しかし、橋梁部は橋梁が支障となり、かさ上げができないため、この付近の堤防は付近の堤防に比べて低い状態にあります。
増水時には、堤防の低い部分から水が溢れて堤防が決壊する危険性が生じるなど、治水対策上の大きな問題となっています。
橋梁架替の必要性
治水対策を行うためには、橋梁部の堤防を必要な高さまでかさ上げをする必要があります。
そして、堤防かさ上げを行うためには支障となっている橋梁を堤防よりも高い位置へ架け替える必要があります。
平成14年には京成押上線荒川橋梁の架替事業が終了し、京成本線荒川橋梁の架替に向けた調査を進めています。
今後の取り組み
この架替ルートは、交差する首都高速道路橋梁(首都高速中央環状線)や並行して隣接する道路橋梁(堀切橋)などの現地状況を踏まえ作成したルートです。
今後、国土交通省・京成電鉄(株)・地元自治体(足立区、葛飾区)と連携し、事業に対して地域の方々の理解と協力のもと進めていきたいと考えています。
とのことでしたが、この工事には用地買収を行い、買収が終わってから、16年かかるとのこと、つまり、これから20年はかかる事業だと言うことです。
また、区は「計画運休で電車は止まるのだから線路にも土嚢を積み上げて対応することも考えている。」としていますが、地域住民の方々の不安は消えたわけではありません。
今回の台風では、上流の滝沢ダムにまだ若干の余裕があったことや台風が通過すると途端に雨が弱まったことなど、いくつもの幸運があり、荒川の決壊は回避されました。
 今後も災害対策の充実を求めていきます。
今後も災害対策の充実を求めていきます。
みなさんのご意見、ご要望などお寄せください。












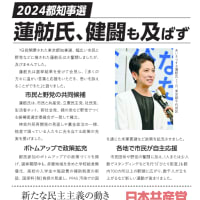




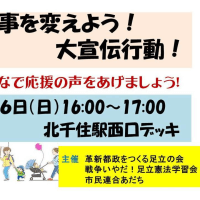
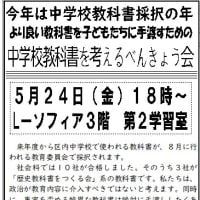


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます