
ヘルムート・ラッヘンマン:
・アレグロ・ソステヌート ピアノ、クラリネット、チェロのための
・子供の遊び 7つのピアノ小品
・虚無より 1名のクラリネット奏者のための
・印象 1名のチェロ奏者のための
ピアノ:ベルンハルト・ヴァンバッハ
クラリネット:ダーヴィット・シュメイアース
チェロ:ミヒャエル・バッハ
CPO: 999 102-2
クラシックの中でも圧倒的に聴く人が少ないのがグチャグチャの現代音楽。その中でも私が最も酷い(いい意味で)と感じているのがラッヘンマンの作品です。このディスクでも存分に発揮されていますが、楽器の特殊奏法を多用した作品が多いです。特殊奏法とは要するに普通ではない方法で楽器から音を出すというもので、ギコギコ、バフォバフォ、チュクチュクチュ、のようにおおよそ楽器とは思えない音によって作品が構成されています。
特殊奏法に限らず、従来の音楽的お約束を破壊しているようです。もっとも前衛音楽なんてどれもそうなんですが、ラッヘンマンの作品の場合はそれがどこか笑えるものになっているのが貴重です。このディスクで最も笑えるのが「子供の遊び 7つのピアノ小品」でしょう。こういうタイトルでは、子供が遊んでいる様子を音楽にしたものと考えるのが普通です。ところがこの曲では、子供がピアノで遊んでいる様子をそのまま再現したかのようです。YouTubeに演奏の動画(4曲目まで)がありましたのでご確認ください。
特に1曲目がふざけています。ピアノの鍵盤を最高音から最低音まで半音ずつ下がるというものです。家でこんな音が聴こえてきたら「静かにしなさい!」と叱りたくなるでしょう。あと7曲目も驚異的に馬鹿馬鹿しいので、ご興味のある方はそちらも探してみてください。
このディスクの残りの3曲はフツーの現代音楽に近い耳ざわりですが、特殊奏法のせいで「その音どうやって出しているの?」という疑問が常にまとわりつきます。「アレグロ・ソステヌート」ではピアノの内部奏法(ピアノ内部のピアノ線をかき鳴らす)も聴こえますが、それがあまりにも古典的な手法に思えてくるほどです。ラッヘンマンの作品の演奏をぜひ生で見てみたいですが、演奏する側としては高価な楽器で演奏したくないでしょうね。
クラシックCD紹介のインデックス










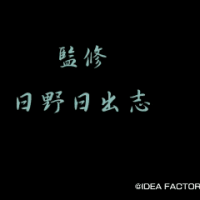
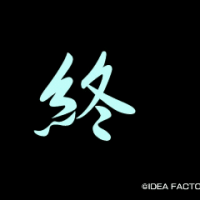
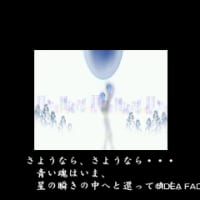


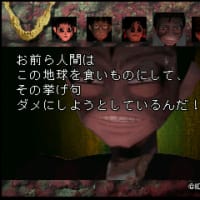

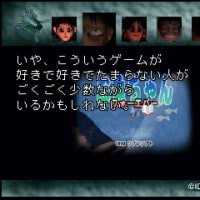

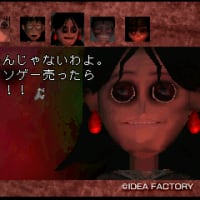
このピアノの動画を見た後、別の動画も見てみたのですが、余りにも変さが極まっていて、このピアノの動画が非常にまともに見えるぐらいでした…。
難解と言われる現代音楽ですが、このラッヘンマンの作品は確かに「いたずら」的で面白く感じます。素人が演奏しているように見せかける音楽というのは古くからいくつか存在するのですが、ここまで「でたらめ」に接近した「演奏」を演奏するのは珍しいかもしれません。しかも演奏者によって印象もかなり変わってくるという奥深さもあるようです。
続きの動画も見ていただいたとのことですが、5曲目も異様でしたね。何の儀式か、と思うほどです。音を出さないように鍵盤を押してピアノ線を解放し、鳴っている音と共鳴させるという特殊奏法です。動画では聴こえづらいですけど。