 昨日は久々に秋晴れ。
昨日は久々に秋晴れ。
絶好のテニス日和という事で日比谷公園のテニス場でプレーをしました。
ところがこのところ雨の為にプレーする機会を逸していたのでなかなか勘が戻りません。
足ももたつき相手の緩急にうまく適応できません。散々な結果となりました。
思わずタブーにしているあの言葉を言ってしまいました。
「もう若くはないな」
でも悲しい事にこれが現実なのです。もう若かった時代の私ではないのです。
二年前の私はこうではなかった。まして十年、二十年前の私は・・・。
「この様な若さの喪失を積み重ねて、同時に経験というものを得ていくのが老いというものか」
この様な繰言を言い続けて老いていくのですね。
という事で、さて前回の演出ノートの続きです。
前回提示した「時代を纏う」という意味合いを解説したいと思います。
 今回の芝居の中心的な役割を背負う役は、20代前半の若者です。
今回の芝居の中心的な役割を背負う役は、20代前半の若者です。
時は昭和20年4月から6月に至る日本の南端にある陸軍航空基地での話です。
つまり63年前の話話です。
これから「払暁の時・手紙」という作品に役者として立つ若い俳優諸君にすればその当時はすでに時代劇の世界です。
その実感できない芝居にどう生きた人間として立つことができるのか。
その具体的な方法論が「時代を纏う」という言葉に隠されています。
近代日本の大きな分岐点であった昭和20年8月15日の敗戦。
これを境に日本のあらゆるものが大きな変貌を遂げました。
つまり戦前の日本と戦後の日本は同じ日本という国名でありながら価値観の異なる全く別の国になったのです。
そして戦後から続く現代を生きて俳優をやりこの作品に取り組もうとしている俳優諸君は、まさしく戦争を知らない世代な訳です。
私はここで歴史的な講釈をしょうとしているのではありません。
しかしながらこの芝居に役者として立つ俳優諸君のそれぞれが担う役は、戦前の教育を受け、当たり前にそれに疑問を持たずに生きてきた若者達です。
その役を演じるためには何が必要でしょう。
戦前の日本を文献で知ることも映像で知ることも勿論重要な事に違いありませんが、それだけでは足りません。
それは自分で調べたことをどう実体化していくのか、そのプロセスを考えることが必要なのです。
知識で芝居はできません。知識を役の実体化とどの様にリンクさせていくかが問題なのです。
「時代を纏う」為の具体的な方法論の①は、姿勢を正す事です。立つ・座る。すべての居方の姿勢を正す事です。
その様な教育をされる時代なのです。それはやってみるととても苦しいものです。
②大きな声で明瞭な発声。人との距離関係なくそれは求められました。声が小さいだけで殴られた時代です。
この様に具体的な事柄を探り出しやってみる事が、その不自由さを感じる事が、現代との違いを認識する為の第一歩なのです。
「時代を纏う」やり方は一通りではありません。役者の工夫の数だけあるのです。
しかしここで注意しなければならない事は、抽象的に捉えたままでは表現にならないという事を認識することです。具体的に、具体的に。












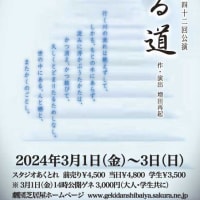
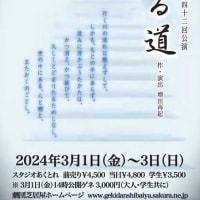

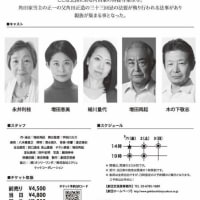

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます