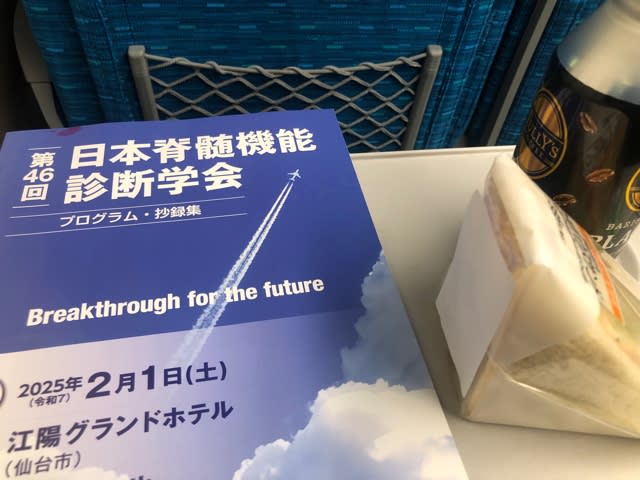私は関西医療大学で教務部長という職をいただいております。そのため、昨日の臨床検査技師、理学療法士、作業療法士の国家試験発表では朝から緊張していました。臨床検査学科、理学療法学科は100パーセント合格、作業療法学科は全員合格ではありませんでしたが最高の結果となりました。本当に学科運営している先生方には感謝しかありません。ありがとうございます。また、特筆すべき点としては、理学療法学科は初めての2年連続100パーセントです。
私は理学療法学科の前学科長です。私が学科長の時には残念ながら一度もなく、私の前の学科長で全員合格となるということでした。
私は100パーセント合格がどれほど大変か知っています。だから本当におめでとうと言いたいです。関西医療大学は来週に看護師、保健師、助産師、鍼師、灸師、柔道整復師の合格発表があります。緊張する日々が続きます。頑張れ 関西医療大学