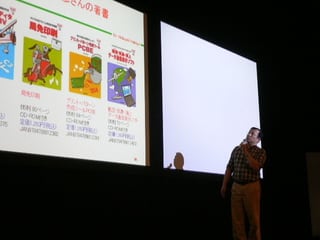第二回の授業から教室が7号館1階の丹羽ホールに変更になりました。
まず最初に少しだけ試験問題のことについて触れられました。
昨年の記述式の問題ですが、今、様々な方面で生体認証(バイオメトリクス認証)という方式が採りいれられつつあります。この方法ですが、確かに認証の方式としては確かな方式ではあるのですが、一旦 この情報がデジタルデータとして情報漏えいしてしまった場合に暗証番号のようにその変更が効かないため、漏れてしまった場合の対策方法を考えるものでしたという話をされました。
あとは計算問題。記述式の問題については授業の何回目かのときに考えてもらいたいことを投げかけるので試験までの3ヶ月の間に考えて欲しいということ、また試験は教科書・ノート・資料持込可であるというようなお話がありました。
また、今後話していく話の中で今主流になっているデジタルの通信方式の中でOFDMがあるのですが現在のものは増幅の効率が悪く、高効率のアンプの話をしていくということ
日本が失敗したビジネスの中で携帯電話の端末のベンダーとして成功できないわけをお話されました。日本のビジネスモデルは垂直統合型でキャリア会社がすべてどのようなものを作って欲しいかを指示して、それに合ったものを作ればいいという形になっていたため、携帯電話のベンダーは開発コストのリスクをしょわなくてはならない反面、独自性のある端末を作ることができなかった。韓国の場合はビジネスモデルは似ているもののキャリアと端末ベンダーは協調統合という方式をとっていたためある程度、世界の市場に食い込むことが出来た。3Gのマルチメディア端末はコンテンツ作りのほうが大切でそれが供給できていないところでは普及は見込めない。今のところ3G端末が盛んなのは日本と韓国であるというお話でした。
2010年に
LTEという制度が出来て、次の次世代携帯電話が始まると日本の携帯ベンダーにはチャンスも訪れると同時に海外の安くて優秀な端末が流入してきて戦えない状況になる不安もあるそうです。
2011年はテレビの地上波アナログの放送が終了して地上波デジタルテレビに完全移行するわけですが、空いたVHFの部分、またUHFの上のバンドの部分のことを話されました。
730~770MHzまではFDD方式で900MHzと携帯電話をペアで使う。
170~202.5MHzまでは基本的には自営通信に割り当てて普段はWiMAXで使いますが、災害など非常事態が発生した場合 警察ー消防ー国ー地方自治体が共通して連携した通信を行えるような形に変更して使うということが考えられているそうです。
日本で今最も力を入れようとしているのはとにかく無線LANを強化しようとしていて5GHzの無線LANはAV機器同士の通信、情報家電など FMC(fixed Mobile Convertion?)というのがキーワードになるようです。(上の括弧部分はいい加減なので間違っていたら直してください)
携帯電話は家の中では無線LANと接続して固定電話として使用して外にでると携帯電話のネットワークで使用できるようにしたいそうです。
総務省の構想としては無線LANに使用する周波数を2008年までに480MHz幅確保、2013年までに740MHz幅確保するということが至上命題ということです。
今、少々問題になっているのはオーストラリアの国立研究所がOFDMの基本特許について権利を主張してきており少し動向を見極める必要はあるが、業界としては楽観視する見方が多いということです。
総務省が力を入れようとしている無線LANですが、それについては台湾に一日の長があり、台湾の技術は経験も価格も長じているので油断は出来ないですし、そのことはひとつの大きな課題だということです。
無線LANについてはMIMOなどの技術も進んでいて、アンテナを増やすとそれについてのメリットもありますが、その分デジタル信号処理が難しくなるということもあるようです。
また、ブルトゥース、ZigBee、WiBreeなどについても触れられました。
今まで電波に関するものというのは総務省が管轄していましたが、経済産業省などが関わることによって今後新しいものを開発する際には前のものより消費電力や効率などを上げるということが法律で義務づけられるようになるようです。情報通信の分野も地球温暖化に対して見逃してもらえるという甘い考えは通用しないとのことです。
第1回、第2回の授業に関する資料は下記からダウンロードできます。
http://www.amplet.co.jp/tdu/
 | 高周波・無線教科書―基本をおさえて無線工学の基礎を理解する (エレクトロニクス講座シリーズ)根日屋 英之CQ出版このアイテムの詳細を見る |