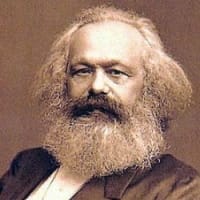本ブログ 総目次へ戻る
いわれなき高齢化社会への恐怖 社会負担は所得を向上させる(場合がある)
生産年齢人口とは15歳から65歳の人口を言う。雇用者として働ける人の数である。もっとも最近は65歳を過ぎても働くことが増えてきているが、当面15歳から65歳を生産年齢人口とする。実際に働いている人は就業者数である。
全人口に占める生産年齢人口の減少:少子高齢化を以下のように捉える論調が大勢を占めている。(wiki)
- 生産年齢人口(労働力人口)の減少による国力の低下
- 若年労働者の減少による深刻な人手不足
- 消費者の減少による経済の縮小
- 高齢者の増加による国民負担率の増加
この「問題」を供給側(企業)から捉えるとそうなるだろう。では需要側から捉えるとどうなるだろう。

生産年齢人口逆数とは人口÷生産年齢人口のことで、よく言われる「一人で何人支えるか」を表している。1945年に1.72であったものが1990年には1.44まで下がりその後2020年には1.73となっている。1945年では「多子少老」であったが2020年には「少子多老」となっているが数字そのものはあまり変わらない。
需要面から考えると、同じような1.7程度でも「多子少老」社会と「少子多老」社会では後者の方が需要は多くなるだろう。食費等は少ないかもしれないが医療・介護に需要が高まるからだ。これは総需要拡大⇒経済成長のチャンスだが、多くの人はそう考えられない。社会負担の増大は経済に悪影響を及ぼすと考える。たしかに個別企業で考えれば企業負担が増えるに違いない。
前項で扱ったように個別企業にとっては負担でも経済全体で見れば所得の移転であり移転先で使われれば、負担した側にそのまま所得になって返ってくる。企業経営者が騒ぐのは分からないではないが、そういう人にはきちんと理屈を説明するしかない。「自分の会社に内部留保を貯めこむより、きちんと負担して、使ってもらった方が自社の所得は増えるんだよ」と。
需要が拡大する政策を取って良い時と良くない時がある。それは供給面の弾力性にかかっている。これ以上供給の余力がない時に総需要拡大策を取ればインフレに陥るだけであり経済は成長しない。資金は余っているのだから悪性のインフレに陥る可能性も高い。供給の余力がある時はインフレ気味になりつつ経済は成長する。結構な事である。これが、社会負担は所得を向上させる場合だ。
現代日本の貯蓄投資バランスから見て必要なのは投資である。それも成長産業に投資するのが望ましい。
では成長産業とは何か?

2002年を100として医療福祉産業とそれ以外の雇用者の増え方を比べたものである。この医療福祉産業を成長産業と言わずして何というのだろうか?もちろん「顧客」は高齢者を対象としている。つまりまだまだ伸びるのである。そのうえ社会保険によってまかなわれている部分が非常に大きい。つまり望ましい投資先:民業を圧迫せずに国民の厚生を上げるという条件を満たしている。
社会負担は使われれば所得。貯蓄は使われなければマイナスとなる。
しかしながら、社会にも政府にも政党にも労働組合にも、「世論」にも、どこにも医療福祉産業を成長産業ととらえて高齢化社会を長期停滞から抜け出す好機だ、と捉える論調は見いだせない。
ここにこそ真の危機があるのではないか。