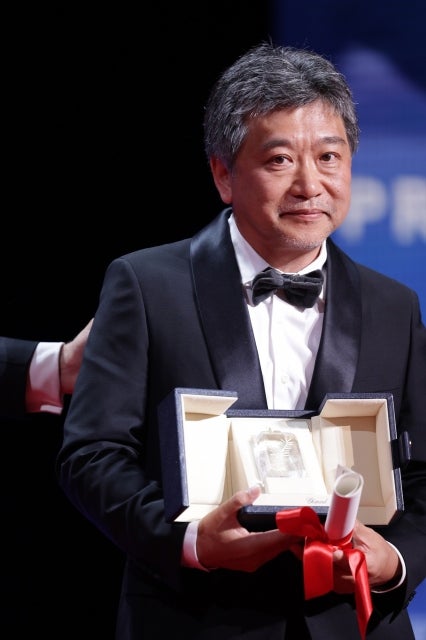「南方録」に「掛物ほど第一の道具はなし」と記されている。茶の湯の床の中心となる書画をテーマにした出光美術館の展覧会。
(会場は一切撮影禁止のため写真はネット画像を借用しました。)
今回は、ネットで購入した初単眼鏡を、いそいそと携えて鑑賞…
初単眼鏡には最適な展覧会でしたʘ‿ʘ

平沙落雁図(部分) 牧谿 中国 南宋時代
右の点々が雁4羽、肉眼では分からなかった

螺鈿楼閣人物図稜花食籠 中国 元時代
これも単眼鏡で観ると、螺鈿の象嵌が繊細かつ精緻で、妖しい輝きが手に取るように見えます、上から図柄が変化し、見飽きない優品でした

待花軒図 伝周文 室町時代
破墨山水図 雪舟 室町時代
画像はありませんが、この隣に、相阿弥の廬山観瀑図があります
観瀑図と言いながら、滝の主張は控えめで、小さく描かれた二人の高士が遠くに小さく描かれた二重の滝を眺める、かなり引きの画面が気に入りました
偈頌 宗峰妙超(大燈国師) 鎌倉末期〜南北朝初期
大徳寺開山大燈国師の書
大徳寺は“茶ヅラ”ですね
画像は無いが、隣に夢窓疎石の林和靖梅花詩があり、書は分からないのに何故か惹かれたら、夢窓国師だった

蓮下絵百人一首和歌巻断簡
本阿弥光悦下絵俵屋宗達 桃山時代
下絵は、蓮の葉を意匠化したもので
“肉まん”ではありませんw
真ん中の和歌は、有名な「しのぶれど色に出でにけりわが恋は…」平兼盛
伝藤原信実 鎌倉時代
この佐竹本にまつわる有名なエピソードがある
『旧秋田藩主・佐竹侯爵家に伝わったことから「佐竹本」と呼ばれ、数ある三十六歌仙絵の中でも最高の名品として珍重されてきた。この作品の「流転」が始まったのは大正時代になったからのこと。佐竹家は茶人にとって憧れの的である佐竹本を大正6年に実業家・山本唯三郎に売却。しかしながら山本はその2年後、経営不振を理由にふたたびこれを売りに出した。
しかし売りに出された佐竹本は、その高価さゆえ、単独での買い手がつかないという事態に陥る。そうした状況を打開すべく、三井物産創設者で茶人でもあった益田孝(鈍翁)を中心とする当時の財界人たちは、作品の分割購入という手段を取った。分割された作品にはそれぞれ異なる値段が付けられ、その総額は当時の金額で37万8000円(正確な換算はできないが、現在の価値でおおよそ数億〜数十億円になると考えられる)に及んだ。絵巻を一歌仙ずつ分割され、誰がどの歌仙を買うのかは、くじ引きで割り当てられたという。
この分割売却は、「絵巻切断」事件として当時の新聞でスキャンダラスに取り上げられた。そして分割された歌仙絵は、それぞれの所有者のもとで掛軸となり秘蔵され、またその多くは持ち主を転々とすることになる。全37件(下巻に歌仙絵ではない「住吉大明神」が含まれているため37件となる)のうち、現在は17件を日本各地の美術館博物館が、2件を文化庁が、1件を寺院が所蔵しており、残る17件は個人蔵となっている。』参照元美術手帖adam2019.2.16
いつもの、「八ツ橋図屏風」酒井抱一、「四季花木図屏風」鈴木其一、「芙蓉図屏風」伝尾形光琳も展示されています
会場には、“茶の湯”を嗜まれるとおぼしき、上品な奥様方が熱心に鑑賞されていました
★★★★☆
5/28まで、お勧めします
行ってみたかった、根津の串揚げ“はん亭”へ移動
しばし根津をぶらぶら…
岡倉天心らが“根津党”を名乗って遊興していた雰囲気を味わう…

串揚げの「はん亭」は登録有形文化財(建造物)大正6年(1917 )、木造3階建編集
夜のコースは、野菜スティック、串揚げ12本、小鉢2品

野菜スティックと本日の小鉢はタコの酢の物と何かのポタージュ
きれいにぎっしり入った野彩は最後までちょうどいい分量、最初にキャベツを食べると揚げ物の罪悪感が消える!?

海老、空豆、谷中生姜… 以上、撮るのを失念、ネット画像借用

ピノ・ノワールと串揚げ
アスパラ、魚、ホタテ、牛肉、麩の田楽、うなぎ、など
素材を活かした、あっさり美味しい串揚げ、
12本はペロッといっちゃいます(。•̀ᴗ-)✧
★★★★☆
ランキングに挑戦中
下のボタンを2つ、ポチッ、ポチッと押して頂けると嬉しいです!