今朝の信州は、いつもの気温に冷え込みました氷点下9度
この気温前後から寒い~と感じ、ホッカイロがありがたく
感じます。
今日は鏡開きとかで神様のお餅を下ろしてそのカチコチに
硬くなってひび割れたお餅をお雑煮にして食べる、我が家
は武士の家系ではありませんので、切るとか切腹は関係が
ありませんが昔からお婆様がすり鉢に入れて、すりこ木で
叩いてお雑煮にしていました。我が家と言えば昨日のカレ
ーの残りを温めなおしての朝食でした、ナベがあかないと
困るので( >_< )ということです。今夜あたりお雑煮になる
かもしれません。
それとは別に、今日は塩の日、1569年永禄11年、時は戦国
時代、越後の国(新潟北陸)を統治した大名上杉謙信が、宿敵
甲斐の国の大名武田信玄に塩を送り、「敵に塩を送る」と
いう言葉のもとになったことから、塩の日が決まる元とな
ったようです。新潟県糸魚川市と信州長野県の松本市を結ぶ
「塩の道・千国街道」によって塩が運ばれた。今日1月11日
は武田領の松本に塩が届いた日とされ、松本市とその周辺
ではこの日「塩市」が開催されていました。現在はこの日
前後の土曜日とか日曜日に開催されています。そしてその
名称も「塩市」との呼び方が江戸時代からは「飴市」と呼
ばれて、先週の七日と八日に松本市の商店街を中心に開催
松本市の広報によれば、当日は、日本各地の有名なあめや
珍しいあめが並ぶ「全国あめ博覧会・即売会」、飛騨高山
や九州の物産等が並ぶ「商都大物産市」のほか、中心市街
地が歩行者天国となり、上杉軍・武田軍に分かれて綱引き
を行う「塩取合戦」や「初春抽選会」「時代行列」「太鼓
連と演舞連の競演」に加え、歩行者天国内の商店街ではさ
まざまな催しが行われ、松本の新春の一大イベントとして
多くの来街者で賑わったようです。
そしてその塩の最終お届け先が我が町「塩尻」の語源とい
う説もあながち外れてはいないような気がしています。
そんなことで、今日は「塩の日」を語ってみました。










この気温前後から寒い~と感じ、ホッカイロがありがたく
感じます。
今日は鏡開きとかで神様のお餅を下ろしてそのカチコチに
硬くなってひび割れたお餅をお雑煮にして食べる、我が家
は武士の家系ではありませんので、切るとか切腹は関係が
ありませんが昔からお婆様がすり鉢に入れて、すりこ木で
叩いてお雑煮にしていました。我が家と言えば昨日のカレ
ーの残りを温めなおしての朝食でした、ナベがあかないと
困るので( >_< )ということです。今夜あたりお雑煮になる
かもしれません。
それとは別に、今日は塩の日、1569年永禄11年、時は戦国
時代、越後の国(新潟北陸)を統治した大名上杉謙信が、宿敵
甲斐の国の大名武田信玄に塩を送り、「敵に塩を送る」と
いう言葉のもとになったことから、塩の日が決まる元とな
ったようです。新潟県糸魚川市と信州長野県の松本市を結ぶ
「塩の道・千国街道」によって塩が運ばれた。今日1月11日
は武田領の松本に塩が届いた日とされ、松本市とその周辺
ではこの日「塩市」が開催されていました。現在はこの日
前後の土曜日とか日曜日に開催されています。そしてその
名称も「塩市」との呼び方が江戸時代からは「飴市」と呼
ばれて、先週の七日と八日に松本市の商店街を中心に開催
松本市の広報によれば、当日は、日本各地の有名なあめや
珍しいあめが並ぶ「全国あめ博覧会・即売会」、飛騨高山
や九州の物産等が並ぶ「商都大物産市」のほか、中心市街
地が歩行者天国となり、上杉軍・武田軍に分かれて綱引き
を行う「塩取合戦」や「初春抽選会」「時代行列」「太鼓
連と演舞連の競演」に加え、歩行者天国内の商店街ではさ
まざまな催しが行われ、松本の新春の一大イベントとして
多くの来街者で賑わったようです。
そしてその塩の最終お届け先が我が町「塩尻」の語源とい
う説もあながち外れてはいないような気がしています。
そんなことで、今日は「塩の日」を語ってみました。




















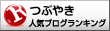

















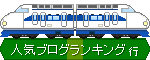
ますが、どんな味だったか思い出せません。博学のワ
イコマさんなら知っています?
それにもう一つ、江戸時代に「塩市」から「飴市」に
名称が替わったのはどういう経緯だったのでしょう?
何時も面倒なことだけコメントしてすみません。
英雄たちを支えたのが「塩の道」でした。
闇ルート網で専売の塩を捌き活動資金としました。
現代でも物と情報のルートを制する者が世の中を制しています。
鏡開きに実家では、土蔵や外の小宮やトイレに至るまで8ヶ所に飾ったお供えを下ろして金槌で壊しました。割れ目に青カビがふいていました。近年超合理的な生活をするようになった私は、お供えなどカザルのを忘れて居ました。
松本城下の最大の行事であった。1615年(慶長20年)
には正月の市初めに塩やあめが売られている記録がある。
1835年(天保6年)につくられた絵巻物「市神祭之図
(いちがみさいのず)」には、当時の行列の様子が詳しく
描かれている。
当初は塩も飴もその他の産品も一緒に売られていたよう
ですが、明治38年(1905年)に塩について国の専売品
となって、民間では塩を販売できなくなってから、飴市と
なったという説が一般的なようです。古く江戸時代は塩も
飴も売られていましたが、多分飴の需要の方が圧倒的と
想像できます。
塩飴・・夏の水分補給などに使われますが・・ネットでは
沢山の作り方が載っていますが、簡単に普通の飴に塩とクエン酸を加えたもののようです。
甘いのにしょっぱい、不思議な味で私は大好きです。
1905年(明治38年)に制定された、塩の需給と価格
の安定に寄与してきた塩専売制度は1997年に廃止
されるまで、実に92年間国の管理販売となって
いましたが、現在は『塩事業法』という法律のもと
原則自由の市場構造へと移行しています。
この塩は人間にとって生きるための必需品ですから
その昔は、戦略物資だったんですね~
私も昔は、得意先もあったりして、いつも飴市に
出かけましたが、 仕事の一線を離れてからは
行ってません、そしてこのコロナ禍では年寄りは
危ないと、近寄りません (≧∇≦)
我が家も、お供え餅は神棚と、水神様のお勝手と
玄関の三か所・・予想通り今夜はそのお供え餅の
お雑煮となりました。これで正月の餅は全部終わって
後は15日の小正月にもう一度お餅を飾って・・
今年の正月の餅飾りは終わります。
こんなことをしながら、春が近づいてきます。
おはようございます。
塩の日っていうのが
あるのですね。
塩尻の名前ももしかしたらそこから
来てるのかもしれませんね。
どんなものが売ってるのか見てみたいお祭りですね😆😆
武田は遠州今川と争って、塩を止められて苦しんで
いたが、武士は武士らしく戦って決着を・・塩を止めて
卑怯な戦いはしない・・という上杉謙信の、塩送り
その塩が最後の尻尾となったのが我が町の塩尻の
名前の由来と言われています。
飴市は https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/75/96952.html
をご覧ください、全国の飴が集まっているようです