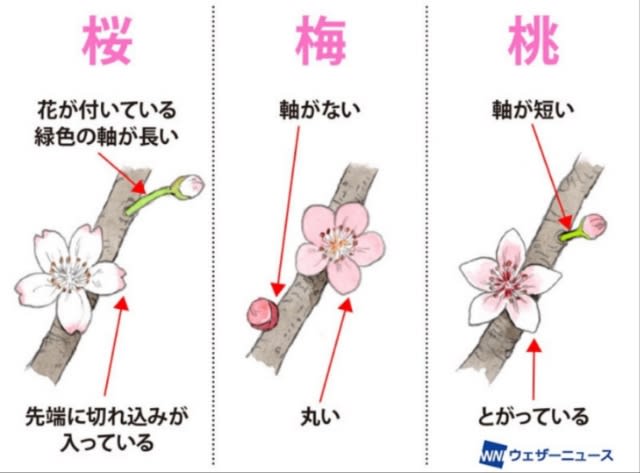今日は勤務先の小学校でスポーツテストがありました。主にソフトボール投げとシャトルランを行ったのですが、こういうものになると男子が俄然張り切ります。
特にシャトルランは次々と脱落していく中でクラスの体力自慢たちが残って、最後にはもはや意地と意地とのぶつかり合いの様相を呈していました。内心、
『あんまり張り切り過ぎると、後が大変だぞ〜…』
と思っていた予想を裏切ることなく、その後はほぼ使い物にならない男子ができあがっていて、申し訳ないながらも笑ってしまいました。
そんな小学校勤務を終えてから、帰宅前にちょっと小田原城址公園に寄り道していくことにしました。こちらでは現在、《あじさい花菖蒲まつり》が開催されています。
本丸前の東堀には、

有志が丹精込めて育てた花菖蒲が咲き誇っています。毎年思いますが、



これほどの数の花菖蒲を株分けしたりして育てていく労力というものは、並大抵ではないでしょう。
東堀に面した斜面には




色とりどりの紫陽花の花が見頃を迎えています。この斜面はかつて本丸の石垣でしたが、関東大震災で崩落してしまった場所です。よく見ると


かつて石垣に使われていて崩れた巨石が、そこかしこに放置されたままになっています。
この《あじさい花菖蒲まつり》は、6月16日(日)まで開催されています。日没から20:30まではライトアップも開催されていますので、興味を持たれた方は是非訪れてみてください。