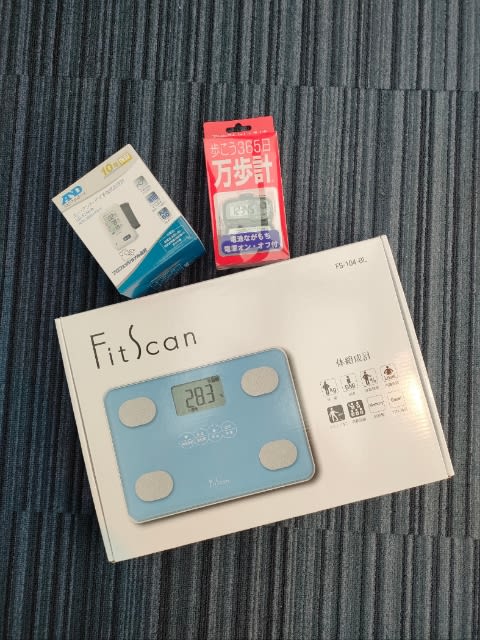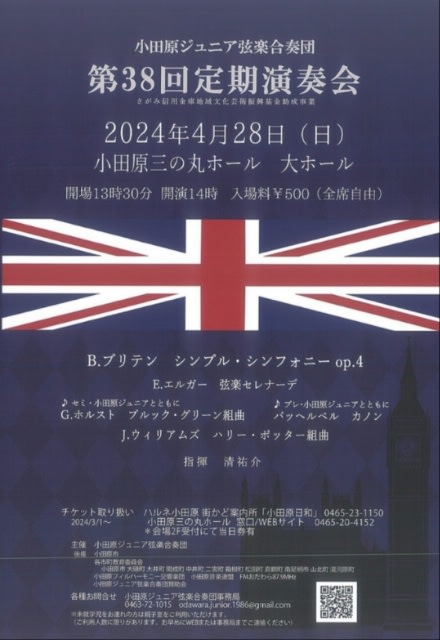今日は朝のうちから雨の降りしきる、生憎の天候となりました。こうなると、一部の支援級の子たちが無気力モードを発揮し始めます。
今日もご多分に漏れず、中学年の子が
「交流級に行って勉強したくない…!」
とゴネ始めました。とにかく、自分の気が乗らないことを最大の理由にしてグチグチ言い始めるのです。
そんな子に向かって、担任や主任はあれやこれやとなだめてすかして、何とか交流級に行ってもらおうと必死でした。しかし、たまたまその時私がサポートに行くことになっていたのが、その子にとっては運の尽きでした。
「ゴチャゴチャ言ってないで、早く立ちなさい。」
と強めに言ったのですが、その子は
「行きたくない!」
と言い返してきました。しかし、これは私にとって実に好都合な返しだったのです。
「『行きたくない』と『できない』では、全然話が違います!」
「『できない』というのであれば、私たちが全力で学習をサポートします。『行きたくない』というのは、ただのアナタの我が儘です!」
「今日この時間に交流級で勉強することは、一週間前からお知らせしてあります。知らなかったとは言わせませんよ!」
ここまで畳みかければ、さすがの支援級の子も突っかかってこられません。何しろ全て事実ですから、反論の余地がないのです。
結局その子は私を睨みつけながら、不承不承立ち上がって交流級に行きました。後ろで主任が何やら言いたそげな顔をしていましたが、私は気づかないフリをしてその子の後ろから付いて行き、きちんと交流級で授業を受けてもらいました。
支援級の子たちは、通常級の子たちのようにいろいろとできないことが多くて不便だと思いますが、それは『不便』なのであって決して『不幸』なことではありません。そして、『不便』を克服して道を切り拓いていくのは本人次第です。
何とか全てのカリキュラムを終えて子どもたちを下校させてから、主任にとっ捕まる前に私もサッサと退勤しました。どうせとっ捕まったら、長い『ご要望』を聞かなければなりませんので。
小雨の残る中、小田原駅までの道を歩いていたら、どこからともなく甘い花の香りが漂ってきました。その香りを辿って風上に向かって歩いていくと、道すがらのお宅の垣根に

ハゴロモジャスミンの花が咲いていました。
いろいろとあってちょっとササクレだっていた私の心にハゴロモジャスミンの香りが届いて、少しばかりホッとすることができました。明日また出勤したら主任にとっ捕まるかも知れませんが、その時はその時です。