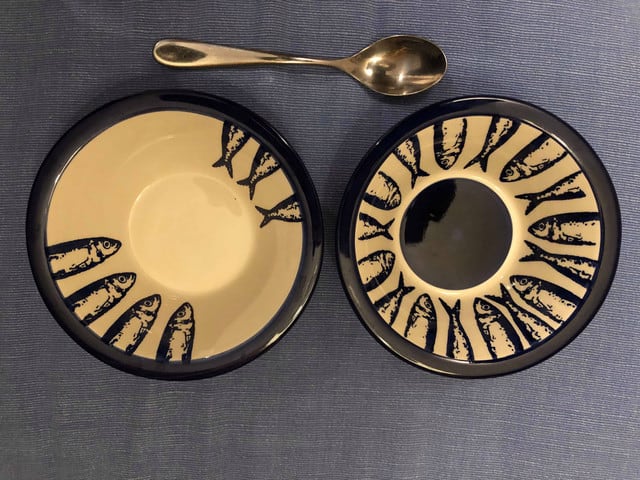昨日は予告通り、暑かったです!ここ北西部も日中気温がついに30℃を超えました。

毎週土曜日は、例によってチャリティ・ショップ、オックスファム Oxfam で店番のボランティア、駐車場と店への行き来以外は屋外に出ませんでした。
店内は気温が26℃、扇風機でけっこう涼が取れました。
入ってくるお客さんが「お、涼しいね」「外から来たら天国だよ」などと声をかけてくれます。
屋外の気温が高くても、日かげや屋内はびっくりするほど過ごしやすい湿度の低い英国です。汗がスッと引く爽快感が味わえます。

英国でも(特に年配の人の)あいさつの常とう句は「天候の不満」です。
通常、夏があまり暑くない英国では人々の暑い夏に対する渇望、執着が並ではない...ということをストックポート日報ではくどいほど書き続けてきましたが、さすがに熱波の4日目、暑ければ暑いでモンクを言う人の相手を多数(6時間の間に20人ほど)してしまいました。
...「そんなにたくさん店員と世間話や天候話をする客がいるのか」と思われましたか。店の雰囲気にもよるでしょうが、いるんです!店員も客に対するフレンドリーなジェスチャーとして天気の話をしてきます。
こっちから話題をふる必要はありませんが、もしも英国滞在中に店員から天候のグチでも吹っかけられたらとにかく同意してあげてください。礼儀です。英語で言うのがめんどくさいなら手で顔をあおいで暑そうにするとか寒そうに首をすくめるとか雨ならば肩の水滴を払うふりとかで充分です、
ニュースをつければ、水不足(干あがった貯水池や湖の映像)農作物の値段の高騰、水難事故、大規模火災(川で釣ったサカナを焼いた火の不始末で農地と生態保存エリアを全焼!!!)、熱中症、屋外での運動アクティビティを制限する警告...等々暑さに関連するウンザリ報道がくりかえされます。
私は「暑くてまいった」と言う人には「来週から涼しくなって雨も降るみたいね」と繰り返しました。客の反応も一律でした。「それはありがたいけど、そうすると夏が終わってしまうのね、あ~ぁ、残念だ!」... 勝手にしろ!
「南欧でのホリデー(休暇旅行)だったらいくら暑くてもいいんだけどな」という年配の人もいましたよ。「そういえばポルトガルでは今日40℃ですって」と、温度計の華氏(105℉)の目盛りをさして教えてあげました。その人はホリデーだったら105℉でもうれしくて屋外を歩き回るそうです。
...前置きが長くなりました。写真は、カタルーニャの内陸都市ジローナGirona の伝説的名所、ジローナのメスライオン像 El Cul De la Lleona です。「また今回は説明抜きで何なんだ?」と思われた方もいるでしょう
暑いのがひときわ苦手で、暑い時に暑い南欧なんかに行くのがイヤだった私です。
それでも美しい街並みとまぶしい日差しに心が躍って気温34℃の中、積極的に歩き回った、カタルーニャ旅行最後の日の高揚感を思い出しました。
たしかに猛暑の中、見なれた英国(近所)をほっつきまわる気力は皆無ですが異国の風景の魔法...はたしかに効いていたようです。
中世の城壁の上をかなり歩いたあと、大聖堂わきの小さな広場のバーで一休みしました。
その時は暑さがたたってかなりくたびれていました。
息子がスマートフォンの観光案内ページを私に手渡して「もう一か所、どこか見てみたいところある?」と聞いてくれたので、サッと見て、「これ。ここからすぐに行けるところだったら見てみたい」と石の柱にへばりついたマヌケな顔をしたライオン像の写真を指差しました。
中世のライオン像のおしりにキスした人には幸運が訪れるという伝説があると書かれていました。
中世の頃からジローナを訪れた人は必ずキスしていくいわくつきの、由来はナゾだという奇習です。
動物の古いオブジェとへんてこりんな土着の奇習が大好きな私が見逃すわけにはいかない現地に来るまで知らなかった名所です。
あら、びっくり!なんてラッキーなの!?「 今いる場所から30m」とGPSの電波が教えてくれていました。
「あれ?」と横を見れば、30mどころか、私たちが座ったテーブルから10歩ぐらいのところに全く目立たない石の柱と知って見上げないと絶対に目に入らないマヌケ顔のライオンがいました。
観光案内ページには読者が投稿した、ライオンのおしりにキスする自分の写真が何枚か掲載されていましたが、この高さでどうやって...?
身長190cm のうちの夫を無理やりそばに立たせて写真を撮りました。

肩車でも無理ですね、アクロバットのように肩の上に立てば何とか可能です。

カタルーニャ語のみで「ライオン像のおしりにキスするの禁止」と書かれているらしい(ライオン像がカピバラのように表現された図解入り)立て札がありました。
だから、どうやってキスするのって言ってるのよ...
帰国して、改めて観光記事の写真をいくつも見てビックリ、納得。パンデミック開始まではライオン像の下に鉄の段々が備え付けてあったのです!
コービッドで「キス禁止」になり、とりはらっちゃったんですね。
観光案内ウェッブページには「中世の石像」と書かれていたので、そんな貴重な考古学資料にキスなんかしていいものかという強い疑問がありました。吹きさらしなのも荒っぽすぎますし。
そういえばコロナウィルスが蔓延するなか他人が口をつけた場所にキスする是非なんてそういえば、思いつきませんでした。
「キス禁止」立て札を撮った上の写真を拡大してみたら、行って見た時には気が付かなかったカタルーニャ語の説明に、各国共通語の covid 19 という単語があるのを見つけました。
観光客にキスさせるためのこのライオン像はレプリカだそうです。もともとこの場所にあったというオリジナルは11世紀のロマネスク彫刻で、現在は博物館で展示中だとか。なるほど、納得。
息子が見つけた観光案内ウェッブサイトには「ライオンのおしりにキスした人には幸運が訪れる」と書かれていましたが(諸説あるようです)実際は「ライオンのおしりにキスした人は再びジローナを訪れることができる」が正しいようです。
帰国して、いろいろな観光サイトを見て確認しました。
もっと涼しい時にでももう一度、ぜひ行きたいジローナ!大聖堂の中も旧ユダヤ人街も見なかったものですから。キスしてくればよかったですね、あ、禁止でしたのでもちろん無理でした(第一、高すぎます)
カタルーニャ語で(!)由来が書かれた銅板には絶対にライオンには見えないライオン像の復刻浮彫がありました。

手でなでなでした人がいかに多いかがツヤツヤ度で判明する、復刻レリーフのライオンのお尻です。
暑さが少し落ち着いた来週あたりからまた少し出歩いて、ストックポートやマンチェスターなど地元の話題を拾ってみるつもりです。