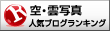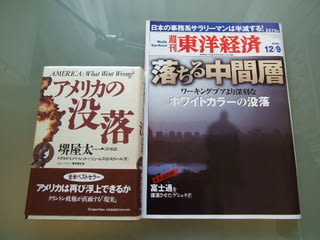今回の内容
・少子化対策と人手不足。
・雇用の現状(働き手は減少)
・生産性向上と人手不足対策は、非正規雇用者を制限する。
はじめに
本稿は2016年8月4日に投稿したものです。当時、殺害された安倍首相が「一億総活躍社会」、「働き改革」を訴えていました。
そして今、岸田首相の「異次元の少子化対策」と「人手不足」が話題です。
振り返れば少子化という言葉は . . . 本文を読む
労働組合。労働者の権利を守る役割では一定の役割を果たしている。経営の不当労働行為を防止している。しかし、筆者の労働組合への評価は手放しの礼賛ではない。所属する会社および労働組合という枠の中でしか利益を追及できない。広く深く長きに渡る社会課題を解決するのは困難だ。労働組合員数が少ないというだけではない。企業別組合が、原発廃止の障害となっている。先の都議選では「都民ファーストの会(幹部には核武装論者 . . . 本文を読む
昨夜投稿した英国総選挙の続き。表題の「Zero-hour contract」も焦点になっている。労働党はこの雇用契約の禁止を公約にしている。日本では非正規労働者の増加が問題であるが、英国では、さらに進んだ雇用契約がある。日本では、雇用者と被雇用者双方に、所定労働時間(1日、あるいは1週、もしくは1月当たりの労働時間。変形労働時間制も認められる)という義務がある。ゼロ時間契約には、これがない。必要 . . . 本文を読む
利潤は「差異」により生まれるのか。あるいは「労働量(と質)」によるものなのか。後者はマルクス先生の説である。労働者の労働により付加価値が生まれる。この付加価値を搾取するのが資本家。だから労働者による社会主義国家の樹立が必要。だが、社会主義はうまく機能しなかった。
前者は岩井克人先生の説である。新商品開発にあけくれる現代社会を見れば、簡単に分かる話である。先駆者利潤は山ほどの事 . . . 本文を読む
広く知られていることだが、パート社員の争奪戦が起こっている。
時給UPだけでは、決定打にならない。安心して働ける環境整備が急がれている。 できるだけ公平な評価制度。労働基準法の遵守。定年の延長。厚生年金の積極的な運用。
さらに、内部通報制度の整備。職場の明るい人間関係の構築。作業マニュアルの改善改革。働く意欲の沸く職場作り。働いた結果の社会的価値が認識できるビジネス。 &nbs . . . 本文を読む
「アメリカの没落」 日本で出版されたのが93年2月。この本の第一章は「中流階級の崩壊」だ。これを読んだとき、この先の傾向が読み取れた。米国、そして日本、さらには欧州。3日付の日経の国際面には、「崩れる中間層、貧困5000万人」とのタイトル。米国の実態だ。
1950年代にアメリカの労働者階級は頂点に達した。一家に2台の車があり、青々とした芝生に囲まれた家に住み、子供 . . . 本文を読む
巷、説明を聞く「日本の成果主義」には、昔よりどうしても合点がいかない。ところが、昨日、法政大学教授 小池和男さんの文章を読んだ。うなづくことが多いので紹介したい。要約すると以下の通りである。
1) 既製の観念
年功 ⇔ 成果主義
あるいは、
非競争・非実力 ⇔ 競争・実力主義
なる対立。
2)実態
長期成果主義 ⇔ 短期成果主義
ではないか。 . . . 本文を読む
近況紹介
上場企業会社員です。
只今69歳。65歳と2か月で脳梗塞を発症、5か月間の入院を経て、6か月後に復職しました。
月に10日ほど仕事をしています。
仕事場は、自宅近くにあるサテライトオフイスです。
好きな言葉は、「着眼大局、着手小局」です。
モットーは、「実態は、現場・現物・現実・数字で確認する」です。なので、根拠は出来るだけ現物を示します。
原理原則は「観察(問題点を探る)・分析(その原因を探る)・判断(緊急と根本的な対策)」です。
読書・運動・公園散歩・旅・映画館での映画鑑賞時間を過ごすのが好きです。