テレビ業界の動向や現状、ランキングなど
テレビ業界の動向と現状(2021-2022年)
2021年のテレビ業界は前年から回復も、コロナ前の水準に届かず
下のグラフは、テレビメディア大手5社の売上高の推移を示したものです。(2015年を100とした場合の売上高割合)
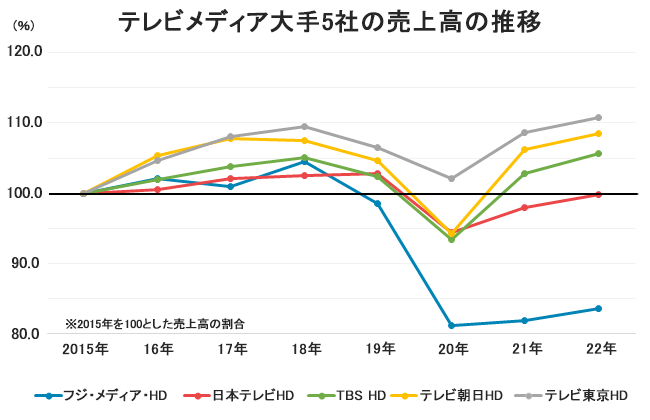
テレビメディア大手5社の売上高の推移(各社有価証券報告書、グラフは業界動向サーチが作成)
テレビメディアの売上高は2020年にかけて減少傾向でしたが、2021年には回復を見せています。2021年はテレビ東京、テレビ朝日、TBSの3社が2015年の水準を上回りましたが、日本テレビとフジテレビは下回りました。とくにフジテレビの下落幅は大きく、2021年にも明確な回復は見られませんでした。
続いて、直近の動向です。2022年のテレビ広告売上高が2023年2月に公表されたので見てみましょう。下のグラフはテレビ業界の収益源であるテレビ広告売上高の推移です。経済産業省の特定サービス産業動態調査によると、2022年のテレビ広告業の売上高は、前年比11.4%減の1兆2,949億円でした。
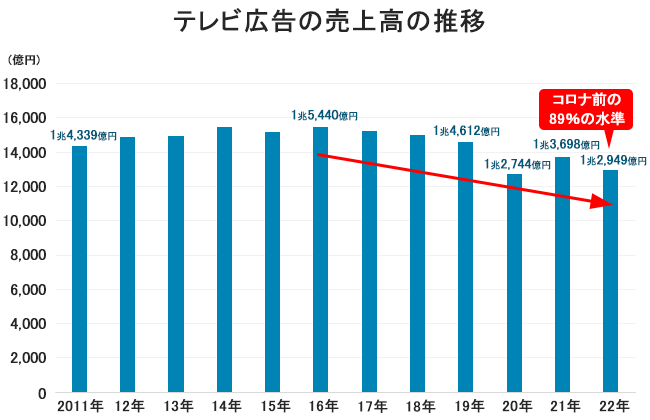
テレビ広告の売上高の推移(出所:経済産業省、グラフは業界動向サーチが作成)
グラフの推移を見ますと、2020年はコロナの影響で減少幅が拡大しましたが、2021年に入り4年連続の減少は止まり増加に転じています。一方、2022年のテレビ広告は再び減少に転じ、コロナ前の19年と比較しますと、約89%の水準にまで低下しています。こうしたことからも、長期的にテレビ広告の売上高は2016年をピークに減少傾向にあることが分かります。
一方で、2021年にはインターネット広告が初めてテレビ広告を抜きました。2022年のインターネット広告は前年比5.1%の増加を記録、テレビ広告とは1,471億円の差をつけインターネット広告が2年連続で首位となりました。広告の主軸がテレビからネットにシフトしており、テレビ業界にとっては厳しい状況となります。
近年では、スマートフォンや高速通信環境の普及で「YouTube」や「Netflix」などの動画配信サイトが急速に浸透しました。若年層をはじめ、近年では50代や60代の中高年もネットへと移行しつつあります。こうした動向を受け、スポンサー企業は広告費をテレビからインターネットネットへと移行させており、テレビ業界の広告収入の流出が止まりません。
このような傾向は今後も続くものと見られ、テレビ業界にとっては深刻な問題となっています
(朱字は管理人による)
フジテレビは開局65周年なのに「深刻で緊急事態ともいえる状況」 宮内会長も危機感を募らせる“低視聴率の実態”
2022年度の個人視聴率が全日帯(午前6時~深夜0時)もプライム帯(午後7時~同11時)も4位に終わり、今年度に入ってからも復調していないフジテレビ。宮内正喜会長(79)は7月10日、社内の新体制全体会議で「深刻で緊急事態とも言える状況」と発言した。かつて民放の王者だったフジが、いよいよ危機感を募らせ始めた。(視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区)
ついに危機感を表す
宮内会長は営業畑と編成畑を歩み、民放ビジネスを熟知した人として知られる。その宮内会長が全体会議でこう呼び掛けた。 「テレビ業界全体の広告収入が悪化し、とりわけフジは深刻で、緊急事態と言える状況。緊急対策を講じないと、(2023年度)通期でも厳しい業績になる可能性がある」 危機感を隠さぬ発言。かつて民放の王座に長く君臨したためか、フジは視聴率低下後も強気の姿勢を崩さないという社風があったことから、局内外を驚かせた。
1年前に就任した港浩一社長(71)はバラエティ畑が長く、有力子会社の共同テレビ社長として実績を残した。その港社長は同じ全体会議でこう述べた。
「(今年は)開局65周年の勝負どころ。まずは放送収入を取り戻しましょう」
視聴率低下を表す言葉である。数字を上げないと、CMは高く売れないのである。
港社長は就任すると矢継ぎ早に番組改革を行なった。現場時代に「オールナイトフジ」(1983年)、「とんねるずのみなさんのおかげです」(1988年)を大ヒットさせた人でもあるので、バラエティを軸とした改革だった。1982年から1993年までのフジ一強時代を支えたのもバラエティ。原点回帰を思わせた。
だが、思うようにはいっていない。特に1月から始まった昼のバラエティ「ぽかぽか」(月~金曜午前11時50分)は個人視聴率がほぼ連日1%割れ。バラエティでありながら、コア視聴率(13~49歳の個人視聴率)は0.5%を割ってしまうこともある。
参考までに3年前からテレビ界では使われていない世帯視聴率も記すと、ほとんど1%台。出演者が少なく、制作費がはるかに安いと思われるテレビ東京「昼めし旅 ~あなたのご飯見せてください! ~」(月~金曜午後12時)にも敗れ、横並びで最下位になる日もある。
前身番組「ポップUP」も視聴率は低かったが、それでも個人で1%を超えることが珍しくなかった。世帯は2.5%に達したこともある(昨年10月12日)。1982年から2014年まで続いた「笑っていいとも!」も当初は苦戦したが、半年が過ぎるころには同時間帯でトップを争っていた。
「ぽかぽか」の場合、観た人なら思う通り、つまらないわけではない。だが、他局の大半は情報番組。「いいとも」の全盛期とは人口形態も大きく変わってしまった。高齢者が増えた。今の視聴者の多くは昼番組にバラエティを求めていないのではないか。
「ぽかぽか」が全体の足を引っ張る
2時間やっている「ぽかぽか」のような大型の帯番組に勢いがないと、後に続く番組にも悪影響が出る。テレビ界の常識だ。日中は特にそう。チャンネルを積極的に替えない視聴者が多いからである。 「ぽかぽか」の放送終了後に始まるドラマの再放送「+ストリーム!」の第1部(月~金曜午後1時50分)「離婚弁護士」は、7月18日放送の視聴率が個人0.8%(世帯1.6%)。一方、テレビ朝日「シッコウ!! 犬と私と執行官」は個人1.3%(世帯2.8%)。やはり厳しい。 「オールナイトフジ」(1983年)のコンセプトを採り入れ、4月にスタートさせた「オールナイトフジコ」(金曜深夜0時55分)の7月14日の視聴率は個人0.7%(世帯1.4%)。深夜で2時間と長い番組なので、他局との単純比較は難しいが、横並びで2、3位といったところ。こちらは、まずまず。
苦戦中なのが4月30日に鳴り物入りで始まった「まつもtoなかい」(日曜午後9時)。元SMAPの香取慎吾(46)がゲスト出演し、同・MCの中居正広(50)と6年ぶりに再会した初回は個人7%(世帯10.5%)と高視聴率だった。同じ日、個人7.8%(世帯13.1%)だったTBS「ラストマン―全盲の捜査官―」(同)の第2話よりコア視聴率は上だった。
しかし、その後は急失速。6月11日放送は個人2.7%(世帯4.4%)と落ち込み、テレビ東京「家、ついて行ってイイですか?」(同)の個人3.3%(世帯5.4%)を下回り、横並びで最下位に。柄本明(74)、古田新太(54)たちがゲスト出演した7月9日放送も個人3.0%(世帯4.9%)。16日放送の総集編は個人2.9%(世帯4.9%)だった。
ドラマにも1980~90年代を思わせる作品がある。7月10日に始まった森七菜(21)と間宮祥太郎(30)がダブル主演する「真夏のシンデレラ」(月曜午後9時)。東京のエリート顔をした若い男性たちと神奈川県・江ノ島で地道な暮らしを送る女性たちが恋をする。全編からバブル期とあのころの海の匂いがする。
初回の視聴率は個人4.0%(世帯6.9%)。総個人視聴率(PUT=その時間帯にテレビを観ている人の割合)がこの10年で約6、7%落ちているので、古い作品と視聴率を比べるのは無謀極まりないが、前々作「女神の教室~リーガル青春白書~」の初回は個人6.4%(世帯10.5%)、前作「風間公親-教場0-」(月曜午後9時)は同じく個人7.2%(世帯12.1%)だったから、見劣りする。17日放送の第2話は個人3.2%(世帯5.4%)とさらに落ちた。
この作品のメインターゲットであるはずの今の若者はバブル期、バブル崩壊直後の若者と比べ、はるかに勉強し、働き、アルバイトをすることを迫られている。バブル期の価値観が採り入れられたと思しき作品をどう受け止めるのだろう。
フジの蹉跌の理由について、芸能プロダクションや制作会社はさまざまな分析をしている。共通するのは次のような言葉だ。 「フジは時代をつくり続けた。あるいはつくろうとしてきた。今はそうではないのではないか」 確かに、真っ昼間にお笑い芸人が勢ぞろいした「笑ってる場合ですよ!」(1980年)とそれに続く「いいとも」は斬新だった。女子大生を前面に押し出した「オールナイトフジ」も他局には真似できそうにない遊び心満載の番組だった。トレンディドラマもある種の発明と言って良かった。
やることなすこと新しかった。だから若い視聴者が飛びついた。今はどうだろう。
視聴率とCM売上高はほぼ一致する
2022年度の年間個人視聴率とCM売上高を見てみたい。民放界の現状が浮かび上がる。個人視聴率と売上高はほとんど一致する。
なお、エビデンスも示さず、「今はTVerが中心の時代」とする向きもあるが、その売上高はCMとは比べものにならない。各局のTVerなどの売上高はCMの約50~30分の1に過ぎない。TVerは認知率(15~69歳)すら今年1月段階でまだ68.5%(マクロミル調べ)。「TVerが中心の時代」とするのはプロパガンダに過ぎない。現段階でテレビ局の大黒柱はあくまで電波なのだ。
【個人視聴率・全日帯:午前6時~深夜0時】
1 日本テレビ 3.6%
1 テレビ朝日 3.6%
3 TBS 2.8%
4 フジテレビ 2.4%
【個人視聴率・プライム帯:午後7時~同11時】
1 テレビ朝日 5.6%
2 日本テレビ 5.4%
3 TBS 4.2%
4 フジテレビ 3.8%
【CM売上高】
1 日本テレビ 2369億800万円
2 テレビ朝日 1791億4100万円
3 TBS 1628億8500万円
4 フジテレビ 1603億8000万円
個人視聴率で日テレより優勢のテレ朝が、なぜCM売上高では大きく下回っているかというと、コアは日テレが断トツであるため。コアは行動が活発な世代であることから、スポンサーが歓迎する。 コアの数字も見てみたい。
【コア視聴率・全日帯】
1 日本テレビ 2.9%
2 フジテレビ 1.8%
3 TBS 1.6%
4 テレビ朝日 1.4%
【コア視聴率・プライム帯】
1 日本テレビ 4.7%
2 TBS 3.1%
3 フジテレビ 3.0%
4 テレビ朝日 2.8%
個人で上位に水を空けられたフジがCM売上高で差を詰められたのはコアが2位だったから。コアが下がると、きつくなる。だが、今年度に入ってからはTBSがコアを伸ばしている。今年4月のプライム帯のコアは、日テレ4.3%、TBS 3.3%、フジ3.0%、テレ朝2.1%だった。
最後になるが、フジに限ったことでなく、話題の番組や魅力的な番組をいくつも制作したら、その局は必ず浮上するはず。ところが最近は番組づくりよりTVerや番組などの話題づくり、イメージ戦略が先行している局が目立つのではないか。
局の幹部の中には「情報操作をしている局がある」と指摘する人までいる。具体的な例まで示された。まさかと思う。もし、それが事実となったら、報道機関による風説の流布となり、その局も関係者も壊滅的打撃を受ける。日本テレビの社員が行った2002年の「日テレ視聴率買収事件」以上の事態になる恐れがある。
そんな疑念の声が上がるのも話題づくり、イメージ戦略が先行しているからだろう。観る側がテレビに望むのは面白い番組だけだ。
鈴木文彦 デイリー新潮編集部
 (フジテレビ 宮内正喜会長:画像はネットから借用)
(フジテレビ 宮内正喜会長:画像はネットから借用)
「機器」は、機械や器械、器具の総称です。
電子機器・精密機器という感じで使われます。


























