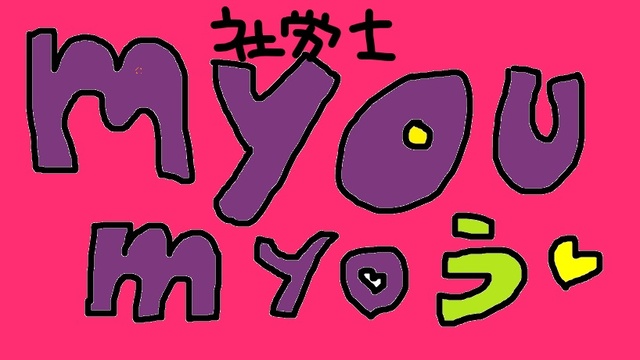先日労働災害防止についての講義を受けました。講師は労働基準監督署長でした。
私は珍しく後ろの方に座っており、昼過ぎという時間帯でもあったせいか、睡魔と闘っていたのですが、さらに後ろのほうでは、高らかないびきと共に安らかな眠りについている方もいらっしゃいました。
講義内容が眠気を誘うものであったとは思います。私も最初は正直「キツイ…」と思いました。しかし、労働災害防止がなぜ退屈な内容となってしまうのでしょうか。講師の腕でしょうか?受講生としては講師のせいにしたくもなりますが、じゃあ、自分がこのテーマで講義をして、昼過ぎに受講生の目を開けておく自信があるのかと言われたら、自信ないですよ!
安全衛生だの快適な職場環境の形成だの、マネジメントシステムの運用だのリスクアセスメントだのを羅列されれば不眠症だって治るってもんじゃないですか。
私がなんとか脱落せずに(居眠りと空想に逃げずに)講義を聞けたのは、最終レポートを提出して修了したオンライン講座『東日本大震災を科学する』での内容に通じるものをかんじたからです。地震の規模や揺れがどれほど大きくても、それが砂漠の真ん中とかで、人や財産に被害がなければ災害ではないという考え方。これは業務災害でも同じです。「人間」をどのように守るかが最重要であるにもかかわらず、地震にしろ仕事における事故にしろ、人間が軽んじられています。
なんでだろうな~~
自分を振り返ってみて思うのは、たぶん大きな災害って、「想定外」なんだと思います。他人の身には起きるかもしれないけど(報道されているものは他人事なので)自分の身には起きないと、なんとなく思っている、というか考えていない・想像しない。えーっと、それが「想定外」ってことですね。
労働災害なんかも、自分の会社ではそんな大きな悲惨なものは起きない。自分が関与している事業所で起きることはないだろな~というかんじかもしれません。
危機意識を持つにはどうしたらいいのだろう。
地震や労働災害だけじゃなく、子どものことや夫婦のこと、経済的なこと、健康のことなど、どれも悪いことは「想定外」として責任逃れが許されるはずないですね…
さて、講義ですが、もし10代~20代の人に労働災害というテーマで話をするとしたら、どんなテキストを使用して、どんな形でやれば関心を持ってもらえるでしょうか。
人の講義にはケチをつけるだけじゃなく、自分ならどうやるか、という観点がないと身につかない苦行となってしまいます。
私は珍しく後ろの方に座っており、昼過ぎという時間帯でもあったせいか、睡魔と闘っていたのですが、さらに後ろのほうでは、高らかないびきと共に安らかな眠りについている方もいらっしゃいました。
講義内容が眠気を誘うものであったとは思います。私も最初は正直「キツイ…」と思いました。しかし、労働災害防止がなぜ退屈な内容となってしまうのでしょうか。講師の腕でしょうか?受講生としては講師のせいにしたくもなりますが、じゃあ、自分がこのテーマで講義をして、昼過ぎに受講生の目を開けておく自信があるのかと言われたら、自信ないですよ!
安全衛生だの快適な職場環境の形成だの、マネジメントシステムの運用だのリスクアセスメントだのを羅列されれば不眠症だって治るってもんじゃないですか。
私がなんとか脱落せずに(居眠りと空想に逃げずに)講義を聞けたのは、最終レポートを提出して修了したオンライン講座『東日本大震災を科学する』での内容に通じるものをかんじたからです。地震の規模や揺れがどれほど大きくても、それが砂漠の真ん中とかで、人や財産に被害がなければ災害ではないという考え方。これは業務災害でも同じです。「人間」をどのように守るかが最重要であるにもかかわらず、地震にしろ仕事における事故にしろ、人間が軽んじられています。
なんでだろうな~~
自分を振り返ってみて思うのは、たぶん大きな災害って、「想定外」なんだと思います。他人の身には起きるかもしれないけど(報道されているものは他人事なので)自分の身には起きないと、なんとなく思っている、というか考えていない・想像しない。えーっと、それが「想定外」ってことですね。
労働災害なんかも、自分の会社ではそんな大きな悲惨なものは起きない。自分が関与している事業所で起きることはないだろな~というかんじかもしれません。
危機意識を持つにはどうしたらいいのだろう。
地震や労働災害だけじゃなく、子どものことや夫婦のこと、経済的なこと、健康のことなど、どれも悪いことは「想定外」として責任逃れが許されるはずないですね…
さて、講義ですが、もし10代~20代の人に労働災害というテーマで話をするとしたら、どんなテキストを使用して、どんな形でやれば関心を持ってもらえるでしょうか。
人の講義にはケチをつけるだけじゃなく、自分ならどうやるか、という観点がないと身につかない苦行となってしまいます。