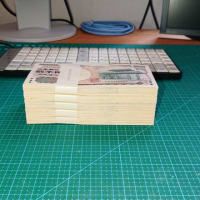私はこのシリーズで,軌間2000 mm程度の超広軌鉄道と,日本中の鉄道をその軌間に移行させることを提唱しようとしている.こうした話に辿り着くには様々な経路がある.たとえば,単純に輸送力を増したいとか,スピードを上げたいとか,安全性を向上させたいとか,軌間の統一によって車両や路線の互換性を確保し利便性の向上につなげたい,などという切り口から超広軌を提唱することが可能である.他には,「歴史的な事情によるしがらみや固定観念の打破」などと大上段に構えて話を始めることも可能である.前回は前者のアプローチをとったわけであるが,今回は後者のアプローチを試みてみたい.
人間の社会において,規格というものは欠かせないものであり,そしてごく当たり前のように存在している.身近なところを見ればSI単位系,ISO,JIS,DIN,IEEEなど枚挙に暇がない.言語も規格といっていいかもしれないし,極論すれば「常識」というものも規格の一種であろう.
規格が国や地域によってまちまちという例も枚挙に暇がない.車が右側通行か左側通行か,商用電源周波数は50 Hzか60 Hzか,他にも色々ある.言語もバラバラである.そして,鉄道に関する規格も例外ではない.
しかしながら,決められた規格はなくとも,事実上の標準(デファクトスタンダード)が存在する分野も多い.車はどちらかというと右側通行が,商用電源周波数は50 Hzが,言語は英語が,それぞれ世界のデファクトスタンダードであると言ってよいだろう.そして,鉄道の分野には標準軌間(1435 mm)というものがある.
また,それら世界のデファクトスタンダードと日本国内のデファクトスタンダードが異なっている場合も多い.例えば自動車は左側通行であるし,商用電源周波数はそもそも東日本と西日本で異なり,日本語と言語学的に類似した言語はない(しいて言えばハングルが近いが).そして,鉄道の軌間は標準軌間よりも狭い狭軌(1067 mm)が主流である.
日本の規格や標準は世界のそれよりも高水準であったり厳しかったりする分野もあるが,概して鉄道や道路など交通の分野では,残念ながら世界水準に劣るものが多いと思わざるをえない.道路の法定速度しかり,自動車の全幅などがいい例であろう.そして,鉄道路線の多くが狭軌であることは,まさに本シリーズでやり玉に挙げようとしているテーマである.
日本の道路は欧米のそれと比較して狭く,そこをサイズ,排気量ともに小さい車両が低速で走っている.都内の住宅地には全幅1700 mm以下の車でないと不便な道路が多い.また,自動車の全幅が2500 mm以下に抑えられていることは,海外ではメジャーな40フィート海上コンテナを貨物自動車で陸送するにあたり,安全面でのリスクを大きくしている.また,一般道の法定速度は60 km/hであり,高速道路のそれは100 km/hに抑えられている.島国根性に染まった日本人は,「日本は島国だからいいんだ」,「日本は狭いんだから道路が狭いのは当たり前」,「こんなパワーのある車なんか日本には要らない」,「狭い日本そんなに急いでどこへ行く」などと言う.
私は,そうした「島国根性」に,ここで異を唱える.日本の他にも島国はいくらでもあるし,日本より狭い国も枚挙に暇がない.日本が小国であった大昔ならいざ知らず,今はGDPで世界第3位,ついこの間までは世界第2位であった経済大国である.土木技術もこの百数十年で大きく進歩した.日本がわざわざ世界標準よりも劣る規格に甘んじなければならない理由などもはやないのだ.
だからと言って,ただ日本のデファクトスタンダードを捨てて世界のデファクトスタンダードに合わせるというのも能のない話である.どのみち現在の規格や標準を捨てなければならないのであれば,世界標準を凌駕するものを打ち立て,それを世界に向けて提案するくらいの意気込みが必要なのではないか.それくらいのマインドが,現在の日本に蔓延している閉塞感を打破するために必要なのではないかと私は思う.
人間の社会において,規格というものは欠かせないものであり,そしてごく当たり前のように存在している.身近なところを見ればSI単位系,ISO,JIS,DIN,IEEEなど枚挙に暇がない.言語も規格といっていいかもしれないし,極論すれば「常識」というものも規格の一種であろう.
規格が国や地域によってまちまちという例も枚挙に暇がない.車が右側通行か左側通行か,商用電源周波数は50 Hzか60 Hzか,他にも色々ある.言語もバラバラである.そして,鉄道に関する規格も例外ではない.
しかしながら,決められた規格はなくとも,事実上の標準(デファクトスタンダード)が存在する分野も多い.車はどちらかというと右側通行が,商用電源周波数は50 Hzが,言語は英語が,それぞれ世界のデファクトスタンダードであると言ってよいだろう.そして,鉄道の分野には標準軌間(1435 mm)というものがある.
また,それら世界のデファクトスタンダードと日本国内のデファクトスタンダードが異なっている場合も多い.例えば自動車は左側通行であるし,商用電源周波数はそもそも東日本と西日本で異なり,日本語と言語学的に類似した言語はない(しいて言えばハングルが近いが).そして,鉄道の軌間は標準軌間よりも狭い狭軌(1067 mm)が主流である.
日本の規格や標準は世界のそれよりも高水準であったり厳しかったりする分野もあるが,概して鉄道や道路など交通の分野では,残念ながら世界水準に劣るものが多いと思わざるをえない.道路の法定速度しかり,自動車の全幅などがいい例であろう.そして,鉄道路線の多くが狭軌であることは,まさに本シリーズでやり玉に挙げようとしているテーマである.
日本の道路は欧米のそれと比較して狭く,そこをサイズ,排気量ともに小さい車両が低速で走っている.都内の住宅地には全幅1700 mm以下の車でないと不便な道路が多い.また,自動車の全幅が2500 mm以下に抑えられていることは,海外ではメジャーな40フィート海上コンテナを貨物自動車で陸送するにあたり,安全面でのリスクを大きくしている.また,一般道の法定速度は60 km/hであり,高速道路のそれは100 km/hに抑えられている.島国根性に染まった日本人は,「日本は島国だからいいんだ」,「日本は狭いんだから道路が狭いのは当たり前」,「こんなパワーのある車なんか日本には要らない」,「狭い日本そんなに急いでどこへ行く」などと言う.
私は,そうした「島国根性」に,ここで異を唱える.日本の他にも島国はいくらでもあるし,日本より狭い国も枚挙に暇がない.日本が小国であった大昔ならいざ知らず,今はGDPで世界第3位,ついこの間までは世界第2位であった経済大国である.土木技術もこの百数十年で大きく進歩した.日本がわざわざ世界標準よりも劣る規格に甘んじなければならない理由などもはやないのだ.
だからと言って,ただ日本のデファクトスタンダードを捨てて世界のデファクトスタンダードに合わせるというのも能のない話である.どのみち現在の規格や標準を捨てなければならないのであれば,世界標準を凌駕するものを打ち立て,それを世界に向けて提案するくらいの意気込みが必要なのではないか.それくらいのマインドが,現在の日本に蔓延している閉塞感を打破するために必要なのではないかと私は思う.