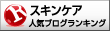一時のピークは過ぎたように思いますが、相変わらず インフルエンザ感染者・コロナ感染者が来院されています。
また、先週あたりから 嘔吐下痢の方も散見します。
冬になると ノロウイルス感染症による食中毒ニュースが増えてきます。
夏は どちらかといえば細菌感染による食中毒 冬はウイルス性の食中毒が多いです。
いずれの食中毒でも、下痢止めは使わないほうが良いです。
市販の下痢止めを仕事や学校に支障があるから という理由で使用される方がいらっしゃいます。
下痢止めを使用すると 便から細菌やウイルスが排泄されず、症状の悪化や回復を遅らせる原因となってしまいます。
できるだけ、悪いものは早く体外に排出した方が良いので、基本的には下痢止めは禁止です。
吐き気止めに関しては、適宜使用することができます。
感染症ではない ストレスの下痢や食べすぎ・冷えに伴う下痢の場合は下痢止めを使うことができます。
いずれの胃腸炎においても、整腸剤などの使用は可能です。
嘔吐が落ち着いたら経口補水液やスポーツドリンクでこまめに水分補給をおこない、安静に過ごすようにしましょう。
細菌感染症では抗生剤の内服をすることがありますが、感染性胃腸炎では残念ながら特効薬というのはありません。
できるだけ早く、悪いものを身体の外に出して、水分を補給して安静にする というのが、早く治すための秘訣です。
手洗いや うがい などは予防のためにとても大切です。
インフルエンザや コロナ感染症も 大変身体にとってつらいものですが、嘔吐下痢などの消化器感染症も消耗しますし、身体への負担は大きいです。
引き続き、感染予防に努めて、万が一 症状が出てしまった場合は 正しい対応ができるとよいなと思います。
ぜひ参考にしてください。
トップ画像は先日お誕生日だったのですが、頂いた胡蝶蘭の花です。自宅で大切に愛でています。
ここ最近、日中はとても暖かく、春のような陽気が感じられますね。
休診日の本日は 普段は手が回らない家事をしたのちに、自宅の庭の作業をしていました。
暖かいので 気分もよく外に出られます。
先週あたりから、そろそろ花粉が怪しい と患者さんと話していたのですが・・
無防備に マスクなく 普通に外に出ていたら、なんとなく目がしょぼしょぼしました。
そろそろお天気が良い日には少しずつスギ花粉が飛んでいるのでしょうか。
先週、日本気象協会が発表をした2025年の花粉飛散予測では、
- 2月上旬に九州から関東の一部で飛散開始
- スギ花粉のピークは早い所で2月下旬から、ヒノキ花粉は3月中旬から4月上旬
- 飛散量は、広い範囲で例年より多く、四国・近畿は例年の2倍以上の所も
とのことです。暖かい日が続くと 花粉の飛散が始まります。
花粉症の代表的な症状は、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどです。症状が重い場合は、頭痛、呼吸苦、倦怠感、集中力低下などが現れることもあります。
花粉症の方は早めの対策が必要ですね。
ピークになってから内服するよりも飛散が開始される少し前から花粉症のお薬を内服をして、対策をしておいた方が、症状が楽だと思います。
2月は例年より早く暖かくなるようです。早めの対策がお勧めです。
参考になれば幸いです。
今日は暑いくらいの良いお天気でした。
朝一番はこれから稲刈り という人が数名いらっしゃいましたが、その後はゆったり外来でした。
お天気が良い日はしばらく外来がのんびりの予感です。田舎なので、田んぼや畑に大きく左右されます。
週末は晴れの予報なので、皆さん稲刈り予定かもしれませんね。
さて、良い睡眠がとれていますか。
以前、大手寝具メーカーが全国の18歳から79歳の男女1万人を対象に実施した「不眠判定調査」によると、約半数の人に不眠症の疑いがあるという結果が出ました。
眠れない悩み このことをいくつかの脳内物質との関係で見ていきます。
睡眠は生活リズムに影響をされます。
眠気をもたらす脳内物質メラトニンは朝起きてから14-15時間後に分泌が始まり、2-3時間でピークを迎えます。
例えば、朝7時に起きたとすると夜の12時には眠りに入ることになります。
しかし、メラトニンには強い光を受けると分泌が止まるという性質があります。
パソコンやスマートフォンなどのブルーライト(強い光)を寝る前に浴びていると、メラトニンの分泌が抑えられ、入眠が妨げられてしまう恐れがあります。
先ほどの例でいえば、朝7時に起きる人は夜9時以降はパソコン・スマホの使用を控えるようにしてみてください。
睡眠に関係する物質はメラトニン以外にもいくつかあります。
その中の一つアデノシンは脳や身体で細胞のエネルギーが使われた後にできる物質です。アデノシンが脳にたまると脳は疲労を感じ、睡眠へと向かいます。
ところが、アデノシンにはカフェインによって働きが阻害されるという性質があります。
カフェインが脳内で消費される時間を考慮して、睡眠の8時間前からカフェインを摂取しないようにしましょう。
コルチゾールという物質は人が目覚めているときに使われ、睡眠と大きく関係します。
ところが、コルチゾールは別名 ストレスホルモンと呼ばれるように、ストレスを受けると分泌される性質があります。
寝る前にストレスを受けるとコルチゾールが分泌されて、そのために目が覚めてしまいます。
睡眠のためにストレス対策も大切な理由はこういった点にもあります。
快適な睡眠のためにいろいろ試してみてください。参考になれば幸いです。
先週末から立て続けに 子宮頸がんワクチンの接種者が増えました。
皆さん、駆け込み注射です。
標準的な接種スケジュールでは初回から終了まで6か月かかりますが、短縮した最短スケジュールでは4か月が最短で投与できる期間になります。
10月にスタートでも3回分のワクチンを公費で終了可能ですので、希望の方は接種予約をお願いいたします。
さて、明日から10月ですね。空気もだいぶ秋らしくなってきました。
10月1日からは新型コロナワクチンの定期接種が開始となります。
対象となるのは65歳以上の方と 60~64歳で重症化リスクの高い(心臓や腎臓、呼吸機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される。免疫機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能)方となっています。定期接種対象の方以外は、任意接種になります。
ワクチンによって得られる抗原(免疫反応を起こす物質)はJN.1系統となっています。
JN.1株はオミクロン株の変異株がさらに変異したウイルスです。昨年末あたりから流行をしています。
今年の夏に感染が広がったKP.3株はJN.1系統に属するため、このウイルスに対しても重症化リスクを低減する効果が期待できます。
また、今月からインフルエンザワクチンも開始になります。
例年15日ごろから市の助成のもと、65歳以上の方の接種が始まっていましたが、今年は1日からスタートです。
一時は感染者数が大幅に減少したインフルエンザですが、昨シーズンは大流行となりました。
中にはコロナウイルスとインフルエンザの同時感染や立て続けに感染する例もあり、深刻な状況になった方もいました。
予防接種は重症化を避けるための選択肢の一つです。感染しないのが一番ではありますが、ワクチン接種も可能な範囲で検討いただければと思います。
ちなみに、この二つのワクチンは同日の同時接種が可能です。
疑問点などありましたら、外来でお尋ねください。
10月からの深まる秋も楽しんで過ごしていきたいです。
新学期が始まり、1週間がたちました。親子ともなれない生活で ちょっと疲れました。
夏休みにダラダラしすぎたせいで、子供たちも毎日疲れているようです。
先にお知らせです。液体窒素が入荷しています。いぼ・首いぼ・老人性いぼなどの治療が可能ですので、必要な方は来院してください。
さて、お盆時期から ここ最近にかけて、鳥刺し・たたきなど を食べて、かなりひどい 食中毒になる方が 散見されました。
鳥の生肉に関係した食中毒でしたので、おそらくカンピロバクター腸炎であろうと考えます。
発熱や嘔吐・下痢など また頭痛や倦怠感などの症状が出ます。たいていは1週間ほどで完治してきます。
食中毒の原因菌の半数以上がカンピロバクターと呼ばれる細菌です。
カンピロバクター菌はニワトリや牛をはじめとした家畜や多くの動物が保菌している細菌です。
一般に市販されている鶏肉のカンピロバクター汚染率は20-40%とする報告と60-90%とする報告などばらつきがありますが、
いずれにせよ、高い汚染率が示されており、鶏肉の生食=カンピロバクター腸炎の危険性があると考えてもよいと思います。
食鳥処理後の鶏肉のカンピロバクター汚染率67.4%(厚生労働科学研究報告「食品製造の高度衛生管理に関する研究」だそうです。
カンピロバクターは加熱調理で死滅します。
台風の進行がかなりゆっくりなようで、今後の見通しがはっきりせず 金曜土曜日の診療が大丈夫かな と今から心配です。
昨日、ハチのお話を書いたばかりですが・・
今日はムカデに咬まれた方が来院されました。
ムカデ というと 梅雨時期に家の中に入ってきやすい イメージですが・・・調べてみると 暖かい季節を好み、寒い時期は活動が鈍化するようです。
3~12月にかけて発生し、6-8月は特に被害が増える時期だそうです。
暖かさと湿気が大好き ということなので、最近の暑さ そして雨上がりのムっとするような湿気に誘うわれ、活発に活動していたのかもしれません。
基本的にはムカデは夜行性の生き物です。
日中は草むらや落ち葉の下などに潜んでいます。えさを求めて活動をするのは主に夜間で、布団の中に入ってきて夜に咬まれた という方が多いのもそのためです。
暗い場所が好きなので、落ち葉が多い場所は掃除をし、石の下や外に置いておいた履物の中に潜んでいることもあります。
ムカデに咬まれると 激しい痛みが出現します。
局所の発赤や腫れ、咬まれた部位に2か所の出血斑が見られることもあります。
万が一咬まれた場合には 傷口を流水で洗い流します。局所を冷やすことで、疼痛を緩和する方法も一般的です。
ムカデ毒に関しては43度の温水に浸す温熱療法が効果があったとする報告もあるようです。しかし、科学的な根拠にとぼしいことや ムカデ毒が拡散してしまうことも危惧されますので、冷やす方が無難で安全です。
ハチ同様にアナフィラキシー症状(気分不快・呼吸困難・頻脈・腹痛など)が生じた場合はすぐに病院受診をしてください。
なお、ムカデ毒とハチ毒の間には免疫学的な交差反応性がある可能性が示唆されています。
ハチに刺されてアナフィラキシーを生じる人はムカデにも注意が必要です。反対にムカデに咬まれたことがある人はハチに刺されたことがなくとも、ハチ刺症でアナフィラキシーを生じる可能性があります。
また、大変に生命力が強い生き物なので、ムカデは頭部がない状態で死んでいると思ってもしばらくは咬まれることがあります。油断は禁物。
いずれにせよ、腫れがひどい場合、痛みがひどい場合などは無理せず受診をしてください。
台風、大きな被害がありませんように。
明日は休診です。よろしくお願いいたします。
台風が近づいていますね。
明日からの様子が不安だからと今週初めからは 早めにお薬を取りに来ました と備えていらっしゃる方が散見されました。
お薬不安な方は 天気が崩れないうちにご来院ください。
子供たちの夏休みが終盤・追い込みに差し掛かりました。
あともう少しで夏休みおしまい。やりたいことや 出かけたい場所が たくさんありましたが、あっという間に終わってしまいます。
宿題は終えているのですが、自由課題を あれもやろうかな これもやりたかった と今もまだ取り組むので、仕事以外の時間はお付き合いをしています。
ブログ・ホームページも更新が滞っています。
田んぼの稲穂も少しずつ膨らみ 皆さん 草刈りも大変。お盆明けは木を切ったり、畑に出たりといろんな場所で、ハチに刺されてしまった方が 続きました。
ハチに刺されると 患部が赤く腫れあがります。刺された直後から 激しい痛みが生じ、その後、かゆみを伴うことがあります。
はじめて刺された場合には 腫れは1日から数日で引くことが多いです。
ハチに一度でも刺されたことがある人は、体内にハチの毒に対しての抗体ができます。そのため、同じ種類のハチに2回目以降刺された場合は、人によっては皮膚の局所症状だけではなく、ハチの毒に対してのアレルギー反応が強く出ることがあります。
アナフィラキシーショックといい、命にかかわることもある こともあり 注意が必要です。
アナフィラキシーの症状は ハチに刺されて数分以内で出現します。
唇や粘膜が腫れたり、息苦しさ・呼吸困難・喘鳴(ぜいぜいした呼吸音)・激しい鼻水やくしゃみ その他 動悸や息切れ 血圧低下などが起こってきます。
ハチに刺されて、呼吸が苦しい・めまいがする・気分不快などの症状が出た場合は迷わず、すぐに病院を受診してください。
アナフィラキシーが起きない場合でも、さされて腫れがひどい場合や 改善しない場合は受診をされるのが安心です。
今の時期(夏から秋にかけて)はハチたちも活発に活動しています。野外活動をする際には特に気を付けて下さい。
ここ最近来院された方々は皆さん、複数匹のハチに追いかけられて、数か所 刺されてしまっていました。
ハチは黒い色に対して、攻撃をするそうです。黒色の衣類や荷物は避けて、白っぽいものを身につけた方が安心です。
香水や整髪料などの強い匂いもハチを刺激するようなので、避けてください。
また、大きな声や 急な動きなどにも反応があります。ふいにハチに遭遇したら、思わず手で払ってしまうのですが、大きな声を出したり、手で払ったり、走って逃げたりということは避けましょう。
姿勢を低くして、ゆっくりをその場を離れるのが賢明なようです。
参考になれば幸いです
前回記事の続きです。
環境的な要因に関して書いてみます。
総務省の調査によると熱中症で救急搬送された人の43.9%は住居の敷地内で発症しています。
これは屋外の9.4%を大きく上回る結果です。
また、東京都監査医務院の調査では、熱中症により屋内で死亡した人のうち、89.9%がエアコンを使用していなかったそうです。
熱中症予防のポイントは
室内の見やすい場所に温度計、湿度計を備えておき、暑さを感じていなくても
室温が28度、湿度が60%を超えるときには「積極的にエアコンを使用」しましょう。
自宅でエアコンを使用できないときは、公民館や図書館、大規模商業施設(ショッピングモールなど)で昼間2時間程度過ごすことなども一つの案です。
屋外での熱中症の危険度を知るための目安に「暑さ指数(WBGT)」があります。
そして天気予報でよく聞かれる言葉に「真夏日」「猛暑日」という言葉があります。
最高気温が30℃を超える日は真夏日、35度を超える日が猛暑日です。
暑さ指数と真夏日、猛暑日を重ね合わせると「真夏日は熱中症に厳重警戒」「猛暑日は熱中症の危険日」となります。
熱中症の死亡率は気温が30度を超えると上昇し、34度を超えると急激に増加します。
気温が30℃を超えていたら、不要不急の外出は控えましょう。屋外での運動は避け、屋外作業には十分注意するようにしてください。
熱中症が疑われる方でまず確認するのは「意識障害」があるかどうかです。
意識がない、意識があっても認識が明瞭でない、言語の混乱といった場合には、至急、救急車を呼んでください。
救急車を待つ間はできるだけ、涼しい場所に移動し、服を緩めます。
太い血管がある首の周り、わきの下、股関節部の足の付け根を冷やしてください。
直接身体に水をかけ、うちわであおぐ処置も救急処置としては効果があると思います。
まだまだ暑さが続きます。時間帯を選んで、屋外活動をするようにしてください。
参考になればうれしいです。
暑い日が続きます。
早朝から草刈りの音が響きますが、早朝といえども暑い毎日です。
先日は、加東市内で田んぼで倒れてなくなった方のニュースが報道されていました。
今の時期は草刈りと水の管理が忙しいと皆さんおっしゃっています。午前中でもかなりの高温ですので、熱中症にかかるのも納得です。
人間の体温は高くなると汗を出して、その汗が蒸発することで、一定の範囲におさまるように調節されています。
しかし高温多湿の環境で、発汗と汗の気化のメカニズムが阻害されると、命に危険が及ぶほど体温が上昇します。
これが熱中症です。
症状としては発熱、けいれん。嘔吐、意識障害、失神といったことが起こってきます。
体温を調節するには発汗と汗の蒸発の両方が大切です。汗の元になる「水分」をこまめに補給する。
湿度が高いと汗は蒸発しにくくなるので、「湿度の高い環境」に注意が必要です。
また、熱中症で死亡する人の割合は65歳以上の方が85%以上を占めています。
その理由として、加齢によって体温調節の機能が低下している。のどの渇きを感じにくくなり、水分補給が不足する。暑さを感じにくくなり、エアコンの使用控えをしているといったことが挙げられます。
実際に高齢者ではこれだけ暑い環境でも、エアコンを使用してなかったり、季節外れの冬の下着を着ている方を時々見かけます。
とっても危険な状況です。
65歳以上の方は体感に頼らず、こまめな水分補給とエアコンの使用を心がけてください。
長くなりましたので、続きは後日。
明日は当院休診です。暑くなりそうですので、熱中症予防をしてお過ごしください。