2019年(平成31年・令和元年)
俳句作品の鑑賞と批評の学習会 (「風韻集」「あすかの会」の作品の合評による)
総括記録 武良竜彦
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
野木メソッドを実践的に身につけるための合評会
〇 俳句作品の「評価の二ステップ」の視点に基づいた鑑賞をする力を養う。
① 取り上げた句に心を動かされた理由。
② どのような表現だからそう感じたか。
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
「あすか塾」7
「風韻集」2019年8月号掲載句より
多摩の森多摩陵墓地も緑さす 加藤 和夫
(評)
「緑さす」の「さす」が繊細な色合いの変化を表わしてみごと。「陵墓」は文字通り墓地。死者の領域を「緑さす」と表現して、正反対の命燃え出る季節の空気で包み込む表現ですね。
声高に薔薇を愛づるや遠汽笛 加藤 健
(評)
「声高に」で、華やぎ上気した気分が伝わります。「遠汽笛」で海を眺望する丘に咲いている薔薇にそそぐ、海辺の明るい光まで感じさせます。
牡丹崩る風の悪戯かも知れぬ 坂本 美千子
(評)
牡丹の重なり合う大きな花びらの散り方を見事に捉えた句。実際には牡丹は突然、という感じで「崩れるように」散る。呟くように「風の悪戯かも知れぬ」と添えた言葉が生きています。牡丹では加藤楸邨の「火の奥に牡丹崩るるさまを見つ」という句が有名。句集『火の記憶』。これは戦火に追われる途中、どこかの家が燃え落ちる中で垣間見た景だという。同じ牡丹でも美千代さんの句は平和の景ですね。
影を置く色やわらかき若楓 佐藤 照美
(評)
「影」が差しているのではなく「置く」とした表現がみごと。その丁寧さを感じる表現に作者の心根を感じる句です。
子雀の浴びゐる砂のくぼみかな 摂待 信子
(評)
これは言葉の絞り、カメラのズームアップが効いた句。雀が砂浴びしているという、なんの変哲もない平凡な日常の一瞬が、小さき命への慈愛にみちた景に一変します。
隣家の空家となりぬ山帽子 長谷川 嘉代子
(評)
社会問題にもなっている「空家」の増加現象。それを「隣家(となりや)」という距離感に引き寄せて表現して、切実感があります。「山帽子」は五~十メートルにもなる樹で、葉は四センチから十センチで対生し楕円形または卵円形にやや波打つ。花は六~七に開き、淡黄色で小さく多数が球状に集合し、その外側に大形白色の総包片が四枚あり、されもまた花弁のように見える。下五に置かれたこの植物の名が、ただの季語扱いには思えなくなります。元の住民が植えて愛でていたのかと想像する。それが伸び放題になっているのでしょう。
稲の花よちよち歩く女の児 服部 一燈子
(評)
「稲の花」は香る。強烈な匂いではなく風向きでふと気づくような稔りの予感のような香りです。その初々しさと「よちよち歩く女の児」の表現が相乗効果となって、独特の味わいが生まれている句。ここは男の児ではだめで、「女の児」でしょう。
春あかとき兜太に目覚め立禅す 星 利生
(評)
立禅(りつぜん)とは、立って行う東洋的瞑想法の名称。仏教も本質的には立禅を主体とし托鉢に始まり歩行、沈思、四念処と立禅に依って成り立つとされる。立禅の修行によって心身をひとつにする、身体の中心感覚を養成する、人間の持つ本能を呼び覚まし動物的な反応や動きが可能になるという。立禅は早朝、自然の中で行うのが良いとされる。自然の中で土や木々のエネルギーを取り込み、風を全身で感じ取ることで立禅の効果は高まるとされる。上五の「春あかとき」が青春時代をも包含する響きがあって、その中で兜太俳句に開眼したときの感動を表現しているように感じます。言葉が観念的になって実体を失うことを批判し、身体性・風土性を重んじた兜太の俳句思想を体現したような表現ですね。
睡蓮や夢は今でも夢のまま 本多 やすな
(評)
描写俳句ではなく、中七下五で直接的に心情を吐露したメッセージ俳句ですね。こういう表現の場合、季語との取り合わせが命になりますね。「睡蓮」の花の咲き方は鮮やかで、何か大願成就したような趣があります。上五にそのイメージを置いたことで、いつかそのように開花させたい思いを抱えている作者の姿が浮かびます。他の言葉だったら、その味わいは出ないでしょうね。
縞蛇は動物園には呼ばれない 三須 民恵
(評)
動物園の動物たちを飼育しているとか、飼われているというようには見ていない作者の眼差しが、この句の前提としてあります。「呼んでいる」というお招きしているような優しい視座を感じます。その上で「呼ばれない」と言っているのですから、微かな排除感、差別感に心を揺らしている繊細な表現ですね。
野に遊ぶ身の内の湖穏やかに 宮坂 市子
(評)
作者は自分の身体の中に大きな湖の、水平に広々と開ける世界を抱えています。「野に遊ぶ」とき、その思いが共鳴するのですね。
斜度80十薬灯るモノレール 矢野 忠男
(評)
傾斜、角度と言わず、ずばり「斜度」ときて数字の80を置く。その急峻な土手に咲く「十薬」の花を揺らして、すれすれにモノレールが通過してゆきます。「灯る」という言葉に点滅感がありますね。小さな十文字の白い花が土手一面に揺れるさまが目に浮かびます。かすかなときめきのように。
母の日のははを見つけに浅草寺 渡辺 秀雄
(評)
現実の母の今の姿を限定せず、ふわりと置く表現で、読者にさまざまな感慨を引き起こす表現になっている句ですね。現実の母を探す景なら迷子感が出ます。回想の母なら、「浅草寺」まるごと、懐かしい響きに変わります。どちらで鑑賞するかは、読者の自由です。
夏の川われを軸として曲りゆく 伊藤 ユキ子
(評)
自然の中に生きて在る自分の命の鼓動がみごとに造形されていますね。「われを軸として」という固い言い回しを、ダイナミックな詩語に転換しましたね。
旅先の詩片となりし春の星 稲葉 晶子
(評)
一見、ふつうの感慨や抒情を詠んだような句に見えますが、しっかり工夫がこらされた表現ですね。まず「詩篇」とは言ってもあまり「詩片」とは言いません。そういうことで、条々たる詩篇ではなく、ひとかけら感のある表現になりますね。「なりて」という現在形ではなく、「なりし」という過去形にしたことで、他にもたくさん見てきた「春の星」の中で、あるときだけ特に、そのような感慨に捉われたという回想的な思いが強調されています。
野仏の台座傾く苔の花 大澤 游子
(評)
「傾く」で軽く切れている感じの詠み方がされています。意味的には「傾く」力が「苔の花」から及ばされているわけで、下五に置いた「苔の花」が「野仏の台座」を押し上げている感じも出ますね。その力が「台座」の傾きという、永い永い時間の経過を表わす抒情的な表現を生み出していますね。
第7回 あすかの会 令和1年7月26日 兼題『追』『円』 記録 大本 尚
【当日の作品】(清記順・○主宰選◇武良先生選 黒塗りは特選)
〇◇列島のくまなく晴れて蟬の羽化 奥村 安代
追伸に父の筆跡釣忍
(評)
一句目、「くまなく」が効いていますね。日本全体が夏に突入したという感じです。二句目、本文には母の思いが長々と綴られた手紙を想像させます。父は筆圧強く、ただ一言添えただけです。下五の「釣忍」が効いていて、両親がいる座敷が見えます。
風鈴市音のさざ波寄せてくる 大本 尚
追憶の時空さまよふ夕端居
(評)
尚さんの俳句はいつも、外のものが自分の身体の中まですーっと忍び込んでくるような表現と、自分の内側で動き出す命の小さな変化が、外の何かと共鳴しているような、実存感のある表現を、さらりと書き留める作風ですね。この二句にもそれがよく表れています。
能衣装両袖広げ夏館 鴫原 さき子
人の眼をもてあそびおり熱帯魚
(評)
一句目、ピンと左右に開いた袖の幅にフォーカスを絞ったのがみごとですね。夏の空気感が捉えられています。二句目、視点を「熱帯魚」の方に反転させたことで、水槽とその周りの人の姿まで浮かび上がられせて、みごとです。
追伸はたださりげなく薄衣 丸笠 芙美子
〇 万緑の山の深みにおぼれけり
(評)
一句目、下五の季語「薄衣」がただの措辞ではなく、実感的な空気感の中にいるような表現ですね。二句目は「おぼれけり」という表現に尽きますね。芙美子さんは季節の空気感とその中で揺らいでいる気持ちの表現がうまいですね。
〇◇同心円つぎつぎに生みあめんぼう 高橋 みどり
〇◇雲ひとつ虹ひとつにも旅心
(評)
一句目、「同心円」は中心的が不動であることを条件とします。そして「つぎつぎに」という言葉で、その位置的な不動の微動、小さな「あめんぼう」という命の鼓動を、外に波及する大きな「同心円」と包み込む表現ですね。二句目、「ひとつ」の丁寧なリフレーンが効いていますね。まさに夏。自然も人も動的になる季節、ただ眺めているのではない、噛みしめるような丁寧な生き方を感じる句です。
◆ 円墳の丸さに添うて青葉風 金井 玲子
〇 影追へど風に失せたる夏の蝶
(評)
一句目、円墳は古代遺跡であるだけでなく、基本的にはお墓であり、立ち入り禁止の管理墓が多い。元々の石積みの外壁は木々に覆われて森状になっている所がおおい。円い森である。その佇まいを正確に捉えた句ですね。二句目、どこからか表れて、視界から消える蝶。「風に失せたる」という表現がぴったりです。
◇ ドーナツの穴の明るさ夏の空 近藤 悦子
上り框円座にゆくり一服す
(評)
一句目、ドーナツの穴というのは不思議ですね。「穴」というのはそれ自身で存在しない、「穴」という現象に過ぎず、ドーナツを食べてしまえば消えてしまう現象です。つまりこの句はその現象の「明るさ」を詠んで、夏の空気感を表現しているのですね。二句目、「上り框」があるのは古い一軒家ですね。玄関とか土間から板張りの部屋に上がる境にその中段の高さにあり、腰かけるのにちょうどいい高さでした。「ゆくり一服」と、そこにかつては流れていた時間が表現されています。
五円玉手に駄菓子屋へ心太 砂川 ハルエ
戦国の水攻めの跡白南風す
(評)
一句目、「五円玉」で時代が象徴されています。現代の五円では何も買えない。「駄菓子屋」「心太」、掌に昭和が握りしめられています。二句目、戦国時代の城攻めの方法の一つで、城まで追いつめて、その周りを池状に水で包囲して、兵糧が尽きるのを待つ戦法ですね。直接刃を交えて殺し合いをしない、ある意味、残酷ではない戦法に感じられますが、降参しないと餓死するしかなく、城主は自刃か斬首の道しか残されていないという意味では、戦は戦、過酷なものです。「白南風す」の下五にそんな複雑な思いが込められています。
◇ 指先の円月殺法蜻蛉逃げ 白石 文男
波を追ひ波に追はれて雲の峰
(評)
一句目は楽しい俳句ですね。指先でくるくる円を作っているだけなのに、柴田錬三郎の小説「眠狂四郎」の「円月殺法」の大きなアクションを引き合いに出して表現して、しかも「逃げ」られたというオチが笑いを誘います。二句目、夏そのもの解放感のある景ですね。波と戯れているその遠景、水平線の上空には積乱雲が高くそびえています。
トマト捥ぐ度に追肥のひと握り 宮坂 市子
七夕の短冊揺らす円らな瞳
(評)
「トマト捥ぐ度に追肥」と時間の同時性で表現していますが、実際は別々の行為ですね。敢えてリズミカルにそう詠まれていることが大切で、農作業を常の暮らしのリズムのようにして生きている人の、心もちまで伝わってくる句ですね。二句目、「短冊」を揺らしているのが、子どもの「円らな瞳」という表現がみごとですね。
円形の記憶の風呂や浮いてこい 坂本 美千子
● 追従を許さぬ走り青蜥蜴
(評)
一句目の「浮いてこい」は風呂または水遊びの小さな玩具のことですが、この下五の言い切り風のリズムが、記憶を生き生きとしたものにしている効果がありますね。二句目、「追従を許さぬ」という言い回しは、他より優れた知能、身体能力、成し遂げた成果を評価するときに使いますね。それを「青蜥蜴」のすばしこい走りの表現として使っている意外性が楽しいですね。二句とも言葉に技があります。
日雷円相紋を二尺皿 磯部 のりこ
追風に水滴ころりキャベツ畑
(評)
一句目、「円相紋」というのは、太い墨跡で、閉じた円ではなく、閉じないで最後を風のように流すようにして書く、一筆書きの模様ですね。そんな紋をあしらった大きな「二尺皿」が飾られている和風の施設か、民家の床の間か。上五の「日雷」でその場全体を包む、夏の空気感まで表現されていますね。二句目、早朝のキャベツ畑の景ではないでしょうか。玉なす朝露の一粒ひとつぶに朝日が宿っているのが見えます。陽が射すと空気が動きだします。そうやって生じた「追風」で朝露がキャベツの葉の上をしずかに転げ落ちてゆく一瞬を捉えた句ですね。
追伸に本音を隠すはたた神 山尾かづひろ
壇の浦平家の化身夜光虫
(評)
一句目、下五の「はたた神」の音響感のせいで、この「追伸」は本当はもっと重い内容のことを書き添えるつもりのところ、ぐっと抑えた言葉にしたというようなことを推理してしまいます。作者の心の中で雷が鳴り響いているようです。二句目、平家一族滅亡の運命を滲ませる「壇の浦」、その海面に怪しい「夜光虫」の光が揺れています。滅んだ者たちの情念の明かりをそこに読み取っている句ですね。
あの話追求はせず梅雨明ける 大木 典子
ぎしぎしや請わるるままの円空仏
(評)
典子さんはいつも斬新な表現に挑む、進取の志を感じさせる句を詠む方です。十七音の一行で、前後の「文」がない独立した俳句の中で「こそあど」の指示語を使うのは、常識的にご法度です。何を指すのが不明であり、句が完結しないという理由からですが、典子さんはそのことを逆手にとってこの句を詠んでいます。曖昧なままにしておいた方が「梅雨」が「明ける」ように時間は過ぎるよ、きっと、という言外の味わい深い表現に転換してお見事。二句目、「円空仏」のあの気合で彫ったような味わい深い仏像は、木の素材も選ばす、廃材のような木で、人に請われたら気軽に造って与えたという咄が伝わっています。「ぎしぎし」という上五の季語である路傍の草が効いています。円空さまの生き様に似ているところがありますね。
廃屋の闇住む汝や円座虫 石坂 晴夫
空蝉に霊遺しゐる朝かな
(評)
一句目、「円座虫」は百足に似たヤスデの別称ですね。「廃屋の闇住む汝や」という呼びかけ表現が相応しい虫ですね。晴夫さんの古語に命を吹き込む作風に拍手です。二句目、この「霊」は「たま」の読みと意味ですね。抜け殻なのにまるで生きてそこにいる感じを捉えた句ですね。命の気配はどこにでもこうして刻まれています。
【野木桃花主宰の句】解釈と鑑賞のヒント
細工場に藺草の匂ふ円座かな
居間にあるのではなく、これは労働の場にある「円座」ですね。「細工場(さいくば)」という設定が効いていますね。ピンとこない人のために、どんな場所かという文例を次に揚げてみます。
細工場、それは土間になっているところと、居間とが続いている、その居間の
端、一段低くなっている細工場を、横にしてそっちを見ながら坐ったのである。
(幸田露伴「鵞鳥 」より)
普通の民家の一画を占める「労働の場」だったのですね。まだ新しい円座なのか藺草の香りがしているというのも、しっくりくる表現ですね。
◇ 十薬の匂いの育つ昼の闇
「匂い」が「育つ」という表現が効いていますね。「十薬」、つまりドクダミの白い花ですが、結構匂立つ花ですね。「昼の闇」で、燦燦と陽の当たる場所は好まず、木々の茂る暗い日陰に自生しているのをよく見かけますが、その佇まいそのものですね。
追伸の絵文字の笑ふ夏見舞
絵葉書ではなく、字を絵のようにあしらった葉書による「夏見舞」ですね。本文は定番の「暑中お見舞い申し上げます」としたためてあるのでしょう。その脇に添えた「追伸」の内容と文字が「笑って」いる。なにやら楽し気な雰囲気が伝わりますね。
※ 参考 武良竜彦の句
円なる命の重さを大西瓜
〈自句自解〉
最初は「円なる重さいとほし西瓜抱く」としていました。野木先生から「いとほし」と直截的な心情吐露の是非を指摘されて、推敲してこの形になりました。
「を」の使い方は議論を呼びそうですが、私としてはここで軽く切れて、「円なる命の重さを」、私の腕に伝えてくるこの西瓜よ、という言外の気持ちを込める表現にしたつもりです。成功しているかどうかは不明ですが。
〇 人生に追試はなくて雲の峰
〈自句自解〉
これは野木先生や同人の方たちが採ってくれた句で嬉しく思いました。「追」の字の課題で詠んだ句ですが、下五の「雲の峰」で人生の遥々感を添えたつもりです。
紫陽花やいま亡き姉妹の手鞠唄
〈自句自解〉
子をなしてすぐ他界した妹、癌闘病後逝った一人娘を見送ってから自分も癌で逝った姉。幼いころ、その二人が唄いながらついていた手鞠の色を、紫陽花を見るたびに思いだします。なんの技巧もなくそのまま詠んだ句です。
「あすか塾」6 から 夏休み 作品鑑賞文を書いてみよう
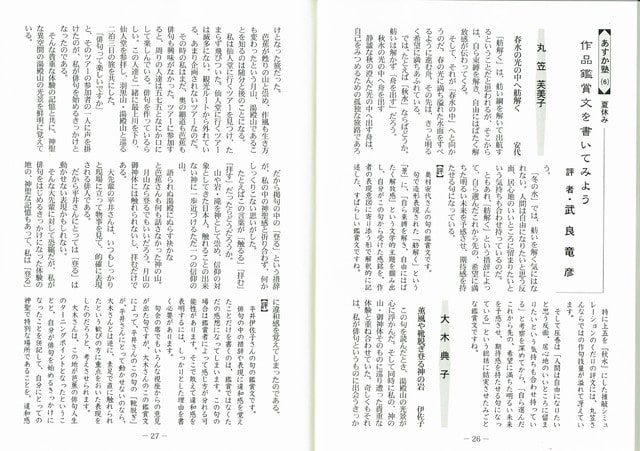
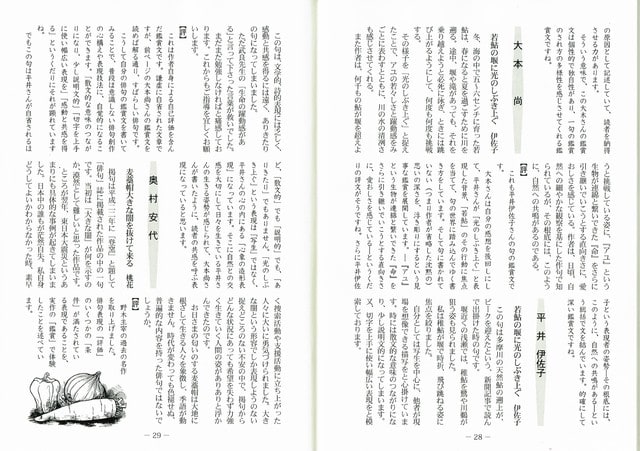
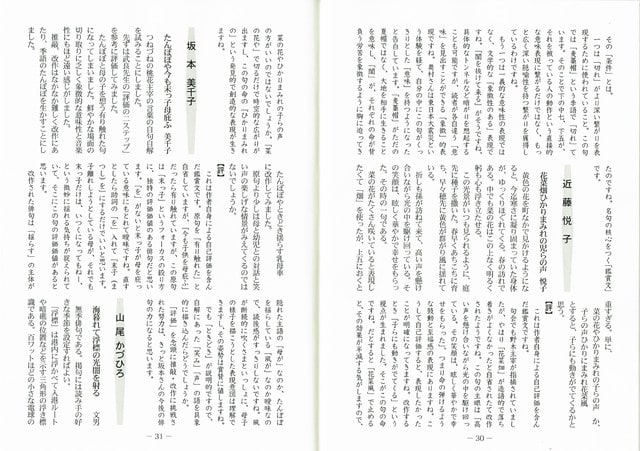
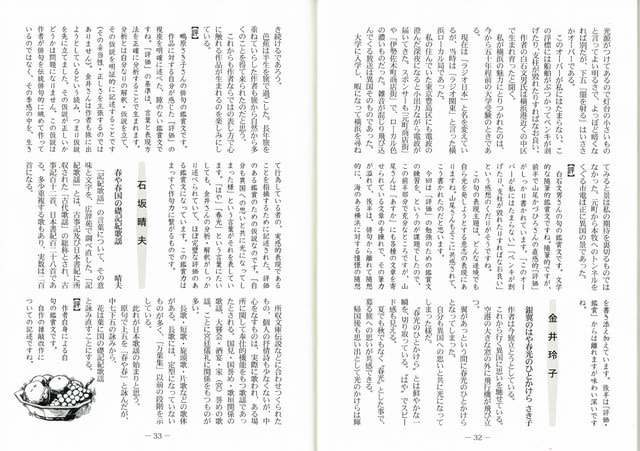
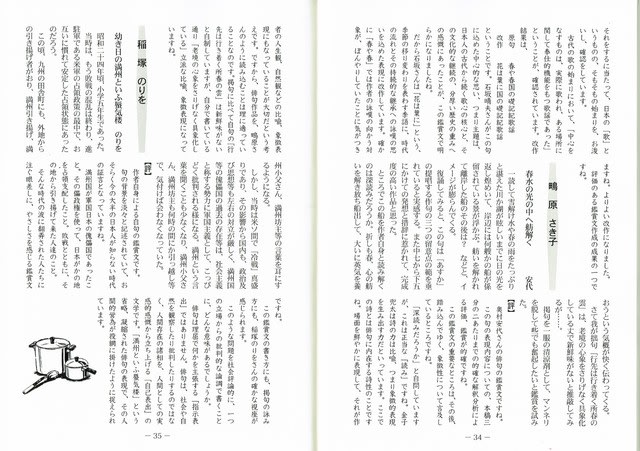
〇 第6回
〇「風韻集」 2019年7月号掲載句より
救命具着けて乗り込みさくらかな 加藤和夫
船見の桜の句で、「救命具」というフォーカスの絞り込み、切り取りが見事な表現ですね。大胆な省略表現だけで、情景と作者の心の様子まで表現されています。
船頭の声柔らかし花の昼 加藤 健
俳句表現の豊かな力を感じさせる句ですね。「柔らかし」という言葉が船頭さんの声だけに留まらず、流れる川、桜、空、そして乗船者みんなの表情にまで広がってゆく情景が目に浮かびます。
譲られし座席のリズム目借り時 佐藤照美
この見事な省略技法! 省略は深い余韻をうみだすというお手本のような句です。席を譲ってくれた行為への謝辞を直接述べる代わりに、「座席のリズム」の心地よさで表現するという技の冴え。仄かに眠気を誘う季語「目借り時」が動かないですね。
こつこつと靴音桜へ消えゆけり 摂待信子
空間的な静寂(しじま)の広がりを感じる表現ですね。
それは下五の「消えゆけり」という遠近法的な動的表現の効果だと思います。
静けさを、逆の音で表現して、お見事です。
庭隅を好むすずらん幼稚園 長谷川嘉代子
「好む」はずばり主観的表現ですね。客観写生を金科玉条とする伝統俳句派の主宰なら、そこを批判するでしょう。しかし、野木主宰は採って風韻集に載せています。何故か。それがとても大切なところです。それは野木主宰が率いる「あすか」が心象造形の表現の良さも大切にする会派だからですね。
幼稚園は成長の度合から、家族の影響の度合まで個人差、個性も違う子供たちが集うところです。日の当たる場所で伸び伸びと振る舞う子ら以外にも、日陰で静かにしていることを好む子もいるでしょう。どんな子にも居場所をあたえて包み込むような慈愛の心で、子供たちを抱擁しているような雰囲気が、この「好む」という言葉で表現されていますね。
涼しさや沼に魔性の言伝え 服部一燈子
様々な怪異現象の歴史的伝承がある古い沼でしょうね。上五の「涼しさ」がぴったりくる雰囲気を醸し出しています。今風に言えば「ミステリースポット」なとと言って、観光資源化されてしまうご時世でしょうが、かつての日本人の感性では、そういう処は、畏怖すべき神聖な場所でもあった筈です。そういう感性を大切にする作者の思いが伝わってきますね。
飛び石を拾ふ一歩に花の塵 星 利生
さりげなく、淡々と詠まれていますが「飛び石を拾ふ」とは言えそうで言えない表現の冴えがありますね。たとえば、踏む、進むと慣用的に言った場合とくらべて、とんな表現的深さが増すか。丁寧に、今、この時を愛しむように桜散る中に歩を進める作者の心情が立ち上がってくる表現になっているからですね。
この他の句の「春の息吹を聴く」「全身で泣く児」などの表現にも共通することですね。皆さんも学んで欲しい表現です。
山百合や流人の墓の傾ぎたる 本多やすな
その昔、島流しの刑に処せられて、その地で生涯を終えた「流人」の苔むした墓の佇まいが浮かびますね。その人達の焦げつくような望郷の思いを、鮮やかに具象化した「傾ぎたる」という表現、素晴らしいですね。その表現によって、「流人」だけに留まらない不遇の境遇に寄せる作者の優しい眼差しが普遍性を獲得していますね。
潮引いてはしゃぐ子供の日の子供 三須民恵
この句の命は、「子供の日の子供」という限定表現にしたところですね。そこに作者の特別な思いが立ち上がるからですね。
すでに芽に力のありて芋の種 宮坂市子
硬い幹から新芽が出て、みるみる葉の形に成長していく姿に「力」を感じるのは普通ですが、芽の状態に「力」を感受する感性がすばらしいですね。
鰐口の音の夏めき石大工 矢野忠男
鰐口(わにぐち)とは仏堂の正面軒先に吊り下げられた仏具の一種。神社の社殿で使われることも。金属製梵音具の一種で、鋳銅や鋳鉄製のものが多く、鐘鼓をふたつ合わせた形状で、鈴を扁平にしたような形をしています。上部に上から吊るすための耳状の取手が二つあり、下側半分の縁に沿って細い開口部があります。金の緒と呼ばれる布施があり、これで鼓面を打ち誓願成就を祈念します。梅雨の時期、どことなく湿った感じだったその音が、乾いた響きに変わってきたことを感受して、夏だなーと思っている状況ですね。下五で屋外の作業をしている「石大工」が描かれていて、情景がありありと浮かびます。
椿落ちこころに話し掛けてくる 渡辺秀雄
椿の花が咲いて枝にある状態と、落ちて地面にある状態の違いに着目して詠まれた句のように感じるでしょうが、そんな「理屈」の解釈は無用ですね。その一連の動きの結果としての終着と静止。そのすべてに投網かけられている表現ですね。まっすぐ読者の心に響いてくる句です。
郭公や湖底の鳥居日にゆらぐ 伊藤ユキ子
この鳥居は湖底のあるのですから、海のように満ち潮で水中に没しているのではなく、ダムの建設などで湖の底になってしまった村の神社の鳥居でしょう。上五においた「郭公」の声が、その湖面に響き空間的心理的余韻を深くしています。下五の「日にゆらぐ」に、万感の思いが立ち上がります。
フクシマに咲くほかはなき桜かな 稲葉晶子
避難指定という言葉は、人間に対してだけのものだと気づかされます。植物である桜は自ら移動などしません。降りしきる放射性物質を、まるで受難の雨のように浴びて、そこに佇み続けるしかありませんね。不条理、怒り、悲哀を「説明」するのではなく、鮮やかな俳句的表現に結晶させた力作ですね。
そのようにこの句に良さを評価鑑賞した上です。その一見便利な記号になった「フクシマ」という表記をめぐっていろんな意見が出ました。
福島の地が、このようにカナ書きにするだけで原発事故禍のことだとすぐ解る地になったことは不幸なことです。
福島の人でこう書かれるのを嫌がっている人がいるので、使う側はその気持ちに寄り添うべきではないか、という意見がありました。
私(武良)は水俣出身で「ミナマタ」と書かれるのはあまりいい気分ではありませんので、その気持ちはよく解ります。
表現内容だけでも原発事故禍のことは解るので、私たちが俳句で詠むときは、記号化した「フクシマ」という文字の便利さに頼らないで、「福島」と漢字で書きたいと思う、という意見もありました。みんなで考えてみるべき意見だと思いました。もちろん、この合評での意見は、稲葉晶子さんのこの句の評価とは別のことです。
遊歩道埋めて地の星いぬふぐり 大澤游子
あの地味で小さな水色の花、目にも止められず踏まれて通り過ぎてしまわれる花を、「地の星」と名付けた。それがこの句の命ですね。俳句は比喩を断言的言い切りだけで表現するので、深い余韻、味わいが生まれます。その効果を熟知している俳人だけができる表現ですね。
第6回あすかの会 令和1年6月28日 兼題『点』『線』 (記録報告 大本 尚)
【高得点句】 ( ○主宰選 ◇武良先生選 黒塗りは特選 )
〇◇ つば広の夏帽海の匂ひして 奥村 安代
「つば広」という形状、一転して「海の匂ひ」に転換してゆく表現で、軽い発見的なときめき感を出しているところが、この句のすばらしさですね。
◆ 生命線をゆるゆる歩く天道虫 磯部 のり子
私が「特選」にいただいた句ですが、この温もりを感じる掌感、手の内感覚がすばらしいですね。「天道虫」を歩かせる、ゆったりとしたスピードで、運命的ものとして受け止められる「生命線」の纏わる重たさが消滅し、爽やかに転換されています。
潔き孤独ありけり鉄線花 白石 文男
蔓が鉄線のように強いと言うことが名の由来の、放射状に大きな六つ萼を水平に広げる花で群生しています。ぽつんと一つ視るからに「孤独」な風情ではなく、群れなかの「孤独」の表現でしょう。「潔き」と形容した作者の心の在処を思わせます。
【当日の作品】 (清記順・○主宰選◇武良先生選 黒塗りは特選)
〇 蛇の衣令和の風に吹かれをり 砂川 ハルエ
引ききこもる二人を点し緑雨かな
一句目は、改元という時代の「脱皮」に、作者の内面的な思いを託した句ですね。上五に置いた季語の「蛇の衣」、そして下五の「吹かれをり」という空気の流動感がいいですね。二句目の「引ききこもる二人を点し緑雨かな」は「二人を点し」には、独りでいる孤独感ではなく、二人しての孤立感があり、胸に迫ります。
三十年住めば氏子よ祭寄付 稲塚 のりを
父の日や子供等やっと話題とす
のりをさんの今月の二句はユーモラスな句ですね。一句目の「住めば氏子」は「住めばみやこ」という慣用句をもじったような面白さがあります。町に溶け込んで生きるには「祭寄付」のむような義務を果たすことが不可欠でもあります。二句目の「父の日や子供等やっと話題とす」の句は、「忘れられたかな」というちょっと落胆しているような思いに対する、「オチ」的な笑いを誘う表現が見事。そこはかとない寂寥感も漂います。
〇 あの雲へ曲線放つ蜘蛛の糸 奥村 安代
白南風や少女の胸のエンブレム
一句目の出だしの「あの」という遠くに読者の視線を向ける遠近感の効果が抜群ですね。普通、指示語を句や文の冒頭に書くのを禁忌とする常識がありますが、この句はその禁を破って、逆の効果を出している句ですね、その距離感に言外の憧憬の思いが生じます。二句目のポイントはなんと言っても「少女の胸の」としたところですね。希望に膨らむ若々しい思いを抱えた青春の胸なのですね。上五で「白南風や」と空間と時間性を設定しておいて、下五で「エンブレム」という不動の具象に絞り込んでゆく表現はお見事です。
神妙に発散してる線香花火 鴫原 さき子
句読点どこに打ちても梅雨の晴
一句目は、句会の席で「神妙」という言葉が議論になりましたね。「発散してる」という様態の形容に違和感があることと、この言葉は作者側の主観のことばなので、「線香花火」という物自身の形容表現としても違和感がでるのかも知れません。作句意図はみなさんも理解できていた句ですから、「神妙」を一考すればもっといい句になりますね。二句目は梅雨の晴れ間感じを「句読点」で表現したすばらしい句ですね。「どこに打ちても」という中七の言葉に、生活のリズムまで感じさせます。
昼の灯の点る農小屋梅雨湿り 近藤 悦子
梅雨晴間水飲むきりんの青き舌
二句とも動かないぴたりと決まった表現の俳句ですね。一句目は昼間で灯を点して作業している、梅雨の時期の「農小屋」の雰囲気が体感できるようなリアルな表現になっていますし、二句目は「きりんの舌」にフォーカスを絞り込んで、その思いがけない「青」と「梅雨晴れ間」の空と共鳴させた表現がみごとですね。
〇 情熱の欠片を探す桜桃忌 高橋 みどり
梅雨晴間放りし靴の放物線
一句目、挫折感を纏いつつも、それでも自分の中の命の炎を燃え立たせてようとしているいい句ですね。ただ、下五の「桜桃忌」はただの季語ではなく、太宰治が強烈な個性なので、読者の印象に個人差があり、受け止め方が分れる可能性もありますね。二句目は子供たちの天気占いの場面ですね。下五の「放物線」にフォーカスを絞ったのがよかったと思います。
その辺り人影のなく立葵 大本 尚
賑ひにまだ早き町濃紫陽花
季節の中で生きて「在ること」の実感を大切にして俳句を詠むことが、野木桃花メソッドの重要な点ですが、大本尚さんの句は常に「理屈」を丁寧に排除して、「実感」の深いところから句想を立ち上げる静かで定まった視座を感じますね。表面的な「実感」を超えた深さを感じます。一句目の「その辺り」という何気ない季節の中の空間の設定は、なかなかできないものです。「人影のなく」で軽く切れて季語の「立葵」で結ぶ。群生しているではなく、思いがけず一つだけ佇むように咲いている姿に心を動かされた、その心の微妙な動きの見事の表現ですね。二句目の「まだ早き町」のという表現も、作者の繊細な心の表現ですね。地味な作風なので句会では高得点になりませんが、こういう俳句の良さを評価して欲しいと思います。
若葉して正にスーラの点描画 白石 文男
梅雨晴れや送電線は山越ゆる
白石文男さんの場面を鮮やかに切り取ってみせる描写的表現力にはいつも感心します。そして常に句が動的な生命感にあふれています。「若葉して」の上五の使い方も枝から若葉が萌え出たばかりという時間の変化の一瞬を捉える表現で、それがまるで「スーラの点描画」のようだと、ぴたりと決まる表現ですね。二句目は下五の「山越ゆる」という表現で、「梅雨晴れ間」の光景に動的な奥行き、空間的な広がりが出て、視界が一気に開ける読後感を与えていますね。
◇ 廃線の向う岸より浜万年青 大木 典子
麦畑鴉飛ばそか点描画
一句目は「より」が見事。駅の向かい合うホームの距離感の表現であると同時に、読者に何か訴えかけるような効果を生んでいます。かつては人の往来でにぎわっていた場所、「浜万年青」はそのころからずっとそこで咲いていたに違いありません。
二句目は点描画独特の物や人の輪郭が背景に滲んで溶け合っている、一言で言えば「何かぼんやりして、はっきりしない」絵の特徴を、そのまま自分の心象風景として取り込んで、そこに鮮やかな濡れ羽色の黒く「くっきり・はっきり」した「鴉」を「飛ばそか」と思案しています。
手花火の一点となる静寂かな 金井 玲子
夕焼けて点描となるさざれ波
一句目は、放射状に可憐な火花を散らしているさまを読み取った読者は、下五の「静寂(しじま)かな」に少し違和感を持ったようですが、私は火花を散らし終えて、一点の小さな火の玉になって、落ちる一瞬前の時間と場面を切り取った表現だと読みました。そう解すると「手花火」が効いてきます。その手の内感の「静寂」で心の表現だなと感じるからです。二句目は「夕焼けて」で時間の推移、変化は表現されていますから、「点描となる」の「となる」の変化表現が重なってもったいないので、「夕焼の点描」とまず言い切って、「さざれ波」につなぐ表現を工夫したら、もっといい句になるのではないでしをょうか。
〇◇ 背のライン母に似てきぬかたつむり 松永 弘子
夕暮や蚊取線香かほる縁
松永さんの「心情吐露」表現は、読者の気持ちをわしづかみにする共感性の高い表現が多いですね。「似てきぬ」で切れて、季語の「かたつむり」を置く表現はお見事です。二句目は上五中七がすべて「縁」に収斂してしまう表現になっているところが惜しいですね。どこかに切れを入れて時空の広がりを感じる表現にするといい句になると思います。
百点に夢は大きく雲の峰 坂本 美千子
秘めやかに刀自の住む路地鉄線花
一句目は、先生から返された答案用紙に多重の花〇つきの百点と赤く記されていたのでしょう。その弾けるような喜びと季語の「雲の峰」の盛夏感、盛り上がり感がぴったりの俳句ですね。二句目は「刀自」という古語的表現が効いていますね。その住まいの歴史的時間の分厚さを感じます。また「鉄線花」という季語を下五に置いたのが成功していますね。「秘めやか」な落ち着いた暮らしぶりが目に浮かびます。
●◇ 五線譜に心の休符若葉風 丸笠 芙美子
褪せしともひときは凛と立つ薔薇
一句目は着想がすばらしい。席題の「線」で詠む課題に応えるために「五線譜」を思いついて詠んだのだとしても、それを「心の休符」としたの並みの表現力ではないですね。一小節丸ごとの全休符ではなく、きっと一フレーズの最後に置かれた、八分休符ほどの「間」でしょう。下五の「若葉風」も効いていますね。二句目は全体が説明調の理屈文脈なってしまったのが惜しいですね。そこを描写的な表現にすれば、着想はとてもいい俳句だと思います。
〇 くさむらに点滅蛍の息遣ひ 磯部 のりこ
唐突に闇を切り裂く螢かな
二句とも「螢」で詠みましたね、一句目はその「息遣ひ」を、二句目は激しく燃え立つような命を輝きとして詠みました。そんなふうに多様に表現できていることがすばらしいですね。二句目は「唐突に」と言わずに、その一瞬のうちの出現感が表現できれば、もっとよかったと思います。
◇ 夏の朝定置網操る鋭声かな 石坂 晴夫
線香花火思ひ思ひの火種とよ
一句目は、「鋭声(とごえ)」という、いかにも年季の入った漁師さんらしい雰囲気の言葉がいいですね。二句目の「線香花火」は、人が手元にかざして点火、鑑賞している姿から、個別感の「思ひ思ひ」の表現がぴったりくる表現ですね。この「火種」は、世間を騒がすような大きな火種ではなく、一人ひとりが抱えるささやかな思いの「火種」に違いありません。晴夫さんは古語を意識的に使い、それに息吹を吹き込もうと挑戦しています。その姿勢は賞賛に値しますね。これからも、みんなが忘れたか、知らないでいる貴重な古語を復活させてください。
◎ 野木桃花主宰の句の鑑賞
初夏の一点となり沖の船
上五の「初夏」と、その「一点」という言葉に、今それを発見したという、ときめき感がありますね。
読みさしの「点と線」あり籐寝椅子
この小休止の中断感がいいですね。推理小説だから、普通読みだしたら止まらないような、スリリング展開で書かれているはずですが、結末を知りたいという逸る気持ちを押さえている、膨らみのある時空表現になっていますね。
うぶすなの水平線に雲の峰
「うぶすなの水平線」という表現は、できそうで、そうはできない表現ですね。水平線上に雲の峰が見える。どこにでもある光景です。でも、私が生まれ育ったこのこの地、この海、この空の、という特別感がこの一言で投網かけられる表現ですね。
※参考 武良竜彦の句
人生に伏線いくつ虹二重
虹に謝す三度目の恋の妻とゐて
※ 自解
二句とも、描写型俳句ではなく、メッセージ性の強い箴言型の俳句です。
一句目は課題の「線」を使うために、「伏線」というドラマ的な言葉を思いつき、考えているうちに「人生」を思いついたという、まったく頭の中だけで作った句です。
二句目は早朝のウォーキングの途中で虹に遭遇し、中村草田男の「虹に謝す妻より他に女知らず」という句を思い出して、「ああ、私の妻は三度目の人だよなー」と思ったことを、草田男句の「本歌取り」句にしたものです。
※「箴言(しんげん)的表現」
一般的には格言、金言と同義に見なされますが、キリスト教では知恵文学の
一つと見なされています。何かしらの真理を突いた言葉として共感してもら
えるような、発見的な表現を目指す表現姿勢です。まだ誰も言葉にしていな
いオリジナリティ(独自性)が求められます。
以上、同人、野木主宰、武良の句を分類すると、
◎発見的な描写俳句
◎象徴性の高い造形俳句
◎箴言的俳句
の三種類がみられますね。それぞれの長所を生かした表現にすることが大切ですね。
〇 第5回
夏燕飛翔に影の追ひつかず 奥村 安代
爽快なスビート感 生命力
減反の村を抜け出す羽抜鶏 奥村 安代
ユーモラスな社会批評
脱皮する少年少女夏休み 坂本 美千子
思春期の成長を「脱皮」と
卯の花腐し脱出不能の円周率 大木 典子
人間が発見した法則に捕らわれ
何処にも仏は御座す木葉木菟 石坂 晴夫
自然の中に存在する神性の発見
気紛れな風は何色薔薇の園 丸笠 芙美子
環境に合わせた自然さ
若葉風動き出しそな離れ島 白石 文男
自然の生き生きとした動的把握
薫風や靴脱ぎ上がる神の岩 平井 伊佐子
神聖なものに直に触れた歓び
郭公の遠ざかるほど眠くなる 鴫原 さき子
空間的な距離を心理に転換
余花に会う追伸を詠むこころもち 鴫原 さき子
季節狭間のたゆたう心理
二人して昭和の子ども麦こがし 近藤 悦子
時代を象徴する「物」と記憶
初夏の雲湧くところ神の道 磯部 のりこ
自然現象に神性を発見
たかんなの描く紋様昨夜の雨 山尾かづひろ
一夜で急成長する生命力
切れ切れにジャズの流れて薄暑かな 丸笠芙美子
薄暑と音楽の切れぎれ感
薔薇の香にひたりみぬちの襞緩む 大本 尚
自然、季節感の身体的実感的把握
引力を脱し宇宙へ夏の夢 大本 尚
宇宙の果てしなさを夢に取り込み
起き伏しの気ままが薬夏の風 稲塚 のりを
初夏のくつろいだ気分の表現
冷奴に山菜づくしふたり膳 砂川 ハルエ
「ふたり膳」に細やかな愛情
一条に山気を集め滝怒涛 金井 玲子
深山の淑気を「一条」にの冴え
☆ 野木主宰の句
作句の視座・発想の立ち上げ方・表現技法、そこに込めた自然観などの思想性のあり方などの点において、自分の俳句と、どこがどう違うか考えてみましょう。
たかんなに雨後の高さのありにけり
ヒント 驚異的な成長の速さに力強い生命力を感受し、それを説明的ではない「雨後の高さ」と心象造形表現にして、そのことに深く感動し共振している作者の心の表現にもなっているところ。
脱藩の道縦横に雷走る
ヒント 「縦横に」が上の「脱藩の道」にも、下の「雷走る」にも係るように、ブレが生じる「曖昧」表現がなされている。失敗すると、係り結びが不明確な曖昧な句になってしまう危険性がある。敢えてそういう冒険までしてなされた高等表現技術。その意図は、そのことによって、「道」の描写だけではない、厳しい試練に挑んだ人と自分の心の表現となっているところ。
〇第4回
春水の光の中へ舫ひ解く 安 代
※開放感。沸き立つ命の力。
しやぼん玉風の伝言閉ぢ込めて 〃
※人や自然と爽やかに繋がりたい思い。
幼き日の満州といふ蜃気楼 のりを
※歴史の記憶の苦さ頼りなさ。
花菜畑ひかりまみれの児らの声 悦 子
※弾けるような原初的命の歓び。
花冷えや心の螺子を巻きもどす 〃
※心を引き締め、決意新たに。
行き先は行き着くところ春の雲 さき子
※自然体、万物も人生も、同じだという発見的感慨。
若鮎の堰に光のしぶき上ぐ 伊佐子
※命の躍動と自然の力に共振する心。
囀と光のシャワー朝の森 和 子
※春の爽やかさ。感謝と喜び。
海暮れて浮標の光闇を射る 文 男
※闇の中でも煌めき止まぬ存在感。
ささへ合ふ命の余白蝶の昼 ハルエ
※生かし生かされる命の「余白」。
それぞれの人に光陰五月来る 尚
※生きとし生けるものに等しく。
闇を突く光年の先花明り 典 子
※地球自身が光年を旅した花である。
光り合ふ粒を残して花の雨 芙美子
※相照らされることで輝きを増す命。
光なす若葉の色を数えけり 弘 子
※命の芽生えの愛おしさを慈しむ心。
春一番懐に入れ苞とせり 晴 夫
※自然との一体感。全身全霊で。
たんぽぽや今も末っ子母庇ふ 美千子
※小さな命への母の慈愛。深い絆。
機関庫の朝の体操花馬酔木 かづひろ
※季節の変化と今生きている実感。
〇 第3回
ひもすがら春をまさぐる象の鼻 鴫原さき子
濾過されぬ記憶のかけら春愁 白石 文男
ほつほつと物の芽大地動き出す 砂川ハルエ
バイエルの記憶は指に雛霰 松永 弘子
一輪は地に触るるまでしだれ梅 金井 玲子
青き踏む風土記の丘の埴輪かな 大木 典子
ほろ苦きものに箸ゆく春の膳 大本 尚
卒業歌未来の扉開け放つ 奥村 安代
さくら咲く一行のみの日記かな 丸笠芙美子
春や春国の礎記紀歌謡 石坂 晴夫
鴫原さんの句は「春をまさぐる」季節感、
白石さんの「濾過されぬ記憶」という心の澱、
砂川さんの大地の躍動感、
松永さんの「指に」という直截的な身体感覚に記憶を結び付けたところ、
金井さんの「地に触るるまで」という命の懸命で自然な在り様、
大木さんの句は「風土記」ではなく「風土記の丘」と言い、そこに今、「埴輪」を立ているところ、
大本さんの「箸ゆく」という「思わず・どうしても」という動作の一瞬の繊細な心の揺れの表現、
奥村さんの「未来の扉」と「開け放つ」で、センチメタル表現になりがちな「卒業」の季語的因習を吹き飛ばしているところ、
丸笠さんの「一行のみの」という表現で読者を多様な感慨に誘い込むところ、
石坂さんの句の、齋藤愼爾先生が指摘された「国の礎が政治や経済の豊さではなく、詩歌の心だという視座」など、
みなさんの句がすべて、個人的な感慨を超えた高次の抒情表現になっていますね。
〇 第2回
心のあの日の記憶ミモザ咲く 大木典子
発掘の石に番号日の永し 平井伊佐子
菜の花や海の光を独り占め 白石文男
菜の花や今日の地球は黄色なる 鴫原さきこ
抗ひし記憶ばかりが梅真白 奥村安代
息白し始発電車の同じ顔 高橋みどり
惑星にはやぶさ二号春連れて 砂川ハルエ
どの句もしっかりと内面化した心象が造形されていて、季語がただの記号的な措辞に終わらない鮮度で、その季節の時空の中での実存的手応えを包み込んでいます。
大木さんは瑞々しい「あのときの記憶」を、
平井さんは日々を丁寧に噛みしめて生きている人の眼差しを、
白石さんは内側からこみ上げる歓びを、
鴫原さんは悠久の時間の流れのなかの一瞬の命の煌めきを、
奥村さんは生きる心の軸としたものを、
高橋さんは他者と共有する今、このときを愛しむ心を、
砂川さんは春という季節感を宇宙大へ各々、造形的に表現しています。
この地点から野木俳句のようにさらに表現を深めてゆくために、一元的な「わたくし性」を脱し、かつ「合〈目的〉的な主張性」を脱した、「普遍性のある」表現とは何かと、絶えず自分に問いかけてゆきましょう。
〇 第1回
風花や受話器の奥の発車ベル 奥村安代
煮凝りの余白は海の深き色 白石文男
根詰めし文机におく葛湯かな 金井玲子
冬晴やパンドラの箱空け放つ 高橋みどり
どの句も日常の一瞬にフォーカスを絞って鮮やかに描き出しつつ、そこを超えて、自分以外の誰かへ、世界へ、自然へ、宇宙へと突き抜けてゆくような、読者を共感で揺すぶる、意志と悟性の働きを感じますね。
生き生きとした作者の魂の力を感じます。
奥村さんはここにいない誰かへ、
白石さんは食卓から自然へ、
金井さんは共存する他者へ、
高橋さんは不安や恐れを吹き飛ばして魂を天に開放しています。
このような作句と鑑賞は「意志」の力を「悟性」で受け止めて、初めて可能になるのです。















