発達障害という用語は、もう限界かもしれないな、と、
武田双雲さんの、このブログ記事を見て思いました。
こんな記事にもなってました。
ここ何年かの間に、発達障害という医学用語?福祉用語?は、流行り物のように多くの人に認知されるようになりました。
空気を読まない人、片付けられない人、人の話を聞かない人、天然な人、オタクな人、友達がいない人は、「発達障害じゃない?」なんて、軽く揶揄されるような雰囲気も世間にあったり。
乳幼児期の息子の健診では、この種のパンフレットは必ずもらったし、健診する側の保健師やドクターからは、子どもを診ながらつねにその可能性がないかどうかを探っているな、というのが、ひしひしと伝わってきました。
息子の言葉の出始めがやや遅めだったこともあり、私もそれなりに勉強しましたね。でも、結局よくわからなかった。発達障害とは、そうといえばそう、そうといわなければそうでもない、という曖昧な理解しかできなかったんです。
しかし、武田双雲さんがね、こんな記事を堂々と載せると、改めて、発達障害の人が障害者で、発達障害じゃない人が健常者とか定型発達って、その定義がやっぱり心許ないなぁって思えてしまうんです。
苦手と得意の差が極端なのが障害、
苦手と得意の差が少ないのが定型、
集団行動が苦手なのが障害、
集団行動が苦手でないのが定型、
空気を読めない、読まないのが障害、
空気を読むのが定型、
こだわりが強いのが障害、
こだわりが弱いのが定型。
なんでこっちが障害なのー?
なんでこっちの定型なのー?健常なのー?
いや、どっちが障害でどっちが健常って、そのジャッジメントがすでに、今の時代には合わなくないかな。
例えば、苦手と得意の差が激しいことを障害とすることが、もうナンセンスなんじゃないか、限界なんじゃないのかな、という気がします。
やっぱりどこまでいっても、障害なんかじゃなくて、個性でしかないんじゃない?そんな風に感じるんです。
🔹🔹🔹
私の身近なところにも発達障害と診断されている人がいます。
職場にもいますし、息子の仲の良いお友達にも、息子のお友達のパパにも、私が援助した人のなかにもいます。
確かに、彼らや彼らの家族の多くは困っています。当事者や家族が困っているから、だから、診断名を療育を治療を、となるわけなんですよね。
でも、彼らが困るのは、この国のスタンダードが彼らの個性を「障害」としない限りは受け入れないよ、という懐が深くないところに困っているだけで、彼らは自分自身には、自分自身であることには困っていないんじゃないかな。
つまり受け手側の問題、逆にその個性を障害というカテゴリーに押し込めてしまう、こちら側の心性に障害かあるのかもしれませんよね。これは、発達障害に限ったことではないですが。
ただね、徐々に、時代も、日本人も気づき始めている気がします。
自閉症スペクトラムやADHDの発達障害に特有な個性が、この閉塞感のある時代に、この国を牽引するチカラのあることを。
もちろん、誰もが武田双雲さんになれるわけじゃない。エジソンや、スティーブジョブズやビルゲイツになれるわけじゃない。
でも、夫がこんな話をしてくれたんですよ。
彼の勤務先は、比較的保守的な会社です。
出世する人、実力のある人というのは、かつては、集団を束ねる力や調整力が抜群ないわゆる「やり手」だったり、家庭なんて全く顧みない滅私奉公的な人だった。
それが最近は明らかに変わってきた、と。
例えば、ひと昔前には、パソコンオタクとしてオフィスの片隅に押しやられていたような人が重用されるようになったと言います。
また、閉塞感が漂うとき、数字を上げることが求められるとき、場の空気を殆ど考えず自分の感覚だけで物を言うようないわば子どもっぽい人の意見が採用されたりするんだとか。しかも、その8割がいい結果に結びついているという感触があるといいます。
その、傍若無人なところや、ジコチュー的なところを敬遠したり、嫌う人は多いのに、でも、いざと言う時には、その人の声、感覚に頼ってしまう、という現象が起きているといいます。
決して有名ではない人たち、爆発的な才能を表現する「天才」ではない人たちの間でも、こうしたことが起きているってことです。
🔹🔹🔹
誰に、どう、思われるか。
発達障害ではない普通の人は、何かをしようとする時、ここに多くのエネルギーを割きます。ここに消費されたエネルギーの分だけ、集中力は削がれます。
たとえ、素晴らしいアイデアが生まれても、表現する段階でここにエネルギーが奪われたら、それは最初のインパクトをもって周知されません。
これを突破していくチカラが、発達障害の人には生まれつき備わっていると思います。
苦手なことばかり、標準よりも劣っているところばかりがフォーカスされがちな発達障害ですが、得意なところ、優れているところに目を向ければ、その能力はすさまじいはずです。
もちろん、そんないい話ばかりじゃないとか、診断された方が楽に決まってるとか、家族の気持ちはどうなるのとか、障害のレベルによる、とか色々な事情はあると思います。
私が、こんなことを書くのは、自分の周りにいる発達障害の人を通してしか私が発達障害というものを知らないからなんですが、何よりも私は彼らが好きなんです。正直に言うと、憧れにも似た感情も覚えるんです。
発達障害を一つの個性ととらえ、発達障害の人たちの能力を伸ばしていく方向、少なくとも、自然に伸びていくのを邪魔しない方向に受け入れ側の意識が、私たちの意識が変わったら、(すでにその兆候は始まっていると思います)、それは、とてもいい世界だな、と感じます。
そして、そんな世界は、発達障害の人たちにとってだけ最良なのではなくて、そうでない人たちにも居心地のいい世界なんじゃないかな、と思うのです。
武田双雲さんの、このブログ記事を見て思いました。
こんな記事にもなってました。
ここ何年かの間に、発達障害という医学用語?福祉用語?は、流行り物のように多くの人に認知されるようになりました。
空気を読まない人、片付けられない人、人の話を聞かない人、天然な人、オタクな人、友達がいない人は、「発達障害じゃない?」なんて、軽く揶揄されるような雰囲気も世間にあったり。
乳幼児期の息子の健診では、この種のパンフレットは必ずもらったし、健診する側の保健師やドクターからは、子どもを診ながらつねにその可能性がないかどうかを探っているな、というのが、ひしひしと伝わってきました。
息子の言葉の出始めがやや遅めだったこともあり、私もそれなりに勉強しましたね。でも、結局よくわからなかった。発達障害とは、そうといえばそう、そうといわなければそうでもない、という曖昧な理解しかできなかったんです。
しかし、武田双雲さんがね、こんな記事を堂々と載せると、改めて、発達障害の人が障害者で、発達障害じゃない人が健常者とか定型発達って、その定義がやっぱり心許ないなぁって思えてしまうんです。
苦手と得意の差が極端なのが障害、
苦手と得意の差が少ないのが定型、
集団行動が苦手なのが障害、
集団行動が苦手でないのが定型、
空気を読めない、読まないのが障害、
空気を読むのが定型、
こだわりが強いのが障害、
こだわりが弱いのが定型。
なんでこっちが障害なのー?
なんでこっちの定型なのー?健常なのー?
いや、どっちが障害でどっちが健常って、そのジャッジメントがすでに、今の時代には合わなくないかな。
例えば、苦手と得意の差が激しいことを障害とすることが、もうナンセンスなんじゃないか、限界なんじゃないのかな、という気がします。
やっぱりどこまでいっても、障害なんかじゃなくて、個性でしかないんじゃない?そんな風に感じるんです。
🔹🔹🔹
私の身近なところにも発達障害と診断されている人がいます。
職場にもいますし、息子の仲の良いお友達にも、息子のお友達のパパにも、私が援助した人のなかにもいます。
確かに、彼らや彼らの家族の多くは困っています。当事者や家族が困っているから、だから、診断名を療育を治療を、となるわけなんですよね。
でも、彼らが困るのは、この国のスタンダードが彼らの個性を「障害」としない限りは受け入れないよ、という懐が深くないところに困っているだけで、彼らは自分自身には、自分自身であることには困っていないんじゃないかな。
つまり受け手側の問題、逆にその個性を障害というカテゴリーに押し込めてしまう、こちら側の心性に障害かあるのかもしれませんよね。これは、発達障害に限ったことではないですが。
ただね、徐々に、時代も、日本人も気づき始めている気がします。
自閉症スペクトラムやADHDの発達障害に特有な個性が、この閉塞感のある時代に、この国を牽引するチカラのあることを。
もちろん、誰もが武田双雲さんになれるわけじゃない。エジソンや、スティーブジョブズやビルゲイツになれるわけじゃない。
でも、夫がこんな話をしてくれたんですよ。
彼の勤務先は、比較的保守的な会社です。
出世する人、実力のある人というのは、かつては、集団を束ねる力や調整力が抜群ないわゆる「やり手」だったり、家庭なんて全く顧みない滅私奉公的な人だった。
それが最近は明らかに変わってきた、と。
例えば、ひと昔前には、パソコンオタクとしてオフィスの片隅に押しやられていたような人が重用されるようになったと言います。
また、閉塞感が漂うとき、数字を上げることが求められるとき、場の空気を殆ど考えず自分の感覚だけで物を言うようないわば子どもっぽい人の意見が採用されたりするんだとか。しかも、その8割がいい結果に結びついているという感触があるといいます。
その、傍若無人なところや、ジコチュー的なところを敬遠したり、嫌う人は多いのに、でも、いざと言う時には、その人の声、感覚に頼ってしまう、という現象が起きているといいます。
決して有名ではない人たち、爆発的な才能を表現する「天才」ではない人たちの間でも、こうしたことが起きているってことです。
🔹🔹🔹
誰に、どう、思われるか。
発達障害ではない普通の人は、何かをしようとする時、ここに多くのエネルギーを割きます。ここに消費されたエネルギーの分だけ、集中力は削がれます。
たとえ、素晴らしいアイデアが生まれても、表現する段階でここにエネルギーが奪われたら、それは最初のインパクトをもって周知されません。
これを突破していくチカラが、発達障害の人には生まれつき備わっていると思います。
苦手なことばかり、標準よりも劣っているところばかりがフォーカスされがちな発達障害ですが、得意なところ、優れているところに目を向ければ、その能力はすさまじいはずです。
もちろん、そんないい話ばかりじゃないとか、診断された方が楽に決まってるとか、家族の気持ちはどうなるのとか、障害のレベルによる、とか色々な事情はあると思います。
私が、こんなことを書くのは、自分の周りにいる発達障害の人を通してしか私が発達障害というものを知らないからなんですが、何よりも私は彼らが好きなんです。正直に言うと、憧れにも似た感情も覚えるんです。
発達障害を一つの個性ととらえ、発達障害の人たちの能力を伸ばしていく方向、少なくとも、自然に伸びていくのを邪魔しない方向に受け入れ側の意識が、私たちの意識が変わったら、(すでにその兆候は始まっていると思います)、それは、とてもいい世界だな、と感じます。
そして、そんな世界は、発達障害の人たちにとってだけ最良なのではなくて、そうでない人たちにも居心地のいい世界なんじゃないかな、と思うのです。










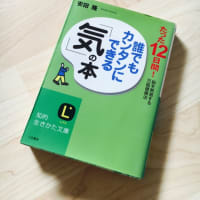

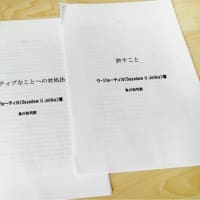
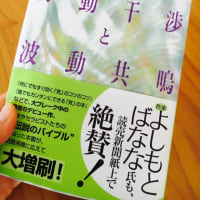




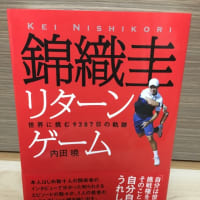
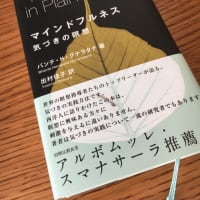
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます