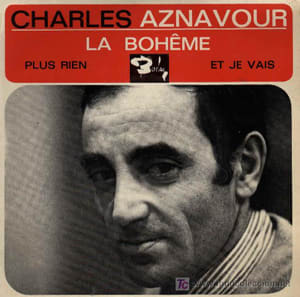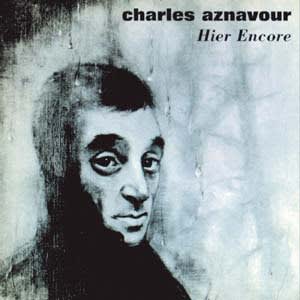”Le Mauvais Garçon” Salvatore Adamo

アダモには『ブルージーンと皮ジャンパー』のように道を外した若者を諌める系列の歌があります。
この曲 ( 原題=不良少年 ) も、一人称の歌詞で失恋によって少しやさぐれた若者の姿を嘆いています。
アダモ自身の作詞・作曲で1965年のセカンド・アルバムの一曲なのですが、意外と知られているわりには
ヒットチャートには顔を出していません。
Ce jour-là, dans ce vieux bistrot
Au bout du monde de mes souvenirs
J'avais bu un peu plus qu'il ne faut
Ça me faisait mal de réfléchir
J'étais rond, j'en avais le droit
Elle me quittait à tout jamais
Depuis, on me montre du doigt
Encore un peu, on me pendait
Le mauvais garçon
Le mauvais garçon
Mon Dieu, quelles façons !
Oh oui, quel polisson !
↓はサルヴァトーレ・アダモの『ろくでなし』 YOUTUBEより