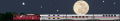私たちは大人は,子どもの気持ちを先回りして考えてしまうのではないか。相手の考えを聴くよりも先に,自分の気持ちを押しつけているのではないか。
小さな絵本『君のためにできるコト』(菊田まりこ・作 学習研究社)を読んでそう思いました。
気のきくくまおくんは,口べたくまこちゃんのために何でも優しくしてあげます。
「どこか行きたい? 僕がどこでもつれてってあげる。」
「おなかがすいた? 僕がなんでもつくってあげる。」
口べたのくまこちゃんは,「あのね」と話しかけるのだけれど,くまおくんは聞いてくれません。次々と優しい言葉をかけてくれます。
「暑くない?僕が木陰をつくってあげる」
「寒くない?僕がマフラーつくってあげる」
くまこちゃんの「あのね」の話しかけは無視されつづけます。
何も言わない(言えない)くまこちゃんに,くまおくんは
「僕がきらいなの」「それなら君の前からいなくなってあげる」
と言ってしまいます。
くまこちゃんは涙をいっぱいため,「あのね,あのね」を繰り返し,言えない言葉を,ずっと言えなかった言葉を溢れ出させます。
「ずっといっしょにいてくれる。」
先回りをして自分の思いを伝えることでなく,まず相手の思いに耳を,心を傾けること。それをしないと「君のためのできるいちばんのこと」が「あたりまえすぎて」分からなくなってしまうのです。
季節は秋。秋には花鶏(あとり)や尉鶲(じょうびたき)などの美しい鳥が渡ってきます。」。
小鳥の声に耳を寄せるのもいいでしょう。コロナ禍の学校で自分の思いを思いっきり話せない子どももいるでしょう。この時期だからこそ、子どもと向き合う時間も多く持ちたいものです。ただ向き合っているならまだしも、善意の押し付けみたいになっても困ります。子どもたちの「言えない言葉」を、「言えなかった言葉」を聴く時間にできたらいいですね。