
オホーツクミュージアムえさし。枝幸町三笠町。
2022年6月18日(土)。

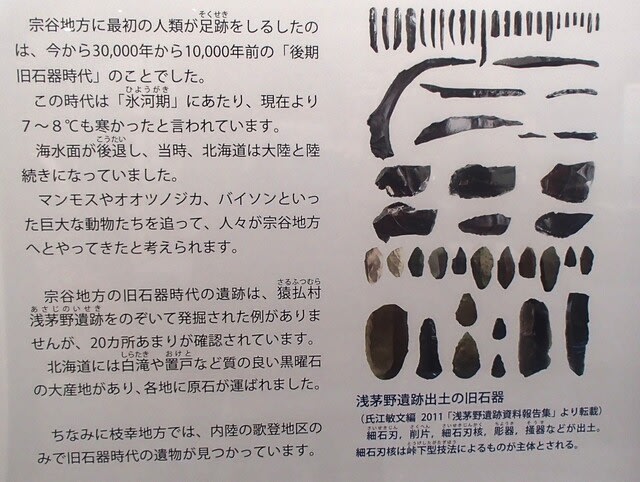



シュブノツナイ式土器。縄文時代前期。枝幸町音標トイナイ遺跡出土。
櫛目文土器。縄文時代前期後半から中期前半の標識土器。湧別町信部内長野遺跡を標識遺跡とする。


網走式土器。縄文時代前期。

北筒式土器。縄文時代中期。
北筒式土器は北海道円筒式土器の略で、縄文時代中期後半に主として道東や道北に分布した、若干の繊維を含んだ円筒形の土器である。


両頭石器。縄文時代中期。

メノウ製削器。縄文時代中期。

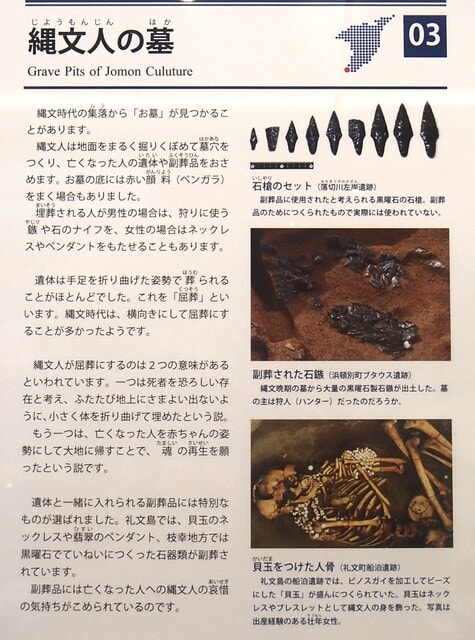




宇津内IIa式土器。続縄文時代前期、紀元前4~1世紀頃。
宇津内式土器は、続縄文時代前期から中期の道東北部網走地域を中心に分布する土器である。Ⅱa式とⅡb式に細別されており、前期の型式であるⅡa式は口唇部直下にめぐる突瘤文を特徴とする。


続縄文時代後半は土器型式によって後期・晩期に分けられている。後期は後北C1式土器、後北C2・D式土器が中心に作られた時期で、晩期は北大I式土器、北大II式土器が中心に作られた時期である。
後北式土器文化。
後北式土器とは後期北海道薄手縄文土器の略である。続縄文時代後半期には、その初めには道央に限られた後北式土器が、やがては全道一円に進出するとともに、東北地方南部まで分布域を拡大した。
続縄文時代前半期には海岸線に沿って遺跡の分布がみられたが、後半期には河川沿いに遺跡が分布する傾向を見せることから、この時期になって海洋での漁労・狩猟活動から、河川での漁労活動に生産手段が変化したと考えられる。
藤本(1994)は、各地の河川中流域に多くの遺跡が分布し、拠点的な大遺跡と小規模な遺跡の組み合わせがみられること、川筋に沿ってみられることから、後の擦文文化、アイヌ文化に続く河川漁労を主とした生業体系がこの時期に成立したとしている。


後北C1式土器。
2世紀から4世紀ころまでの土器である。道央方面で作られていた後北式系統の土器がオホーツク海沿岸地域でも広く作られるようになった。
後北C2式土器。
後北C2・D式土器は続縄文時代後半期の北海道全域に分布し、サハリン南部・南千島、東北地方、越後平野まで広範囲に拡散した土器型式であり、この時期の常呂地域でも多数出土している。
文様要素の違いから後北C2式土器と後北D式土器とに分類されていたが、のちに両者に時期の違いがないことが分かったため、現在では「後北C2・D式土器」とよぶのが一般的になっている。



















