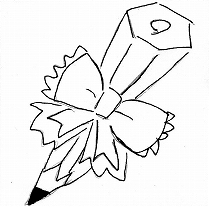本文詳細↓
「何を無様に固まっておるか。精霊とは皆このようなものよ」
「いやでも、ヘタに動いて蹴ってしまったら申し訳ないじゃないか」
頭上のアダムに向かってそう答えたら、返ってきたのは鈴が弾けるような笑い声だった。
『蹴ったら申し訳ないですって』
『かわいいわあ』
『うふふ……』
目を白黒させていると、アダムに頭を叩かれた。
「おぬしはどこまで阿呆なのだ、トルル。実体を持たぬ精霊を蹴る心配など、見当違いも甚だしいことよ」
そういえば故郷の町で妖精たちと一緒に遊んだことはあっても、精霊に会うのは初めてだった。だから接し方が分からずにいるといきなり、頭の上から緑の光が落ちてきた。楽しそうな笑い声を伴った緑の光が、何度も僕の身体を包んでは離れることを繰り返していた。
『ふふっ、ずいぶん初心で素直な子。気に入ったわ』
『私もよ。いいわ、話を聞いてあげる』
『何が知りたいの? 蜜詰めの惚れ薬の作り方? 炭をダイヤへ変える方法?』
『なんでも教えてあげる。だって私たちは、全ての大地と空にあるものだから』
口から飛び出たお礼の声は、自分でも驚くぐらいうわずっていた。
そして語った。忘れられない、蒼き月夜の想い出を。