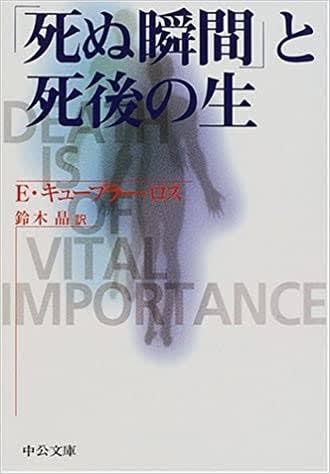
🔲続・死ぬ瞬間🔲
有名なE・キューブラー・ロスさんの本を久しぶりに手に取りました。「最後に人が求めるものは」という副題がついております。
医療従事者、宗教家、葬儀業者には読んでもらいたい本ですが、小生もなかなかページが進みません。でも今朝読んだ「ユダヤ人の死観/悼みの道しるべ」は深く感銘しました。
ユダヤの律法は「死にゆく人はすべての点からみて生きている人と同じと考えられる」と教えているそうです。ユダヤ人の喪の慣習が賢いと言われるのは「人が死を受容し、完全に慎み、そして再び充分に生きることを学ぶ」トータルな枠組みをしているからであります。
死にゆく人に安らぎを与え、哀悼者に悲嘆を解除して、共同社会へ再統合されていくために儀式があります。アメリカの死否認社会ではなくて、死にゆく人は、これまでどおりに生きてるときと同じに扱われなければならないというハラカ(ユダヤの葬儀)に共鳴します。死にゆく人は決して独りきりにしてはならない、ねんごろに世話をするのが共同社会でなされるべき正当な行為です。まさに「儀式は人と人の絆を再確認する装置である」と考える小生は頷いて読みました。
死は終わりであり、始まりであります。ユダヤ教では哀悼者に死の現実から逃げることを許さず、死を見ることを命じ、彼が死と折り合うのを助けるため、埋葬と喪の手続きなど死後の儀式すべてに参加させるようです。「寝ずの番」で死を看取ることの重要性を痛感しましたが、「無縁社会」と呼ばれる現代で、ますます死は人目から離れつつあります。死を認知できない人々が増えれば共同社会が崩壊し、ますます孤立化が進むと考えます。
またユダの伝統は感情の抑圧に反対します。哀悼者に悲しみと嘆きを人前かまわずに表すように命じます。「ハラカ(葬式)」の中に「クリアー(裂く)」という行為があります。これは、葬式の前、哀悼者が自分の衣服を引き裂くことです。引き裂くのは心理的緊張解除の機会なのです。つまり哀悼者に、制御された、宗教上認可された、破壊行為という手段によって、彼の鬱屈した怒りと苦悶とにはけ口を与えることなのです。
また「食」を共にすることは社会復帰、回復のために必要な行為で哀悼者が独りきりではなく、他の人々が彼を助けてくれることを教えて安心させる共同体的連帯意識を眼に見える仕組みであることを学びました。
共に食べるという「共食」は、人間社会の原始的でありますが、家族と共同社会、そして神仏と一つになるという絆を強化し、関係を受容させることであることも学びました。
儀式には意味付けがされております。「学び直し」によって「生」を確認する手段なのであります。だから、だからこそ儀式が必要なのです。儀式を軽んじる国家は滅びると孔子も明言しております。
儀式とは感情のカタチではないでしょうか?「感情の表現は絶望へ落ち込むためのものではなく、人生の次のページにおいて感情の資本をとりもどし再投資するを合法化し、より容易ならしめるためである」(ジャクソン論文)




























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます