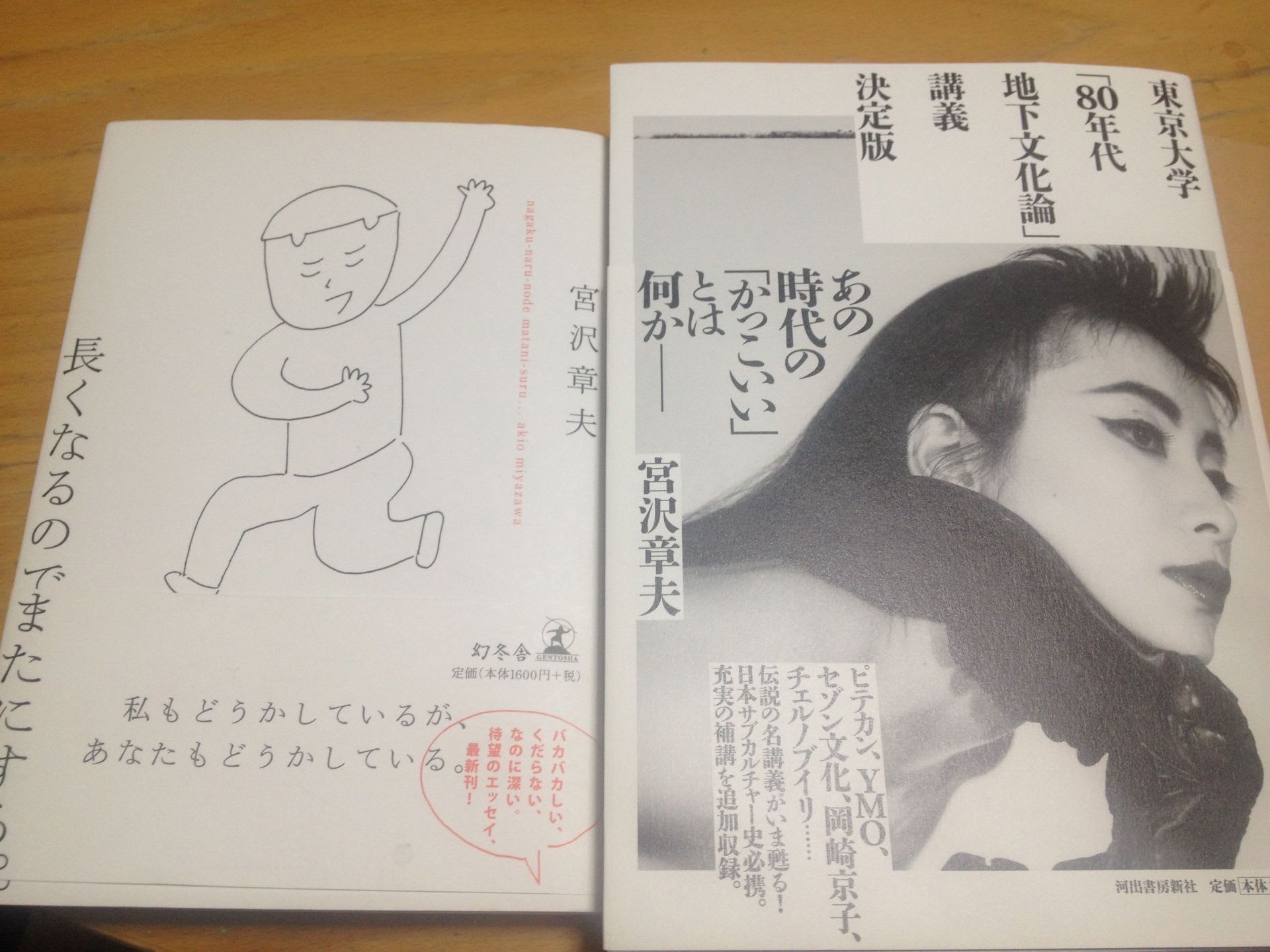facebookのタイムラインで以下のような記事が流れてきた。
「40歳になった女性・綾が住む街…それでも女の人生は続く」
東京カレンダーという雑誌のサイトの記事で、いろんな年齢の女性を主人公に、そんな生き方の女性が住んでいそうな街をピックアップして、その女性の人生のストーリーを語るシリーズ記事らしい。たぶんフィクション。
シェアしていた主が「後味が悪い」と書いてたのが気になって読んでみた。たしかに後味はあんまりいいものではなかった。主人公の女性・綾は別に周囲に迷惑をかけるような人ではないが、こんな女、実際にいたとしたらなんかヤだな、というようか感じの人物造形である。
で、こんな女性、私の周りにはいないな…の一言で片付けようかとも思ったが、最後の一文が気になったので、ちょっと考えてみた。
その最後の一文とは「私が“何者か”になるのを諦めない限り、この街は、上京した時に抱いた圧倒的憧憬のまま、キラキラと輝き続けるはずですからね。」というもの。なんかユルい締めだなあと思ったが、ユルいどころか、これって結構絶望的だ。
このカギ括弧で強調された彼女に取っての“何者か”とは結局“何者”だったのだろうか。何者が何者かわからないまま、人からの羨望とか、目の前の贅沢とかを当面の理由に、どこからか差し出されたタスクを粛々とこなしてきたのが、彼女の17年だったのではないだろうか。そのタスクと引き換えに自己実現はあったはずだが、その実現するべき何かをいまだ“何者か”と表現する彼女には、その実現すべき自己が何かも見えていないはずだ。
「上京した時に抱いた圧倒的憧憬」の“圧倒的”の部分は、往々にして若さ故の無知が生んだ無分別に彩られている。年月を経て無知が解消して行く中で、圧倒的装飾のメッキは剥げて、その奥にある本当に自分が求めるものの鈍い輝きが目の前に現れて来る。しかし、この文章の主人公である40歳の女性は、上京してからの17年間で、その輝きに気づくことはなかったようだ。
彼女は“何者か”が何者であるかが分からないまま走ってきたから苦しかったのではないのか。なのに、さらに彼女は“何者か”になることを諦めないと言う。
しかし、若い頃より眼力が養われたといっても、自分にとっての“何者か”を見つけるのは容易なことではないのも事実。もちろん、アラフィフも近い私にもまだ分からない。
そういう意味で、今気になっているのが、「即身成仏」という言葉だ。すいません、突然、仏です(笑)。これは、生きながらにして仏になるという密教の教え。仏になるなんて、ちょっとおこがましいが、「目標は仏ですから!」と笑ってしまえば、よく分からない“何者か”を目指す苦悩から解放される。
「自己実現」という西洋発の考え方は、「自己が何者であるか」が分からねば、堂々巡りの迷宮に陥ってしまう。そんな迷い子を騙して、彼女のパワーをうまいこと絡めとる人だって出て来るだろう。それが、現代の資本主義だとは言わないが、なんだか今の世の中には、そんな状況がいっぱい転がっているようにも見える。
「自己実現」ではなく、「即身成仏」が目標ですから!と言っちゃえば、目指すのは圧倒的に仏の境地。自己がどうかとか軽く超えてしまう(笑)。自己がどうかに関わらず、世の中にとって良いと思うことをやる。健康を目指す。人を愛する、自然を愛する。人目を気にしない…などなど。仏に近づくことをやってると、いつのまにか“何者か”なんてどうでもよくなっている気もする。
いや、「即身成仏」を目指す中で、いろんな“何者か”に出会い、これもあり、あれもあり、たぶんあり、きっとありって感じで、レインボーマンのように変身出来る自らの化身がいっぱいできたらいいじゃないですか。密教の曼荼羅に描かれたたくさんの仏は宇宙の中心・大日如来が様々な形に化身したものだそうだ。“何者か”っていっぱいいていいし、それは「即身成仏」を目指す過程で、出会う自分の様々な化身なんだと思う。
実は、facebookのタイムラインでこの文章を見たとき、ちょうど梅原猛の仏教のはなしをPodcast的なもので聞いていた。それが面白過ぎて、こんなことを考えちゃいました。
その梅原猛の講演記録はラジオデイズで購入出来まする。
http://www.radiodays.jp/artist/show/575