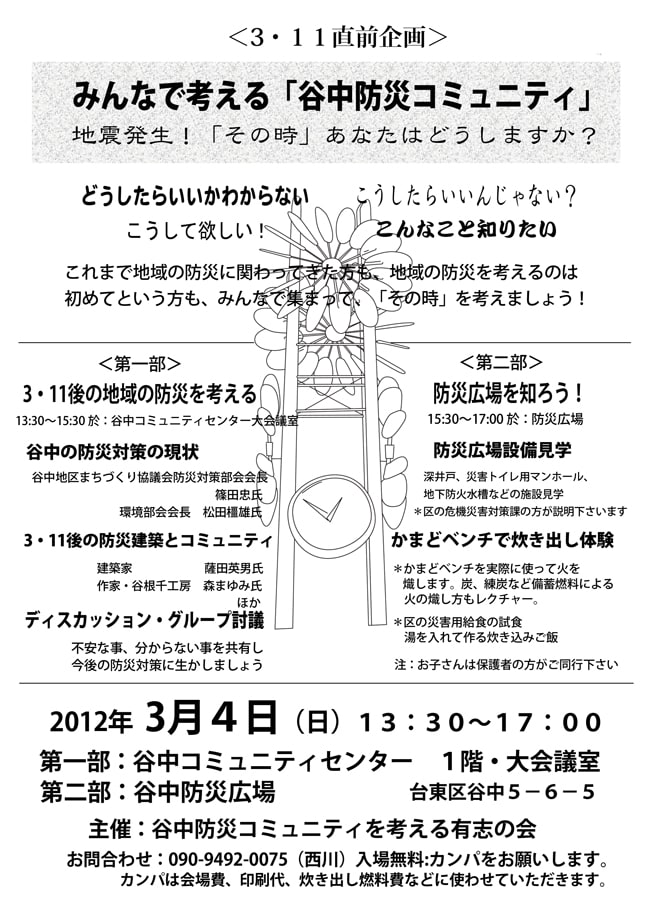今日の東京新聞のこちら特報部、「首相 世論見て見ぬふり」。
もちろん脱原発ゼロを求める世論のことです。27日に放送されたNHKクローズアップ現代でも、出演した野田さんは「様々な立場の意見を聞いていきたい」と発言しただけだったみたいです。東京新聞では2面でも「首相真意まだ見えず」と野田総理の「原発ゼロ」に対する態度がはっきりしないことを指摘。脱原発にはっきり舵を切ろうとしない総理を暗に批判しています。
先日の市民団体ほかとの面会でも、予想通り「話し合いは平行線」でした。総理にとってはハナからそこは「話し合いの場」などではなく、「自分の話を聞いてもらう場」だったようです。面会前、野田さんは「自分の意志が伝わっていない。」と語っていました。
野田さんが伝わっていないという「自分の意志」とは、彼の言葉から類推すれば「当面、原発ゼロは目指さない」ということとしか思えないのですが、当然ながら、彼はそうは言いません。そうは言わないから、勝手な類推でものを言えないメディアは「首相真意まだ見えず」ということしか言えません。そして、はっきりものを言わない野田さんにメディアや脱原発派の人々が焦らされているうちに、彼(ら)は徐々に、「自分の意志」をいろんなところに潜ませ始めています。
【『脱原発依存』という言葉】
例えば「脱原発依存」という言葉。
野田さんが使い始めたのはいつごろからだったでしょうか。「脱原発」が可及的速やかに原発ゼロを目指すのに対し、「脱原発依存」は原発だけに依存するのはやめるけど”ゼロにするわけではない”ということ。突然この言葉を使い始めたことに、私は野田さんの「原発やめたくない意志」を見た気がしました。最初は「脱・原発依存」ではなく「脱原発・依存」に聞こえてしまい、「え?“脱原発に依存する”ってどういうこと???」と、一瞬頭がこんがらがりそうになりましたが、ある意味、この言葉の目くらまし度の高さを象徴しているともいえます(いえないかww)。
すでに、メディアの一部はこの言葉に目くらまされています(確信犯のところもあるかもしれませんが)。昨日行われた脱原発に関する国民の意識調査を分析する専門家会合は、「少なくとも過半の国民は原発に依存しない社会の実現を望んでいる」と結論づけました。これを受けて、いくつかのメディアは見出しで【「過半数の国民」は脱原発依存】とか、【「国民の過半、脱原発依存望む」検証会合で総括】とか書いています。
本当にそうでしょうか?調査の数字を見れば、“過半数の”国民が望んでいるのは「脱原発依存」ではなく「原発ゼロ」です。2030年における原発依存度は、政府の意見聴取会のアンケートでは81%が原発ゼロを望み、政府の意見公募でも87%がゼロ希望でした。討論型の世論調査では原発ゼロ派は過半数をわずかに切りましたが、それでも46.7%と限りなく過半数に近い数字です。
正しくは【国民の過半数が「脱原発」を望む】ではないのでしょうか。
言葉の専門家であるはずのメディアが、そこに突っ込みを入れないのはいかがなものでしょう。こうして、ものごとはなし崩しになっていくのになあ・・・。
そういえば、「反原発」という言葉もいつのまにか使われなくなりました。その運動チックな匂いや妥協を許さない頑な感じが嫌われたんでしょう。私自身もある時期から、脱原発と言った方が原発を無くすことに拒否感持つ人が減るよな、なんて思い、意識して「脱原発」を使うようになっていました。でも、反対勢力は、そんな私たちの配慮や逡巡を利用して、さらに言葉の骨を抜いて行くんですね。
なんだか、再び「反原発!」って言ってみたくなりました。でもまあ、そこまでいきり立つこともないかなと思います。やはり「反」という字のニュアンスに反発を持つ人はいるし、二項対立的な感じは対立のもとですしね。あくまでも「脱原発」で。
もとい、「脱原発」と「脱原発依存」は似て非なる言葉だと思います。
政治の言葉には、一般名詞なのをいいことに、どうとでもとれる言葉がよくあります。「脱原発依存」も、どこまで原発が減れば依存を脱したかは明確になっていませんから、その幅が太くなるかも細くなるかも状況次第です。「日米同盟」という言葉も、一体どんな関係なのかがいまひとつよくわからないまま状況によって使い分けられてる気がしますが、「脱原発依存」もそのくらい大きな問題をはらむ一般名詞なのではないでしょうか。
【『市民団体ほか』という言葉】
そういえば、先日の「野田総理と市民団体ほかの面会」では、官邸前に集まる数万人の中から、代表としてしかるべき団体の主催者などが官邸に招かれましたが、私はこの「市民団体ほか」もちょっと気になりました。
官邸前のデモには市民団体もたくさん集まっていますが、このデモが今までと違うのは、団体主催ではなく、ツイッターなどの呼びかけで、組織化されない人々が何万人も集まっていることです。もちろん官邸内に全員入ることなどできませんし、野田さんも官邸の外に出て行って脱原発派を喜ばせることなど決してやりたくはなかった。なら、代表を官邸内に呼ぶしかありません。そのときに、多くのデモの人の中から、市民団体の代表やツイッターを始めた人を呼ぶのは妥当な考えではあります。そして、官邸も配慮して「市民団体”ほか”との面会」としたんだとは思います。でもやっぱり「ほか」は「ほか」。人数から考えれば「”ほか”と市民団体との面会」が正しいのです。
官邸が「市民団体ほか」という言葉を使う時、これまでとはちょっと違う次元に入りつつある現在の脱原発運動を、想定内の「市民運動」の枠内にとどめておきたいという思いも、無意識かもしれませんが、働いているような気もするのは考え過ぎでしょうか。
そういう意味で、現在の祭りの縁日のような官邸前デモは、永田町やその周辺の人々にとって想定外の理解不能の不気味なものに映っているかもしれません。敵対勢力に対しては、なるべく意味不明、正体不明、理解不能な存在でいた方が闘う上では絶対に有利です。この状況をいかにわけの分からないものにして行くかが、脱原発実現に近づく道ではないかと思うほどです。とらえどころのない、ある意味わかりにくい脱原発デモ。誰が首謀者かもわからない。それでも日々人数は増えていく、まるでアメーバのようなデモ。そんな活動を目指したいものです。なぜって聞かれても、そんな気がするというだけなんですが・・。
【『国民生活』という言葉】
もう一つ、「国民生活」という言葉も曲者です。
野田さんが守りたいという「国民生活」は「お金で買える国民生活(経済)」ということではないかと思います。それは大飯原発再稼働を決定したときの声明からも明らかです。脱原発派の人が原発のない安全安心な世の中を求めているのに対して、野田さんは原発がないと日本経済は立ち行かないと語り、理解を求めます。そもそも原発に対して立脚する場所が違うこの両者の話がかみ合うわけはありません。一方で、この2つの「国民生活」が表す内容は、震災後の日本がどういう国を目指すのかの選択肢でもあり、「脱原発」という問題を考えることは、そんな大きなテーマも含んでいます。
「お金で買える国民生活(経済)」を選ぶ人は、これまでの人生において、ほとんどのものの価値をお金で計ってきた人でしょう。言い換えれば、言葉で説明するよりも、お金の価値で見せた方が分かりやすいと実感し、世の中の価値をことごとくお金に換算して表現してきた人たちでしょう。彼らはなかなか言葉だけで説得したところで納得してはくれますまい。そして、戦後の日本ではこの価値観がかなり根強くはびこっています。現在、ニュースでとりあげられるのも、税金や年金や生活保護や貧困や失業や景気や貿易や為替や…ほとんどがお金の話です。その価値観を超えて、野田さんとどう話し合うか…、財界の経営者をどう説得するのか…。かなり難しそうです。そして、それが難しいのは、脱原発派の人々の中にも、こと原発以外の話となれば、経済が判断の基準となる人も少なからずいるからではないかと思います。
私たちに染み付いたこの価値観を客観化しないことには、この問題には出口が見えてこない気がします。
【そして、『脱原発』という言葉】
脱原発を求める私たちは、脱原発を実現する過程において、また実現して後、本音のところではどんな暮らしをしたいと思っているのでしょうか。抽象的な理念としては語れても、具体的にどんな家に住み、空調はどんな感じで、どんなものを食べ、どんな服を着て、どんな教育を受け、どんな仕事をし・・・となってくるとどうでしょうか。
そして、そのイメージする生活があったとしても、その実現と脱原発は両立するのか・・・?
多分「脱原発」という言葉の先にあるものも一つではありません。
イメージする将来の暮らしの姿は人それぞれでしょう。そんな様々な将来像を抱いた人々や、イメージはないけどとにかく安心安全が欲しい人などなど、いろんな思いを抱く人々が、ひとつ「脱原発」という言葉で集っています。
脱原発をめざす理由はいろいろで良いと思います。でも、闘う時、味方内ではその理由の違いを理解し合っとくことも大切かなあとも思います。
言葉はごまかすためにあるのではなく、
やはり、理解し合うためにあるのだと思いたい。
その2はまた。