先週末のテレビの情報番組は、立川談志追悼企画が花盛りだった。花盛りと言っていいのか分からないが、どこの番組もやっていた。たいてい、みんな芝浜のVTRを使っていて、撮影の年代はバラバラだった。
先日、このブログで、同じ芝浜でも演者によってずいぶん違うと書いたが、いろんな時代の談志の芝浜を見ていて、演者によってどころか、同じ演者の落語でも、演じる時々で随分と違うものだということにあらためて気づかされた。
日曜の朝の番組で使っていたのはいつの芝浜だろう、結構昔、たぶん90年代。土曜日の午前中、NHKのBSプレミアムで使っていた芝浜は2006年の立川談志独演会。どちらの番組も、下げの部分を使っていたが、おかみさんの演じ方が全然違っていた。後者の方が断然良かった。
06年の独演会。旦那が3年断ってたお酒を、「私も飲むからさ」と勧める女房のことば。
「酔っちゃえよぉ、ベロベロんなっちゃえ」
かわいくて、ちょっとドキッとした。だってこのあとに続くのは、口には出さずとも「私も酔っちゃうからさ」でしかない。これ、90年代初頭に流行ったCM「女房酔わせてどうするつもり?」の100倍素直でかわいくないですか?
そこにいるのは糟糠の妻ではなく、旦那のことが好きでたまらないおかみさんで、いい夫婦なんかじゃなくて、仲の良い男と女。相手のことを好きだと思っている時にだけ生まれる会話の初々しさとなれなれしさ、そしてちょっとの照れくささ。おちついた夫婦愛じゃなくて、そわそわする恋。何年も連れ添っているのに、この夫婦まだ恋してる。恋と愛が同居してる。そんなかんじを抱かせる演出なのだ。それを71のダミ声のジジイが演じている。
なんだか、女子高生のようでもある(意外に好きな男には一途であるとかそういう意味で)。バブル直後のアラサー女みたいに打算がない。「あの人の為なら私がんばる」と、旦那を支え、背筋延ばしてがんばってきた末の「酔っちゃえよぉ」。書いてる私もなんだか照れくさい。そんなキュンとする芝浜のラスト。
日曜日の情報番組で紹介していた十年以上前の芝浜のおかみさんには、恋しているような初々しさは感じなかった。あれは夫婦愛。昔見た時には、それはそれで、かわいいおかみさんだったような気がしていたけれど、談志の芝浜は自らはジジイになりながら、その初々しさを増していたのだった。
その時の芝浜の全体像を見ないで、「酔っちゃえよお、ベロベロんなっちゃえ」の一言で語るのは乱暴かもしれないが、あの一言がすべてを表している気がした。
談志の落語の登場人物には、今を生きる人が見える。そしてその今とは、私たちが生きる現代でもあり、話の設定の江戸時代でもあり、その間はタイムトンネルで繋がっている。一瞬と永遠の同居。恋と愛を同時に演じることができる落語家は談志のほかにいるだろうか?
「落語を現代に」っていうのは、こういうことなのかもしれない。
2000年代を象徴する女性像というか、消費に明け暮れてもったいぶってるバブルの残党女でなく、自分って何?とか探してる場合でもなく、焼け野が原でも、何もなくとも、べそかきながらでも、よくわかんないままでもわかってても、まっすぐ突っ走って、最後に好きな男に「いっしょに酔っちゃおう」と言える女。そんな女たちこそ、この沈みかけた日本って国をなんとかできるんじゃなかろうか。
談志の演じるかわいいおかみを見ながら、こんなことを考えた。
しばらく落語に接していない自分がこんなことをつらつら書くのも気が引けるが、談志の「酔っちゃえよお」があまりにリアルだったので、こんなことを書くに至ってしまった。いや、あまりにリアルは嘘だ。あんなおおげさな身振り口ぶりの子はいないのかもしれない。でも、そんな人間描写で見るものドキッとさせるのが、談志のイリュージョンなんだろうなあ。ああ、うまく伝わらない・・・。でもそろそろ仕事に戻ります。銀行いかにゃあ。もうすぐ3時。












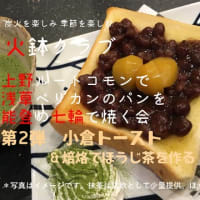



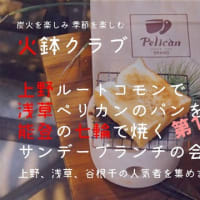



家元のと比較するためです。
その結果、改めて分かったことは
”家元の落語は常に発展途上である”
”家元の落語は登場人物が勝手に一人歩きする”
”家元の落語のさわりを世間に伝えるには芝浜は絶好な素材である”
というありきたりな結論でした。
うまく説明できないのですが、家元は落語の「髄」を解剖して再構築することで落語を理解しようとした、いわば落語ルネッサンスの体現者であると思います。
くだんの「女房」のこともお話をうかがったことがあるのですが、「何故この女房は亭主をだましてまで亭主を働かせたのか」を考えるにあたってそれまでの古典の演出に疑問をもたれていました。
私の解釈ですが、この女房は世間体を気にして夫を働かせ安定した生活を欲したのではなく、夫が好きだからささやかでもいいから一緒に平穏な時間が欲しかったのではないかと思います。
家元の表現(かわいいおかみさん)は、いわばそのデフォルメではないかと。
志ん朝師の「芝浜」は淀みの無い立て板に水のような正に完成形です。
それに対して家元はいつも噺の真髄を掘り下げようと色々な角度からの解釈を交えたものです。
家元は創造活動の過程を芸に昇華しているともいえますね。
あぁなんだか分からない。もう寝ます。
なんだかこなれてない考えをそのままアップしてしまい、もうちょっと考えてからアップすればよかったなあと思ってます。
あのあと、100年インタビューで、この06年の芝浜はミューズが降りたという話を知りました。勝手に登場人物が動き出すってことは、家元の中にあるものが無意識も含めて宿るってことかなあと思うと、やはり立川談志というひとは、優しい人であったのだなあと思えます。
たまたまYOUTUBEで黄金餅を見たのですが、焼き場までの道のり、今の東京の道路が見えました。なんだかグッときました。やはりすごいですね。