昨日、折り紙をやってる方に、折り紙を少し教えてもらった。
鶴はまだ折ることができる。
けれど、子どものころに折っていた、カブトや袴、百合の花
椅子とピアノ、お菓子の入れ物、などなどの折り方はほとんど忘れてしまっている。
けど、そんなものを今更教えてもらってもしょうがない。
で、教えてもらったのがこれだ。

薔薇の花。
実は私、折り紙には子どものとき以来ほとんど触れていなくて、
こんな薔薇の花の折り方が考案されていることも知らなかった。
凄いなあ。これ1枚の紙で、一個の切れ目も入れずに折ってるのだ。
やはり、鶴やかぶとなどとは比べ物にならない複雑な折り方で、
昨日教えてもらった時には、完成させる事ができなかった。
今日、ネット上に掲載されている作り方を見て復習して
再度挑戦して、上の写真の薔薇ができた。
この折り紙の薔薇は、折り方を考えた人の名前をとって川崎ローズと呼ばれていて、世界中に広まっている。YOUTUBEで川崎ローズ(kawasaki rose)で検索すれば、英語の字幕のついた折り方を見せるVTRがいくつも見つかる。
考案した川崎敏和氏は高専の先生。折り紙の研究で博士号をとってるらしい。
折り紙は展開図をみれば分かるが、まさに幾何学だ。
そして、この「薔薇」が面白いのは、淡々と直線折りを続けていけば次第に形ができていく鶴やかぶとと違って、形ができていく過程のところどころにカタルシスがある点だ。
川崎ローズの作成過程には、有名な「Kawasaki Twist(川崎ねじり?)」という折り方(折るとは言わないかな?)の部分があるのだが、4方の山折をつまんで少し立体化して、その後、ねじって押さえたら、再び平面になる。
ねじりを介して、一瞬にして三次元から二次元になるあの感じが、なんかたまらなくぐっとくる。
なんというのか、メビウスの輪に感じる空間の謎というか、物理学的好奇心というか、宇宙空間に放り出されるような快感が、一瞬、ほんの一瞬だけどあるのだ(また大げさに書いてもたかな)。
このKawasaki Twistだけでなく、平面から立体的薔薇の花びらが一瞬にして立ち上がる時のカタルシスは言うまでもない。
このサイトに川崎ローズの折り方が実演されている。
川崎ローズの折り方 VTR
このページにあるVTRのパート1の7分35秒あたりから上記の「Kawasaki Twist」が、パート2で薔薇の花びらが立ち上がるところが見られる。
しかし、このカタルシスは、自分で折ってみないと、多分見ただけではわからないと思うなあ。
で、もう一個作っちゃったのがコレだす。

それにしても、どう頭を使えば、直線で作られた展開図からこういうリアルな薔薇の形ができるのかが分かるのか?
まるで、将棋や囲碁で、100手先を読むような感じで、頭の中のコンピュータが、自動的に薔薇の形から展開図を解析するのか。
と思って、ググっていたら、こういうページを見つけた。
川崎先生ではないが、この方も大学で折り紙の研究をしている。三谷純さんという方のインタビュー記事だ。
三谷さんの場合は、コンピュータを使う。まず三次元コンピュータグラフィックスで形を造形し、その展開図は計算で求めるのだそうだ。展開図はできたのもの、折るのが難しくて完成しないものもあるらしい。
また、三谷さんによれば、海外の研究者には、昆虫の脚の本数や長さなどの骨格情報を入力して展開図を自動的に導きだすシステムを作った人もいるとか。一体それってどういう計算式を使うのだ??謎が謎を呼ぶ。
折り紙の折り方は、今では、人工衛星の太陽光パネルなどにも応用されていて、今後も様々な利用法が模索されている。
例えば、ミウラ折りという折り方は、大きな判型のものを小さく折り畳む際の最強の折り方として、活用されているようだ。開いたり閉じたりしやすくて、折り目から破れにくいんだって。
折り紙は、かなりビジネスとしても有望な存在なのだ。
しかし、やはりそれよりも、私の中では、あの薔薇を初めてちゃんと折れた時に感じたカタルシスのほうに興味がある。
本当に、宇宙への好奇心に近い何かを感じたのだ。
おそるべし、折り紙の世界である。
その謎を解くために、いつか川崎氏や三谷氏など折り紙数学者にインタビューを敢行したいなあ。
資金ができて、ブログをリニューアルしたら、取材に出たいと思う。
でも、とにかく、折り紙思ったよりオモロいです。
手先も使うし、ボケ防止にも良さそう。
みなさんも作り方を見て挑戦してみませんか?
以下は、福山工業高校の有志が、川崎敏和氏などのアドバイスを受けて、初心者が折ばらを完成させられる事を目標に作られた
作り方のウェブサイトです。折ばらウェブサイト
上記のビデオとは、少し折る順番が違うみたい。
こちらは、折線を書いた折り紙の静止画も多数掲載され、より分かりやすくなっています。
まず、以下の本を読んでみなきゃな。
鶴はまだ折ることができる。
けれど、子どものころに折っていた、カブトや袴、百合の花
椅子とピアノ、お菓子の入れ物、などなどの折り方はほとんど忘れてしまっている。
けど、そんなものを今更教えてもらってもしょうがない。
で、教えてもらったのがこれだ。

薔薇の花。
実は私、折り紙には子どものとき以来ほとんど触れていなくて、
こんな薔薇の花の折り方が考案されていることも知らなかった。
凄いなあ。これ1枚の紙で、一個の切れ目も入れずに折ってるのだ。
やはり、鶴やかぶとなどとは比べ物にならない複雑な折り方で、
昨日教えてもらった時には、完成させる事ができなかった。
今日、ネット上に掲載されている作り方を見て復習して
再度挑戦して、上の写真の薔薇ができた。
この折り紙の薔薇は、折り方を考えた人の名前をとって川崎ローズと呼ばれていて、世界中に広まっている。YOUTUBEで川崎ローズ(kawasaki rose)で検索すれば、英語の字幕のついた折り方を見せるVTRがいくつも見つかる。
考案した川崎敏和氏は高専の先生。折り紙の研究で博士号をとってるらしい。
折り紙は展開図をみれば分かるが、まさに幾何学だ。
そして、この「薔薇」が面白いのは、淡々と直線折りを続けていけば次第に形ができていく鶴やかぶとと違って、形ができていく過程のところどころにカタルシスがある点だ。
川崎ローズの作成過程には、有名な「Kawasaki Twist(川崎ねじり?)」という折り方(折るとは言わないかな?)の部分があるのだが、4方の山折をつまんで少し立体化して、その後、ねじって押さえたら、再び平面になる。
ねじりを介して、一瞬にして三次元から二次元になるあの感じが、なんかたまらなくぐっとくる。
なんというのか、メビウスの輪に感じる空間の謎というか、物理学的好奇心というか、宇宙空間に放り出されるような快感が、一瞬、ほんの一瞬だけどあるのだ(また大げさに書いてもたかな)。
このKawasaki Twistだけでなく、平面から立体的薔薇の花びらが一瞬にして立ち上がる時のカタルシスは言うまでもない。
このサイトに川崎ローズの折り方が実演されている。
川崎ローズの折り方 VTR
このページにあるVTRのパート1の7分35秒あたりから上記の「Kawasaki Twist」が、パート2で薔薇の花びらが立ち上がるところが見られる。
しかし、このカタルシスは、自分で折ってみないと、多分見ただけではわからないと思うなあ。
で、もう一個作っちゃったのがコレだす。

それにしても、どう頭を使えば、直線で作られた展開図からこういうリアルな薔薇の形ができるのかが分かるのか?
まるで、将棋や囲碁で、100手先を読むような感じで、頭の中のコンピュータが、自動的に薔薇の形から展開図を解析するのか。
と思って、ググっていたら、こういうページを見つけた。
川崎先生ではないが、この方も大学で折り紙の研究をしている。三谷純さんという方のインタビュー記事だ。
三谷さんの場合は、コンピュータを使う。まず三次元コンピュータグラフィックスで形を造形し、その展開図は計算で求めるのだそうだ。展開図はできたのもの、折るのが難しくて完成しないものもあるらしい。
また、三谷さんによれば、海外の研究者には、昆虫の脚の本数や長さなどの骨格情報を入力して展開図を自動的に導きだすシステムを作った人もいるとか。一体それってどういう計算式を使うのだ??謎が謎を呼ぶ。
折り紙の折り方は、今では、人工衛星の太陽光パネルなどにも応用されていて、今後も様々な利用法が模索されている。
例えば、ミウラ折りという折り方は、大きな判型のものを小さく折り畳む際の最強の折り方として、活用されているようだ。開いたり閉じたりしやすくて、折り目から破れにくいんだって。
折り紙は、かなりビジネスとしても有望な存在なのだ。
しかし、やはりそれよりも、私の中では、あの薔薇を初めてちゃんと折れた時に感じたカタルシスのほうに興味がある。
本当に、宇宙への好奇心に近い何かを感じたのだ。
おそるべし、折り紙の世界である。
その謎を解くために、いつか川崎氏や三谷氏など折り紙数学者にインタビューを敢行したいなあ。
資金ができて、ブログをリニューアルしたら、取材に出たいと思う。
でも、とにかく、折り紙思ったよりオモロいです。
手先も使うし、ボケ防止にも良さそう。
みなさんも作り方を見て挑戦してみませんか?
以下は、福山工業高校の有志が、川崎敏和氏などのアドバイスを受けて、初心者が折ばらを完成させられる事を目標に作られた
作り方のウェブサイトです。折ばらウェブサイト
上記のビデオとは、少し折る順番が違うみたい。
こちらは、折線を書いた折り紙の静止画も多数掲載され、より分かりやすくなっています。
まず、以下の本を読んでみなきゃな。
 | バラと折り紙と数学と川崎 敏和森北出版このアイテムの詳細を見る |
 | 折り紙夢WORLD 花と動物編川崎 敏和朝日出版社このアイテムの詳細を見る |












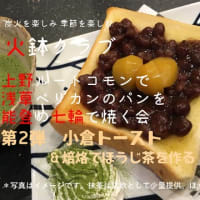



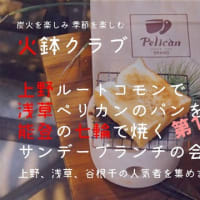



私も挑戦してみたいです。
でも、難しそうだな~。(^_^;
昔、TVチャンピオンで「折り紙王」を見て、これは数学だ・・・っと思いました。