ふと、このブログのタイトルである価値とは何かを考えてみることにした。
こんなタイトルをつけるくらいだから、常にぼんやりと考えてはいるのだが、今回はちょっと文字にしてみようかと思う。
そして、まずは、モノの値段ということを考えた。
モノの値段はおおざっぱに言えば、
コスト<原材料費+人件費+運搬費+設備費+広告費+付加価値(ブランドとか有機無農薬とか)>+利益だ。
コストを細かく分解して行くと、原材料費は、そのまた原材料とそれを作った人の人件費が含まれる。もちろん設備費としての機械や運搬に使う車なども、それを設計したコンピューターも結局は人が作ったわけで、それをさらに分解して行くと、最後にそこに残るのは、天から与えられた自然界に存在する素材と人件費となる。広告費もしかり。
天から与えられた素材はその大元は無料である。そうすると、モノの値段は結局のところ人件費と付加価値のみ。付加価値というのは人間の脳みそが生み出すものだから、つまり、モノの価値とは、人間の労働と想像力の集積ということになる。
そーいうことか。
いや、自分で勝手に納得してしまったが、経済学をちゃんと学んでないので、何か重要な変数を忘れてないか、適当なことを言ってないか不安ではあるが、
どうなんですかね?この考え。
ただ、私がこんなことを思いついたのは、人間の労働の価値というものが、最近ものすごく軽んじられているからじゃないかと思う。
昔、経済学の授業で、モノの値段は需要曲線と供給曲線の一致するところで決まると教わった。「神の見えざる手」だ。
高校生のときは、暗記だけして意味なんて考えてもいないアホだった私は、確かにそうだろうなあと思っていた。
しかし、現在のデフレ状況を考えると、この「神の見えざる手」が人間にとって暴力とならない範囲で働くのは、「人件費の市場に格差が無い場合」に限るのではないか。つまり、世の中がグローバル化した現在、この理論はあてはまらないのではないかと思うのだ
最初に掲げた「モノの値段の内訳」のうち、付加価値の部分が低い生活必需品的なものは、どんどん需要側の圧力により値段が下げられて行くのだと思う。
だって、普通に考えて、ある程度の市場だったら、供給側より需要側のほうが圧倒的に人数が多いんだから、圧力だって大きいんじゃないだろうか。
学校で習った経済学からは、人の欲望とか、怠惰とか、身勝手などなど、人間の行動における特性の係数が見えてこない。欲しいvs売りたいというたった2項の要素だけだ。
しかし、その「欲しい」という欲求を分析して行けば、それは何かを満たす「欲望」もあれば、「怠惰を補う」という機能もあれば、「自らの想像力を補う」という機能などもあるだろう。
欲望:食べたい、着飾りたいなどなど
怠惰を補う:ご飯を作らずコンビニ弁当を買うとか
想像力を補う:ミュージシャンの作った音楽を買うなど
モノの値段が人件費と人間の想像力に集約されると書いたが、つまり、誰かの労働がだれかの労働負荷を助けたり、本来ならば自分でやるべき事を貨幣で誰かに肩代わりしてもらってる。
なんか私、当たり前の事を言ってる?
何で私が突然、こんな訳の分からない事をつぶやき始めたかと言うと、それは高橋源一郎氏がツイッターでつぶやいたルソーの「社会契約論」の一節に触発されたからだ。
高橋源一郎のツイッター@takagengen
以下は高橋氏が「議会制民主主義は奴隷制か?」と題して9月14日の午後0時から27回にわたってツイッター上につぶやいたものの一部だ
<ここから引用>
「民主主義」5・少し長いが、「人民主権」というものを、ルソーがどう考えていたか、引用してみる。
「市民たちの主要な仕事が公務ではなくなり、市民たちが自分の身体を使って奉仕するよりも、自分の財布から支払って奉仕することを好むようになるとともとに、国家は滅亡に瀕しているのである...」
「...[兵士として]前線に出兵しなければならないというなら、市民は[傭兵の]軍隊に金を払って、自分は家にとどまろうとする。会議に出席しなければならないというなら、市民は代議士を任命して、自分は家にとどまろうとする..」
「...怠惰と金銭のおかげで、市民たちはついに兵隊を雇って祖国を奴隷状態に陥れ、代議士を雇って祖国を売り渡したのである..うまく運営されている公民国家では、市民たちは集会に駆けつけてゆくものだが、悪しき政府のもとでは、市民たちの誰も、集会に出席するために一歩でも...」
「..動こうという気にならないものだ。誰も集会で決議されることに関心をもたないからであり、集会では一般意志が支配しないことが予測できるからであり、最後に自宅での[私的な]仕事に忙殺されるからである...誰かが『それがわたしに何の関係があるのか』と言いだすようになったら」
「...すでに国は滅んだと考えるべきなのである」。
だから、ルソーが考えた「人民主権」の原理は、「市民(国民)」が全員参加する直接民主主義だった。さて、どうだろう。ルソーは実現不可能な「机上の空論」を書いたのだろうか。『社会契約論』を読んでいると、そうは思えないのだ。
<引用ここまで>
ここで語られているのは、直接民主制と議会制民主主義の話だ。
議会制つまり代議制になった場合、市民は自らの怠惰から、金を払って公務を他人に委託する。そして最後には、自宅での[私的な]仕事に忙殺され、『それがわたしに何の関係があるのか』と言い出し、集会に出席しなくなる。そうなったら国は滅んだと考えるべきだとルソーは語る。
私が特に反応したのは、『怠惰と金銭のおかげで』ということろだ。
この話で、人々が払う金銭とは『税金』のことであり、ルソーは、市民全員で担うべき公務を、金銭で一部の人に任せる事によって、公務への関心が薄れ、国は滅びると論じている。
まさに今、この通りの事が私たちの国日本でも進行していると思う。
そして、その『怠惰と金銭』の関係は、政治の場面のみならず、現代の私たちの生活全てを覆い尽くしていると思うのだ。
このブログの前半で、ものの値段を決める価値は、人間の労働力と想像力の集約だと書いた。
それを貨幣つまりお金を媒介にして、他人に肩代わりしてもらっているのが、「経済」だ。
「政治」の場面で、自らの怠惰により、お金で誰かに肩代わりしてもらった公務には、人は関心を寄せなくなる。
それと同じことは「経済」でも言えるのではないか。
例えば、自分でやろうと思えばできる食事の準備を怠って買ってきたコンビニのおにぎりの質やその制作過程に人はどのくらい関心を寄せているだろうか。
「仕事が忙しいから」と、食事を作るという労働を誰かに肩代わりしてもらっているのが、この場合のコンビニおにぎりだ。
別に、コンビニおにぎりが悪だというのではない。労働をお金で肩代わりしてもらった人が、どのくらいそのことを意識し、そのお金の使われた先の有り様を考えるだろうかということだ。
現代の大量消費社会を生きる私たちは、政治の場面にしろ、暮らしの場面にしろ、「お金」によって自分の様々な責任を誰かに肩代わりしてもらっている。
肩代わりをしてもらうということは、他の人がやることによって、自分が知らないところで生まれるかもしれない負の利益も被る可能性があるという事だ。
お金を払って肩代わりしてもらった時点で、私たちは正の利益とともにそうした負の利益の可能性もしょっていることを忘れてはいけない。
「お金を使う」とはそういうことなんだなあと、ルソーに再認識させられた。
「お金を使う」とは、自分が把握できるはずの事象を人にまかせることでもあるから、何か想像もしない事が起こりうる可能性も考慮に入れなくてはならないのだ。
「お金を使う」ということは、便宜やモノを得るだけではなくて、お金の使われ方をチェックする責任も生まれるんじゃ無いかと思う。
モノの値段を細分化して行くと、最後は人間の労働と想像力のみに行き着くと考えたが、「モノとお金の交換」を単なる物質の交換と考えることが、今の政治経済を行き詰まらせているような気がする。
経済学の専門家の方が読まれたら恥ずかしくなるようなことかもしれないけど、せっかくいろいろ考えたので、思いつくまま書いてみました。
おつき合いいただきありがとうございました。
私のブログの基本は、こうした考え方のもとに、さまざまな事象を紹介することです。
今後、スタイルも早いうちにリニューアルしてものづくりの現場なども紹介したいのでよろしくお願いします。
そこにはどういった価値が含まれるのかを考えながら、人が作ったモノを愛して行きたいと思います。
また、それと同様に、自分たちが担うべき、政治も考えて行きたいと思います。
こんなタイトルをつけるくらいだから、常にぼんやりと考えてはいるのだが、今回はちょっと文字にしてみようかと思う。
そして、まずは、モノの値段ということを考えた。
モノの値段はおおざっぱに言えば、
コスト<原材料費+人件費+運搬費+設備費+広告費+付加価値(ブランドとか有機無農薬とか)>+利益だ。
コストを細かく分解して行くと、原材料費は、そのまた原材料とそれを作った人の人件費が含まれる。もちろん設備費としての機械や運搬に使う車なども、それを設計したコンピューターも結局は人が作ったわけで、それをさらに分解して行くと、最後にそこに残るのは、天から与えられた自然界に存在する素材と人件費となる。広告費もしかり。
天から与えられた素材はその大元は無料である。そうすると、モノの値段は結局のところ人件費と付加価値のみ。付加価値というのは人間の脳みそが生み出すものだから、つまり、モノの価値とは、人間の労働と想像力の集積ということになる。
そーいうことか。
いや、自分で勝手に納得してしまったが、経済学をちゃんと学んでないので、何か重要な変数を忘れてないか、適当なことを言ってないか不安ではあるが、
どうなんですかね?この考え。
ただ、私がこんなことを思いついたのは、人間の労働の価値というものが、最近ものすごく軽んじられているからじゃないかと思う。
昔、経済学の授業で、モノの値段は需要曲線と供給曲線の一致するところで決まると教わった。「神の見えざる手」だ。
高校生のときは、暗記だけして意味なんて考えてもいないアホだった私は、確かにそうだろうなあと思っていた。
しかし、現在のデフレ状況を考えると、この「神の見えざる手」が人間にとって暴力とならない範囲で働くのは、「人件費の市場に格差が無い場合」に限るのではないか。つまり、世の中がグローバル化した現在、この理論はあてはまらないのではないかと思うのだ
最初に掲げた「モノの値段の内訳」のうち、付加価値の部分が低い生活必需品的なものは、どんどん需要側の圧力により値段が下げられて行くのだと思う。
だって、普通に考えて、ある程度の市場だったら、供給側より需要側のほうが圧倒的に人数が多いんだから、圧力だって大きいんじゃないだろうか。
学校で習った経済学からは、人の欲望とか、怠惰とか、身勝手などなど、人間の行動における特性の係数が見えてこない。欲しいvs売りたいというたった2項の要素だけだ。
しかし、その「欲しい」という欲求を分析して行けば、それは何かを満たす「欲望」もあれば、「怠惰を補う」という機能もあれば、「自らの想像力を補う」という機能などもあるだろう。
欲望:食べたい、着飾りたいなどなど
怠惰を補う:ご飯を作らずコンビニ弁当を買うとか
想像力を補う:ミュージシャンの作った音楽を買うなど
モノの値段が人件費と人間の想像力に集約されると書いたが、つまり、誰かの労働がだれかの労働負荷を助けたり、本来ならば自分でやるべき事を貨幣で誰かに肩代わりしてもらってる。
なんか私、当たり前の事を言ってる?
何で私が突然、こんな訳の分からない事をつぶやき始めたかと言うと、それは高橋源一郎氏がツイッターでつぶやいたルソーの「社会契約論」の一節に触発されたからだ。
高橋源一郎のツイッター@takagengen
以下は高橋氏が「議会制民主主義は奴隷制か?」と題して9月14日の午後0時から27回にわたってツイッター上につぶやいたものの一部だ
<ここから引用>
「民主主義」5・少し長いが、「人民主権」というものを、ルソーがどう考えていたか、引用してみる。
「市民たちの主要な仕事が公務ではなくなり、市民たちが自分の身体を使って奉仕するよりも、自分の財布から支払って奉仕することを好むようになるとともとに、国家は滅亡に瀕しているのである...」
「...[兵士として]前線に出兵しなければならないというなら、市民は[傭兵の]軍隊に金を払って、自分は家にとどまろうとする。会議に出席しなければならないというなら、市民は代議士を任命して、自分は家にとどまろうとする..」
「...怠惰と金銭のおかげで、市民たちはついに兵隊を雇って祖国を奴隷状態に陥れ、代議士を雇って祖国を売り渡したのである..うまく運営されている公民国家では、市民たちは集会に駆けつけてゆくものだが、悪しき政府のもとでは、市民たちの誰も、集会に出席するために一歩でも...」
「..動こうという気にならないものだ。誰も集会で決議されることに関心をもたないからであり、集会では一般意志が支配しないことが予測できるからであり、最後に自宅での[私的な]仕事に忙殺されるからである...誰かが『それがわたしに何の関係があるのか』と言いだすようになったら」
「...すでに国は滅んだと考えるべきなのである」。
だから、ルソーが考えた「人民主権」の原理は、「市民(国民)」が全員参加する直接民主主義だった。さて、どうだろう。ルソーは実現不可能な「机上の空論」を書いたのだろうか。『社会契約論』を読んでいると、そうは思えないのだ。
<引用ここまで>
ここで語られているのは、直接民主制と議会制民主主義の話だ。
議会制つまり代議制になった場合、市民は自らの怠惰から、金を払って公務を他人に委託する。そして最後には、自宅での[私的な]仕事に忙殺され、『それがわたしに何の関係があるのか』と言い出し、集会に出席しなくなる。そうなったら国は滅んだと考えるべきだとルソーは語る。
私が特に反応したのは、『怠惰と金銭のおかげで』ということろだ。
この話で、人々が払う金銭とは『税金』のことであり、ルソーは、市民全員で担うべき公務を、金銭で一部の人に任せる事によって、公務への関心が薄れ、国は滅びると論じている。
まさに今、この通りの事が私たちの国日本でも進行していると思う。
そして、その『怠惰と金銭』の関係は、政治の場面のみならず、現代の私たちの生活全てを覆い尽くしていると思うのだ。
このブログの前半で、ものの値段を決める価値は、人間の労働力と想像力の集約だと書いた。
それを貨幣つまりお金を媒介にして、他人に肩代わりしてもらっているのが、「経済」だ。
「政治」の場面で、自らの怠惰により、お金で誰かに肩代わりしてもらった公務には、人は関心を寄せなくなる。
それと同じことは「経済」でも言えるのではないか。
例えば、自分でやろうと思えばできる食事の準備を怠って買ってきたコンビニのおにぎりの質やその制作過程に人はどのくらい関心を寄せているだろうか。
「仕事が忙しいから」と、食事を作るという労働を誰かに肩代わりしてもらっているのが、この場合のコンビニおにぎりだ。
別に、コンビニおにぎりが悪だというのではない。労働をお金で肩代わりしてもらった人が、どのくらいそのことを意識し、そのお金の使われた先の有り様を考えるだろうかということだ。
現代の大量消費社会を生きる私たちは、政治の場面にしろ、暮らしの場面にしろ、「お金」によって自分の様々な責任を誰かに肩代わりしてもらっている。
肩代わりをしてもらうということは、他の人がやることによって、自分が知らないところで生まれるかもしれない負の利益も被る可能性があるという事だ。
お金を払って肩代わりしてもらった時点で、私たちは正の利益とともにそうした負の利益の可能性もしょっていることを忘れてはいけない。
「お金を使う」とはそういうことなんだなあと、ルソーに再認識させられた。
「お金を使う」とは、自分が把握できるはずの事象を人にまかせることでもあるから、何か想像もしない事が起こりうる可能性も考慮に入れなくてはならないのだ。
「お金を使う」ということは、便宜やモノを得るだけではなくて、お金の使われ方をチェックする責任も生まれるんじゃ無いかと思う。
モノの値段を細分化して行くと、最後は人間の労働と想像力のみに行き着くと考えたが、「モノとお金の交換」を単なる物質の交換と考えることが、今の政治経済を行き詰まらせているような気がする。
経済学の専門家の方が読まれたら恥ずかしくなるようなことかもしれないけど、せっかくいろいろ考えたので、思いつくまま書いてみました。
おつき合いいただきありがとうございました。
私のブログの基本は、こうした考え方のもとに、さまざまな事象を紹介することです。
今後、スタイルも早いうちにリニューアルしてものづくりの現場なども紹介したいのでよろしくお願いします。
そこにはどういった価値が含まれるのかを考えながら、人が作ったモノを愛して行きたいと思います。
また、それと同様に、自分たちが担うべき、政治も考えて行きたいと思います。
 | 社会契約論 (岩波文庫)J.J. ルソー岩波書店このアイテムの詳細を見る |
 | 人間不平等起原論 (岩波文庫)J.J. ルソー岩波書店このアイテムの詳細を見る |
 | 「悪」と戦う高橋 源一郎河出書房新社このアイテムの詳細を見る |












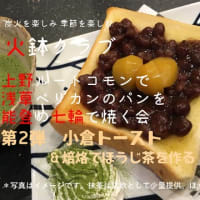



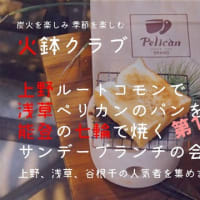



値段は価値であることを常に意識しないといけないと思います
本編で書かれている事は価値という概念が希薄になってしまっていると感じます。
価値という概念でまじめに考えれば
そんなにおかしなことにはならないはずです。
例えば、
①東京に住んでいる人が
鹿児島からわざわざ運んで来た野菜と
お隣の千葉から運んできた野菜が同じ値段で売っています
同じ味でも価値が違うはずなのに同じ値段
②農家の人がJAに最高品質の野菜をおろします
規格外になってしまった野菜を路地販売します
規格外になった不良品の方が何倍もの高値で売れます
品質はJAにおろしたものの方が良くても
なので、デフレは悪いことではありません
お金は人にしか払われないので魅力ある製品が安く並んでみんながどんどん買えば、お金の循環が良くなりデフレで好景気になる事が出来ます。
一方で
インフレは、お金の価値が下がるため、借金している人は得をし、借金をしていない人は損をする構図
また、
2倍にインフレになっても低賃金層の給料は絶対に2倍まで増えません。
高所得層は実質2倍以上の収入を得ます
要は金持ちやお金に詳しい人だけ得をして、普通に生きている人は損をする事になるはずです
経済学者の言うところの地に足の着いていない理論に惑わされてはいけません
そこには色々な条件がついているはずです
一番良いのはデフレ・円高・株高+好景気
です
なので現在問題なのは、株安と景気が悪いことです
間違ってもデフレ・円高ではありません
景気が悪い理由は
企業・政府がお金を溜め込む&海外に捨ててる
魅力ある品物がない
適正な価格でない
企業のビジネスモデルが間違っている
ということです
そのせいでお金が循環しないことです
一時期流行った
某スーパーや某コンビニなどのビジネスモデルは最悪で、通常品の1.2倍の価値なのに1.5倍の値段設定し、そんな雰囲気にする
これは、どんどん買えないのでお金の循環は下がるし、一般人の価値判断を狂わせます。
特に
マスコミやその他メディア主導で誤まった物の価値を浸透させている事が深刻です
メディアの洗脳で天然モノのいきの良い魚より養殖の脂がこんもりのっかっている魚の方が良いものだと勘違いする人が多数います。
民主主義なので養殖の方がいいにしちゃっても良いのですが。。。。ちょっとがっかりします
(なので資本主義と民主主義は嫌いです)
ところで、最後の部分の、
「モノとお金の交換」を単なる物質の交換と考える
の意味がイマイチ、明確に分からないのですが・・・。ご教授願えませんか?
そう考える事で、モノが作られる過程にも無頓着になり、負の利益も引き受ける可能性があることや、モノを得る事により発生する責任について思いをいたすことを怠ってしまう結果になるような気がします。
また、労働価値に無頓着になる事は、デフレを進める原因になっている気もします。
うーん、言葉にするの難しいですね。
販売されるモノ・サービスが単に機能のみの比較になるならば、あっという間に機能競争と価格競争に巻き込まれますよね。
労働価値をどこに置くかは、色々あるでしょうけど、そのモノが出来る過程・背景を取り上げることで、無頓着な大量消費を回避し、吟味した消費生活に近づけるような気がしました。
http://www.dejima2010.com/