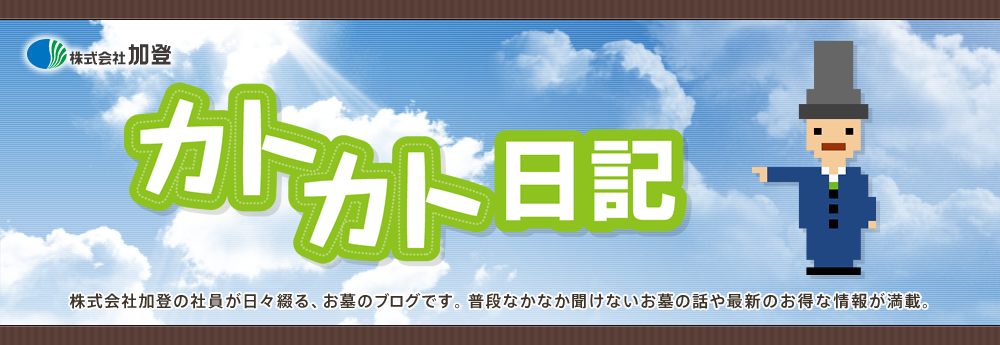カトカト日記。
by |2009-11-26 23:43:01|
かのビートルズが、デビュー作でもなければベスト盤でもない作品に
'The BEATLES'
の名を冠して発表したその意味って何だったんだろ?
ふと思って今日はこんなタイトルにしてみました。

通称「ホワイト・アルバム」。
同名映画のサウンドトラック「マジカル・ミステリー・ツアー」を除外すれば、リリース自体が音楽という枠を超え、歴史に残る「事件」となった「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」以来のオリジナル・フルアルバム。
ジャケットにはもはやメンバーの写真はおろかイラストすらなく、真っ白な背景にただ'The BEATLES'と書かれているだけ。
「塩? 味噌? 醤油? 知らねーよ。うちはラーメンしか置いてねーんだよ」的な潔さ。
アララギ派の方ならきっと「これぞますらをぶり」と快哉を叫んだことでしょう。
そこに込められたメッセージとは?
既にライブ活動も放棄し、メンバー間の溝もどんどん深くなっていたであろう頃の傑作は、
前述の「サージェント・ペパー」がそれまでシングル曲の寄せ集めでしかなかったアルバムを、ひとつの作品にまで昇華したトータル・コンセプト・アルバムだったのとは対照的に、
4つの個性がこれと言ってぶつかり合うことも高め合うこともなく、遮二無二それぞれのやりたいことをやりまくるというある意味野蛮で破天荒な衝動の果実でした。
そこには何の衒いも目論見もなくただ、溢れんばかりの才能だけがあったのです。
そして彼らはそんなアルバムに敢えて'The BEATLES'というタイトルをつけました。
原点回帰ってやつですね。
これこそが、ビートルズなんだという確信。

そこで僕も、自らに問うてみました。
「デビルマンは誰?」
ちがうちがう。
それは、知られちゃいけない。
もとい「カトカト日記って、何?」
そう、無論いろんな思惑があって然るべきではありますが、
お墓や仏事に興味をお持ちの方だけでなく、そうではないお客様にも加登を知っていただき、
欲を言えば加登のファンになっていただきたいと、僕は本気でそう思っているのです。
皆さん、カトカト日記はお墓の話ばかりではありません。
このような悩みを抱えるあなたにもオススメです。
「好投している先発投手の替え時が分からない」
「得点圏打率が極端に低い」
「クリーンナップが固定できず打線につながりがない」
「最近変化球の曲がりが悪くなった」
「スクイズをやたらと外される。サインがばれているのでは?」
・・・・・ちがうちがう。
何て言いますか、特に若い方なんかだと、
お墓とか霊園とか仏事とかってちょっと遠い世界のように感じておられると思うんですよね。
でも、実際僕だってまだ21歳だし(嘘)、20代30代の社員もたくさんいます。
たまたま縁があってこういう仕事をしてますが、みんな四六時中お墓のことばかり考えてるわけではなくて、プライベートではゴルフをやってる人もいれば空手や釣りに精を出す人もいます。
お笑い芸人を目指してた人もいるし、料理教室に通う人もいる。
冬になればスノボにも出かけるし、夏になれば汗もかく、そんな至って普通の人間ばっかりです。
だからどうか皆さん、お墓のブログ、お墓の会社といって敬遠したりしないでください。
よろしくお願いしときますよ。
■ 加登のこと、もっと知りたい方は・・・・・

 霊園・墓石・仏事法要の情報満載! 加登HPは画像をクリック
霊園・墓石・仏事法要の情報満載! 加登HPは画像をクリック
 フォロー大歓迎! 加登 公式ツイッターも画像をクリック
フォロー大歓迎! 加登 公式ツイッターも画像をクリック
 大切な故人やペットの思い出を身につける。手元供養品【SAMSARA】
大切な故人やペットの思い出を身につける。手元供養品【SAMSARA】